「榊 植えてはいけない」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、榊を庭木として植えることに不安を感じているのではないでしょうか。
榊は古くから神聖な木として知られ、神棚や祭事に用いられてきましたが、「榊は縁起が悪いとなぜ言われますか?」と疑問に思う方も多く、その背景には迷信や地域の慣習が色濃く関係しています。
この記事では、榊を庭に植える際に気をつけたい「植える場所」や「植える方角」、さらには「風水」や「家相」から見た注意点まで丁寧に解説します。
また、「絶対に植えてはいけない庭木」とはどういったものなのか、榊や「ヒサカキ」が「庭に植えてはいけない」とされる理由、さらには「育て方」や「鉢植え」のポイント、「植える時期」の見極め方まで網羅。
「庭木として榊は縁起が良いとされていますか?」という疑問に対しても、さまざまな視点からわかりやすく答えています。
榊の栽培を検討している方や、すでに庭に榊を植えている方にとっても役立つ内容となっていますので、どうぞ最後までご覧ください。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 榊は縁起が悪いと言われる理由 | 神聖すぎる木とされ、庶民が庭に植えるのは畏れ多いとされた背景がある |
| 風水での適した方角 | 東・南東が吉とされ、成長や発展の気を引き寄せると考えられる |
| 植えるべきでない方角 | 鬼門(北東)・裏鬼門(南西)は避けた方がよいという考え方もある |
| 家相上の注意点 | 榊のような強い「木の気」が家の気と衝突する恐れがあるとされる |
| 迷信との向き合い方 | 信じる人への配慮が大切で、植える前に家族や近隣と相談すると安心 |
| 絶対に植えてはいけない庭木 | 毒性・トゲ・害虫がつきやすい木は避けられることが多い |
| ヒサカキが嫌われる理由 | 花の匂いが強く、仏事に使われるため「不吉」とされることがある |
| 育てやすい環境 | 半日陰・通気性と水はけの良い場所を好む |
| 鉢植えでの注意点 | 根腐れ防止のために排水性の高い土と定期的な植え替えが必要 |
| 榊に適した植え時 | 春(3〜5月)と秋(9〜10月)が根付きやすくおすすめ |
| 庭木としての榊の縁起 | 「栄える木」とも書かれ、厄除けや家運向上の象徴ともされる |
| ご近所トラブルの回避 | 目立たない場所に植える・剪定をしっかり行うなどの工夫が効果的 |
| 信仰や宗教観との兼ね合い | 植える前に家族内の価値観を確認し、納得したうえで判断することが大切 |
| トラブル時の対応 | 鉢植えで移動できるようにする、見えにくい位置に配置するなど柔軟に対処 |
| まとめ | 榊は注意点もあるが、環境や人間関係への配慮次第で良い庭木となる |
- 庭木を完全に根絶するのは素人では難しい
- 業者に頼むと費用が高い
- 何件も相見積もりをすれば安くできるけど面倒
そこで、カンタンに安く庭木を除去する方法をご紹介します。
タウンライフ外構工事で相見積もりする。
値下げに必須な相見積もりをたった一手間で取得できる。
 著者
著者費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
榊を植えてはいけない理由とは?


- 榊は縁起が悪いとなぜ言われますか?
- ヒサカキ 庭に植えてはいけない理由
- 絶対に植えてはいけない庭木とは?
- 庭木 家相から見た注意点
- 榊を植える時に気をつけるべき迷信
榊は縁起が悪いとなぜ言われますか?
言ってしまえば、「榊は縁起が悪い」と言われる背景には、迷信や過去の価値観が大きく関係しています。榊は古くから神道における神聖な木とされており、神社や身分の高い家でしか扱われない特別な存在でした。そのため、「一般家庭で植えるのは畏れ多い」「分不相応ではないか」といった考え方が生まれたのです。
また、榊が神棚に供えられる木であることから、神様が宿る依り代(よりしろ)と見なされることもありました。これにより「軽々しく扱ってはいけない」とか「不適切な場所に植えると罰が当たる」といった言い伝えが広がっていったと考えられます。
しかし、こうした考えはあくまで過去の文化的背景や地域ごとの習慣にすぎません。現代の日本においては、榊を植えること自体に法律的・宗教的な制限は一切なく、多くの家庭で観葉植物や庭木として育てられています。
このように言うと、なんとなく気が引けてしまうかもしれませんが、必要以上に心配することはありません。むしろ、榊は丈夫で手入れがしやすく、家庭での神棚供え用としても便利な植物です。迷信や言い伝えに左右されるよりも、植物としての価値や育てる楽しみを大切にしていきたいですね。
ヒサカキ 庭に植えてはいけない理由
ヒサカキは、榊の代用品として神棚や仏事に用いられることの多い植物です。そのため身近な存在に感じる方も多いのですが、「庭に植えてはいけない」と言われる背景には、いくつかの理由があります。
まず一つ目は、その見た目や香りに関する問題です。ヒサカキは春になると小さな花を咲かせますが、その際に独特でややツンとした強いにおいを発します。このにおいが苦手な方も多く、住宅街などでは「窓を開けたらヒサカキの匂いが入ってきて不快」と感じるご近所トラブルに発展することもあります。
また、ヒサカキは仏事に用いられることが多く、「お墓に供える木」「死を連想させる植物」として認識されている地域もあります。これにより、庭に植えることを縁起が悪いと受け止められることもあるのです。実際、「不吉だ」として敬遠する家庭も少なくありません。
さらに、庭木としての見た目が地味なことも、植えられにくい理由の一つかもしれません。葉は小さく、花にも派手さはなく、装飾的な観点から見て、あえて選ばれる機会が少ないのです。
ただし、これらの理由はあくまでも地域の慣習や人々の価値観に基づいたものです。風習や宗教観は家庭ごとに異なるため、「絶対に植えてはいけない」というわけではありません。ヒサカキを植えたいと考えている場合は、ご家族や近隣との関係性を大切にしながら、理解を得る工夫をすることが大切です。
そのうえで、香りが気になる方には、風下にあたる場所に植える、あるいは鉢植えにして管理するなど、調整の仕方はいろいろあります。庭の中での役割や育てやすさを重視して、自分なりに工夫してみてくださいね。
絶対に植えてはいけない庭木とは?
例えば、トゲがある木や毒性のある植物は「絶対に植えてはいけない庭木」としてよく取り上げられます。特に、小さなお子さんやペットがいるご家庭では、安全性の観点からこれらの木を避けるのが一般的です。代表的なものには、ヒイラギ、バラ、トゲのある柑橘類などがあります。葉や実に毒を持つ種類もあり、万が一の事故を避けるために植えること自体がリスクになるケースもあります。
また、成長が早すぎて管理が大変な木や、大量の落ち葉や実を出す木も避けられる傾向があります。落葉樹の中には秋から冬にかけて大量の落ち葉が出るものもあり、掃除が追いつかず、景観を損なったり、近隣とのトラブルに発展することもあるのです。さらに、根が広がりすぎて建物の基礎や配管に悪影響を与える場合もあり、慎重な選定が求められます。
一方で、榊はこのような「絶対に植えてはいけない庭木」に分類されることはほとんどありません。ただし、前述のように手入れが行き届かないと虫がつきやすく、特にカイガラムシやコガネムシが寄り付きやすいという性質があります。これにより、周囲の植物にまで悪影響を与えてしまう可能性があるため、植える際には注意が必要です。
このため、榊を含めどんな木を選ぶにしても、単に縁起や見た目だけで判断するのではなく、日々のお手入れがしやすいかどうか、周囲への影響が少ないかどうかといった観点も含めて検討することがとても大切です。自宅の環境やライフスタイルに合った庭木を選ぶことが、長く快適な庭づくりにつながります。
- 庭木を完全に根絶するのは素人では難しい
- 業者に頼むと費用が高い
- 何件も相見積もりをすれば安くできるけど面倒
そこで、カンタンに安く庭木を除去する方法をご紹介します。
タウンライフ外構工事で相見積もりする。
値下げに必須な相見積もりをたった一手間で取得できる。



費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
庭木 家相から見た注意点
家相では、庭木の配置が家庭内の運気や家族の健康に大きな影響を与えると考えられています。特に玄関や鬼門(北東)、裏鬼門(南西)などの方位にある庭木は、良くも悪くも気の流れに作用すると言われています。そのため、榊のような神聖な意味合いを持つ木をこれらの方位に植えることについて、不安を感じる方も少なくありません。
榊を植えることで「気の流れを妨げる」とされるのは、家相の一部の流派や考え方によるものです。特に、強すぎる木の気が家の気とぶつかるとされる場合、凶相と見なされることがあります。たとえば、鬼門の真上に榊を植えることで、神聖な木が悪い運気を跳ね返すどころか逆に溜め込んでしまうのではないか、という懸念もあるのです。
ただし、これは家相の中でも一部の見解に過ぎず、全体のバランスによっては問題ないともされています。実際には、榊を植える位置だけで吉凶が決まるわけではなく、家の間取りや方角、他の植物との調和など多くの要素が複合的に関係してきます。榊そのものが悪いというわけではなく、むしろその清浄な性質から、うまく活用すれば良い気を呼び込む役割も果たしてくれる可能性があります。
ですから、榊を植えようと考えている方は、家全体の家相バランスを確認しながら、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。場合によっては鉢植えにして移動できるようにするなど、柔軟に対応することで問題を回避できます。家族全員が気持ちよく過ごせるような庭づくりを意識して配置を決めていくことが、結果として良い運気を生み出す第一歩となるでしょう。
榊を植える時に気をつけるべき迷信
繰り返しますが、「榊を植えると家に災いが起こる」といった話は、ほとんどが根拠のない迷信です。もともと榊は神聖な木として扱われ、神社や神棚に供えられる木であるため、扱い方に慎重さを求められた背景があります。そのため、「植えるのは恐れ多い」「家に災いがある」などの言い伝えが広がったと考えられます。
しかし、現代では宗教的な戒律も厳しくなくなり、榊を庭に植えることに対する明確なタブーはありません。それでも、地域の慣習や年配の方々の考えの中には、こうした迷信を信じている方も多くいらっしゃいます。特に地方の小さな集落や、古くからの家系に住んでいる方にとっては、迷信も生活文化の一部なのです。
このような場合、せっかく榊を植えても「何かあったときに責められたらどうしよう」と不安になってしまうこともあるでしょう。近所の方や親せきから「そんな木は庭に植えるものではない」と言われてしまえば、雰囲気も悪くなりかねません。
このため、榊を植える前には、まず家族で相談しておくことがとても大切です。家の中で考え方が食い違っていると、後々トラブルになりやすいためです。また、ご近所づきあいの多いエリアに住んでいる場合は、周囲の視線も意識したうえで、なるべく目立たない場所に植えると安心です。必要があれば、鉢植えにして移動できるようにするなどの柔軟な対応もおすすめです。
こうした気配りをしておけば、迷信に敏感な方がいても安心して庭づくりを楽しむことができます。つまり、迷信そのものに振り回されるのではなく、人間関係や周囲の状況に合わせた判断と工夫が大切なのです。
- 庭木を完全に根絶するのは素人では難しい
- 業者に頼むと費用が高い
- 何件も相見積もりをすれば安くできるけど面倒
そこで、カンタンに安く庭木を除去する方法をご紹介します。
タウンライフ外構工事で相見積もりする。
値下げに必須な相見積もりをたった一手間で取得できる。



費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
榊を植えてはいけない時の対処法


- 植える場所 風水で選ぶには?
- 榊を植える方角の正解は?
- 鉢植えでの育て方と注意点
- 植える時期はいつがベスト?
- 庭木として榊は縁起が良いとされていますか?
- トラブル回避!近隣との付き合い方
植える場所 風水で選ぶには?
風水の考えでは、榊のように「木の気」を持つ植物は、東や南東の方角に植えるのが良いとされています。これらの方角は成長や発展を象徴する方位とされ、仕事運や家族の健康運、そして子どもの成長運などにも良い影響を与えると信じられています。特に家庭円満や安定した暮らしを願う方にとっては、東の庭に榊を植えることでその願いを強めると考えられることが多いようです。
一方で、北や西、あるいは北西などの方角は、水や金の気を持つとされており、木のエネルギーとは相性があまり良くないとも言われています。これらの方角に榊を植えると、植物がうまく育たなかったり、気のバランスが乱れるという説もあります。ただし、これはあくまで風水の考え方に基づいたものなので、科学的な根拠があるわけではありません。
また、同じ方角でも日照や風通しの条件が大きく異なるため、方角だけにとらわれずに環境全体を見て判断することが重要です。例えば、南東でも日陰になっていたり、湿気がこもりやすい場所であれば榊には向いていません。反対に、西向きでも半日陰で風通しがよければ、十分に元気に育つケースもあります。
このように、風水を参考にするのは一つの目安にはなりますが、実際には植物の生育環境を第一に考えることが大切です。どうしても方角にこだわりたい方は、植える前にその方角の特性をよく理解し、榊が元気に育つような手入れや工夫を加えると良いでしょう。過度に縛られず、柔軟な姿勢で庭づくりを楽しむことが、心にも良い運気を呼び込むきっかけになるかもしれません。
榊を植える方角の正解は?
榊を植える場合、風水や家相の考え方では「北東(鬼門)や南西(裏鬼門)は避けた方が良い」とされることがあります。これらの方角は、気の出入りが激しい場所とされており、特に神聖な木や霊的な意味を持つ植物を配置するには注意が必要だと考えられてきました。そのため、榊をそこに植えることで「気の流れを乱すのでは」と不安になる人もいるかもしれません。
とはいえ、これらの言い伝えはあくまで伝統的な価値観に基づくものであり、科学的に裏付けられた根拠はありません。むしろ重要なのは、植物としての榊が元気に育てられる環境を整えることです。榊は湿度のある半日陰を好むため、強い直射日光が当たらない場所や乾燥しすぎない場所が適しています。
さらに、風通しが良く、夏の高温にもある程度耐えられる環境を用意してあげると、病気や害虫の発生を防ぎやすくなります。土壌に関しても、水はけが良く有機質に富んだものを用意することで、根がしっかりと張りやすくなり、安定した成長が期待できます。
方角を気にする場合でも、例えば鬼門や裏鬼門の近くに植えたい場合は、鉢植えにしておくことで柔軟に配置を変えることができますし、見た目にも調和が取れる工夫もできます。こうした配慮をすることで、風水を気にする家族や親族とも円満な関係を保つことができるでしょう。
結論として、方角は一つの目安にすぎません。それよりも、榊の健やかな生育を第一に考え、日当たり・水はけ・風通しといった基本的な環境条件を整えることが、植物にとっても家族にとっても幸せな結果につながると言えるでしょう。
鉢植えでの育て方と注意点
榊は鉢植えでも比較的育てやすい植物ですが、元気に育てるにはいくつか大切なポイントがあります。特に気をつけたいのが、水はけと通気性の良さです。鉢植えは地植えと違って水が滞りやすく、根が呼吸できない状態になると根腐れを引き起こすリスクが高まります。これを防ぐために、鉢底には必ず軽石などを敷いて排水性を確保し、土は赤玉土をベースにした通気性の良い配合にするのが基本です。
市販の観葉植物用の土でもかまいませんが、水はけに不安がある場合は赤玉土と腐葉土を6:4で混ぜるなど、手作りの配合土もおすすめです。また、鉢のサイズも重要です。榊は根を広げるタイプの植物ではないため、最初はあまり大きすぎない鉢からスタートし、根が回ってきたらひと回り大きな鉢に植え替えると良いでしょう。目安としては、2〜3年に一度の植え替えが理想です。
置き場所については、直射日光を避けた半日陰が適しています。特に夏場の強い日差しに長時間さらされると、葉焼けを起こしてしまう可能性があるため注意が必要です。一方で、暗すぎる場所では徒長(ひょろひょろと細長く伸びてしまう)することがあるので、明るい日陰やレースのカーテン越しの光が届くような場所が適しています。
水やりの頻度は季節によって調整が必要です。夏場は朝と夕方の2回、表土が乾いたらたっぷり与えるようにし、逆に冬場は控えめにし、土が完全に乾いてから与えるようにしましょう。水やりの後は、鉢皿に溜まった水を放置しないことも大事なポイントです。
最後に、風通しを良くしておくことも忘れないでください。風が通らない場所に長く置いておくと、カビや害虫が発生しやすくなってしまいます。定期的に鉢の位置を変えたり、室内なら換気を心がけたりすることで、清潔で健康な状態を保つことができます。こうしたポイントを押さえれば、鉢植えでも榊を長く元気に育てることができますよ。
植える時期はいつがベスト?
榊を地植えにするなら、春か秋が最適なタイミングです。特に春は3月から5月、秋は9月から10月あたりが目安とされています。これらの季節は気温の寒暖差が少なく、植物にとっても過ごしやすい環境が整っているため、根の活着がスムーズに進みやすくなります。
この時期は、地温も徐々に上がってきており、根が活発に伸び始める時期でもあります。とくに春は、これからの成長期に向けて苗が力強く伸びていく大事なスタートの時期です。秋の場合は、夏の強い日差しが落ち着き、涼しくなった気候が植物にとってストレスの少ない環境を提供してくれます。しかも冬を迎えるまでに根を張る時間が取れるため、翌春から元気に芽吹きやすくなります。
逆に、真夏や真冬に植えるのはあまりおすすめできません。夏場は高温と乾燥によって苗が水切れを起こしやすく、植え付け後の管理が非常に難しくなります。また、真冬は地温が低いため、根がほとんど動かず活着しにくくなります。このような時期に植えると、根付かずに枯れてしまうリスクが高くなるため、避けるのが無難です。
なお、植え付け後は天候にも注意が必要です。例えば、長雨の直後など土がぐちゃぐちゃに湿っている状態では根腐れの原因になることもあるので、できるだけ晴れた日の午前中に作業を行うのが理想です。
このように考えると、榊の植え付けにはタイミングが非常に重要です。適した時期に植えることで、その後の成長や見栄えが大きく変わってきますので、無理せず季節を見極めて作業を行うようにしましょう。
庭木として榊は縁起が良いとされていますか?
実は、榊は「栄える木」という意味合いを持ち、昔から縁起の良い植物として広く知られています。漢字の成り立ちも「木」と「神」が組み合わさってできており、神様に仕える神聖な植物としての印象が強く残っています。特に神棚に供えることで、家庭内の浄化や邪気払い、運気の上昇を促す存在として親しまれてきました。
また、神社や祭事などで使われることが多いため、「神と人とをつなぐ橋渡し」といった役割も担うとされてきました。これによって、榊はただの植物ではなく、精神的な安心感や守護の象徴として、多くの人に大切にされているのです。
こうした背景を知ると、「植えてはいけない」と感じるよりもむしろ「守りの木」「厄除けの木」として積極的に取り入れてもよいのではないでしょうか。実際、榊を庭に植えることで家庭の空気が浄化される、気持ちが整う、という声も少なくありません。
もちろん、育て方や環境によっては管理が必要ですが、縁起の面だけを見れば、榊は非常にポジティブな意味を持つ植物です。家のシンボルツリーとして迎えたり、神棚の近くに植えるなど、暮らしの中にうまく取り入れていけば、家族の絆や気持ちの安定にもつながるでしょう。
このように考えると、榊は見た目の美しさだけでなく、心を整え、運気を高めるための「心の拠りどころ」としても役立つ存在です。縁起を気にする方には特におすすめできる庭木の一つです。
トラブル回避!近隣との付き合い方
どれだけ榊が縁起の良い植物として知られていても、住んでいる地域やご近所の方々との価値観に違いがあると、思わぬトラブルに発展することがあります。特に古くからの住宅地や地域の慣習が根強く残る場所では、「榊は神聖すぎて植えてはいけない」といった考え方を持つ人も珍しくありません。
例えば、近隣の方に「榊はお墓や神社のものだから、庭にあると気持ちが落ち着かない」「縁起が悪く感じる」と言われてしまうと、お互いに気まずい関係になってしまうことがあります。その際、無理に自分の意見を押し通すのではなく、まずは相手の気持ちを受け止め、丁寧に説明することが大切です。「榊には本来、家を守る意味があること」や「家族の健康を願って植えたこと」など、自分の思いを柔らかく伝えることで、相手の理解を得られる可能性もあります。
それでも価値観の違いが大きい場合には、実際に榊の木が目につきにくい場所に植える、あるいは鉢植えにして持ち運び可能にしておく、といった工夫もおすすめです。フェンスや背の高い植物の陰に隠すように配置するだけでも、見た目の印象はだいぶ変わります。また、剪定をこまめにして枝を広げすぎないようにすれば、近隣からの視線も自然と和らぎます。
こうした配慮を重ねることで、榊を通じてトラブルになることを防ぎ、ご近所との良好な関係を保つことができます。庭づくりは自分だけの楽しみではなく、周囲との調和も含めて考えると、さらに心地よい空間になりますよ。
【PR】タウンライフ
シンボルツリーや庭木で失敗したくない!
外構やエクステリアは人生に何度も買うものではありません。
だから、失敗しがち。
失敗しないためには、複数の見積もりを取ることが大切です。



費用を抑える見積もり取得の裏技があるのでご紹介します。
「商品Aを何割引で買えますか?施工できますか?」
「工事Aの実績は年間何件くらいですか?」
「このサイト(URLを送る)みたいな庭を作りたいのですが、最安商品はいくらで、何割引ですか?」
「この手の工事の実績は年間何件くらいですか?」
上記のように複数の外構業者に見積もり依頼するのが、価格とクオリティを理想に近づけるコツです。
1社だけに依頼すると何十万円〜百万円単位で高くなってしまうことがあります。絶対に複数社に見積もり依頼することをおすすめします。



そうはいっても面倒だなぁ



外構一括見積もりサービス



でも本当に工事するかも決めてないんだけど…



もちろん無料見積もりだけでも大丈夫!



本当にいい工事をしてくれるのかな…?



外構一括見積もりサービス



逆にご自身で選ぶ場合、日本に2万社以上ある外構業社から選ぶことになります。2万社の中には当然、悪徳業者も潜んでいます。ゆえに、我流で選べば悪徳業者に騙される可能性があります。



まだリフォームのアイデアが決まってないんだけど…



予算上限を設定してリフォームのアイデアを複数社から貰えるので、良い提案がもらえると思いますよ!しかも無料で!
タウンライフの外構一括見積もりサービス



しつこい営業電話が来たりしないかな?



私の経験で言うと、営業というか、確認の電話が1回来ました。1分くらいしか話しませんでしたけどね。話の内容は下記の通りです。
相手「はなまるさん、お庭のリフォーム業者はお決まりになりましたか?」
私「いえ、まだ決め切れてなくて…」
相手「そうなんですね。いい業者が見つかるといいですね〜。では。」
上記くらいのかるーい内容で、押し売りはされませんでした。
電話がかかってきた時は、嫌な感じの営業電話かな〜と心臓がドキッとしたのですが、さすが利用満足度No.1のタウンライフの外構一括見積もりサービス!しつこくない感じが好感持てました。



費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
榊 植えてはいけないと言われる理由と対策のまとめ
- 榊はかつて身分の高い家で用いられていたため一般家庭では畏れ多いとされた
- 神棚に供える木であることから神聖すぎて扱いに慎重になるという風習がある
- 神の依り代とされるため「植えると罰が当たる」との言い伝えが残っている
- ヒサカキは強い匂いがあり住宅地ではトラブルの原因になることがある
- 仏事に使われるヒサカキは死を連想させるとして避けられることがある
- 落葉・毒性・トゲがある庭木は事故や管理面でリスクがある
- 榊は虫がつきやすいため定期的な手入れが必要とされる
- 家相では鬼門・裏鬼門に榊を植えると運気を乱すとの見方がある
- 植える位置によっては家全体の気の流れに影響を及ぼすとされる
- 「榊を植えると災いが起こる」という迷信が一部に残っている
- 地域や高齢者の価値観に配慮しないと近隣トラブルになる恐れがある
- 風水的には東や南東が榊に適した方角とされる
- 環境条件を無視して方角だけで植えるのは逆効果になることがある
- 鉢植えは通気性・排水性のある土と場所選びが育成のカギとなる
- 春と秋が植え付けに適しており真夏・真冬は避けた方が無難である
シンボルツリー
- おすすめ樹木
- おすすめ常緑樹
- おすすめしない木
- 虫がつかない木
- シンボルツリーの代わり
- ハイノキで後悔する理由
- フェイジョアで後悔する理由
- オリーブで後悔する理由
- ミモザで後悔する理由
- ユーカリで後悔する理由
- アオダモで後悔する理由
- ソヨゴで後悔する理由
- レモンで後悔する理由
- ヤマボウシ
- 建売の木を抜く
- シンボルツリーの足元に石
鑑賞用
- トクサを庭に植えてはいけない理由とは?根絶が難しく縁起が悪いから
- ブラシの木を庭に植えてはいけない理由とは?後悔は大きくなりすぎること
- チェリーセージを植えてはいけない理由を徹底解説!放置して剪定しないと大変なことに
- 笹を庭に植えてはいけない理由は根絶が難しいから!植物界最強とも
- ミソハギを庭に植えてはいけない理由!花言葉や縁起が気になる
- シンバラリアを庭に植えてはいけない理由を徹底解説!耐寒温度つよく冬越しできるグランドカバー
- ユキヤナギを庭に植えてはいけない理由は縁起と手入れの大変さ以外にも
- 鬼門に植えてはいけない木を一挙紹介!裏鬼門に植える植物も紹介
- 【後悔】紅葉を庭に植えてはいけない理由とは!?シンボルツリーにすると落ち葉がひどい
- ホワイトセージを庭に植えてはいけない理由!?木質化すると香りが失われる
- ソテツを庭に植えてはいけない!?縁起が悪いや風水的に幸運が来ない?
- パンパスグラスは庭に植えてはいけない理由!?鉢植えや風水について
- ビオララブラドリカを庭に植えてはいけない理由を徹底紹介!
野菜・果物

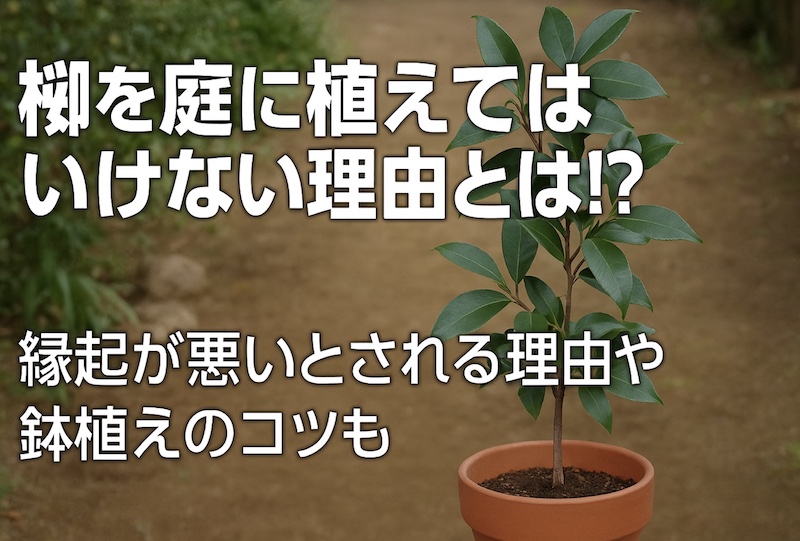

コメント