セキスイハイムで家を建てる際、棟上げの日にどのような差し入れを用意すればよいか悩む方は多いのではないでしょうか。「セキスイハイム 棟上げ 差し入れ」と検索している方に向けて、この記事では実際の現場に即した差し入れの基本を丁寧に解説しています。
棟上げの差し入れの相場はいくらですか?という疑問から、棟上げの差し入れに何がいいですか?という具体的な内容まで、実体験や事例をもとに紹介。
そもそも上棟式に差し入れをするべきか?という悩みに対しても、形式にとらわれず心のこもった対応のポイントを押さえています。
ご祝儀やお弁当を用意すべきかどうか、据付差し入れのタイミング、据付後の追加配慮など、現場の雰囲気を損ねないためのマナーや工夫も満載です。
また、雨の影響による据付延期の判断基準や、ハウスメーカーで上棟式の差し入れはしてもらえますか?といった質問への実用的な答えも取り上げています。
さらに、タイムラプス撮影で棟上げの様子を記録する方法や、地鎮祭との違いとつながりも解説しており、家づくり全体を見通した参考情報として役立ちます。
 著者
著者これから棟上げを迎える施主の方にとって、この記事が安心して準備を進めるためのガイドとなれば幸いです。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 差し入れの相場 | 1,000円〜3,000円が目安。職人の人数に応じて調整 |
| おすすめの差し入れ | ペットボトル飲料・個包装のお菓子・ゼリー飲料・塩飴など |
| タイミング | 午前10時と午後3時の休憩時間に渡すのがベスト |
| 差し入れの方法 | 現場監督に預けて配ってもらうのが安全でスムーズ |
| ご祝儀は必要か | 基本的に不要。贈る場合は商品券や名産品などが無難 |
| お弁当の用意 | 感染症対策や効率化の観点から控える傾向。事前に相談を |
| 雨天時の対応 | 現場監督の判断を仰ぐ。延期の場合は再調整が困難な場合も |
| 据付延期のリスク | 次回の施工が1か月以上遅れることもある |
| タイムラプス撮影 | 棟上げの様子を記録できるおすすめの方法。家族の記録にも |
| 据付後の対応 | 差し入れや感謝の言葉を後日に伝えるのも効果的 |
| 上棟式の有無 | 行わない家庭も多いが、差し入れで感謝を伝えると好印象 |
| ハウスメーカーの対応 | 基本的に施主判断。アドバイスは受けられる |
| 地鎮祭との違い | 地鎮祭は安全祈願、棟上げは作業への感謝を表す行事 |
| 相談のコツ | 現場監督に具体的な人数や時間を確認するのがポイント |



10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
セキスイハイム棟上げ差し入れの基本
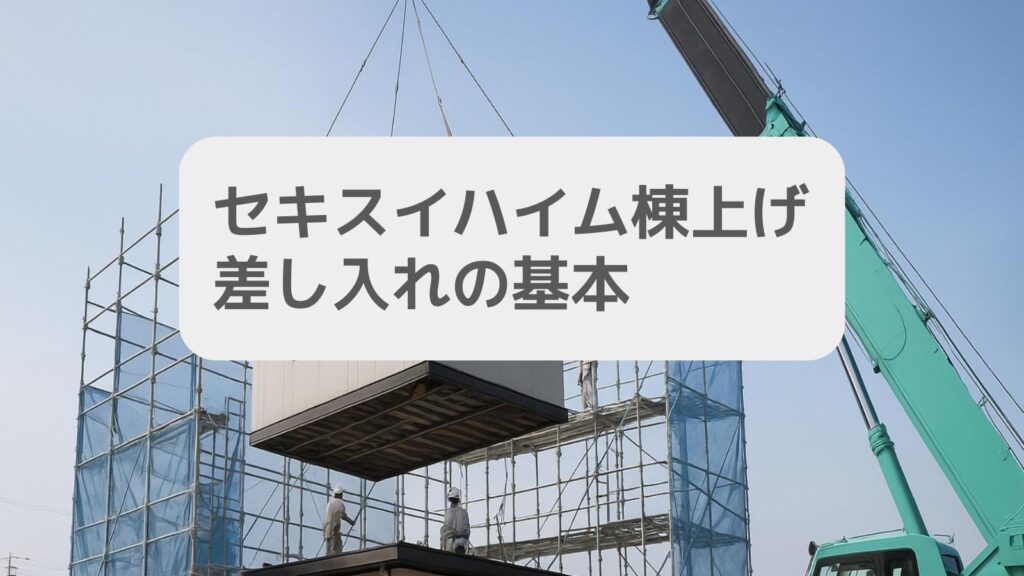
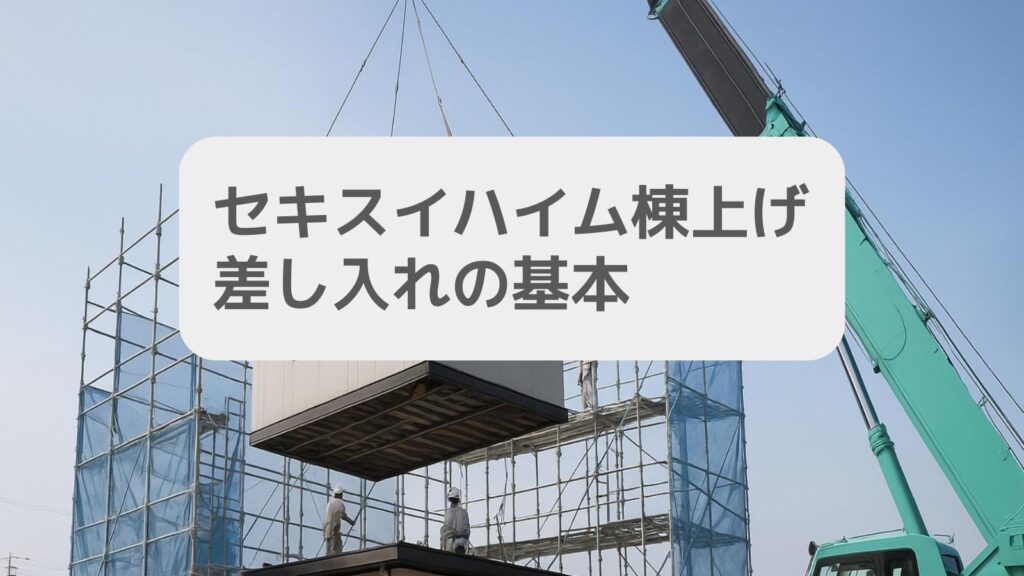
- 棟上げの差し入れの相場はいくらですか?
- 棟上げの差し入れに何がいいですか?
- 上棟式に差し入れをするべきか?
- ハウスメーカーで上棟式の差し入れはしてもらえますか?
- ご祝儀は必要?適切なタイミングと金額
- お弁当の準備は必要か?現場の実情とは
棟上げの差し入れの相場はいくらですか?
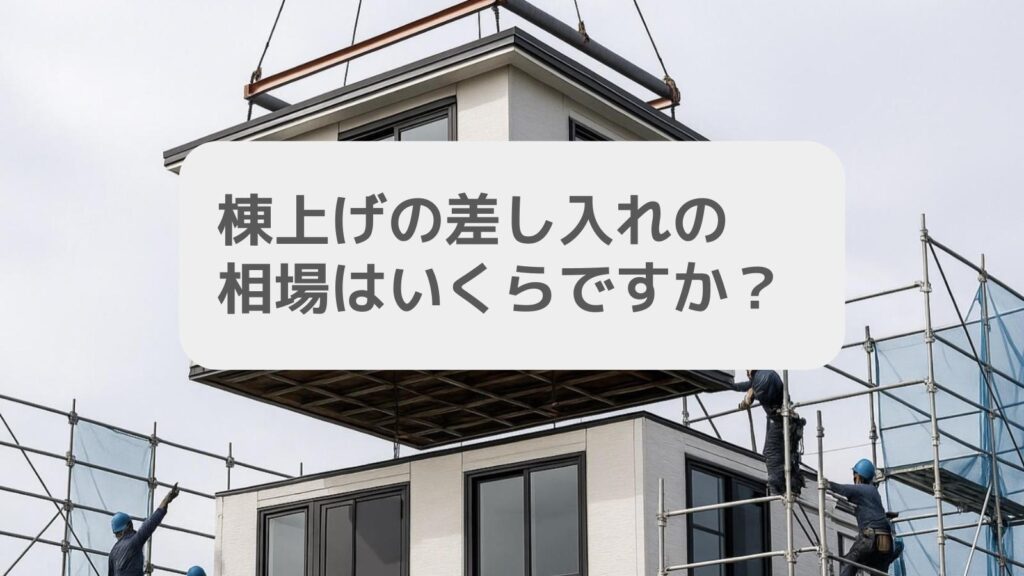
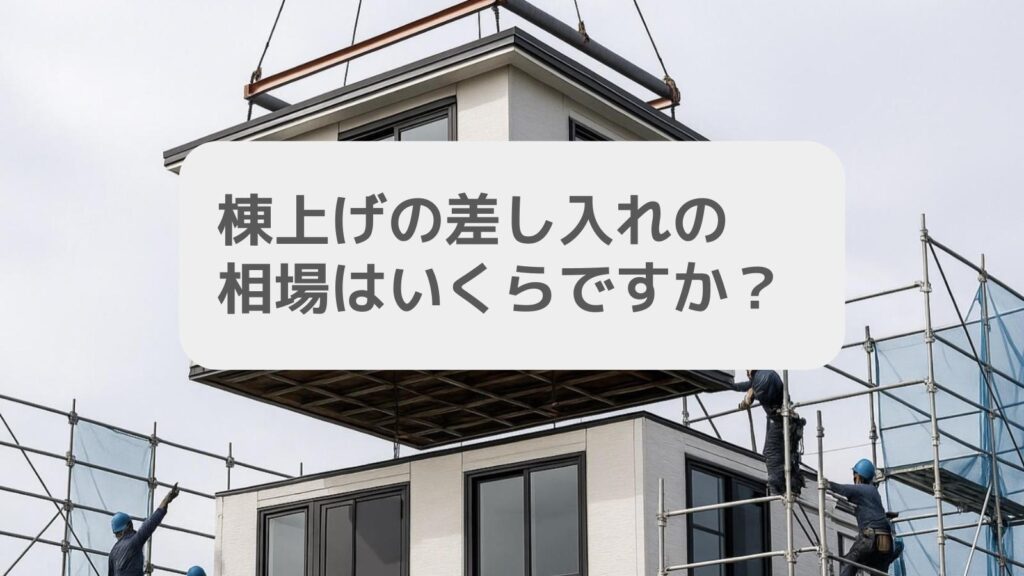
棟上げの差し入れにかける金額の相場は、だいたい1,000円〜3,000円程度が目安とされています。
この金額帯が多く選ばれているのは、作業してくださる職人さんたちに感謝の気持ちを表しつつも、施主側の負担が過度にならないバランスが取れているからです。あまりにも高額になると、かえって相手も受け取りづらくなるケースもあるため、ちょうど良い金額を考えることが大切です。
例えば、ペットボトルのお茶(500ml)を20本と、個包装のお菓子を人数分用意したとしましょう。それだけであっても3,000円ほどで十分に揃えることができます。



手が汚れたままでも食べやすい個包装が喜ばれます。ハッピーターンは甘さもしょっぱさもあり、ウケが良いです。
一方、作業人数が増えるケースでは金額も比例して膨らみます。特にクレーン車のオペレーターや運送トラックの運転手、現場監督、補助スタッフなどが含まれる場合には、用意すべき数も多くなる傾向があります。
このため、差し入れの予算を決める前に、「実際に何人が現場に来るのか?」を営業担当者や現場監督にあらかじめ確認しておくと、無駄もなく、安心して準備できますよ。
さらに、時期によっては冷たい飲み物や温かいものなど、差し入れの内容にも変化を持たせたほうが好印象です。金額だけでなく、中身も季節や時間帯を考慮して選ぶようにしましょう。
このように、1,000〜3,000円という目安を基本にしつつ、現場の状況に合わせて柔軟に対応することがポイントです。
棟上げの差し入れに何がいいですか?
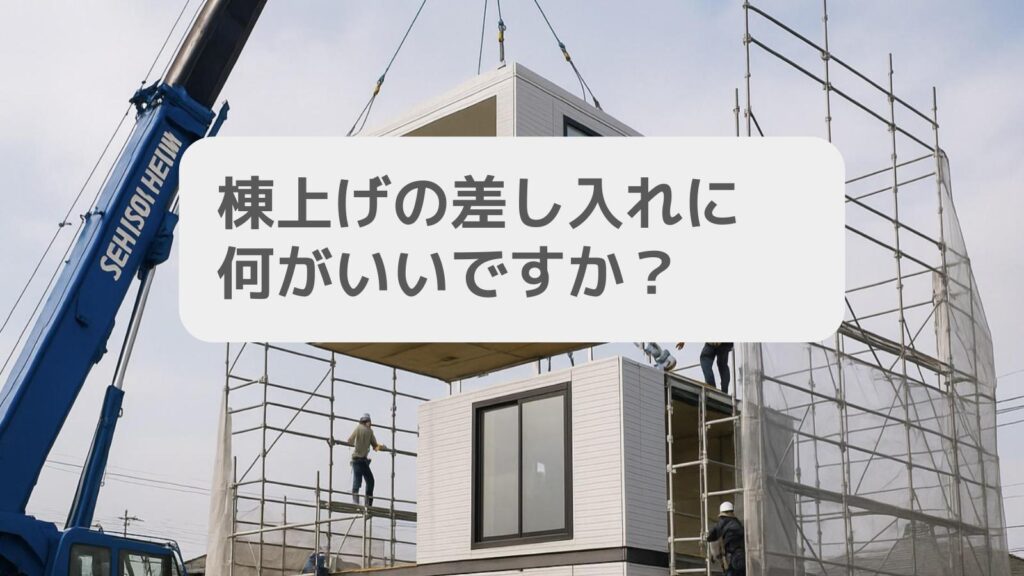
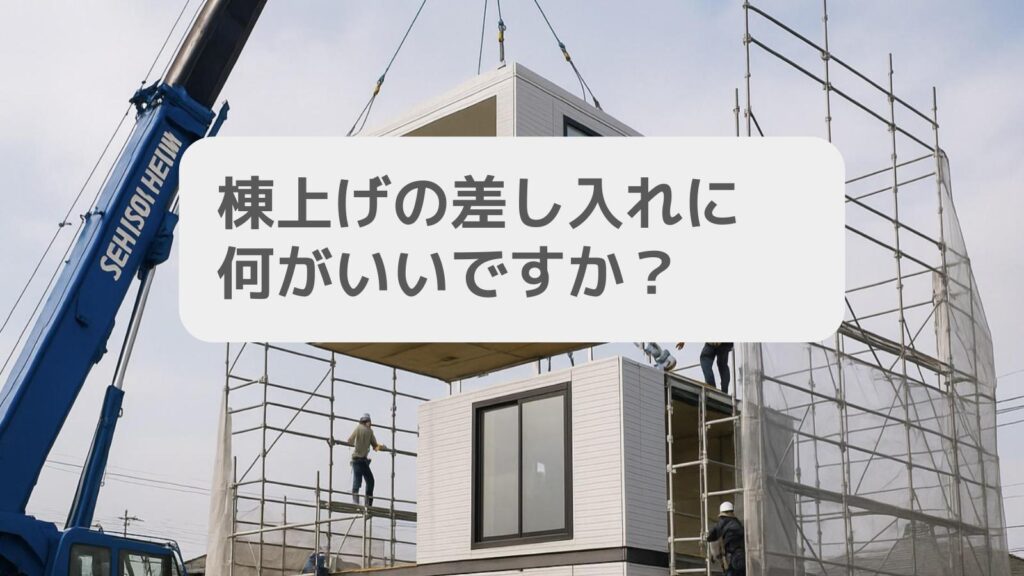
差し入れに適したものとしては、手軽に食べられて、衛生的なものが喜ばれます。特に作業中でもサッと口にできるものや、食べこぼしの心配が少ないものが選ばれる傾向にあります。
その理由は、棟上げの現場では作業が詰まっていることが多く、ゆっくり休憩できる時間が限られているためです。作業員の方々にとって、手間がかからず、すぐにエネルギー補給できる軽食や飲み物がありがたいんです。
例えば、ペットボトル飲料(500ml)は定番で、冷たいお茶やスポーツドリンク、季節によっては温かい缶のお茶やコーヒーも人気です。缶コーヒーにはブラックや微糖など味のバリエーションを持たせておくと喜ばれます。ゼリー飲料やエネルギーバーのような軽食も、動きながらでも摂取できるので非常に便利です。
個包装のお菓子も喜ばれる定番アイテムです。クッキー、チョコレートバー、ミニサイズのドーナツなどは、甘いものが好きな作業員さんにとって嬉しい差し入れになります。甘さ控えめのものやナッツ類を加えてバリエーションをつけるのもおすすめです。
私は以前、7月の暑い日だったのでスポーツドリンクと塩飴をセットにして配ったことがあります。熱中症対策にもなりますし、「こういうの助かる!」という声もいただきました。
そのときは保冷バッグに入れて持っていったのですが、冷たい状態で渡せたことも好印象だったようです。
このように考えると、季節や気温、作業環境を意識した差し入れを選ぶことが大切です。特に夏場なら冷たいもの、冬場なら温かいものと、時期に応じた対応をすると、より相手に感謝の気持ちが伝わりますし、現場の空気も和やかになりますよ。
上棟式に差し入れをするべきか?
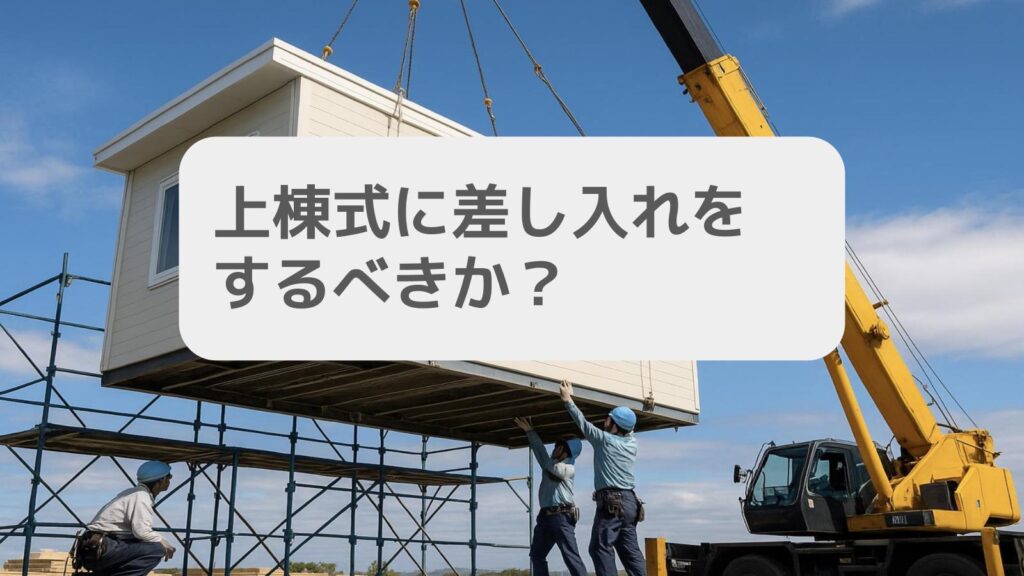
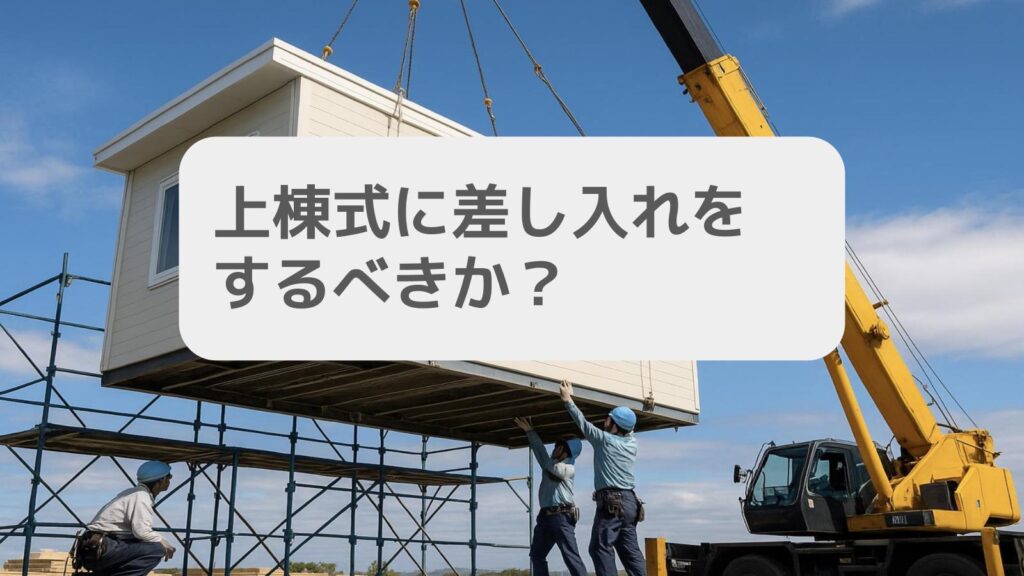
上棟式を行わない場合でも、差し入れはしておくと良いでしょう。
その理由は、上棟という大きな節目の作業を担ってくれる職人さんたちに対して、感謝を伝える絶好の機会になるからです。普段は直接関わることのない方々とも、この場を通じて少しだけでも交流ができるのは、施主としても良い経験になります。
実際、セキスイハイムのようなプレハブ工法では、従来のような神事としての上棟式を行わず、シンプルに棟上げ作業だけで済ませる家庭が多くなっています。工期や費用、宗教的な考え方の違いもあり、無理に式を挙げない選択をする方が増えているのです。
ただし、その中でも「式は省略するけれど、差し入れは用意する」というケースは今も多く、ちょっとしたお菓子や飲み物を現場に届けて感謝を伝える方が多い印象です。施主としても無理なく準備できる内容なので、初めての方でも安心して取り組めます。
私の知人の中には、午前中と午後の休憩タイミングにそれぞれ異なる内容の差し入れを準備した方もいました。例えば、午前は甘めのお菓子とコーヒー、午後は冷たいドリンクと塩分補給になるスナックを用意するなど、さりげない気遣いに職人さんも感動していたそうです。
このように言うと少し大げさに聞こえるかもしれませんが、ほんの少しの心遣いが現場の雰囲気をパッと明るくしてくれることは間違いありません。
差し入れは「気持ちを届ける手段のひとつ」と考えて、自分たちのペースで無理なく準備してみてくださいね。
ハウスメーカーで上棟式の差し入れはしてもらえますか?
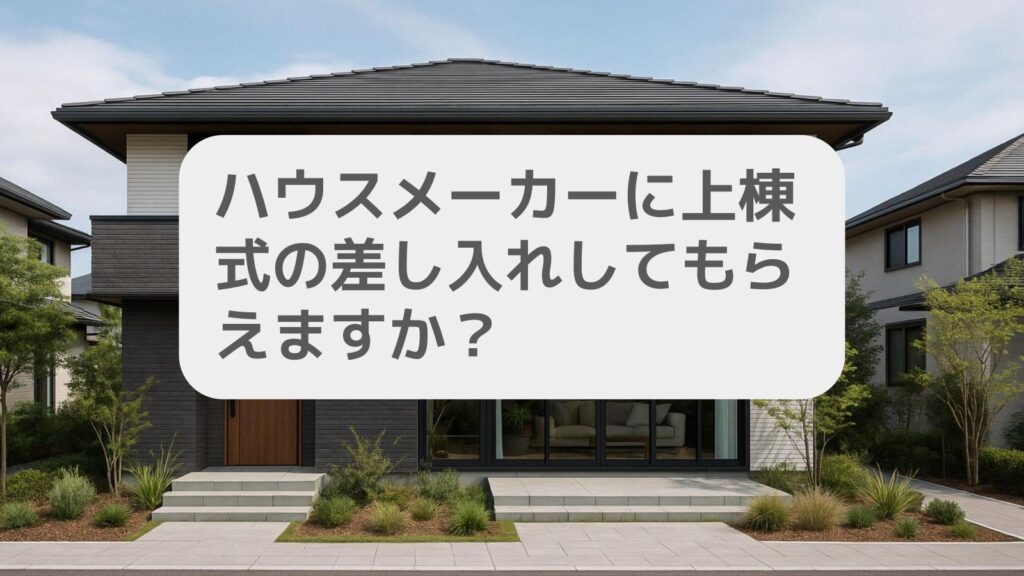
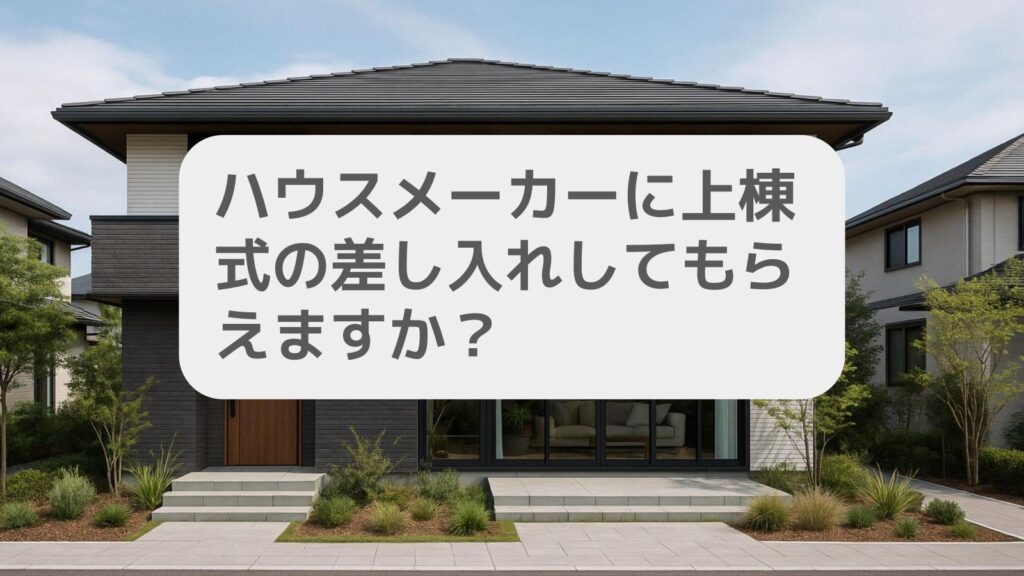
基本的に、ハウスメーカーが上棟式の差し入れを用意してくれることはあまりありません。
その理由は、上棟式や差し入れといった行為は、あくまでも施主の「お気持ち」として任意で行うものであり、ハウスメーカーが提供する標準的なサービスの範囲外とされているからです。そのため、メーカー側が差し入れの手配を代行するというケースは非常にまれです。
ただし、完全にノータッチというわけではなく、担当営業や現場監督がアドバイスやサポートをしてくれることは多くあります。例えば、「差し入れを渡すなら午前10時頃の休憩時間がベストです」といった具体的なタイミングを教えてくれたり、「当日は作業員が20名ほど来ますよ」と人数の目安を知らせてくれたりするので、準備の参考になります。
また、作業中に直接職人さんに話しかけにくいという場合でも、現場監督が差し入れの受け取りや配布を代行してくれることが多いです。実際、「皆さんでどうぞ」と一言添えて監督にお渡しすれば、全員にきちんと行き渡るよう配慮してくれます。
私の知人も、初めての棟上げで不安が多かったそうですが、営業担当の丁寧なアドバイスと現場監督の手厚いフォローのおかげで、当日はとてもスムーズに差し入れを届けられたと言っていました。
このように、差し入れの用意や実施そのものは施主が行う必要がありますが、ハウスメーカーのスタッフと協力しながら準備を進めることで、無理なく円滑に対応できるケースがほとんどです。
気になる点があれば、遠慮なく担当者に相談してみましょう。それだけでも、当日の安心感がぐっと増しますよ。
ご祝儀は必要?適切なタイミングと金額


セキスイハイムのようなハウスメーカーで家を建てる場合、ご祝儀に関しては基本的に不要とされています。
その理由は、職人さんたちが会社に雇われている立場にあるため、個人的にお金を受け取ることが社内ルールやコンプライアンスの面で問題になる可能性があるからです。もし、善意で渡したとしても受け取りを断られるケースもあり、トラブルの火種になりかねません。
ただし、地域性や昔ながらの慣習を重んじる方の中には、気持ちとして少額のご祝儀を用意する方もいます。このような場合、現金を直接手渡すのではなく、1,000円〜3,000円程度のQUOカードや商品券、または日持ちするお菓子などを添えて「感謝の気持ちです」と一言伝える程度が無難です。
一方で、現金を包んでしまうと、受け取りを辞退されるだけでなく、現場での空気が気まずくなることもあります。特に大勢の前で渡すような場面は避け、どうしても何かを渡したい場合は控えめに、そして個別にそっと渡すようにしましょう。
私の場合は、どうしても気持ちを伝えたかったので、地域の名産品を箱詰めにして差し入れとしてお渡ししました。食べ物なら作業後に皆さんで分けて楽しんでもらえますし、現金のような扱いの難しさもなく、喜ばれることが多いと感じています。
このように、ご祝儀は無理に用意する必要はありませんが、もし何か贈りたいという気持ちがあるなら、金銭以外の方法で感謝を表す工夫をしてみるのも良いでしょう。
いずれにしても、判断に迷ったときは担当の営業さんに一度相談するのが安心です。現場のルールや雰囲気に合った対応方法を教えてもらえるはずですよ。
お弁当の準備は必要か?現場の実情とは
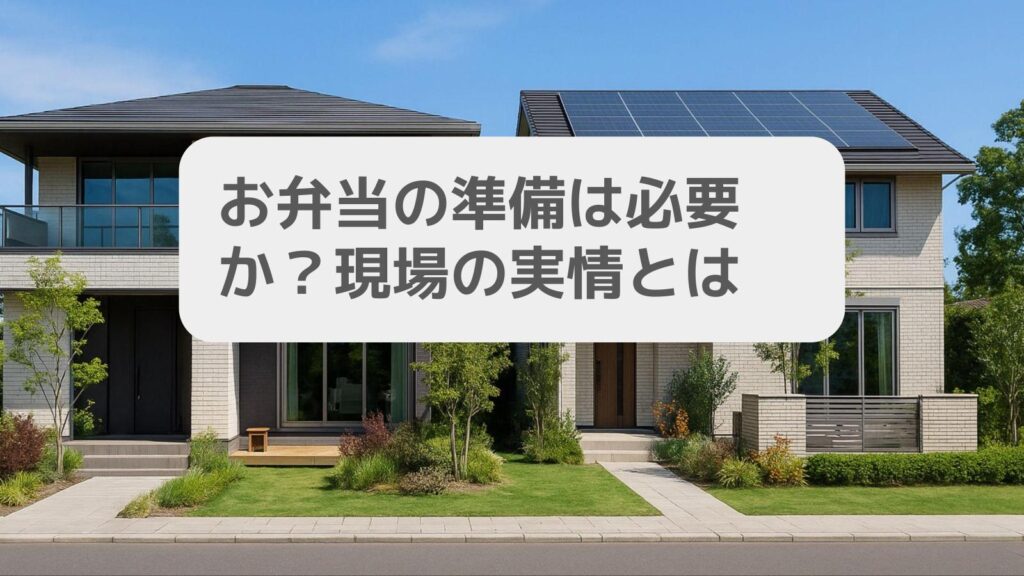
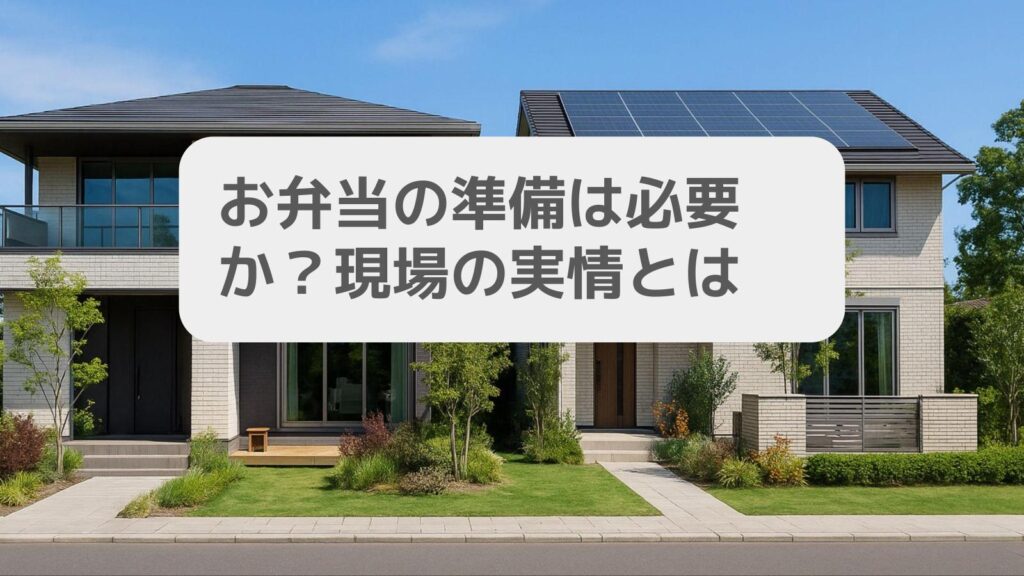
お弁当の差し入れについては、地域性や季節、またハウスメーカーごとの慣習によって対応が分かれるため、一概には言えません。
ただし、最近では感染症対策の観点や、現場の効率化を重視する傾向が強まっており、お弁当の差し入れ自体を控えるという流れが主流になりつつあります。特にコロナ禍以降は、外部からの食事提供に対して慎重な姿勢をとる現場も増えています。
それでも「何かしら用意したい」「お弁当で感謝を伝えたい」というお気持ちがある場合は、まずは現場監督に一度相談してみましょう。現場のルールや状況に応じて、受け入れ可能かどうか、どんな形式で渡すのが良いかなど、具体的なアドバイスをもらえるはずです。
例えば、お弁当を直接手渡しするのではなく、作業の合間に職人さんが自由に取れるように、保冷バッグやクーラーボックスにまとめて設置する方法があります。このようにすれば、衛生面も配慮できますし、作業を中断することなく差し入れができます。
また、お弁当の中身にも工夫を加えると好印象です。おにぎりとから揚げなど定番のメニューに加えて、個包装のウェットティッシュや紙ナプキンを添えておくと喜ばれます。さらに、食後に飲める温かいお茶やコーヒーを一緒に用意しておくと、より気遣いが伝わります。
このように考えると、必ずしもお弁当でなければならないわけではありません。現場の実情や時代の流れを踏まえた上で、飲み物や軽食、個包装のお菓子などでも、十分に感謝の気持ちは伝わりますし、職人さんたちにも無理なく受け取っていただけます。
結果として、負担にならない範囲で、現場の空気を和ませるような差し入れを工夫することが、最も大切なのではないでしょうか。
セキスイハイム棟上げ当日の注意点
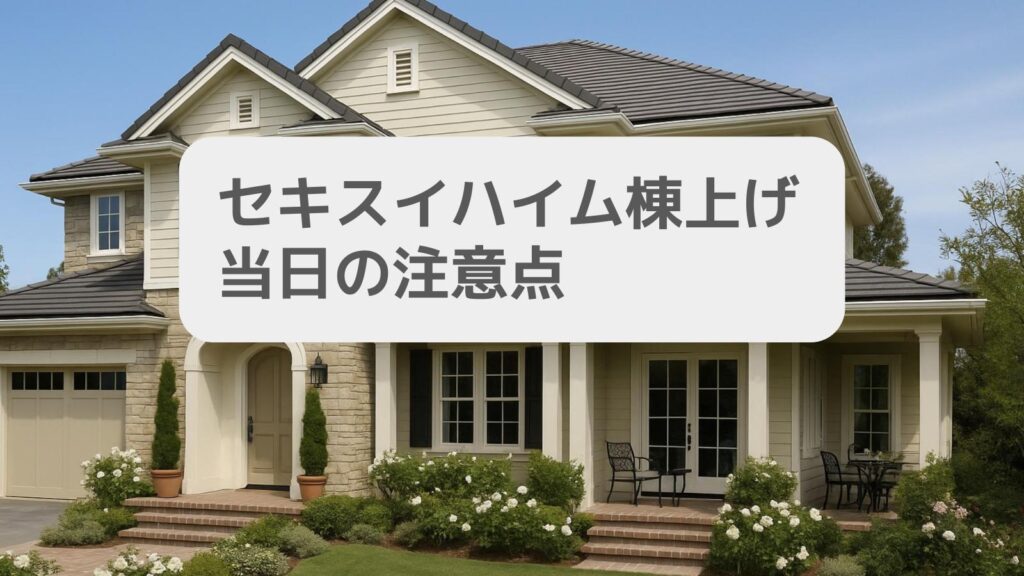
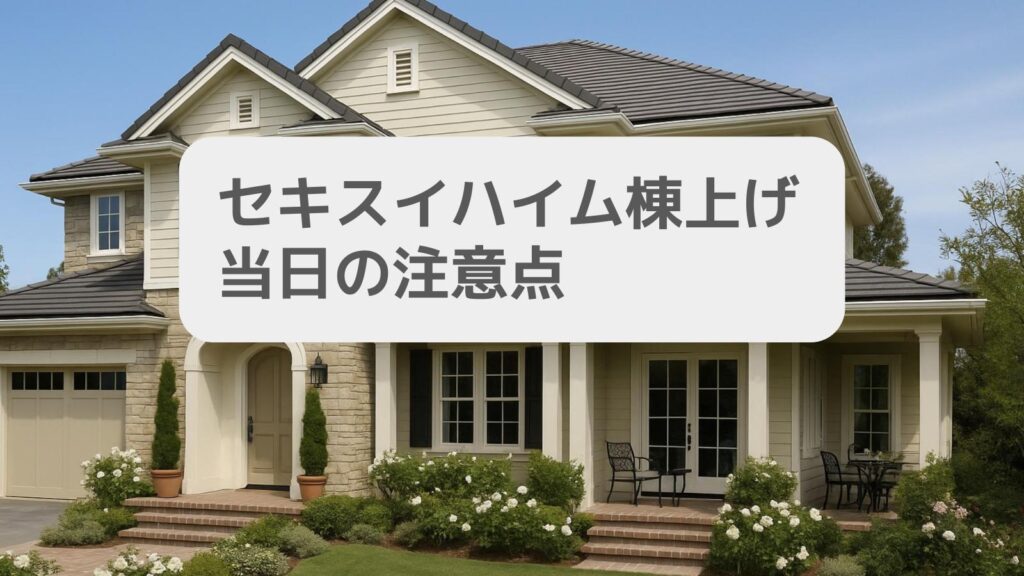
- 雨の日はどうする?据付延期の判断基準
- 据付差し入れのタイミングと方法
- タイムラプスで記録する棟上げの流れ
- 据付後の差し入れやフォローは必要?
- 地鎮祭との違いとつながり
- 迷ったときの現場監督との相談ポイント
雨の日はどうする?据付延期の判断基準
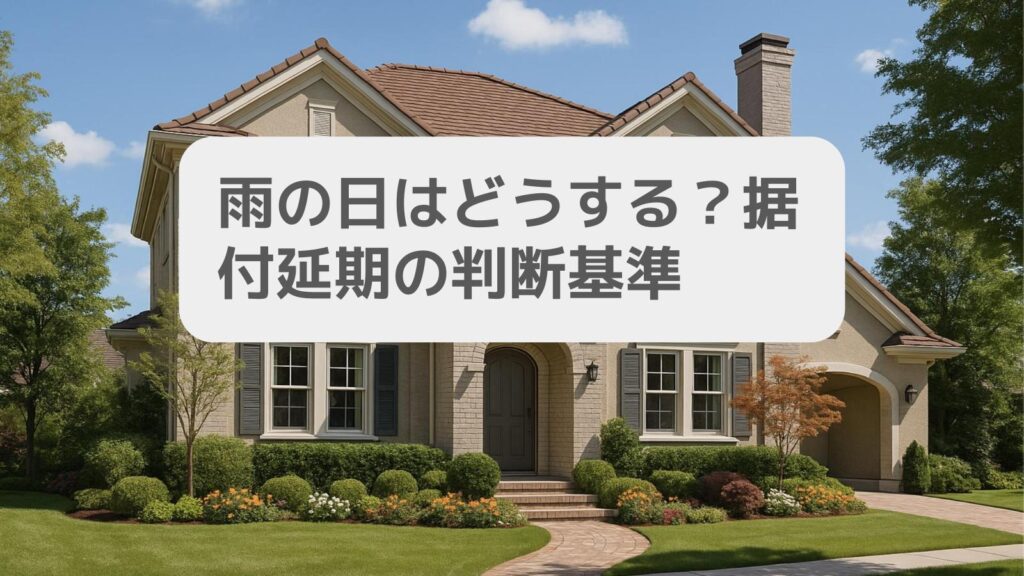
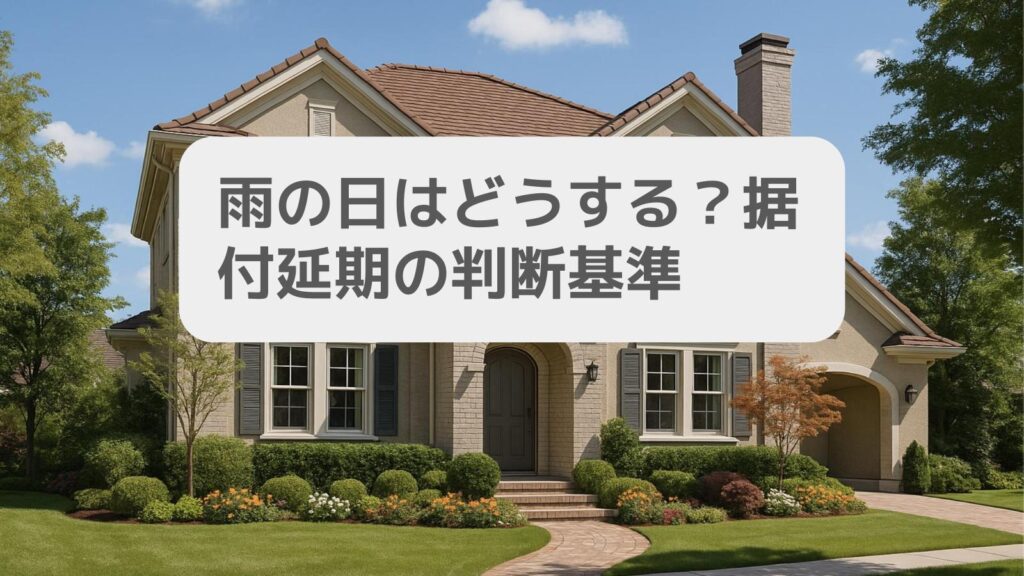
棟上げ当日が雨予報の場合、施工を強行するか、それとも延期するかは非常に迷う判断になりますよね。
その理由のひとつとして、セキスイハイムのユニット工法は、工場で完成されたユニットを一気に運び込み、その日のうちに棟上げ作業を行うスケジュールで進行します。したがって、日程変更が発生すると、そのユニットを運搬するためのトラックやクレーン車の再手配が必要になるため、次回の施工日が1か月以上先になる可能性もあるのです。
また、他の現場との兼ね合いもあり、工事全体のスケジュールに遅れが生じてしまうケースも珍しくありません。そのため、施主としても「できれば延期は避けたい」という気持ちになるのは自然なことです。
とはいえ、多少の小雨であれば棟上げ作業をそのまま続行するという選択を取る現場もあります。ただし、この場合に注意したいのが、まだ屋根がついていない状態でユニットの内部が露出する時間帯があるという点です。もしこのタイミングで雨脚が強くなれば、断熱材や石膏ボードといった内部構造が濡れてしまうリスクが高まります。
こうした事情を踏まえると、最終的な判断はやはり現場監督に相談するのがもっとも安心です。監督は最新の天気予報や施工チームの動き、現場の準備状況を総合的に判断して、「この程度ならいける」「延期したほうがいい」と的確なアドバイスをくれるでしょう。
それでも不安がある方は、万が一雨に降られた場合の対応策についても事前に確認しておくことをおすすめします。具体的には、濡れた箇所をしっかり乾燥させるためのジェットヒーターの使用や、断熱材・石膏ボードの交換手配が可能かどうかなど、確認しておくと安心です。
さらに、施工後に現場を見学し、濡れた箇所がないか自分の目でチェックすることも重要です。不安な場合は写真を撮って記録を残したり、必要に応じて再施工のお願いをすることも可能です。
このように、雨天による棟上げの判断は慎重を要しますが、しっかりと現場と連携を取ることで、安心して家づくりを進めることができますよ。
据付差し入れのタイミングと方法
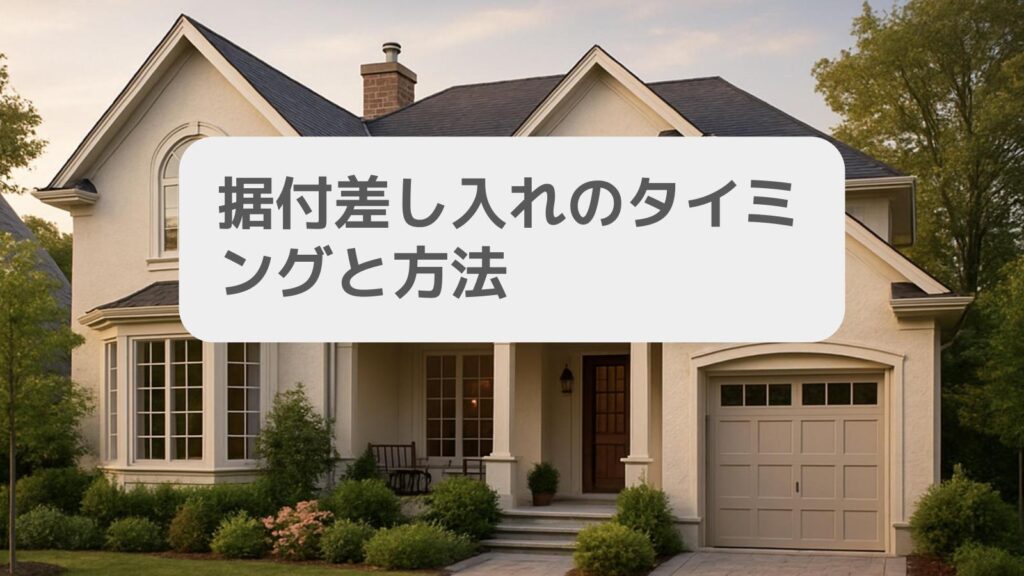
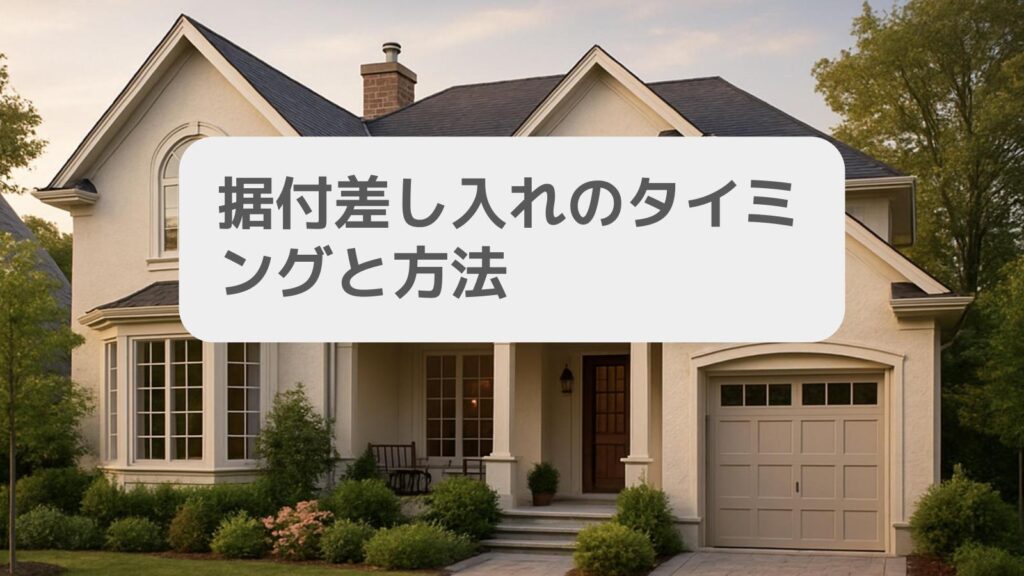
据付(棟上げ)の差し入れは、一般的に午前10時頃と午後3時頃の休憩時間に渡すのが最も自然なタイミングとされています。
この時間帯をおすすめする理由は、作業中は大型の重機が稼働していたり、資材の運搬や設置作業が行われていたりするため、職人さんに直接声をかけることが難しく、また安全面でも支障が出る可能性があるからです。特にセキスイハイムのようなユニット据付工法では、大型クレーンが使われることが多く、作業区域内への立ち入りは制限されていることもあります。
そのため、事前に差し入れを用意しておき、適切なタイミングで現場監督に「皆さんで召し上がってください」と一言添えて預けるのがスマートです。現場監督は現場の進行や職人さんの動きを把握しているため、最適なタイミングで渡してくれるでしょう。
また、差し入れの中身にも少し工夫を加えると、さらに気持ちが伝わります。例えば、冷たい飲み物に加えて塩分補給になるタブレットや、夏場なら保冷剤を添えておく、冬場であれば温かい飲み物を保温バッグに入れるなどの気配りはとても喜ばれます。
さらに、差し入れをまとめて入れる袋や箱に「本日はありがとうございます。暑い中お疲れ様です」といった一言メモを添えるだけでも、施主の気遣いが伝わりやすくなります。大切なのは「何を渡すか」だけでなく「どのように渡すか」も含めて配慮することです。
このように、差し入れのタイミングを見計らうことはもちろんですが、その背景にある「感謝の気持ちがきちんと伝わるかどうか」を意識して行動することが、より良いコミュニケーションにつながるのではないでしょうか。
タイムラプスで記録する棟上げの流れ
棟上げの様子を記録するなら、タイムラプス撮影がとてもおすすめです。とくにセキスイハイムのようなユニット工法では、建物が一気に組み上がっていく様子は圧巻で、ぜひ記録しておきたい瞬間のひとつです。
その理由は、1日がかりの据付作業を短時間の動画で一望できる点にあります。通常は朝から夕方までかかる作業ですが、タイムラプスにすればわずか数分の映像で流れを把握でき、家づくりの過程を印象的に振り返ることができます。また、お子さんがいるご家庭では「この家がこうやって建ったんだよ」と、将来的に見せてあげる思い出資料としても活用できます。
撮影の準備は意外と簡単です。最近のスマートフォンにはタイムラプス機能が標準装備されている機種も多く、専用のアプリを使えばより細かな設定も可能です。もちろん、GoProやDJI Pocketなどのアクションカメラを使えば、より安定した画質と撮影が実現できます。
私であれば、まず三脚をしっかりと固定し、撮影位置はベランダや窓越し、あるいは庭の片隅から据付の様子がよく見えるポイントを選びます。長時間の撮影になるため、モバイルバッテリーも必須アイテムですね。風の強い日などはカメラが倒れないように、重りや固定用テープを使うと安心です。
さらに、撮影中に雨が降ることもあるので、カメラが濡れないようビニールカバーをかけるなどの対策も忘れずに。撮影中はできるだけカメラに触れず、開始から終了までを一気に記録するのが成功のコツです。
このようにすれば、現場の邪魔をせずに、安全な距離を保ちながら棟上げ作業の一部始終を美しく記録できます。家族で動画を見返す時間も、完成した住まいの価値をさらに高めてくれるはずですよ。
据付後の差し入れやフォローは必要?
棟上げの後でも、簡単な差し入れやお礼をすると、職人さんたちのモチベーションにつながります。
ただ単に義務としてではなく、感謝の気持ちを形にする良いタイミングだからです。
例えば、冷えた飲み物やお菓子、ちょっとしたメモなどを現場監督に預けるのも良い方法です。
また、数日後に現場を見に行った際に「ありがとうございました」と直接声をかけるだけでも、印象がぐっと良くなります。
このように、据付が終わっても関係は続くので、小さな気遣いが大切なんですね。
地鎮祭との違いとつながり
地鎮祭と棟上げ(据付)は、家づくりにおける重要な節目であることに変わりはありませんが、それぞれが持つ意味や目的には明確な違いがあります。
まず、地鎮祭は家を建てる前にその土地を清め、工事の安全と無事を祈願する神事です。神主さんをお招きし、土地の神様にご挨拶をするという宗教的な儀式であり、施主や施工会社、関係者が参加して気持ちを一つにする場でもあります。地域によっては非常に重視されており、昔ながらの慣習として受け継がれています。
一方、棟上げ(または上棟)は、建物の骨組みが完成した段階で行う行事で、完成に向けた一区切りとしての意味合いを持ちます。こちらは神事というよりも、作業に携わってきた大工さんや職人さんたちに対する感謝を示すイベントです。近年では簡略化される傾向にありますが、それでも差し入れやねぎらいの言葉をかけるなど、施主として気持ちを伝える文化は根強く残っています。
ただし、共通しているのは「感謝」や「お礼」の気持ちを表す大切な場であるという点です。地鎮祭では神主さんへのお供え物を通じて、棟上げでは職人さんへの差し入れを通じて、それぞれの立場の方々への敬意を表します。このように、それぞれの儀式には異なる役割がありますが、どちらも人と人とのつながりを大切にするという意味では通じ合う部分があるのです。
また、家づくりに関わるすべての人たちに対して「この家をよろしくお願いします」「ありがとうございます」と伝える機会があるというのは、とても貴重なことです。忙しい中でも、こうした節目を丁寧に迎えることで、家づくり全体に対する満足度や愛着も高まります。
このように考えると、地鎮祭と棟上げはそれぞれの意味を理解したうえで、可能な範囲でしっかりと行い、関係者への感謝の気持ちを伝える機会として大切にしていきたい行事だと言えるでしょう。
迷ったときの現場監督との相談ポイント
差し入れの内容やタイミングについて迷ったときは、やはり現場監督に相談するのが最も確実で安心な方法です。
その理由は、監督が現場の状況を把握している立場にあるからです。作業員の人数や作業スケジュール、休憩のタイミングなど、現場の細かな流れを一番理解しているのは現場監督です。だからこそ、最適な差し入れ内容や渡すタイミングを提案してくれる存在として、とても心強い味方になります。
例えば、「差し入れは何人分くらいがちょうど良いですか?」と尋ねれば、正確な人数に応じた準備ができるため、無駄が出ませんし不足することもありません。また、「甘いものとしょっぱいもの、どちらが喜ばれますか?」とか「冷たい飲み物は何が人気ですか?」など、より踏み込んだ質問をすることで、差し入れの内容をより実用的に調整できます。
さらに、差し入れのタイミングについても相談すれば、「午前中の休憩時間が10時頃で、そのときに渡すのがスムーズですよ」とか、「午後は15時頃がちょうどいいですね」といった具体的なアドバイスがもらえるので、安心して準備を進められます。
一方で、「これくらいで足りますか?」といった曖昧な質問だと、監督側も判断しづらく、答えがぼんやりしてしまうことがあります。ですので、相談する際にはなるべく具体的な項目や数字を挙げて聞くようにすると、お互いのやり取りもスムーズになります。
また、差し入れの相談をすること自体が、監督との信頼関係を築くひとつのきっかけにもなります。「ちゃんと考えてくれてるんだな」と思ってもらえることで、今後の対応もより丁寧になったり、相談しやすい雰囲気が生まれることもあります。
このように、差し入れを有意義なものにするためにも、事前に現場監督との密なコミュニケーションを心がけておくことはとても重要です。小さなことでも一度相談しておくことで、全体の流れがスムーズになり、現場の雰囲気もより良いものになるでしょう。
セキスイハイム 棟上げ 差し入れのポイント総まとめ
- 差し入れの相場は1,000〜3,000円程度が目安
- 個包装の飲食物が手軽で好まれる
- 夏は冷たい飲み物、冬は温かい飲み物が喜ばれる
- 差し入れは10時と15時の休憩時間が最適
- 作業員数は事前に現場監督に確認するのが確実
- 甘いものとしょっぱいものをバランスよく用意すると良い
- 保冷バッグや保温ケースの活用で品質保持が可能
- 上棟式を行わなくても差し入れだけで感謝は伝えられる
- ご祝儀は基本不要、贈るなら商品券や名産品が無難
- ハウスメーカーは差し入れの用意はせず施主の判断に任せている
- 雨天時の据付延期は現場監督の判断を仰ぐのが安心
- 雨に備えた対応策を事前に確認しておくと心強い
- 据付後の追加差し入れや挨拶も印象を良くするポイント
- 地鎮祭と棟上げは目的が異なるがいずれも感謝を伝える節目
- 現場監督への具体的な相談が差し入れ成功のカギとなる






コメント