春になると一面に咲き誇る黄色い花、菜の花。可愛らしくてつい庭に植えてみたくなる存在ですが、「菜の花 庭に植えてはいけない」と検索してたどり着いた方は、その管理の難しさや思わぬトラブルに不安を感じているのではないでしょうか。
実際、菜の花は地植えにすると勝手に増える、害虫がつきやすい、こぼれ種がばらまかれて管理が大変になるなど、庭に植えるには多くのデメリットを抱えた植物です。
本記事では、庭に植えてはいけないランキングにも登場する菜の花の注意点や「菜の花は雑草ですか?」と聞かれる理由、ばらまきで広がりすぎるリスクなどを詳しく解説します。また、種まき時期としてよく検討される種まき3月と種まき11月、それぞれの違いや育て方のコツもあわせて紹介します。
さらに、菜の花をどうしても育てたい方に向けては、植える理由を踏まえた上でプランターでの管理方法や代替植物の提案まで含めて丁寧にまとめました。初めての方にもわかりやすく、失敗しないための情報をお届けします。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 虫のリスク | アブラムシやアオムシがつきやすく、他の植物にも被害が広がりやすい |
| 繁殖力 | 勝手に増えるため管理が難しく、庭全体に広がる恐れがある |
| こぼれ種の影響 | ばらまきによって意図しない場所で発芽する可能性がある |
| 地植えのデメリット | 根が広がり抜きにくく、虫や連作障害の問題もある |
| 菜の花は雑草ですか? | 放置すると雑草のように見えるほど広がりやすい |
| 外への影響 | 風で隣家や公共の敷地にまで種が飛ぶことがある |
| 見た目の問題 | 開花時以外は緑だけで、景観が単調になりやすい |
| 手入れの手間 | 花がら摘みや間引きなどの作業が多く初心者には不向き |
| 種まき時期 | 種まき3月と種まき11月で開花時期や株の育ち方が異なる |
| 庭での扱いやすさ | 庭に植えるならプランターでの栽培がおすすめ |
| 連作障害 | 同じ場所で育てると土壌の栄養バランスが崩れる |
| 代替植物の提案 | ヤマブキやスミレなどが見た目も良く管理がラク |
| 庭との相性 | 限られたスペースではレイアウトを崩すリスクが高い |
| 家庭菜園向け | 食用にも使えるが、管理できる環境が必要 |
| 初心者への注意 | 庭への地植えは避け、まずは鉢植えから始めると安心 |
菜の花を庭に植えてはいけない理由とは
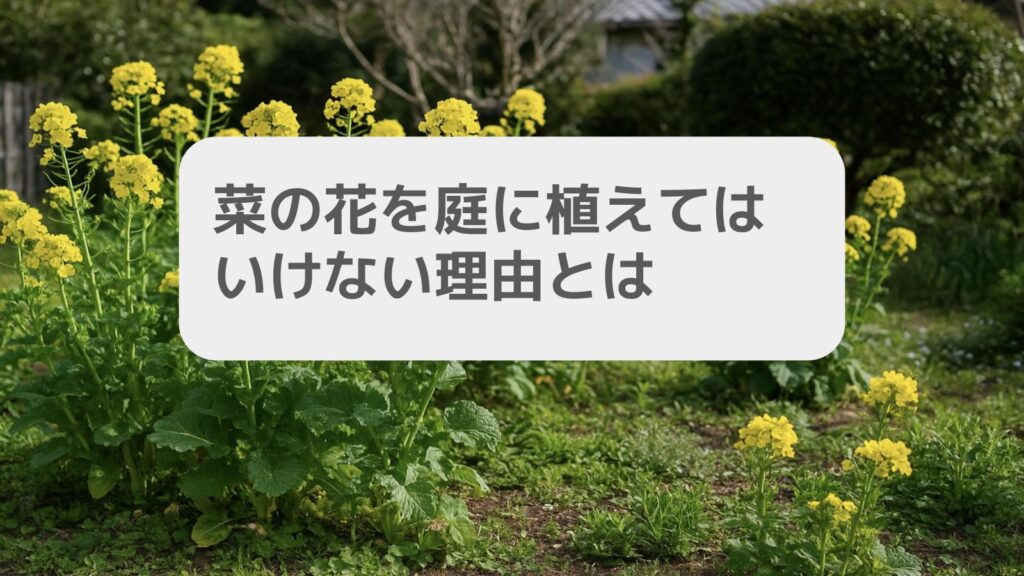
- 菜の花のデメリットまとめ
- 勝手に増える菜の花の性質
- 地植えでの管理が難しい理由
- 菜の花は雑草ですか?と聞かれる理由
- 庭に植えてはいけないランキングに入る理由
菜の花のデメリットまとめ
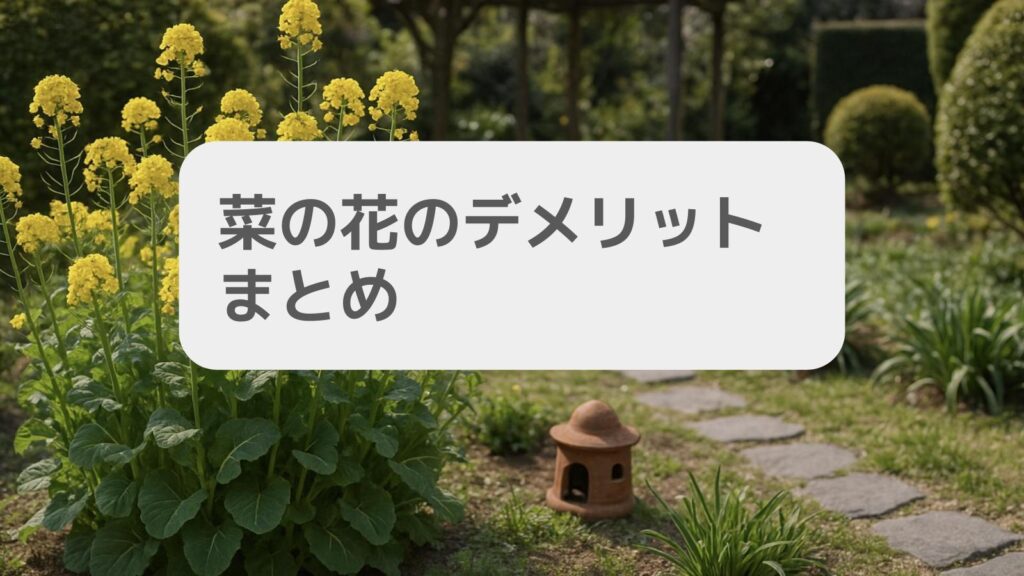
菜の花は見た目がとても可憐で、春になると一面に広がる黄色い花が私たちの気持ちまで明るくしてくれますよね。観賞用としても人気があり、家庭でも育ててみたくなる植物のひとつです。ただし、庭に植える際にはいくつか注意点があります。特に家庭の庭においては、その管理の手間や繁殖力の強さから、慎重に扱うべき存在といえるでしょう。
その最大の理由は、まず「害虫の発生しやすさ」です。菜の花はアブラナ科の植物であり、アブラムシやアオムシ、ナガメなどの害虫を引き寄せやすい特徴があります。これらの虫は一度発生すると増えるスピードも早く、他の植物にも移ってしまうことがあるため、防虫対策を怠ると一気に庭全体に影響が及ぶこともあるのです。
次に問題になるのが、「予想外の繁殖力」です。菜の花は花が終わったあとにたくさんの種をつけ、それが風や雨で周囲にばらまかれることで、翌年以降も自生しやすくなります。つまり、一度植えたつもりが、気がつけば庭のあちこちから芽を出してしまい、思い通りのガーデンデザインが難しくなる場合があるのです。
また、菜の花は連作障害を起こしやすいことでも知られています。つまり、同じ場所で何年も育てると、土壌の栄養バランスが偏り、ほかの植物が育ちにくくなる可能性もあるということです。
このように、一見かわいらしく育てやすそうに見える菜の花ですが、実際には「虫への注意」「広がりすぎることへの対策」「土壌管理」など、意外と手がかかる植物でもあります。そのため、特に初心者やガーデニングにあまり時間をかけられない方には、庭植えよりも鉢植えやプランターでの管理をおすすめします。
勝手に増える菜の花の性質
菜の花の魅力のひとつは、こぼれ種によって翌年も自動的に芽を出して育つという強い繁殖力にあります。一度植えた菜の花が花を終えたあと、種が風や雨で地面に落ち、そのまま次の年にも自然に芽を出して咲いてくれるのです。この性質は手間を減らすという点で便利に思えるかもしれません。
しかし、この「勝手に育つ」という特徴が、実は庭の管理を難しくする大きな要因でもあるのです。たとえば、他の草花を計画的に配置している庭では、予期せぬ場所から菜の花が発芽することでバランスが崩れてしまうことがあります。さらに、菜の花は成長が早く、スペースを一気に占有するため、せっかく育てていた植物が日光や栄養を奪われて枯れてしまうこともあるのです。
また、こぼれた種は必ずしも庭の中だけにとどまるとは限りません。風に乗って隣の敷地や歩道、公共の空き地にまで飛んでいくことがあり、周囲に迷惑をかけてしまう可能性もあります。特に都市部や住宅街などでは、景観や近隣トラブルにつながるおそれもあるため、注意が必要です。
このような背景から、家庭菜園や花壇の一角に菜の花を植える際は、できるだけ区画を決めたり、鉢やプランターなどで管理することが推奨されます。こぼれ種の処理をこまめに行うなど、事前に対策を講じておくことで、無計画な繁殖を防ぐことができます。
一見すると手間いらずで便利なように思える「勝手に増える」性質も、ガーデニング全体を考えると注意すべきポイントがたくさんあるのです。
地植えでの管理が難しい理由
菜の花を地植えにすると、管理が難しくなる大きな理由は「繁殖と害虫のコントロールがしにくくなること」です。地植えというのは、鉢やプランターとは違って土に直接植える方法なので、植物の根がどんどん広がっていきます。そして、それに伴ってこぼれ種も思いがけない方向にまで飛び散ってしまうことがあるんです。
このように根も種も広がりやすい環境だと、繁殖のコントロールが非常に難しくなってしまいます。たとえば、隣の花壇や敷地にまで芽が出てしまうと、ご近所との関係に影響が出るかもしれません。特に、菜の花は成長スピードが早いため、放っておくとすぐに背丈が高くなり、他の植物への日当たりも悪くなることがあります。
さらに、地植えにすることで一度根づいた菜の花を抜くのが手間になるという問題もあります。土の中でしっかりと根を張った菜の花は、簡単には引き抜けません。これが、庭のデザインや植物の入れ替えを難しくしてしまう原因にもなります。
また、菜の花はアブラムシやアオムシといった害虫が寄ってきやすい植物です。鉢植えであれば、虫がついたときにすぐに隔離できますが、地植えではそうはいきません。虫がついたまま放置してしまうと、周囲の植物にも広がってしまうリスクが高まります。
そしてもうひとつ見逃せないのが、地植えの環境によっては、栄養の偏りが起こりやすいという点です。菜の花が同じ場所で何度も育つことで土壌のバランスが崩れ、次に植える植物がうまく育たない可能性も出てきます。
このように考えると、菜の花の地植えは一見簡単そうに見えて、実は多くの配慮が必要な方法なのです。限られた庭のスペースを有効に使いたい場合や、手間をかけたくない方には、地植えではなく鉢やプランターでの栽培がおすすめです。
菜の花は雑草ですか?と聞かれる理由
菜の花が「雑草っぽい」と言われる背景には、いくつかの理由があります。そのひとつが、繁殖力の強さです。菜の花は一度種をまけば、こぼれ種から翌年以降も自然に芽を出しやすく、その様子が雑草とよく似ているのです。また、放っておいてもどんどん増えるという特徴から、「意図せず増える=雑草」というイメージを持たれがちになります。
実際に、道ばたや空き地、河川敷などで菜の花が群生している風景を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?こうした場所に自然と生えている姿は、明らかに人の手が加わっていないため、より雑草のような印象を与えてしまいます。
また、菜の花は生命力が強く、少々栄養状態が悪い土でも根を張り、成長して花を咲かせます。これは植物としてはありがたい特性なのですが、逆に言えば「どこにでも生える」とも言い換えられます。そのため、ガーデニングを楽しんでいる方からすると、計画していない場所にどんどん増える菜の花は、雑草と同じように管理が必要な存在となってしまうのです。
もちろん、菜の花そのものは観賞用にも、またおひたしや天ぷらなどの食用としても人気のある立派な植物です。品種によっては花も大きく、見ごたえのあるものもたくさんあります。ただ、植え方や管理方法を間違えてしまうと、あっという間に庭のあちこちで芽を出し、ほかの植物のスペースを奪ってしまうこともあるため注意が必要です。
だからこそ、菜の花を育てる際には「意図的に」育てるという姿勢がとても大切になります。具体的には、種がこぼれないように花がらを摘み取ったり、プランターで管理して広がりを防いだりといった工夫が必要です。育てる場所や目的をはっきりさせることで、菜の花を「雑草っぽく見える存在」から「上手に楽しめる植物」へと変えることができるのです。
このように、菜の花が雑草と誤解される理由には、見た目や繁殖力、そして管理の手間といった要素が重なっています。適切に育てることで、本来の美しさと魅力をしっかりと楽しむことができる植物であることを忘れないようにしたいですね。
庭に植えてはいけないランキングに入る理由
「庭に植えてはいけない植物ランキング」に菜の花がランクインする理由のひとつは、やはりその管理の煩雑さです。見た目はかわいらしく、春の風物詩としても親しまれている菜の花ですが、実際に家庭の庭に取り入れるとなると、さまざまな問題が浮かび上がってきます。
まず第一に、菜の花は非常に繁殖力が強い植物です。限られた庭のスペースでは、その成長スピードとこぼれ種による自然増殖によって、あっという間に他の植物のスペースを奪ってしまいます。せっかくバランスよく植えた庭のレイアウトも、次の年には菜の花ばかりに埋め尽くされてしまったという声も少なくありません。
さらに、菜の花は虫にとても好かれる植物で、アブラムシやアオムシなどが発生しやすいです。これらの害虫が一度ついてしまうと、他の植物にも移りやすく、庭全体の健康に悪影響を与えることもあります。しかも菜の花自体が虫に強いわけではなく、すぐに葉が食い荒らされたり、見た目が損なわれたりすることもあり、せっかく育てても満足のいく結果にならないことも。
また、菜の花は開花期以外の時期には目立った美しさがなく、ほとんど緑の葉ばかりで過ごすことになります。そして、春の花が咲き終わると一気に枯れてしまい、庭の一角が急にさみしい印象になってしまうのです。通年で緑や花を楽しみたいという方には、物足りなさを感じる要因にもなります。
このような理由から、菜の花は手軽に見えて実は手がかかる存在として、「庭に植えてはいけない植物ランキング」に挙げられることがあるのです。特に初心者や忙しい方、庭のデザイン性を重視する方にとっては、「思ったよりも面倒だった」と感じることが多く、結果的に菜の花の管理が負担となってしまうかもしれません。
もちろん、菜の花そのものが悪いわけではありませんが、こうした特性をしっかり理解した上で育てないと、後悔してしまうことも。だからこそ、育てる前に一度「本当に自分の庭に合っているか?」を考えてみることが大切なのです。
菜の花を庭に植えてはいけない対策
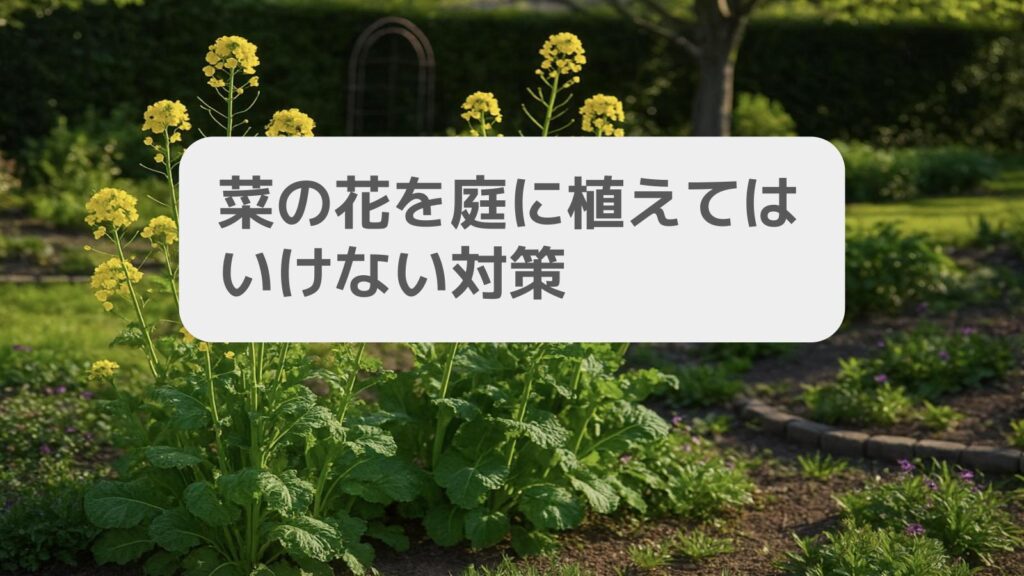
- 植える理由と対処法を考える
- 種まき時期はいつが最適?
- 種まき11月と3月の違いとは
- ばらまき栽培の注意点
- プランターでの菜の花栽培のすすめ
- 菜の花を庭で育てる代替案
植える理由と対処法を考える
一方で、菜の花には「春らしい景色を楽しめる」「食用としても使える」といった魅力もありますよね。その明るい黄色の花は、春を象徴する風景のひとつとして多くの人に愛されています。また、花だけでなく、若芽はおひたしや天ぷらなどに使うことができ、家庭菜園の楽しさをさらに広げてくれる存在です。
だからこそ、菜の花を完全に否定するのではなく、「どのようにすれば家庭でも安全かつ美しく育てられるのか」を考えることがとても大切になります。特に注意したいのが、その繁殖力です。菜の花はこぼれ種からどんどん増えるため、対策なしで植えると翌年には庭が菜の花だらけになってしまう可能性があります。
そこでおすすめしたいのが、鉢植えやプランターでの管理です。これなら根の広がりをコントロールできますし、こぼれ種も限られた範囲でしか広がらないため、繁殖しすぎる心配が減ります。また、鉢なら移動も簡単なので、日当たりの調整やデザインの変更にも対応しやすいですよ。
さらに、種が成熟する前に花がらをこまめに摘み取ることで、こぼれ種の拡散を防ぐことができます。この習慣をつけておけば、庭に思わぬところから芽が出るといったトラブルも避けやすくなります。
また、菜の花の種類にも注目してみてください。観賞用に改良された品種や、背丈があまり高くならない品種もあるので、育てやすくて景観を損なわない種類を選ぶのもひとつの方法です。
菜の花をどのように楽しむかは、まさにその人のライフスタイルや庭の規模、使い方によって異なります。たとえば、少しだけ春の彩りを加えたいという方には、小さな鉢にひと株だけ植えてみるのも素敵ですし、本格的に育てたい方には、専用スペースを用意して管理する方法が向いています。
このように、自分の環境と目的に合わせて菜の花との付き合い方を考えることが、後悔しないための大切なポイントになります。無理のない範囲で、賢く菜の花を楽しんでみてくださいね。
種まき時期はいつが最適?
菜の花の種まきには「春まき」と「秋まき」の2つの方法がありますが、実際にはお住まいの地域の気候条件によって適切な時期は少しずつ変わってきます。一般的に、寒冷地では春まきが適していて3月ごろが目安とされており、逆に温暖な地域では9月〜10月に行う秋まきがよいとされています。
なぜこのような差があるかというと、菜の花はある程度の耐寒性を持っているとはいえ、発芽直後の幼苗は寒さにとても弱く、強い霜や冷たい風にあたると生育が著しく鈍ってしまうからです。逆に暖かすぎると、苗が過剰に成長してしまい、本来よりも早く花を咲かせてしまう場合があります。これは結果として、茎がひょろひょろになったり、花の数が少なくなったりと、満足のいく見た目や収穫ができなくなる原因になります。
さらに、秋まきをすることで苗をしっかりと越冬させ、春の訪れとともに力強く開花する菜の花を見ることができます。一方で、春まきは苗の管理がしやすく、害虫のリスクも比較的少ないというメリットがありますが、そのぶん株が小さくなりがちというデメリットもあります。
ですので、どちらの時期が良いかは、あなたの住んでいる場所の冬の寒さや春の暖かさ、そして管理の手間や目的によって判断するのがポイントです。お花をたっぷり咲かせたいのか、それとも家庭菜園で食用として楽しみたいのか、そういった目的も時期選びには関係してきます。
自分の地域の気候に合わせて最適な時期を選ぶことで、元気で美しい菜の花が咲いてくれます。気温や天候に注目しながら、少し早めに準備を始めておくと安心ですよ。
種まき11月と3月の違いとは
菜の花の種まきには、主に「11月まき」と「3月まき」の2つのタイミングがありますが、それぞれに育ち方や仕上がりに大きな違いがあります。どちらが良いかは育てる目的や環境によっても異なりますので、特徴を理解したうえで選ぶのがポイントです。
まず、11月に種をまくと、いったん苗のまま冬を越えて、春になったときに一斉に花を咲かせるという「越冬型」の育ち方になります。この方法では、寒い時期にじっくりと根を張り、春の訪れとともにしっかりとした茎と葉に育ち、勢いよく花を咲かせることができます。そのため、株が大きく育ち、ボリュームのある見ごたえのある菜の花に仕上がることが多いです。
一方で、3月まきの場合は、暖かくなってから種をまくため、すぐに発芽し成長が始まります。このタイミングでは春の気温に助けられて発育が早く、初夏にかけてスピーディーに開花します。ただし、急速に育つ分、株がやや小さめになったり、花が少し小ぶりになる傾向があるのも特徴です。また、害虫が増え始める時期とも重なるため、管理の面でもやや注意が必要になります。
また、11月まきは種まきから開花までの期間が長くなるため、気温や霜への備えが必要となる一方で、春にしっかりとした景観を作りたい人にはぴったりです。3月まきはスピーディーに成長してくれる反面、タイミングを逃すとすぐに花の時期が過ぎてしまうこともあるため、まき時には気を配る必要があります。
このように、11月と3月では種まきのタイミングによって、育ち方や花の見た目、手間のかかり方にも違いが出ます。観賞用としてしっかりとした菜の花畑を楽しみたいなら11月まき、気軽に春から育ててみたいなら3月まきがおすすめです。
好みや育てる環境、季節のスケジュールに応じて、自分に合ったタイミングで種まきを選んでみてくださいね。
ばらまき栽培の注意点
「ばらまき」とは、種を均一に土の上にばらばらとまく方法のことで、広いスペースを利用して一面に菜の花を咲かせたい場合にはとても適したやり方です。手軽で見た目にも美しい結果が得られるので、特に広い庭や空き地での景観づくりには人気の方法です。
しかし、この方法にはいくつかの注意点が伴います。まず、種を均一にまくことは意外と難しく、どうしても一部に偏りが出てしまうことがあります。すると、発芽後に苗が密集してしまい、十分に日光や栄養、水分が行き届かず、育成不良になる可能性が高まります。そのため、発芽後には早めの間引きが必要ですが、これがなかなか骨の折れる作業になります。
また、菜の花は密集すると風通しが悪くなり、湿気がこもりやすくなるため、病気や害虫の発生を招きやすい環境になってしまいます。特にアブラムシやカビ系の病気が出やすくなるので、防虫・防病対策はしっかりと行う必要があります。予防として、ある程度間隔を取って発芽させることや、定期的な風通しの改善が求められます。
さらに見落とされがちなのが、こぼれ種の影響です。ばらまきでは種のコントロールがしにくいため、強い風が吹く日などには、種が意図しない場所まで飛んでいってしまうことがあります。その結果、翌年には花壇の縁や道ばた、あるいは隣家の敷地などで思わぬ芽が出てくることもあり、トラブルの原因になることも。
このような事態を防ぐためには、ばらまく量を適切に調整すること、風の強い日を避けて作業すること、そして発芽後の間引きや管理を丁寧に行うことが重要です。また、ばらまきで使用する種には、あらかじめ発芽率や成長のバランスが安定している品種を選ぶと、後の手入れがぐっと楽になります。
ばらまきは一見簡単そうに見えますが、実際にはその後の手入れや環境調整をしっかりと行うことで、美しい菜の花畑を実現できる方法です。手軽さだけにとらわれず、丁寧な準備と管理が成功のカギになりますよ。
プランターでの菜の花栽培のすすめ
菜の花を庭に直接植えるのではなく、プランターで育てるという選択肢はとても実用的です。特に庭のスペースが限られているご家庭や、他の植物との共存を考えている方にはぴったりの方法です。プランターなら管理もしやすく、見た目にも清潔感があり、必要に応じて場所を移動させることも簡単にできます。
さらに、プランターで育てると菜の花の「こぼれ種」が外に広がるリスクを大幅に減らせます。これは、翌年に思いもよらない場所から芽が出るといったトラブルを未然に防ぐという点で非常に有効です。また、他の植物との間に距離を保つことができるため、日当たりや水分、養分の取り合いによるストレスも最小限に抑えることができます。
虫がついてしまったときも、プランターなら被害が拡大する前にすぐに隔離できます。庭全体に影響が及ぶ前に、ベランダや別の場所に移すなどの対処ができるため、初心者の方でも安心して菜の花の栽培にチャレンジできます。防虫ネットや不織布カバーを使った対応も、プランターなら容易に行えるのもメリットのひとつです。
また、プランターにはデザイン性のあるものが多く、玄関先やベランダなどに置くだけで春らしい華やかな雰囲気を演出できます。菜の花の明るい黄色は、どんな空間にも明るさと元気を与えてくれますよ。季節のインテリアとしても活躍することでしょう。
プランター栽培は、水やりや肥料管理のタイミングも調整しやすく、初心者でも成功率が高いのが特徴です。まずは小さなプランターからスタートして、菜の花の育ち方に慣れていくのがおすすめです。手軽に始められて、管理もラク。そんなプランター栽培で、菜の花のある暮らしをぜひ楽しんでみてください。
菜の花を庭で育てる代替案
「やっぱり庭で菜の花はちょっと不安…」という方には、似たような雰囲気や色合いを楽しめる代替植物を選ぶのもひとつの賢い方法です。菜の花の特徴である鮮やかな黄色や春らしい印象は、他の植物でもじゅうぶんに表現することができます。
たとえば、ヤマブキ(山吹)は、春に鮮やかな黄色の花をたくさん咲かせてくれる低木で、庭に彩りを加えたい方にぴったりです。背丈も菜の花よりやや低く、広がりすぎる心配も少ないため、管理のしやすさも大きな魅力です。また多年草のため、毎年植え直す必要がなく、長く楽しめるのも嬉しいポイントです。
また、春に可憐な紫や青の花をつけるスミレもおすすめです。スミレは控えめながらも可憐な花姿で、和洋どちらの庭にも馴染みやすい植物です。日陰にも比較的強く、こまめな手入れをしなくても自然に広がってくれるので、ガーデニング初心者にもぴったりです。
その他にも、菜の花に似た印象を持つ「リナリア」や「クリサンセマム・パルドサム」なども春らしい彩りを与えてくれる植物です。これらは一面に咲かせると、まるで菜の花畑のような景観をつくることもできます。
このように考えると、無理して菜の花にこだわらなくても、工夫次第で春の雰囲気はしっかりと再現できます。むしろ、それぞれの庭の条件や好みに合わせて代替植物を選ぶことで、より快適で楽しいガーデニングライフが実現できるかもしれません。
菜の花 庭に植えてはいけない理由の総まとめ
- 害虫が発生しやすく、他の植物に被害が広がりやすい
- 種がこぼれて翌年も勝手に芽を出す
- 繁殖力が強く庭の景観を乱しやすい
- 地植えでは根が広がりすぎて抜きにくい
- 隣家や公共スペースに種が飛ぶ恐れがある
- 花が終わったあとの処理が面倒
- 開花期以外は見た目が地味で寂しい印象になる
- 一度増えると管理が非常に困難になる
- アブラムシやアオムシなどを呼びやすい
- 土壌に連作障害を引き起こしやすい
- 菜の花が雑草と誤解されやすい性質を持つ
- 鉢やプランターでの管理でないと制御が難しい
- 密集すると風通しが悪く病害虫が発生しやすい
- 種まきの時期によっては成長が不安定になりやすい
- 代替植物の方が管理しやすく庭に向いていることが多い
シンボルツリー
- おすすめ樹木
- おすすめ常緑樹
- おすすめしない木
- 虫がつかない木
- シンボルツリーの代わり
- ハイノキで後悔する理由
- フェイジョアで後悔する理由
- オリーブで後悔する理由
- ミモザで後悔する理由
- ユーカリで後悔する理由
- アオダモで後悔する理由
- ソヨゴで後悔する理由
- レモンで後悔する理由
- ヤマボウシ
- 建売の木を抜く
- シンボルツリーの足元に石
鑑賞用
- トクサを庭に植えてはいけない理由とは?根絶が難しく縁起が悪いから
- ブラシの木を庭に植えてはいけない理由とは?後悔は大きくなりすぎること
- チェリーセージを植えてはいけない理由を徹底解説!放置して剪定しないと大変なことに
- 笹を庭に植えてはいけない理由は根絶が難しいから!植物界最強とも
- ミソハギを庭に植えてはいけない理由!花言葉や縁起が気になる
- シンバラリアを庭に植えてはいけない理由を徹底解説!耐寒温度つよく冬越しできるグランドカバー
- ユキヤナギを庭に植えてはいけない理由は縁起と手入れの大変さ以外にも
- 鬼門に植えてはいけない木を一挙紹介!裏鬼門に植える植物も紹介
- 【後悔】紅葉を庭に植えてはいけない理由とは!?シンボルツリーにすると落ち葉がひどい
- ホワイトセージを庭に植えてはいけない理由!?木質化すると香りが失われる
- ソテツを庭に植えてはいけない!?縁起が悪いや風水的に幸運が来ない?
- パンパスグラスは庭に植えてはいけない理由!?鉢植えや風水について
- ビオララブラドリカを庭に植えてはいけない理由を徹底紹介!
野菜・果物

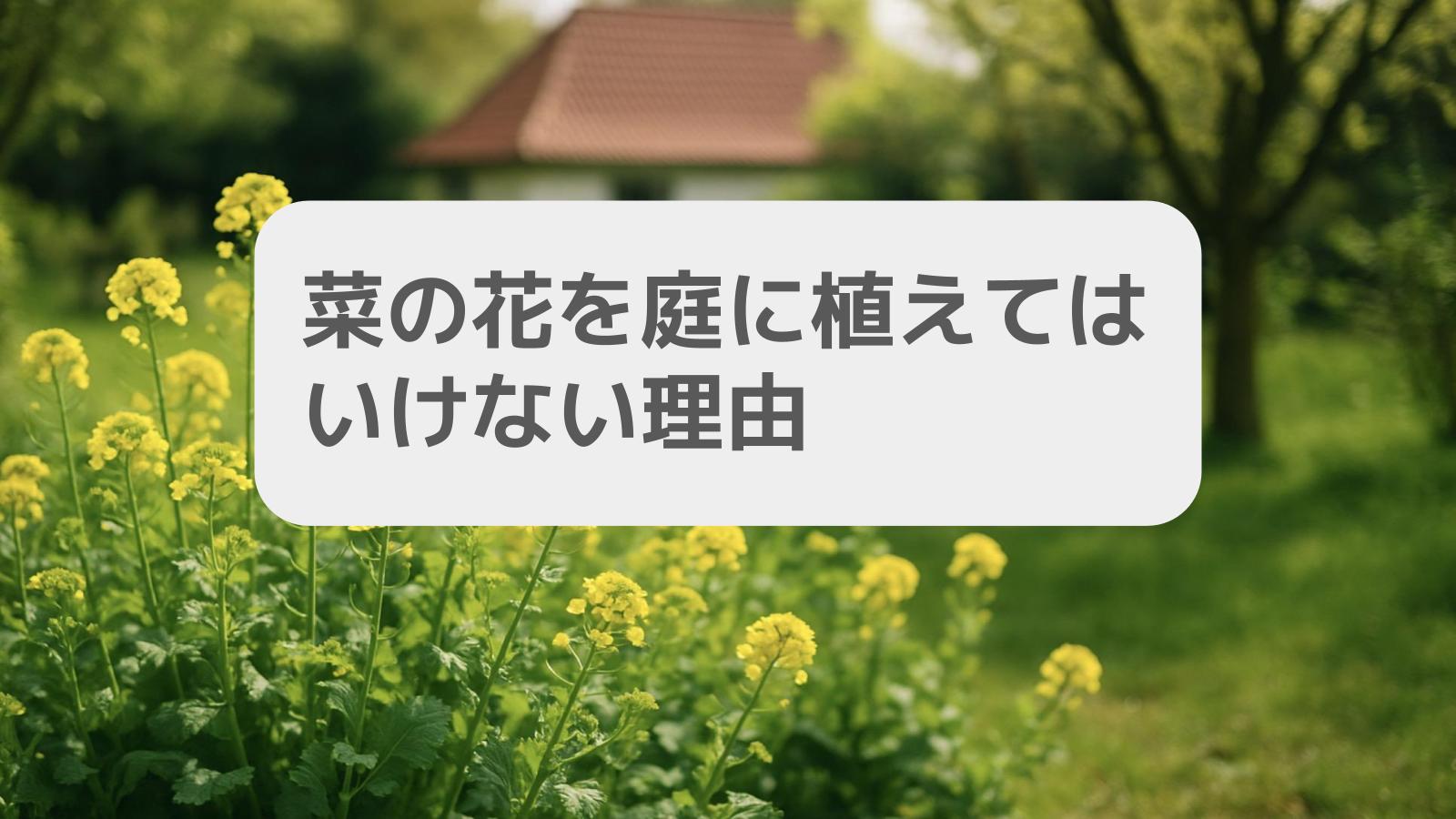

コメント