「防音フェンス 効果なし」と検索しているあなたは、おそらく「せっかく設置したのに音が減らない」「どんな防音対策が本当に効くのか」といった疑問や不安を感じているのではないでしょうか。
実際、防音フェンスは設置の仕方や音の種類によって効果に大きな差が出るのが現実です。
この記事では、防音フェンスが効果なしになってしまう理由を詳しく解説し、室外機の騒音対策、ブロック塀との違い、適切なフェンスの高さ、さらには後付け設置や自作フェンスの注意点まで、具体的で実用的な情報を網羅しています。
正しい防音対策の知識を身につけ、無駄な出費や施工ミスを防ぎたい方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防音フェンスが効果なしになる原因 | 音の種類(特に低音)や反響、回折などによる影響 |
| 高さの重要性 | 2.5m以上でないと十分な遮音効果が出にくい |
| 吸音材との併用 | 遮音性だけでなく吸音性のある素材と組み合わせが必要 |
| 室外機対策 | フェンスの高さや向き、吸音材、防音カバーを併用する |
| ブロック塀との違い | ブロック塀は遮音効果が限定的で、音が回り込みやすい |
| 後付けフェンスの課題 | 設置環境の制約で理想的な位置・角度を確保しにくい |
| 自作フェンスの落とし穴 | 素材・密閉性・施工精度が不足しやすく効果が出にくい |
| おすすめの対策 | 専門業者の調査と吸音・遮音の複合対策を検討する |
| 費用の目安 | 1mあたり1〜2万円+施工費。条件次第で総額数十万円 |
| 製品選びのポイント | 音の種類・設置目的・採光の有無を考慮して選ぶ |
- 防音フェンスが効果なしになる原因
- 室外機や低音に対する適切な対策方法
- ブロック塀との防音性能の違い
- 効果を高めるための設置条件や注意点
【PR】タウンライフ
リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。
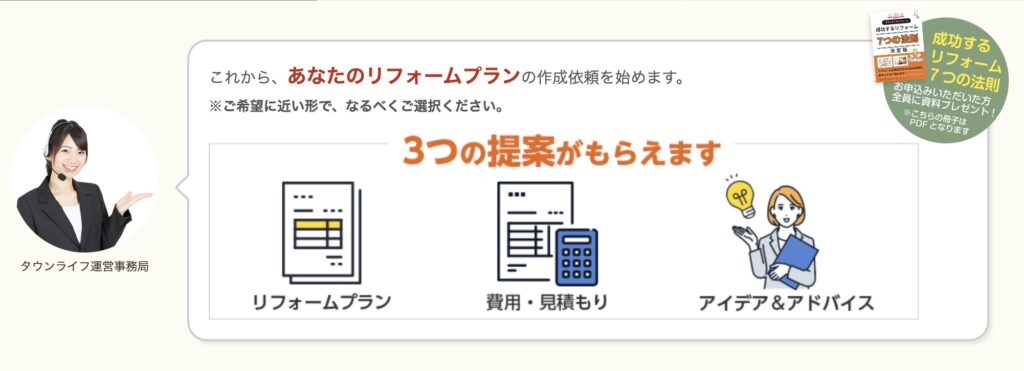
物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!
1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。
タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。
防音フェンス効果なしの理由とは

- 最強の防音対策との違い
- 室外機の音に効果ある?
- ブロック塀の防音効果との比較
- 高さで変わる防音性能とは
- 「すやや」の効果は本当か?
最強の防音対策との違い
言ってしまえば、防音フェンスは「万能」ではありません。どんな音でも遮れるというわけではなく、音の性質や発生源の高さ、反響の有無などによって、防音効果に大きな差が生じるのが現実です。
最強と呼ばれる防音対策は、単体のフェンスや壁だけでなく、複数の対策を組み合わせたシステム的な設計です。例えば、屋外からの騒音には防音フェンスを使い、室内側には二重窓や吸音カーテンを組み合わせて遮音と吸音の両方を実現するような方法が取られます。
さらに、壁の内部構造にまで手を入れる場合もあります。遮音ボードの裏側に吸音材を敷き詰め、音の反射を抑えつつ、構造体そのものの防音性を高めることで、高い遮音効果を発揮します。
また、音の特性を理解した上で設計されるスタジオや病院のように、防音を前提にした建築計画が立てられるケースでは、音の回り込みや漏れが最小限に抑えられています。これが、一般住宅に後から設置する防音フェンスとの最大の違いです。
このように考えると、防音フェンスはあくまで「屋外騒音の軽減策の一つ」であり、住宅全体の静けさを保ちたい場合には、他の方法と組み合わせることが不可欠になります。
室外機の音に効果ある?
このため、防音フェンスで室外機の音を完全にシャットアウトするのは難しい場合があります。なぜなら、室外機の音は主に低音域を含んでおり、この低音は波長が長いため、障害物を回り込む性質が強く、フェンスのような垂直の遮蔽物だけでは十分に抑えきれないケースが多いからです。
例えば、コンビニや飲食店の裏手に設置されているアルミ板のフェンスを見かけたことがあるかもしれません。
これらは見た目にはしっかりとした遮蔽構造ですが、実際にその裏側に立ってみると「ブーン」という重低音が残っていることがあります。これは、フェンスの上部や隙間を通って音が回折して伝わっているためです。
さらに、フェンスの素材や形状によっても効果が異なります。例えば、金属製の遮音パネルは音を反射しやすいものの、反響音として逆に聞こえてしまう場合もあり、結果として周囲に音を拡散させてしまうこともあります。
このような場合は、反射だけでなく音を吸収する「吸音性能」を備えたフェンスを併用することで、より実効性の高い対策が期待できます。
こうした状況では、フェンスの高さを2m以上にすることや、吸音タイプのフェンスを選ぶこと、さらにフェンスの裏側に植栽や防音シートを設置して音の拡散を抑えるなど、複数の対策を組み合わせるのが効果的です。また、室外機の向きを変えたり、防音カバーを併用するなどの方法も一考の価値があります。
つまり、室外機の騒音対策として防音フェンスを選ぶ場合には、その音の性質を正しく理解し、遮音・吸音・設置環境の三点から総合的に判断することが重要です。
ブロック塀の防音効果との比較
多くの人が勘違いしやすいのが「ブロック塀も防音になるのでは?」という点です。確かに、コンクリート製のブロック塀にはある程度の遮音効果があります。これは、音を遮るために必要な「質量則」に基づいており、重くて厚みのある素材ほど音を通しにくいという原理に当てはまるからです。
ただし、ブロック塀は構造的に隙間ができやすく、また一般的な設置高さは1.2〜1.8mと低いため、音がその上を回り込んでしまいます。特に、室外機や交通量の多い道路から発せられるような低音域の音は波長が長く、塀の上部や側面から簡単に回り込んでくるため、防音対策としては効果が限定的です。
例えば、1.2m程度の塀では、通行車両の走行音や室外機の運転音を遮ることは難しく、家の中まで音が入り込んでしまうことがあります。風向きや地形によっては、ブロック塀が音を反射してかえって聞こえやすくなることもあるため、注意が必要です。
一方、防音フェンスは専用に設計されており、遮音材や吸音材を内部に組み込んだ構造を持つため、音を「反射して遮る」「内部で吸収する」といった多面的な機能を備えています。とくに吸音タイプのフェンスでは、音のエネルギーを熱に変えて消す働きもあり、単なる物理的な壁とは異なる役割を果たしてくれます。
さらに、防音フェンスは隙間を極力排除した設計になっており、パネル同士の継ぎ目や支柱との接合部にも防音処理が施されていることが多いため、音の漏れや回折を防ぐ点でも優れています。同じ1.8mの高さで比較した場合でも、ブロック塀よりも防音フェンスの方が明らかに騒音低減の効果が高いと言えるでしょう。
このように考えると、ブロック塀は視線の遮断や境界明示には適していますが、防音性能を本格的に求める場合には、専用の防音フェンスを検討した方が安心です。
高さで変わる防音性能とは

ここで重要なのが「高さ」です。音は空気を伝わって波のように広がる性質を持っているため、フェンスが十分な高さでないと、その上を簡単に越えて回り込んでしまうのです。高さが不十分だと、遮りきれなかった音が反射や拡散によって周囲に届き、思ったほどの防音効果が得られない可能性があります。
ある実験によると、高さが1.8mの防音壁では、騒音源が80dBの音を発していた場合、受音点での音量は48.3dB程度までしか下げられないとされています。これは「少し静かになった」と感じる程度の変化にとどまります。
しかし、高さを2.5mまで高くすると、同じ80dBの音でも44.6dBにまで低減できる結果が得られ、「静かだ」と感じるレベルに到達します。さらに、壁の高さを4.0mまで上げた場合には、音は40dB程度まで抑えられ、日常生活の中ではほとんど気にならないほどの静音環境をつくることが可能です。
この違いは、音の回折という現象に関係しています。音は障害物の端を回り込む性質を持っており、壁が高ければ高いほど、その回り込み量が減少します。
また、高さだけでなく、距離減衰の効果も関係しており、音源との水平距離が伸びることで音のエネルギーも減少します。これらの要素が複合的に働くことで、フェンスの高さによる防音性能の違いが明確になるのです。
したがって、防音フェンスを設置する際には、単に「目隠しになれば良い」という感覚で高さを決めるのではなく、「どの程度の音を、どこまで減らしたいのか」という目的を明確にした上で、最適な高さを設計することが大切です。特に騒音源が近くにある場合には、最低でも2.5m以上を検討すべきでしょう。
「すやや」の効果は本当か?
「すやや」はリクシルが提供する防音フェンスシリーズで、見た目のデザイン性と機能性の両方を兼ね備えた製品として注目されています。その中でも「すややR1型」は、遮音パネルを採用し、騒音を約10dB程度カットできるとカタログなどでは紹介されています。
ただし、この数値はあくまで理想的な設置条件下におけるものであり、すべての住宅環境で同じような効果が得られるとは限りません。たとえば、フェンスの設置高さが足りなかったり、音の回り込みが発生しやすい立地だったりすると、本来期待される遮音性能を十分に発揮できないこともあります。
また、遮音パネルは音を跳ね返す仕組みであるため、周囲に反射音を生じさせてしまうリスクもあります。特に、隣接する建物との距離が近い住宅街などでは、フェンスが反響板のような役割を果たし、逆に音がこもったり増幅されて感じられる場合もあります。
一方、「すやや」シリーズには採光タイプや吸音タイプのバリエーションも用意されており、それらを環境に応じて使い分けることが望ましいです。
たとえば、音の反射を抑えたい場合は、吸音機能を持つフェンスとの組み合わせが有効です。実際に、すややR3型のような吸音面をもつモデルは、音を吸収することによって反射音の発生を抑える効果が期待できます。
さらに、設置場所の地形、風の通り道、音源の位置や種類などを把握したうえでプランニングすることも大切です。施工前に専門業者に相談したり、音響シミュレーションを行うことで、より確実な防音効果を得ることが可能になります。
つまり、「すやや」の効果が本当にあるかどうかは、製品単体の性能だけでなく、設置環境や組み合わせ方によって大きく左右されるという点を理解しておくことが重要です。
【PR】タウンライフ
リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。
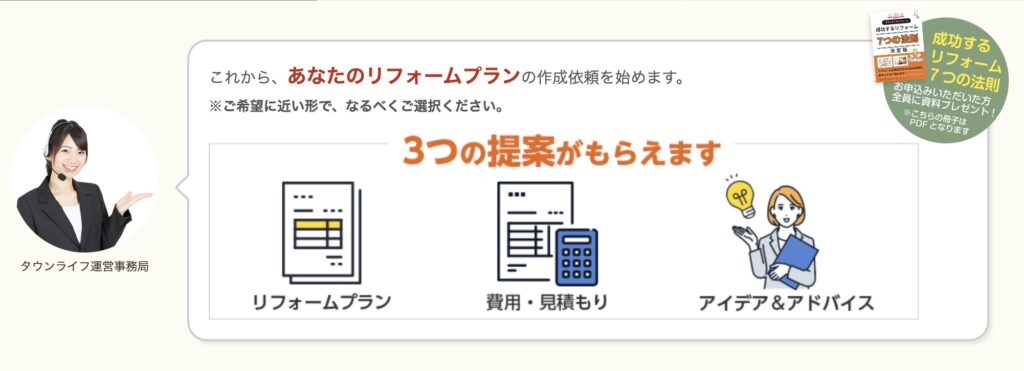
物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!
1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。
タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。
防音フェンス効果なしを避ける方法

- 自作防音フェンスの落とし穴
- 後付けフェンスの限界とは
- 費用・工事費で見る選択基準
- 2階の騒音に効く設置方法
- 防音フェンスを選ぶ前の注意点
自作防音フェンスの落とし穴

多くは、コストを抑えるために自作で防音フェンスを試みる方もいらっしゃいます。材料費や工事費を節約できる点が魅力ではありますが、その一方で防音効果については十分に注意が必要です。
DIYで作られる防音フェンスは、遮音材や吸音材の選定ミス、施工精度の不足によって十分な効果を得られないケースが多く報告されています。特に、防音の基本である「質量」「密閉性」「吸音性」のバランスが欠けていると、期待したほどの騒音低減が実現できないのです。
例えば、ホームセンターで販売されている合板や木製パネルなどを単に重ねてフェンス代わりにしても、音をしっかりと跳ね返すには不十分です。また、防音に適した素材であっても、それをしっかりと密着施工しなければ隙間から音が漏れてしまいます。
さらに、反射音の問題も見過ごせません。遮音性だけを重視して材料を選ぶと、跳ね返った音が周囲に広がってしまい、かえって騒音トラブルを悪化させる可能性もあります。吸音材を組み合わせずに遮音材のみで構成した場合、フェンスの内側に音がこもってしまうという事例もあります。
また、屋外で使用する場合には、耐候性や耐久性の問題も出てきます。水に弱い素材を使えば、雨風によって劣化し、隙間が生じて防音性が失われてしまいますし、金属素材でも防錆処理をしていなければサビが発生しやすくなります。
このように、自作による防音フェンスは一見コストメリットがあるように思えますが、効果や耐久性、安全性の面で不安が残ることも多いため、よほどの知識と経験がない限り、専門業者のサポートを受けた方が安心です。必要に応じて、防音の専門家にアドバイスをもらいながら計画を進めることをおすすめします。
後付けフェンスの限界とは
一方で、家を建てた後からフェンスを設置する「後付け」もまた効果にばらつきがあります。多くの方が、生活音や外部の騒音に悩まされてから初めて防音フェンスの設置を検討するため、後付けになるケースが一般的です。しかし、この後付け設置にはいくつかの制約が伴います。
なぜなら、すでに完成している建物の配置や、既存の外構設備との兼ね合いがあるため、音の通り道を完全に遮るような設計が困難になることが多いのです。
特に、隣家との距離が近い場合や、敷地の形状に制限がある住宅地では、防音フェンスを理想的な位置・角度・高さで設置することができず、効果が限定的になってしまうことがあります。
また、基礎工事を省略して簡易的に設置されたフェンスでは、強風や地震などによる揺れが発生しやすくなり、逆にフェンスそのものが音の発生源になってしまう恐れもあります。
さらに、フェンスが振動を伝えることで、室内の壁や窓に音が共鳴して響くといった二次的な騒音トラブルが発生することもあるため、慎重な設計と施工が求められます。
このように言うと少しネガティブに聞こえるかもしれませんが、適切な設計と信頼できる施工業者による取り付けが行われれば、後付けであっても防音効果を十分に発揮する可能性はあります。
特に、吸音材を用いたフェンスや、騒音源に応じて設置位置や角度を工夫した設計などを取り入れれば、期待以上の静音環境を実現できることもあるのです。
後付けで設置を検討している場合は、事前に現地調査を行い、どこから音が伝わっているのか、どの方向に設置すれば最も効果的かを把握した上で、専門家と相談しながらプランを練ることが非常に重要です。
費用・工事費で見る選択基準
もちろん、どんなフェンスでも気になるのは費用です。防音フェンスにおいては、素材や構造が一般的なフェンスと比べて複雑であるため、価格帯が高くなる傾向があります。
一般的な防音フェンスは1メートルあたり1万円〜2万円程度で販売されていますが、これに基礎工事や設置費用が加わると、総額で数十万円単位になることも少なくありません。
特に、高さが必要な場合や吸音機能を備えたタイプ、デザイン性の高い製品などは価格がさらに上がります。
加えて、設置場所の状況によっては、地盤補強や既存構造物の撤去など、追加工事が必要となるケースもあります。そのため、事前に見積もりをしっかりと取り、想定外の費用が発生しないよう計画を立てることが重要です。
一方、メッシュフェンスや目隠しフェンスのような簡易的な構造のフェンスは、施工費込みで1メートルあたり数千円から設置できることもあります。防音性能を追求しないのであれば、こちらを選ぶことでコストを大幅に抑えることが可能です。
ここで重要なのは、「どの音を、どれだけ防ぎたいか」という目的を明確にすることです。例えば、隣家との会話の声やテレビの音など中〜高音域が中心の音であれば、ある程度の簡易防音対策でも効果があることがあります。
しかし、交通量の多い道路や工事現場のように低音が多く含まれる環境では、より性能の高い防音フェンスが求められます。
このように、目的と予算を照らし合わせて、無理のない範囲で最も効果的な対策を選ぶことが満足度の高い結果につながります。
もし費用を抑えたいのであれば、完全な防音ではなく「目隠しフェンスと植栽の併用」「部分的な吸音パネルの導入」など、段階的な対策も視野に入れてみると良いでしょう。
2階の騒音に効く設置方法
実際、2階に届く騒音への対策は難易度が高いです。なぜなら、音は空気中を波のように伝わり、特に上方向へと回折しやすいため、地上に設置した通常のフェンスだけでは、音の通り道を十分に遮ることが難しいからです。
このような状況では、地上からの音に対して「下から遮る」だけでなく、「上で受け止める」ような設計が求められます。そのため、2階の騒音対策には屋外対策と室内対策の両方を組み合わせることが推奨されます。
具体的には、2階の窓に内窓(二重窓)を設置することで、空気伝播音を大幅に軽減できます。内窓は窓と窓の間に空気層をつくることで、音のエネルギーを弱める効果があります。これに加えて、厚手の遮音カーテンを設置すれば、音の侵入をさらに抑えることが可能です。
また、防音性能を高める目的で「遮音+吸音」のハイブリッド型フェンスを地上に設置する方法もあります。特に屋根付き構造にすることで、上部からの音の抜けを一定程度防ぐことができ、回折音の到達を和らげる効果も期待できます。
さらに、フェンスの外側に樹木や植栽を加えると、音の拡散を減らし、見た目の圧迫感も緩和されます。
一部のケースでは、2階のバルコニーやベランダにも簡易的な防音パネルを設置することで、上階への音の伝達を軽減できることがあります。住宅の構造や設置スペースに応じて、防音スクリーンや吸音ボードを設けるなどの工夫も選択肢となります。
このように、2階の騒音対策は一つの方法で完全に解決できるものではなく、音源・伝播経路・住宅構造の三点を見極めて、適切な複合対策をとることが重要です。
防音フェンスを選ぶ前の注意点
最後に、最も大切なのが「目的に合った製品選び」です。防音フェンスとひと口に言っても、実際には遮音タイプ・吸音タイプ・採光タイプといった複数のバリエーションが存在し、それぞれ構造や目的が異なります。そのため、使用環境や音の種類によって適したものを選ぶことが非常に重要です。
例えば、隣人の話し声やペットの鳴き声のような中高音域の空気伝播音を軽減したいのであれば、音を内部で吸収する構造の吸音フェンスが効果的です。
特に住宅が密集している都市部では、吸音タイプのほうが音の反射を抑える点でも有利になります。一方、幹線道路沿いの騒音や工場の機械音のような比較的低音が多いケースでは、音を跳ね返す遮音タイプの方が効果的です。
また、見落としがちなのが「採光」のニーズです。防音フェンスを設置することで日当たりや風通しが悪くなってしまう場合があります。
採光タイプの防音フェンスは、ポリカーボネートなどの透光性素材を用いることで、遮音性と明るさを両立できます。見た目にも圧迫感が少なく、住宅の外観との相性も良い点が魅力です。
さらに、防音フェンスの効果を最大限に発揮させるためには、敷地の形状や隣家との距離、高さ制限、風の通り道、周辺の建築物の配置など、さまざまな要因を事前に確認しておく必要があります。
これらの情報をもとに、専門業者による現地調査を依頼し、最適な製品と設置方法についてアドバイスをもらうのが理想です。
このように考えると、最初に「何の音を、どこで、どれだけ防ぎたいのか」を整理しておくことが、満足度の高い防音フェンス選びにつながります。また、実際に設置した人の口コミや施工事例を参考にすることで、具体的なイメージが湧きやすくなり、失敗のリスクも減らせます。
防音フェンス 効果なしを防ぐための要点まとめ
- 防音フェンスは音の種類によって効果に差が出る
- 単体では完全な防音対策にはならない
- 低音域はフェンスを回り込むため遮音しにくい
- 高さが不足すると音が上から回り込む
- 金属製フェンスは反響音を生みやすい
- 隙間のある構造では音漏れが発生する
- 室外機のような低音には吸音材の併用が必要
- 自作では素材選定や施工精度が不十分になりがち
- 後付けは設置環境によって効果が限定される
- 遮音性と吸音性のバランスが重要
- 高さが2.5m以上でなければ十分な効果が得にくい
- 遮音タイプだけでなく吸音機能も検討すべき
- 防音フェンスでも反射音による騒音が起こり得る
- 専門家による事前調査と設計が成功のカギ
- 設置目的と音の種類に応じた製品選びが不可欠
【PR】タウンライフ
リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。
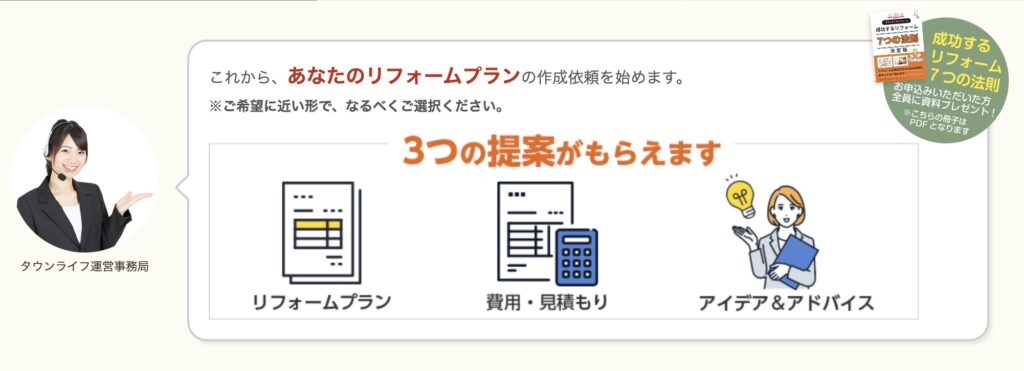
物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!
1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。
タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。



コメント