セキスイハイムに住んでみたい、あるいはすでに住んでいて「うるさい」と感じて検索している方も多いのではないでしょうか。
足音が響く、話し声が漏れる、夜中に家鳴りがする――そんな音の悩みは、快適な生活を一変させてしまいます。特に軽量鉄骨構造のアパートでは音が響く傾向があり、防音がどこまで効くのか不安になる方も少なくありません。
この記事では、セキスイハイムにおける音の問題を徹底解説していきます。遮音間仕切りの効果や、音漏れの実態、快適エアリーがうるさいという口コミの背景、そして近隣トラブルにつながりやすい騒音の種類についても紹介します。
また、施工不良が原因で起きる事例や、苦情への対応策、入居前にできるチェックポイントなども取り上げ、防音性の実力を冷静に検証します。
これからセキスイハイムに住む方、すでに住んでいて音に悩んでいる方にとって、後悔しないためのヒントとなる情報をお届けします。
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
\この記事を読むとわかることの要点/
<t
| 問題点 | 原因 | 対応策・注意点 |
|---|---|---|
| 足音・話し声が響く | 軽量鉄骨構造や床・壁材の遮音性不足 | 遮音間仕切りや吸音材の導入、防音マットなどの工夫 |
| 家鳴り | 構造材の収縮・膨張によるきしみ音 | 許容範囲とされるが、ひどい場合は施工業者へ相談 |
| 快適エアリーの騒音 | 室外機の高出力運転や振動音 | 静音モード設定、防振材追加、設置場所の見直し |
| 音漏れ | 壁の構造、窓の仕様、施工精度 | 複層ガラス、遮音ドアなどで強化可能 |
| 施工不良による音の増幅 | 検査体制の不備や部材の取付不良 | 工場見学・引き渡し前の詳細点検が重要 |
| 隣室・上下階との生活音 | 建物構造や入居者の生活リズム | 内覧時に時間帯を変えて音をチェック |
| 近隣トラブル | 騒音の感じ方に個人差 | 事前の説明・共有と冷静な対応がカギ |
| 防音アパートとの比較 | 建築工法や素材の違い | 建物スペックの確認と住人レビューの参考 |
| 遮音間仕切りの限界 | 完全な遮音は難しい構造 |
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
セキスイハイムは本当にうるさい?
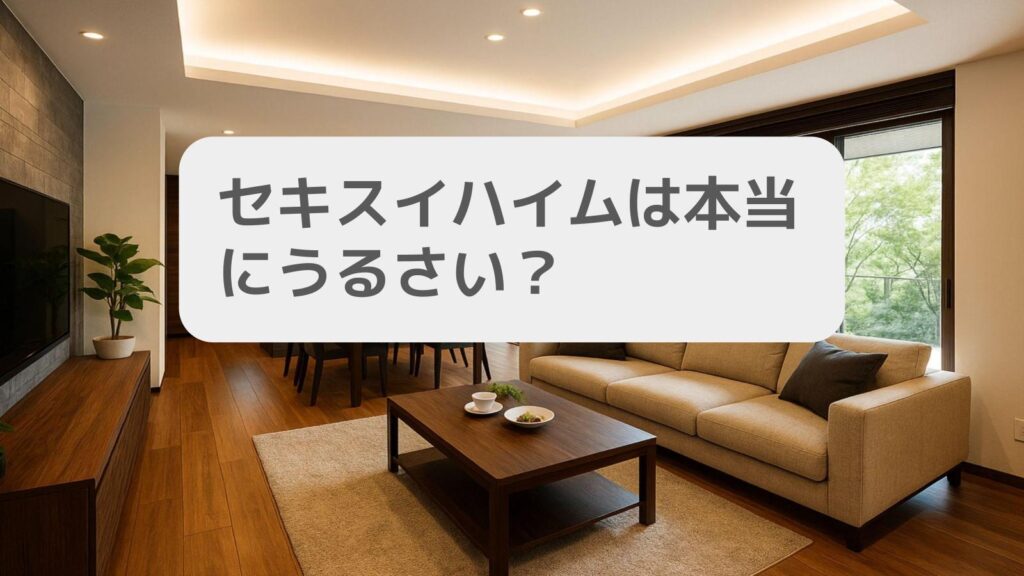
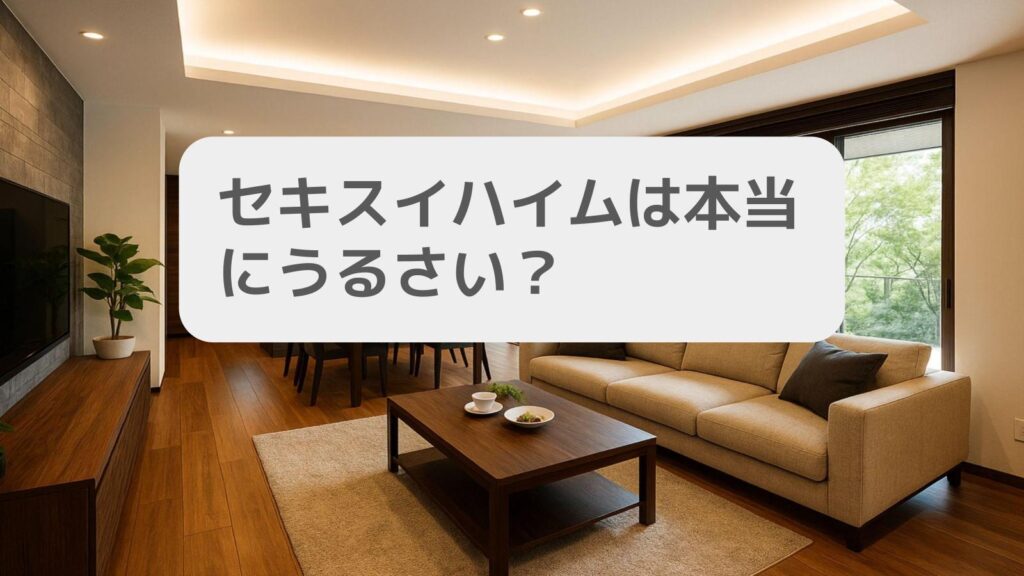
- 足音や話し声など音が響く理由
- 軽量鉄骨のアパートで音はどうか
- 遮音間仕切りは効果がある?
- 音漏れに悩む住人の声とは
- 騒音に関する苦情とその対応
足音や話し声など音が響く理由
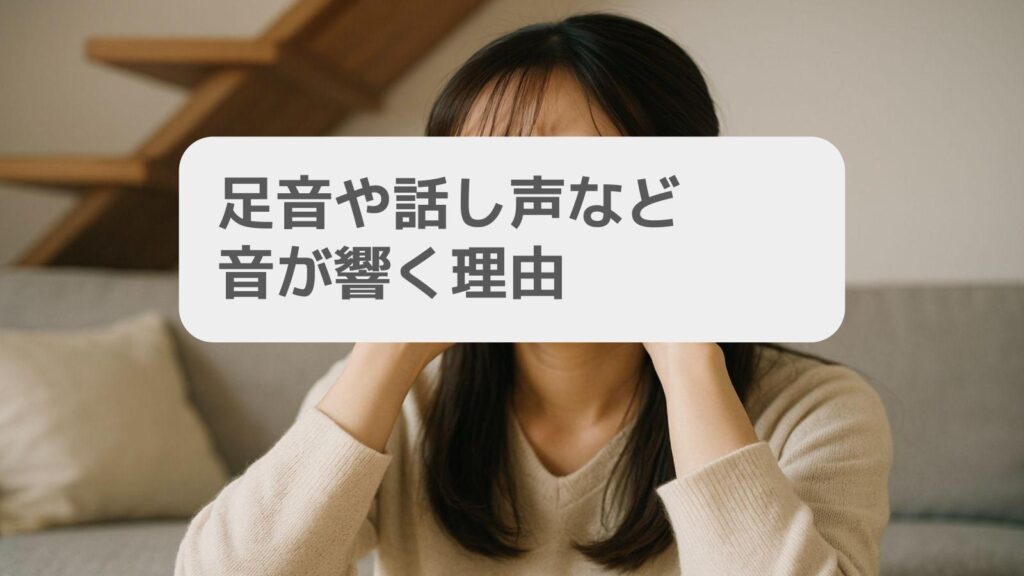
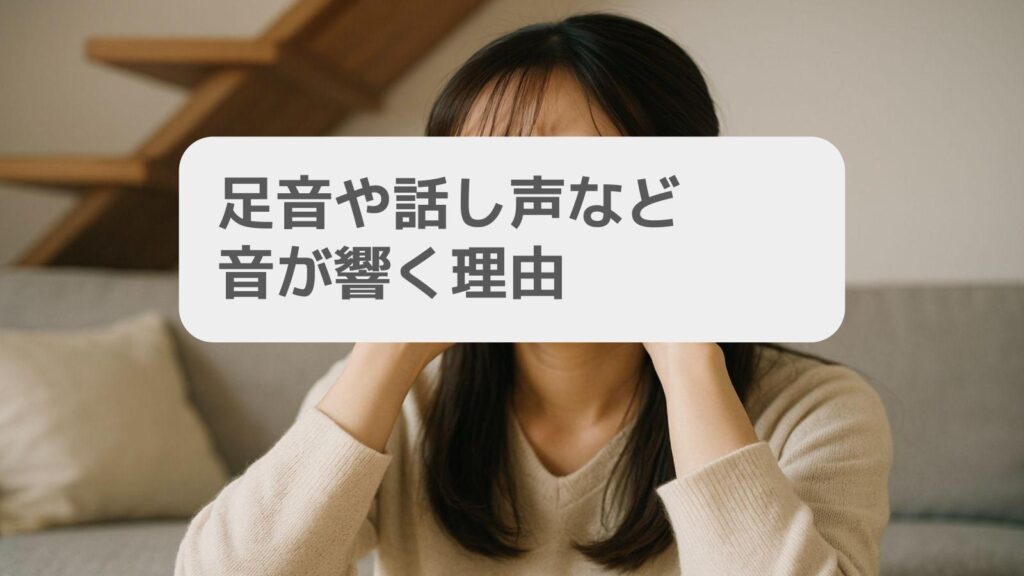
一戸建てでもアパートでも、生活音が気になることって意外と多いものです。特に「静かに暮らしたい」と思って家を建てたり購入した方にとって、想像していたより音が響くと感じたら、それはかなりのストレスになります。
セキスイハイムの住宅に関しても、足音や話し声が気になるという声が見られます。なぜそのようなことが起きるのかというと、構造や使用されている建材の特性が関係しています。音は空気や建材を伝って広がる性質があるため、設計や材料の工夫が必要なのです。
例えば、鉄骨やパネル構造の床材は、木造と比べて反響しやすい傾向があります。これにより、上階の足音が「ドンッ」「バタバタ」と響くことがあるのです。また、壁の構造が単層または断熱材の薄いものだと、話し声やテレビの音が隣の部屋にまで伝わってしまう場合もあります。
加えて、生活リズムが違う家族や隣人がいると、深夜の音や早朝の活動が思った以上に響いて感じられることもあります。とくに家族構成に差がある場合、小さなお子さんのいる家庭では走る音や泣き声が強く伝わる傾向があるため、静音性の高い住宅を希望する方は慎重に検討する必要があるでしょう。
このため、セキスイハイムで建築を考えている方は、契約前の段階で必ず床材の遮音性能や壁材の厚み、吸音材の有無を確認するのが望ましいです。モデルハウスでは静かでも、実際に住み始めてから気になることもありますので、実際の住人の声や体験談も参考にすると安心です。
また、施工の際に防音オプションをつけることや、間取りを工夫することで音の伝わり方を軽減することも可能です。音は「生活の質」に直結する要素なので、妥協せずにチェックしておくことをおすすめします。
軽量鉄骨のアパートで音はどうか
軽量鉄骨構造は、工期が短く耐震性があるというメリットがありますが、防音性については注意が必要です。
これは、壁の厚さや内部の吸音材の使い方によって、音の伝わり方が変わるためです。軽量鉄骨のアパートでは、上下階の生活音や隣室の物音が聞こえやすいというケースもあります。
たとえば、朝のドライヤーの音や夜の足音がはっきり聞こえるといった口コミも見られます。建物の構造上の特徴なので、防音対策がどれほど取られているかが重要になってきます。
遮音間仕切りは効果がある?
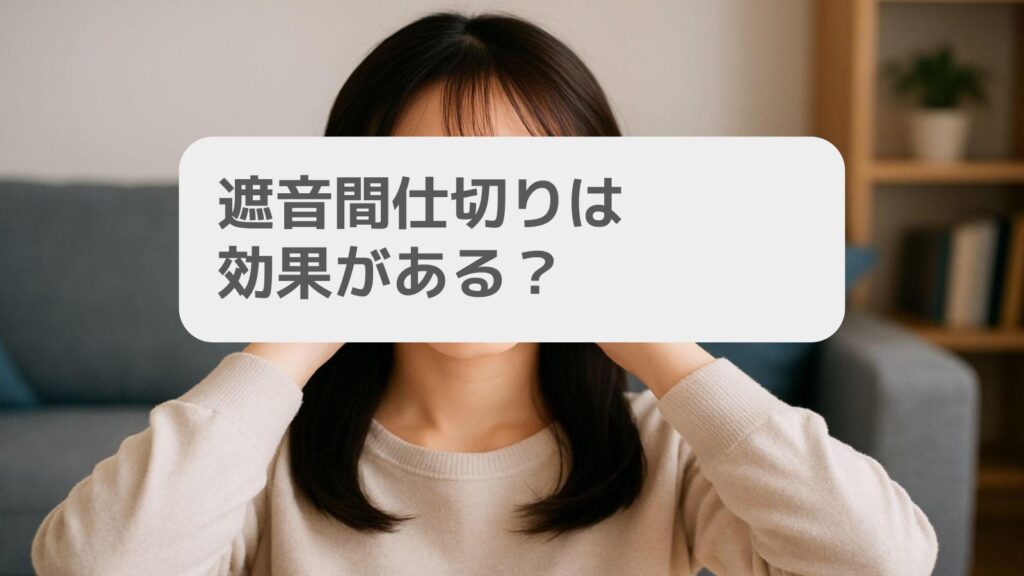
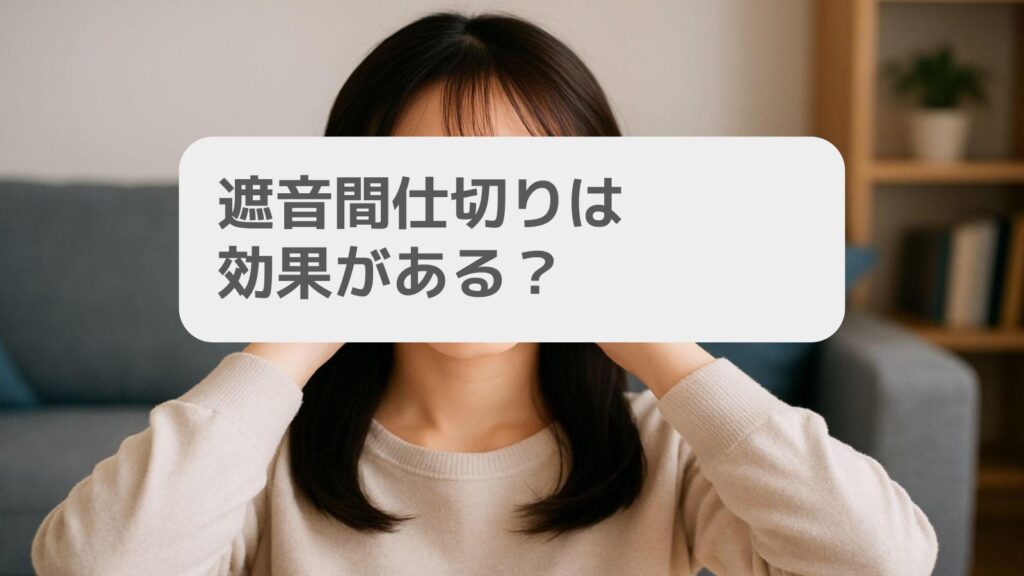
セキスイハイムでは、防音性の強化策として「遮音間仕切り」の採用を積極的に行っています。この間仕切りには、石膏ボードを二重に貼る構造や、吸音性の高いグラスウールを内部に挿入する仕様が使われています。これにより、隣接する部屋からの音がダイレクトに響くのを抑える工夫がされています。
ただし、これはあくまで音の「緩和」を目的としたものであり、「完全な遮音」ではないことに注意が必要です。つまり、遮音間仕切りが導入されていても、大音量のテレビや話し声などは小さく聞こえてしまうことがあります。
特に、構造体が軽量鉄骨など反響しやすい素材でできている場合、遮音効果の限界も出やすくなります。また、施工時の精度によっても性能に差が出るため、現場でどれだけ丁寧に施工されているかも重要なポイントです。
さらに、音に対する感覚は人それぞれ違います。少しの音でも不快に感じる方もいれば、気にならない方もいます。ですから、遮音間仕切りの効果を過信せず、実際に住んでいる人の声やモデルハウスでの音の感じ方を確かめることが大切です。
もし防音をより強化したいと考えるなら、防音カーテンや厚手の家具の配置、防音マットの併用など、生活の中でできる工夫も視野に入れておくとよいでしょう。総合的な対策があってこそ、遮音間仕切りの効果もより活きてきます。
音漏れに悩む住人の声とは
実際に住んでみて、「音漏れが気になる」という声は少なくありません。特に、家族構成や生活リズムが異なる住人が上下・左右にいると、些細な音でも気になってしまうことがあります。たとえば夜勤明けで日中に休みたい人や、小さな子どもがいる家庭では、生活音に対する敏感さが違ってくるものです。
例えば、子どもの走る音、早朝の掃除機、深夜の洗濯機の音などが、思った以上に響いてしまうケースもあります。ドアの開閉音や椅子を引く音、足音が「ゴンッ」と響いたり、隣の音楽が壁越しに聞こえるような場面も珍しくありません。こうした日常の音が蓄積されていくと、精神的なストレスを抱えてしまう方も多いようです。
このような悩みを抱えた住人の中には、「引っ越しを検討した」「管理会社に何度も相談した」という声もあります。とくに賃貸住宅では、建物の構造や築年数によって音の伝わり方に差があるため、防音性の高い物件を探すことが一つの対策になります。
これを防ぐためには、内覧時に時間帯を変えて何度か訪れること、実際に音の響き具合をチェックすることが大切です。朝や夕方など、人の活動が活発な時間帯に訪れてみると、リアルな生活音を確認することができます。また、物件選びの際には、壁や床の素材、遮音構造の有無など、スペック面にも注意を払っておくことが重要です。
さらに、内見時にはベランダや外の道路状況、隣接する建物との距離、上下階の生活音の有無など、複数の視点から音環境を評価するようにすると安心です。音漏れの少ない暮らしは、穏やかで快適な住環境をつくるために欠かせない要素です。
騒音に関する苦情とその対応
騒音に関する苦情は、住環境における大きなトラブルの原因となりがちです。特にセキスイハイムのように高性能な住まいをうたっている住宅であれば、期待が高い分だけ実際に音に悩まされると落胆も大きくなります。
セキスイハイムにおいても、実際に「音がうるさい」という苦情が寄せられた事例があります。例えば、快適エアリーの稼働音や室外機の振動音に対して「低音が響く」「振動で窓ガラスが共鳴する」といった報告がありました。これらは日中だけでなく、深夜や早朝にも動作するため、静かな時間帯には特に気になるものです。
このような騒音に関しては、まず販売店や施工会社に相談するのが基本です。実際、相談を受けた場合には、室外機の設置位置を変更したり、緩衝材を追加して振動を吸収する、あるいは機器の設定を変更して稼働音を軽減するなど、いくつかの対応策が取られています。場合によっては、専門の点検業者が現地に赴いて実測し、具体的な数値として問題を把握することもあります。
また、近隣住民からの苦情につながるケースもあるため、単なる住人個人の問題ではなく、地域全体の良好な関係を保つための配慮としても、早期の対応は不可欠です。クレームが表面化する前に、自主的に音の状態をチェックすることも有効です。
騒音は我慢して生活するものではありません。我慢を重ねることで、身体的・精神的なストレスが積み重なり、住まいに対する満足感を著しく下げてしまいます。だからこそ、「仕方ない」と思わず、些細なことでも早めに相談し、適切な対策を依頼することが、長く快適に暮らすためのポイントになります。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
セキスイハイムのうるさい騒音対策とは
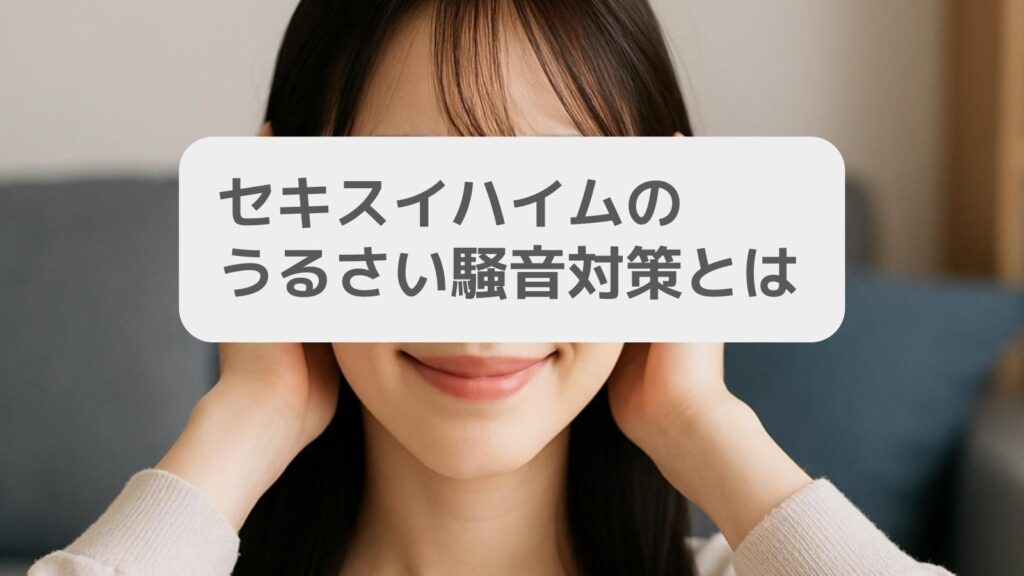
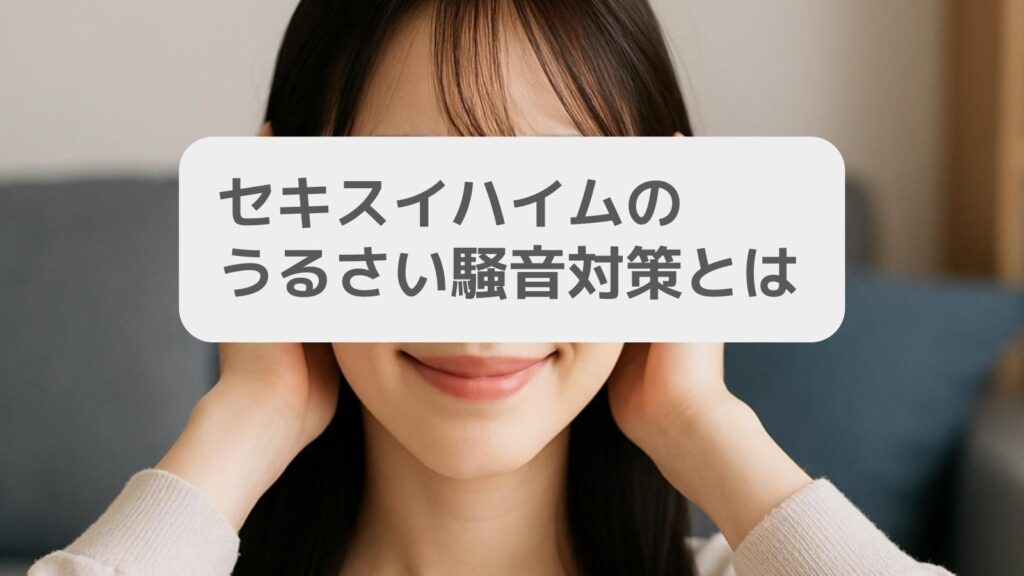
- 家鳴り問題とその実態とは
- 快適エアリーがうるさい原因
- 施工不良が音の原因になる?
- 防音性に弱点はあるのか
- 音による近隣トラブルの実例
- 住む前にできる確認ポイント
家鳴り問題とその実態とは
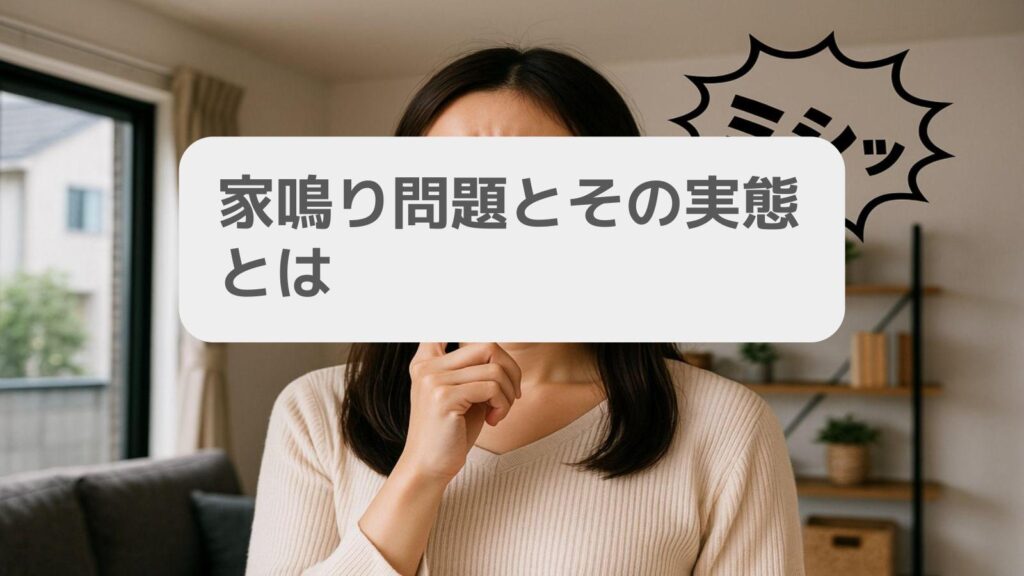
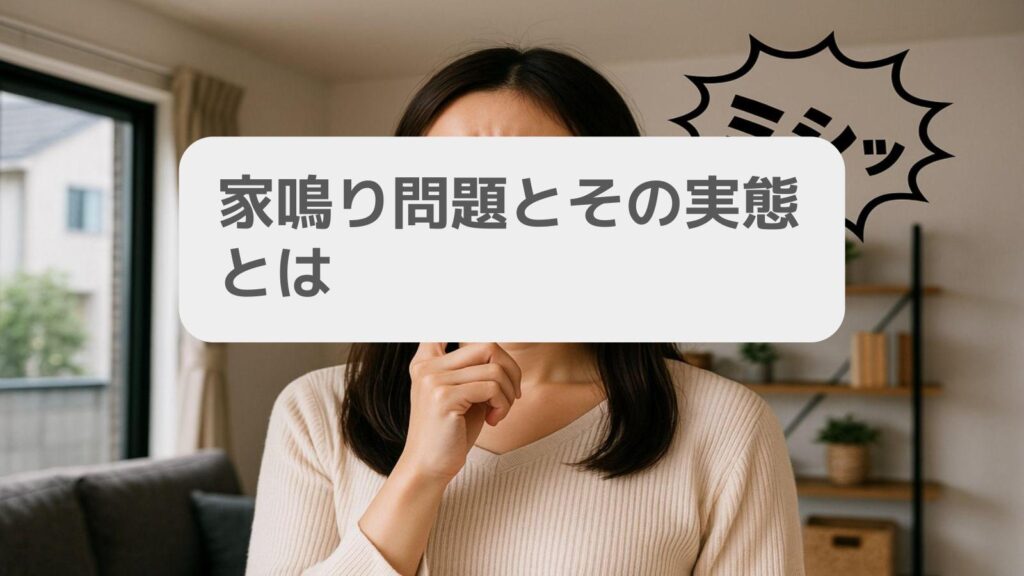
「家鳴り」とは、建物の構造材が温度や湿度の変化で伸縮することにより、木材や金属部材がわずかに動いて「バキッ」「ピシッ」といった音を発する現象のことを指します。これは新築住宅や築浅の建物で特に起こりやすく、セキスイハイムの木質系ユニット住宅でも、居住者から同様の報告が複数寄せられています。音は昼間よりも夜間や早朝の静かな時間帯に目立つため、気になりやすいのが特徴です。
この音の原因は、内部構造の木材や接合部が乾燥や温度差により微妙に収縮・膨張を繰り返すことにあります。特に季節の変わり目や冬場などはその影響が顕著になりやすく、木材が乾燥している時期には音が頻繁に発生する傾向があります。また、複数のユニットを接合して建てるセキスイハイムの構造では、接合部分のズレや隙間が音を増幅する原因となることもあるようです。
一見すると「故障では?」と感じてしまうこの現象ですが、実際には施工マニュアル上で許容範囲とされており、必ずしも不具合とは判断されません。ただし、あまりにも頻度が高かったり、音が大きすぎて睡眠に支障が出るような場合は例外です。こうした場合には、ハウスメーカーやアフターサービスに相談して点検を依頼することが推奨されます。
対応策としては、遮音材の追加施工や、構造部の再調整などが挙げられます。これにより音の発生箇所を特定し、緩衝材を追加することである程度の軽減が可能になります。また、ユニット同士の接合部分にクッション材や緩衝テープを貼ることで、構造の動きが音として現れにくくなるといった方法もあります。
住宅の性能だけでなく、居住者の快適さを守るためにも、「家鳴り」のような細かな問題に対して丁寧な対応が求められます。気になる音が続くようであれば、無理に我慢せず、早めに相談することが安心・快適な住まいづくりの第一歩です。
快適エアリーがうるさい原因
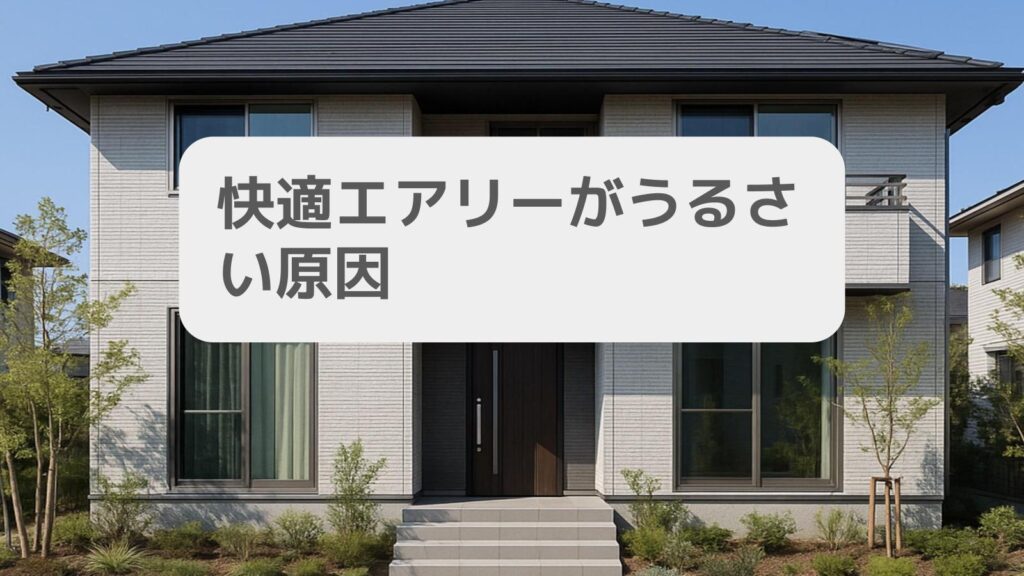
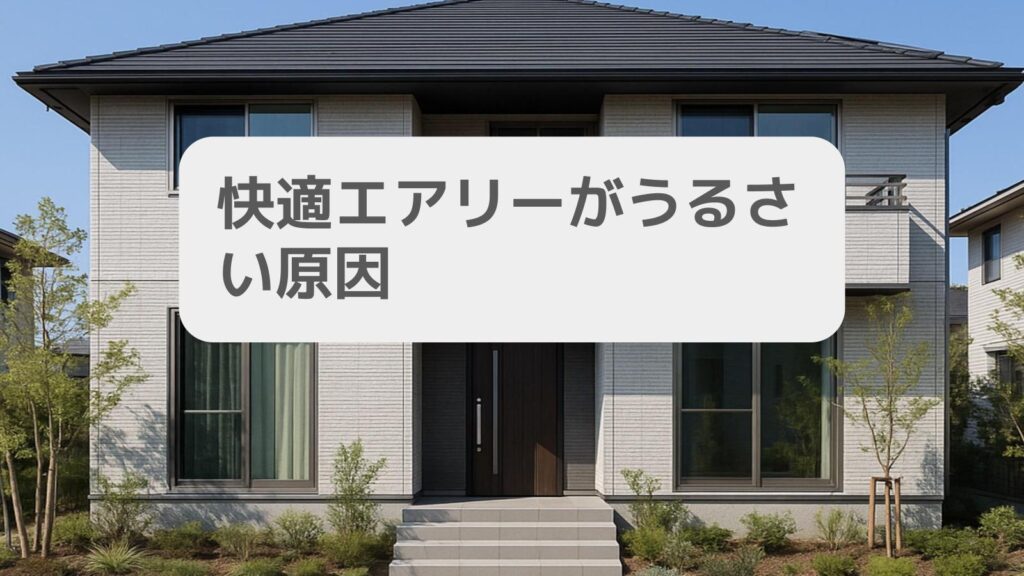
快適エアリーはセキスイハイムの特徴的な全館空調システムであり、室内の温度を一定に保つ快適な住環境を提供するために開発されたものです。ただ、冬場など外気温が大きく下がる時期には、快適エアリーの室外機がフル稼働するため、「音がうるさい」と感じるケースがあります。
その騒音の原因としてまず挙げられるのが、急激な温度変化に対応するための高出力運転です。この際、室外機が全速力で動くことで大きな振動が発生し、それが架台を通じて床や壁に伝わってしまいます。さらに、架台に適切な防振対策が施されていないと、その振動が共鳴して「ブーン」や「ゴォー」といった低音の騒音として広がってしまうのです。
また、機器内部に防音材や緩衝材が十分に入っていない場合、機械音がそのまま外部に漏れ出し、ダダ漏れ状態となって騒音問題を引き起こすこともあります。特に夜間など静かな時間帯には、こうした音がより一層気になりやすく、睡眠や集中の妨げになることもあるでしょう。
さらに設置環境によっても音の感じ方は変わります。例えば、室外機が寝室の外壁に近い位置にある場合や、反響しやすい壁材に囲まれていると、音の反射や共鳴が生じて体感的な騒音レベルが高まります。
もし快適エアリーの音が気になる場合は、まず機器の設定を確認し、運転モードを「静音モード」や「省エネモード」に切り替えることで改善されることがあります。それでも音が収まらない場合は、施工業者に相談して防振材や緩衝材の追加を依頼することが効果的です。室外機の設置場所の再調整や、外壁との距離を取ることで、音の伝達を抑える工夫も可能です。
また、快適エアリーを使用する前に、設置環境に応じた騒音対策が取られているかどうか、導入時にしっかり確認しておくと安心です。実際の音の大きさは図面やカタログではわからないことが多いため、稼働中の現物を見学したり、既存ユーザーの体験談を参考にすることも検討材料になります。
このように、快適エアリーは非常に便利な設備である反面、設置や運転状況によっては音の問題が出ることもあります。しかし早めに対処することで、多くの場合は改善可能です。
施工不良が音の原因になる?
建物の音に関する悩みの中には、「施工不良」が原因になっているケースも少なくありません。住んでみてから気づく「音の問題」は、実は見えない部分の施工精度が大きく関係していることがあります。例えば、外壁の塗装ムラ、断熱材の隙間、窓の水切り板の傾きなど、一見すると些細な施工ミスに見えるこれらが、実際には音漏れや振動音の増幅に深く関わっていることがあります。
窓の水切り板が斜めに設置されていると、そこから風が当たりやすくなり、微細な音が共鳴音として室内に響く原因になることがあります。また、外壁の塗膜にムラがあると、雨や風の音が増幅されたり、湿度変化で壁材が鳴るなど、予期しない音のトラブルが発生する場合もあるのです。
こうした問題の根本には、工場生産の過程での検査体制の甘さが関係していることも指摘されています。セキスイハイムでは「250項目のチェック体制」とされているものの、実際の現場ではその多くが作業者の自己確認に頼っていたという報告もあります。つまり、第三者の厳格なチェックが入らなければ、本来の基準を満たさないまま出荷されることもあるということです。
また、ISO9001といった品質管理の国際規格を取得しているからといって、すべての工程が万全であるとは限りません。検査記録に「対象外」と記載されていた部位が後になって不具合を起こした事例もあるように、制度と現場の運用にギャップが生じることも珍しくありません。
このようなリスクを回避するためにも、事前の工場見学を積極的に行い、自分たちのユニットがどのように製造されているのかを実際に見て確認することが大切です。そして、引き渡し前には隅々まで丁寧に点検し、図面と実物に差異がないかどうかをチェックする姿勢が後悔を減らします。
最終的には、細かな違和感に気づけるかどうかが、快適な暮らしにつながる大きな分かれ道となるのです。
防音性に弱点はあるのか
セキスイハイムの住宅は、一定の遮音性を備えてはいるものの、全ての状況において完璧な静けさを実現できるわけではありません。特に、鉄骨系の構造体を採用している場合は、遮音よりも耐震性や耐久性を優先する設計が多いため、どうしても音への配慮が後回しになる傾向があります。その結果として、生活音や外部からの音が室内に響いてしまう場面も出てくるのです。
たとえば、床材が硬い素材で構成されていたり、ユニット構造の接合部に小さな隙間があったりすると、上階からの足音や物音が階下に響くことがあります。さらに、壁の厚みや断熱材の密度によって、隣室からの話し声やテレビの音などが聞こえてくる場合もあります。音に敏感な方にとっては、こうした生活音が積み重なることで、想像以上のストレスになる可能性があります。
このような構造的な特性に加えて、使用される建材の種類や施工の丁寧さによっても、最終的な防音性は大きく左右されます。遮音間仕切りのような構造上の工夫や、複層ガラスの採用といった標準仕様でもある程度の遮音効果は得られますが、それだけで十分とは限りません。
そのため、防音性を重視したいと考えている方には、初期段階からオプションとしての防音強化プランを導入することを検討することをおすすめします。たとえば、遮音シートの追加や壁の内側への吸音材の充填、防音ドアやサッシの導入などが効果的です。また、後付けでもできる対策としては、防音カーテンの設置や家具の配置による音の吸収、フロアマットを敷くことでの衝撃音の緩和などがあります。
さらに、間取りの工夫も見逃せません。例えば、寝室と隣室の間に収納スペースを挟んだり、水回りの隣接を避けることで、音の干渉を軽減することが可能です。このように、防音対策には設計・施工・生活習慣のすべてに配慮する必要があります。
防音は快適な暮らしを支える重要な要素のひとつです。だからこそ、音に対して敏感な方や静かな環境を求める方は、事前の相談やオプション選択を通じて、より納得のいく住まいを手に入れる努力を惜しまないことが大切です。
音による近隣トラブルの実例
住宅における「うるさい」という感覚は人それぞれ異なります。ある人にとっては気にならない生活音も、別の人には耐えがたい騒音に感じられることがあります。このような感覚の違いから、実際にはささいな音でも近隣トラブルに発展することが少なくありません。
例えば、隣人の赤ちゃんの泣き声が何度も繰り返されると、「育児だから仕方がない」と理解しようとしても、連日の疲れからイライラしてしまう人もいます。また、掃き出し窓のサッシ音が早朝に鳴ることで目覚めてしまったり、夜間の足音が響いて眠れないという声もあります。こういった事例は、住人同士の直接的な関係を悪化させるきっかけになることもあります。
特に、ハウスメーカー側の説明不足が火に油を注ぐこともあるようです。あるケースでは、「ハイムの家は家鳴りが当たり前」と営業担当者が説明していたものの、その後に響く音が予想以上に大きく、住人が「事前にもっと丁寧に伝えてほしかった」と不満を漏らしていたとのことです。こうした説明不足や対応の遅れが、信頼関係の崩壊へとつながる恐れがあります。
このようなトラブルを防ぐには、まず入居前の段階でしっかりと情報収集を行うことが大切です。施工会社や販売店からは、設備の仕様や遮音構造についての詳細な説明を求めるようにしましょう。加えて、実際にその住宅で生活している人の口コミを確認したり、住宅展示場ではなく実物件での音の体験をお願いするなど、納得するまで確認する姿勢が重要です。
また、万が一入居後に音に関する問題が発生した場合でも、感情的にならず冷静に対応することが求められます。管理会社や施工業者に相談する際には、日時・状況・音の種類などを記録しておくことで、対応がスムーズになります。さらに、直接苦情を言うよりも、第三者を介して伝えることでトラブルが深刻化しにくくなる傾向があります。
防音に対する考え方や感じ方は人によって違うからこそ、住環境に関するコミュニケーションや事前準備が非常に大切なのです。
住む前にできる確認ポイント
騒音で後悔しないためには、住む前のチェックがとても大切です。新築やモデルハウスの静けさに安心してしまうのではなく、実際に人が住んでいる状態での環境を確認することが大事です。なぜなら、展示場では外部の音や住人の生活音をリアルに体験できないからです。
例えば、内覧時には朝・昼・夜それぞれの時間帯に訪れて、どのような音がどの程度響くかを感じ取っておくと安心です。朝の通勤時間帯は車の音、昼間は工事や子どもの遊び声、夜間は室内の音が外に漏れていないか、または外の音が室内にどれくらい入ってくるかなど、時間帯によって騒音の種類は変わります。
また、隣接する住宅との距離や配置、壁の厚み、窓の位置、給湯器や室外機などの設備機器がどこに設置されているかも重要なチェックポイントです。とくに室外機が寝室やリビングの壁に近い位置にあると、振動音や作動音が直接響く可能性が高くなります。
さらに、入居者の口コミやSNSでの評判も、リアルな声として非常に参考になります。実際に住んでいる方の投稿から、「音漏れがある」「快適エアリーがうるさい」といった問題点を事前に知ることができれば、自分たちの基準と照らし合わせて判断がしやすくなります。
気になる点があれば、遠慮せずに施工会社に詳細を質問しましょう。例えば、「遮音材はどのくらい使われていますか?」や「音の苦情は過去にありましたか?」といった具体的な質問をすることで、誠実な対応かどうかも見えてきます。
このように、実際の環境をしっかりと確認しておくことで、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性を大幅に減らすことができます。音は目に見えないからこそ、慎重な事前チェックが住み心地の良い暮らしにつながるのです。
セキスイハイム うるさい問題を総括するポイント
- 鉄骨構造の特性で足音や話し声が響きやすい
- パネル工法により音の反響が大きくなる傾向
- 遮音間仕切りは効果はあるが過信は禁物
- 軽量鉄骨アパートでは上下左右の音が通りやすい
- 吸音材の使用や壁の厚みが遮音性に直結する
- 快適エアリーの室外機音が騒音の原因になることもある
- 家鳴りは構造上避けられないが頻度が高いと問題になる
- 施工不良により音が増幅されるリスクがある
- 検査体制に甘さがあり音の問題が見逃される可能性がある
- 防音対策はオプション選択や設計段階での工夫が重要
- 室外機や給湯器の設置場所によっては音が響きやすい
- 実際の住人の口コミに騒音に関する指摘が多く見られる
- 音に関する感覚は個人差が大きくトラブルに発展しやすい
- 入居前の時間帯別内覧が現実的な音環境の確認に有効
- 事前の質問や体験談の収集が後悔を避けるための鍵になる
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/



セキスイハイムで後悔したくない人は下の記事もチェックしてください。
評判
設備
- セキスイハイムの全館空調ってどう?気になる電気代やデメリットの口コミ紹介
- セキスイハイムの外壁で人気の種類は磁器タイル!塗り替え不要で美しい
- セキスイハイムのハイドア検討中なら見て!施工事例や価格相場を紹介
- セキスイハイムの床材の種類や種類|どんな人におすすめか選び方紹介
- セキスイハイムにサンルームを後付けしたい!リフォーム費用や日数は?
- セキスイハイムの新築でベランダなしってどう?リフォームできる?
- セキスイハイムのお風呂どれを選ぶか|気になるリフォーム費用も
- セキスイハイムの2階は暑い!?快適エアリーや24時間換気ならエアコンいらない?
メンテナンス・トラブル
- セキスイハイムのメンテナンス費用は年間5万〜10万円|外壁・屋根・定期点検について
- セキスイハイムの断熱材にカビが!?新築でも鉄骨内部で結露すればカビが発生
- セキスイハイムで新築なのにゴキブリ!?快適エアリーから虫が入り込むのか
間取り

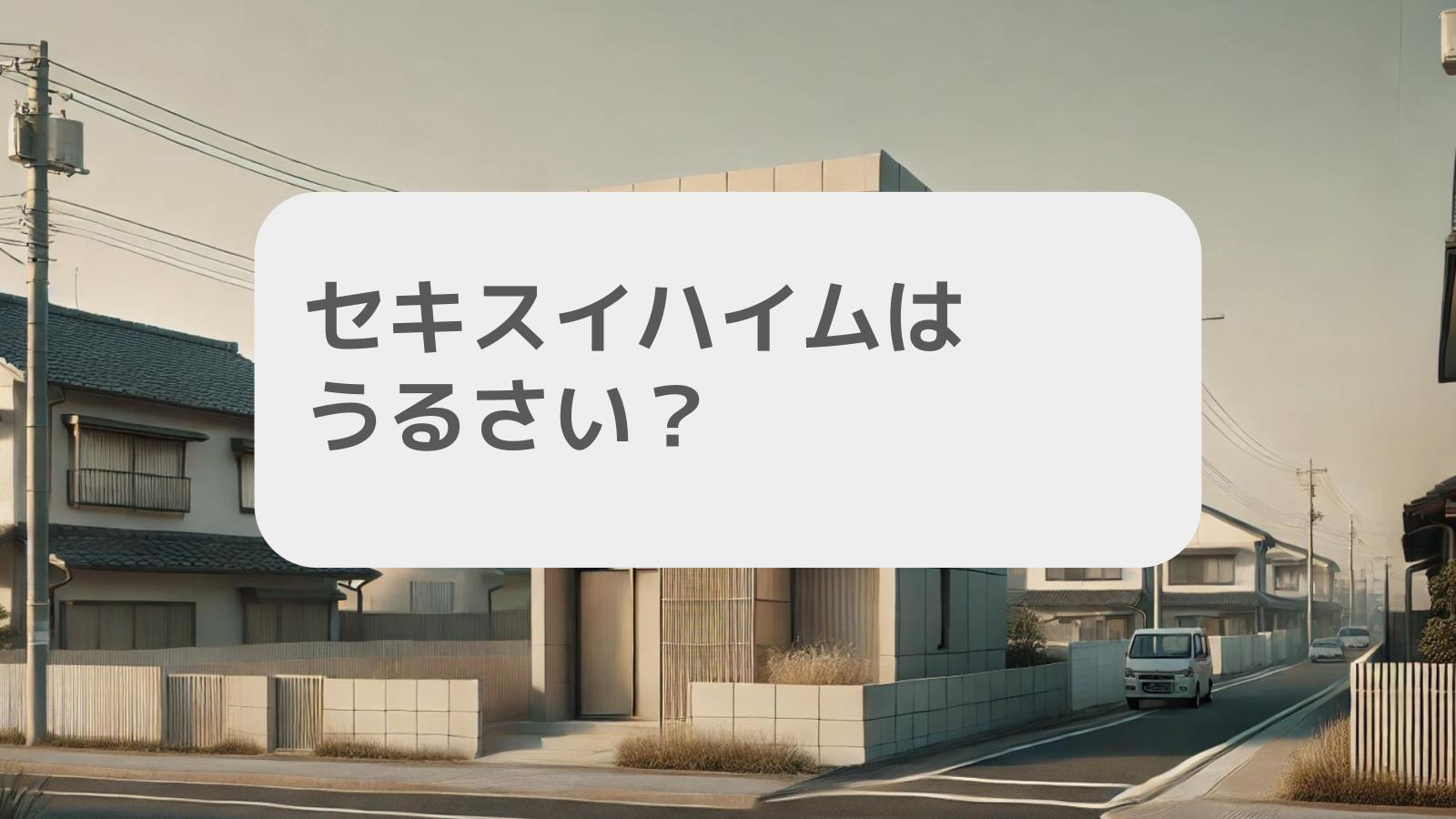



コメント