セキスイハイムで家を建てようと考えている方、あるいはすでに建てた方の中には、「セキスイハイム 断熱材 カビ」という検索をされた方も多いのではないでしょうか。
新築なのにカビ?と思うかもしれませんが、実際には施工ミスや湿気管理の不足によって、天井裏や壁内部にカビが発生するケースがあります。
とくに鉄骨構造では内部結露が起きやすく、それが断熱材に悪影響を及ぼす可能性も。
さらに、湿気がこもる場所には蟻やゴキブリといった害虫も侵入しやすく、新築ゴキブリ問題としても注目されています。
この記事では、快適エアリーのカビとの関係性、北海道セキスイハイムの断熱等級事情、また「セキスイハイムのグランツーユーの断熱等級は?」といった疑問まで、さまざまな観点から断熱材とカビの実態を解説します。
これから家を建てる方にも、すでにお住まいの方にも役立つ追加の対策方法や注意点を丁寧に紹介しています。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新築住宅のカビ発生原因 | 施工中の湿気、断熱材の乾燥不足、現場での湿気管理不足 |
| 断熱材のリスク | グラスウールなどの繊維系断熱材は湿気を吸収しやすい |
| 現場での施工ミス | 濡れた断熱材の使用、密閉構造による湿気の滞留 |
| 鉄骨内部の結露 | 鉄の高い熱伝導率により冬季に内部結露が発生しやすい |
| 快適エアリーとカビ | ダクト内の湿気がカビの温床に、メンテナンス不足が影響 |
| ゴキブリ・蟻の侵入 | 湿気や隙間がある断熱材周辺は害虫の温床になる |
| 防湿対策 | 防湿シートの追加施工や外張り断熱が有効 |
| 換気システムの重要性 | 24時間換気と第一種換気で湿気排出を強化 |
| 北海道での対応 | 断熱等級6相当の外壁TR工法で寒冷地に対応 |
| グランツーユーの断熱等級 | UA値は地域対応で5〜6相当、木質系でも高性能 |
| アフターサービス | セキスイファミエスが小さな不具合にも丁寧に対応 |
| おすすめの点検タイミング | 引き渡し直後と1年目、湿気が多い時期のチェックが有効 |
| 施工時の注意点 | 雨天時の作業回避と資材の保管環境の確認 |
| カビ予防の追加工事 | 抗ウイルスフィルター、通気層追加、換気設定の見直し |
| 日常の対策 | こまめなフィルター掃除と湿気のこもりやすい場所の換気 |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
セキスイハイムの断熱材とカビの実態
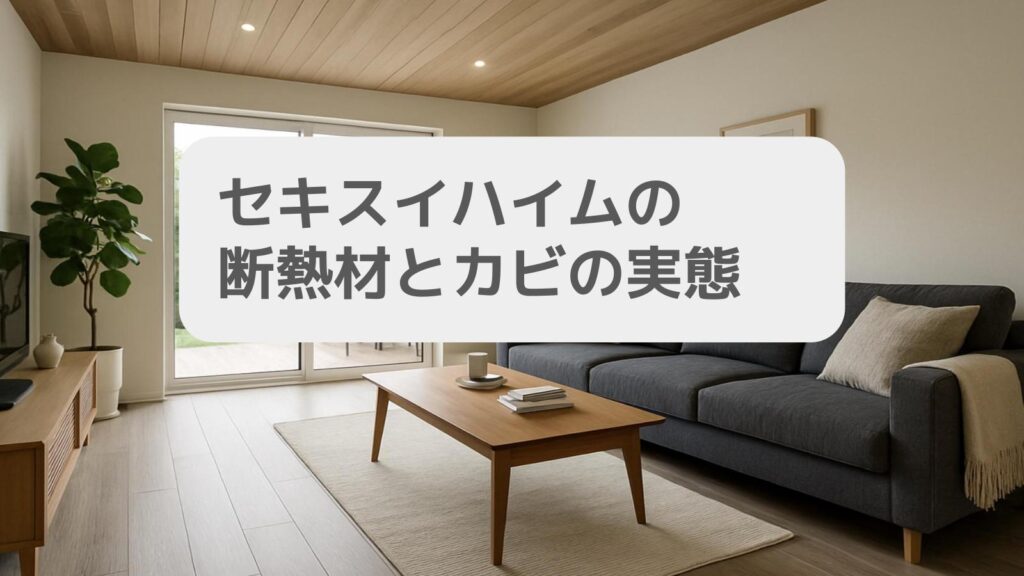
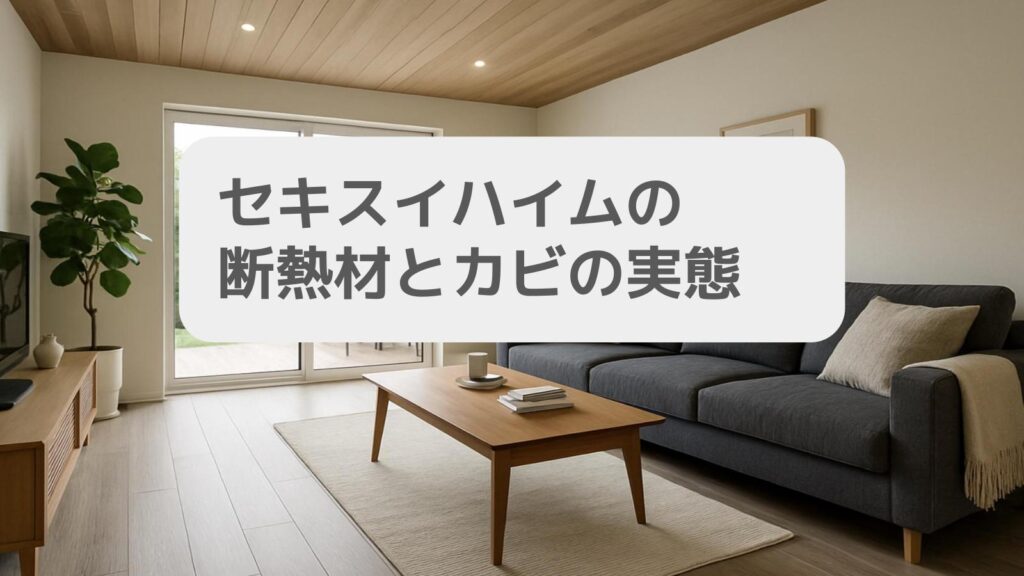
- 新築でカビが発生する原因とは?
- 断熱材に潜むカビのリスク
- 快適エアリーとカビの関係
- セキスイハイムの施工ミス事例
- ゴキブリや蟻の発生との関係
- 鉄骨内部 結露とカビの関係
新築でカビが発生する原因とは?
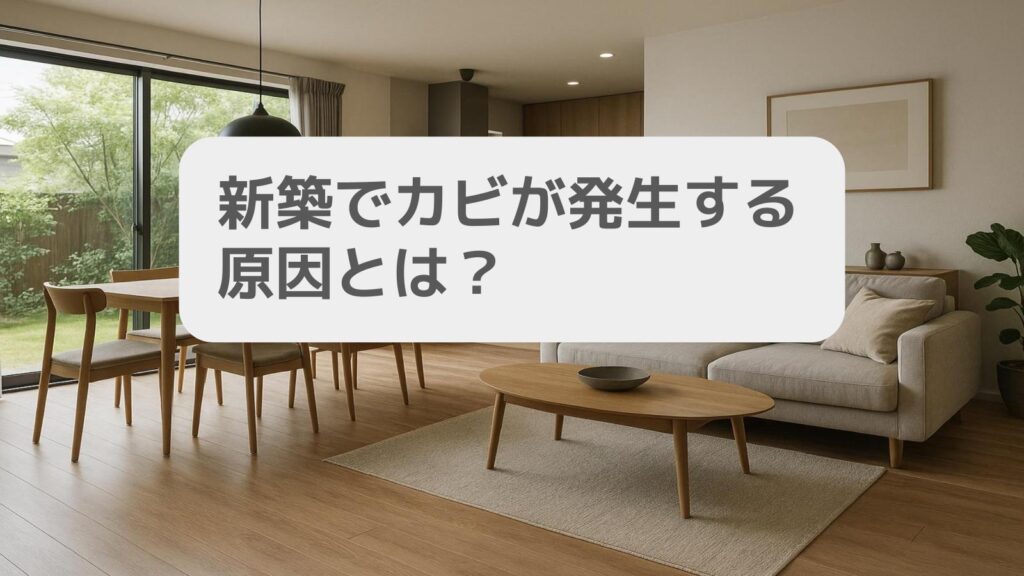
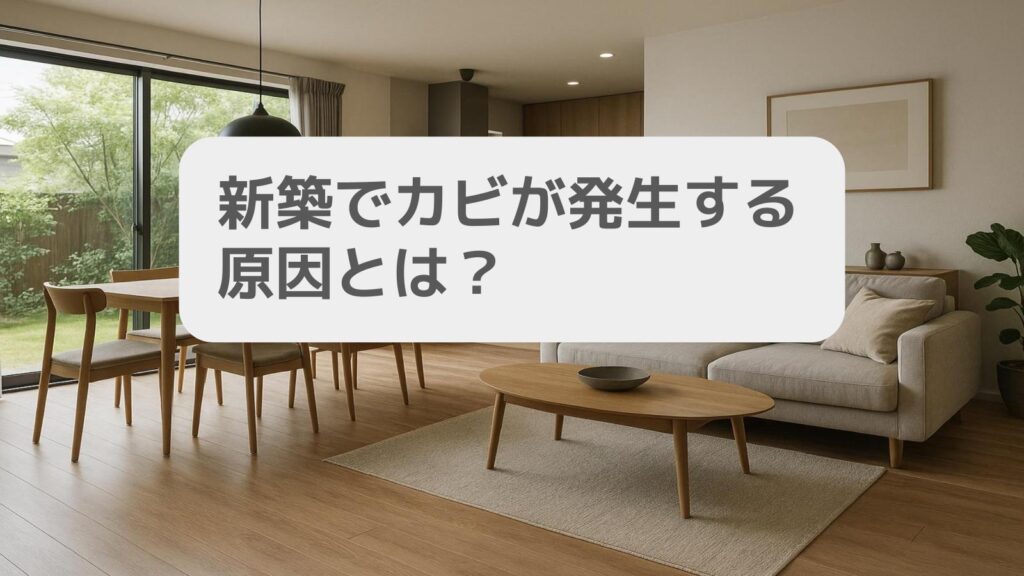
このように言うと驚かれるかもしれませんが、新築住宅でもカビが発生することがあります。よく「新築=清潔でカビなんて無縁」と思われがちですが、実は湿気の管理が不十分だと、完成して間もない家でもカビが繁殖してしまうのです。
その主な理由は、建築中に生じる湿気や断熱材の乾燥不足などです。とくに工場でユニットを組み立ててから現地に設置するセキスイハイムのようなユニット工法でも、現場での仕上げ作業や内装の施工において湿気が入り込むケースが少なくありません。
例えば、梅雨の時期や秋の長雨の中で作業が行われると、壁や天井の見えない部分に湿気がこもってしまいます。この湿気が断熱材や構造体に残ったまま密閉されると、そこにカビが発生してしまうのです。
また、資材の保管環境も重要です。屋外に置かれた断熱材が湿気を吸ってしまい、そのまま使用されると、カビの原因になることがあります。乾燥期間が十分に取られずに工事が進められるケースでは、内部の湿気が逃げ切らずに残ってしまうことも。
施工現場での確認が不足していたり、工期短縮を優先して乾燥時間が足りないまま次の工程に進むことも、リスクを高める原因です。加えて、建築時の天候や気温、湿度といった外部要因も無視できません。
このように、新築であっても湿気管理が甘いとカビの温床となってしまうことがあるため、しっかりとした監理体制と気候に配慮した施工スケジュールが求められます。
断熱材に潜むカビのリスク
言ってしまえば、断熱材の選定と施工ミスがカビの温床になることもあります。なぜなら、グラスウールなどの繊維系断熱材は湿気を吸いやすく、適切に処理されなければ室内に重大な影響を及ぼすからです。
特に注意すべきは、施工時に断熱材が湿った状態で使われるケースです。そのまま壁や天井の中に密閉されると、乾燥できないまま内部に湿気がこもり、目に見えない場所でカビが静かに繁殖していきます。
例えば、外壁側から雨水が浸入したり、床下の湿度が高かったりすることで、断熱材に水分が蓄積されやすくなります。この状態が長く続くと、カビの発生だけでなく、建物自体の寿命を縮める原因にもなりかねません。
さらに、壁内や天井裏など空気の流れが悪い場所では、断熱材に吸収された湿気が逃げ場を失い、温度差が生まれることで結露が発生することもあります。こうした環境下では、カビが急速に成長しやすくなるのです。
このような事態を防ぐには、断熱材の選定時に耐湿性や乾燥性を十分に確認し、施工現場での取り扱いにも細心の注意を払う必要があります。また、断熱材を充填する前に壁内の湿度や温度を計測し、乾燥状態を確認することも重要な工程です。
このため、どんなに高性能な断熱材を使っていたとしても、施工方法や現場管理が不十分であれば、その効果を発揮できないどころか、住む人の健康を損なうようなトラブルの原因になってしまうのです。
快適エアリーとカビの関係
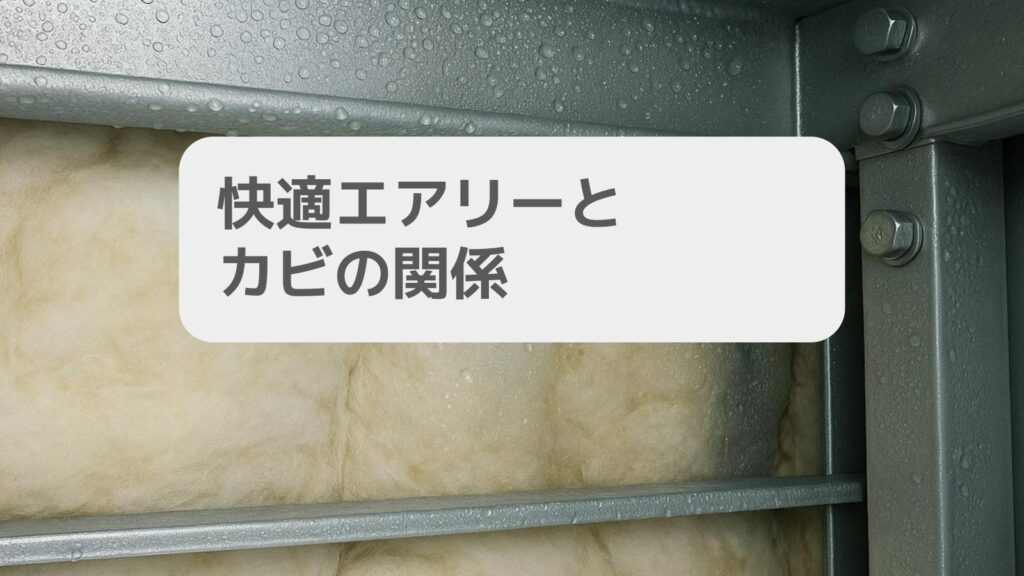
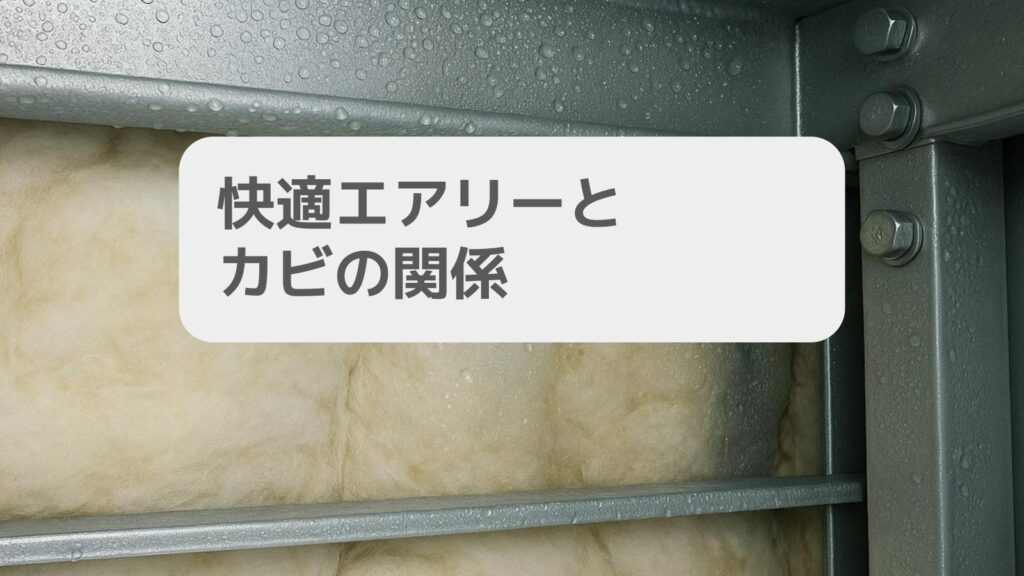
これは意外かもしれませんが、セキスイハイムの全館空調システム「快適エアリー」も、カビの問題と完全に無関係ではありません。見た目や機能は非常に快適で便利に思えますが、実際には運転の仕方や手入れの状況によっては、内部にカビが発生するリスクがあるのです。
このシステムは、家中をほぼ同じ温度に保つことができる優れた設備です。冬は暖かく、夏は涼しく、部屋ごとの温度差が少ないため、ヒートショックなどのリスクも軽減できます。ただし、それがかえって落とし穴にもなり得ます。
例えば、常に湿度が一定に保たれる環境では、カビの繁殖に適した条件が整いやすくなります。特に、ダクト内に湿気がこもったままになっていると、その場所はカビの温床になります。さらに、日々のメンテナンスが不十分だったり、フィルター掃除を怠ったりすると、そこから空気中にカビの胞子が放出される可能性もあります。
また、快適エアリーは24時間稼働を前提としていますが、「電気代がもったいないから」といって運転を頻繁に停止してしまうのも要注意です。システムの起動・停止を繰り返すことで、温度差が生まれてダクト内で結露が発生しやすくなり、その結果、カビが繁殖しやすくなることもあるのです。
このため、快適エアリーを清潔かつ安全に保つには、定期的なフィルター掃除はもちろんのこと、ダクト内の点検や換気モードの適切な活用も欠かせません。通気性をしっかり保つことで、湿気がたまらない環境づくりができます。
つまり、快適エアリーは非常に便利で快適な設備ですが、その機能を最大限に活かすには「正しい使い方」と「こまめな手入れ」が不可欠です。
セキスイハイムの施工ミス事例
このため、施工段階でのチェック体制はとても大切です。現場での丁寧な管理や確認作業が不足すると、たとえ高品質を謳う住宅メーカーでも思わぬトラブルに見舞われることがあります。実際に「天井裏からカビが見つかった」という報告もあり、多くの施主が驚きと不安を感じています。
その背景には、さまざまな施工ミスの可能性があります。特に多いのが、資材の保管状態が悪く、屋外で湿気を含んだ状態の断熱材がそのまま使われてしまうというケースです。また、現場で断熱材を壁や天井に詰める際の取り扱いに不備があると、密閉された空間に湿気がこもり、時間とともにカビが発生してしまいます。
断熱材の裏側やユニット同士の継ぎ目、配線が通る穴の周辺など、普段は見えない場所こそ要注意です。そこには湿気が溜まりやすく、カビが目に見える形で現れるころには、すでに深刻な状態に進行していることもあります。さらに、施工手順が省略されていたり、確認工程が十分に実施されていない場合、問題が表面化するまで気づけないことも少なくありません。
こうした事例を防ぐためにも、建築中はできるだけ現場の様子を自分の目で確認し、違和感を感じたらすぐに担当者に相談することが大切です。施工ミスが疑われる場合は、アフターサービスに記録や写真を添えて連絡し、早期対応を求めましょう。時間が経つと、原因の特定が難しくなったり、保証の対象外になる可能性もあるため、気づいた時点で行動に移すことが重要です。
このように、家づくりでは「完成したら終わり」ではなく、その過程とその後の対応までしっかりと見守っていくことが、安心して長く住める住宅を手に入れるための第一歩となります。
ゴキブリや蟻の発生との関係
もしかしたら意外かもしれませんが、セキスイハイムの家でのゴキブリや蟻といった害虫も断熱材の問題と密接に関係していることがあります。というのも、湿気がこもっている場所というのは、彼らにとって非常に居心地の良い環境なのです。人にとっては不快な湿気も、害虫にとっては生存と繁殖に適した場所だということを忘れてはいけません。
蟻に関しては、特に外壁と基礎のわずかな隙間や、床下から天井裏にかけての狭いスペースから入り込んでくることがあります。実際に、こうした隙間を通じて数匹から十数匹単位で出没することも珍しくありません。彼らはわずかな食べかすや水気を求めて移動し、住空間へと侵入してくるのです。
また、ゴキブリはさらにやっかいな存在です。成虫はもちろんですが、卵の段階で持ち込まれるケースが多く、特に引っ越し時の荷物やダンボール、ネット通販などで届く梱包材の隙間などに潜んでいることがあります。これらが室内に運び込まれ、快適な湿気の多い場所に留まると、いつのまにか繁殖を始めてしまうのです。
特に断熱材がカビや湿気を含んでいるような状態だと、害虫にとってはまさに楽園となってしまいます。このような事態を防ぐためには、建築段階から湿気の管理に注意するだけでなく、建物の構造上の隙間をしっかりと塞ぎ、侵入経路を断つことが欠かせません。
さらに、入居後の対策としては、湿気のこもりやすい床下や収納スペース、キッチン周辺などに防虫剤を適切に配置したり、定期的に点検を行うことも有効です。市販の防虫スプレーやベイト剤だけでなく、網状の素材で通気性を保ちつつ物理的に虫の侵入をブロックする方法も取り入れると安心です。
このように考えると、ゴキブリや蟻の発生は単なる衛生管理の問題にとどまらず、断熱材の状態や施工精度とも大きく関係していることがわかります。住まいの快適性と清潔さを保つためには、こうした見えにくいポイントへの配慮がとても重要なのです。
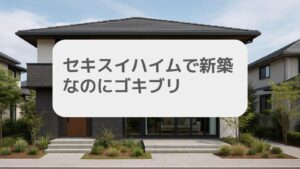
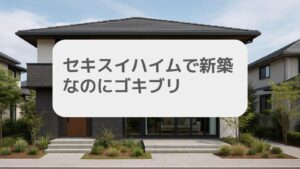
鉄骨内部 結露とカビの関係
これは断熱材の問題とも密接につながっていますが、鉄骨構造の住宅では、内部結露が非常に起きやすい傾向があります。なぜなら、鉄という素材は熱伝導率がとても高く、外気温との差が大きくなればなるほど、冷たい表面に湿気が触れて水分へと変化しやすいからです。
例えば、寒い外気と暖かい室内の温度差が大きい冬場では、鉄骨部分が外気で冷やされ、内部の温かく湿った空気が冷たい鉄表面に接触することで結露が発生します。この水分は目に見えるほどの水滴になる場合もあれば、断熱材の中にじわじわとしみ込んでいくこともあります。
その結露水が断熱材に吸収されてしまうと、長期間にわたってカビの繁殖や腐食を引き起こすリスクが高まります。鉄骨は木材のように腐ることは少ないものの、湿気が継続的に付着することでサビが発生しやすくなり、構造体の強度低下につながるおそれがあります。
さらに、サビが進行すれば接合部の耐久性が落ち、地震などの揺れに対する耐性が弱まるという懸念も出てきます。これは特に築年数が経過した後に表面化しやすいため、初期の段階で対策を講じておくことが大切です。
このため、鉄骨住宅では適切な防湿処理が必須となります。例えば、防湿シートの正しい施工や、断熱材の外張り・内張りを組み合わせた方法での施工、さらに通気層の確保などが効果的です。また、空気の流れを計算した設計や、気密性と換気性のバランスを考慮した家づくりが求められます。
実際、断熱材と鉄骨の接触部分に十分な絶縁層を設けることで、熱橋(ヒートブリッジ)を減らすことが可能になります。こうした工夫により、結露の発生自体を抑えられ、カビやサビのリスクも大幅に下げることができます。
このように、鉄骨構造の家づくりでは「見えない湿気との戦い」が大きなテーマになります。安心して長く暮らすためには、断熱だけでなく、防露対策・通気・設計力を総合的に考えることが必要です。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
セキスイハイムの断熱性能と対策|断熱材にカビが生えたら
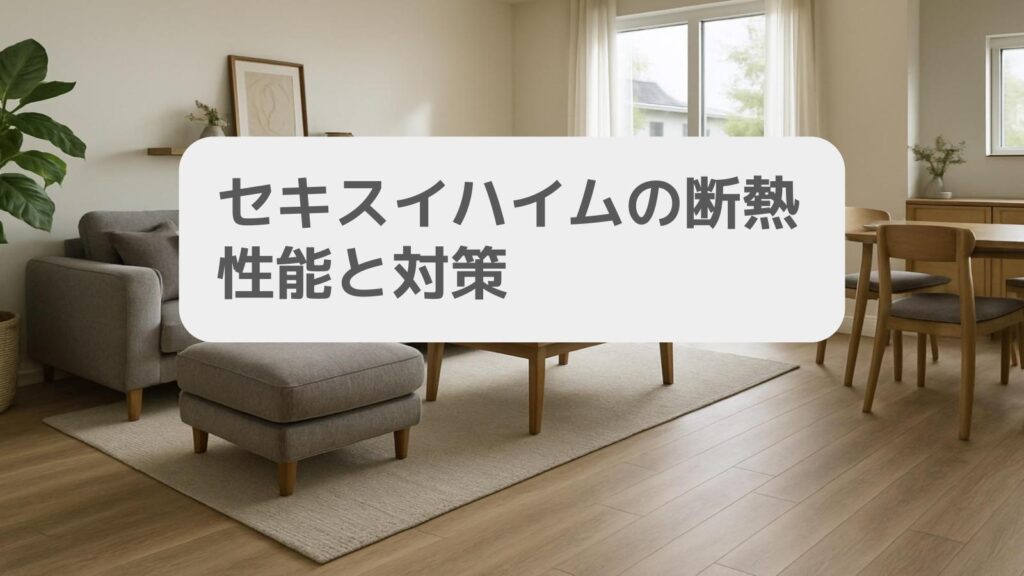
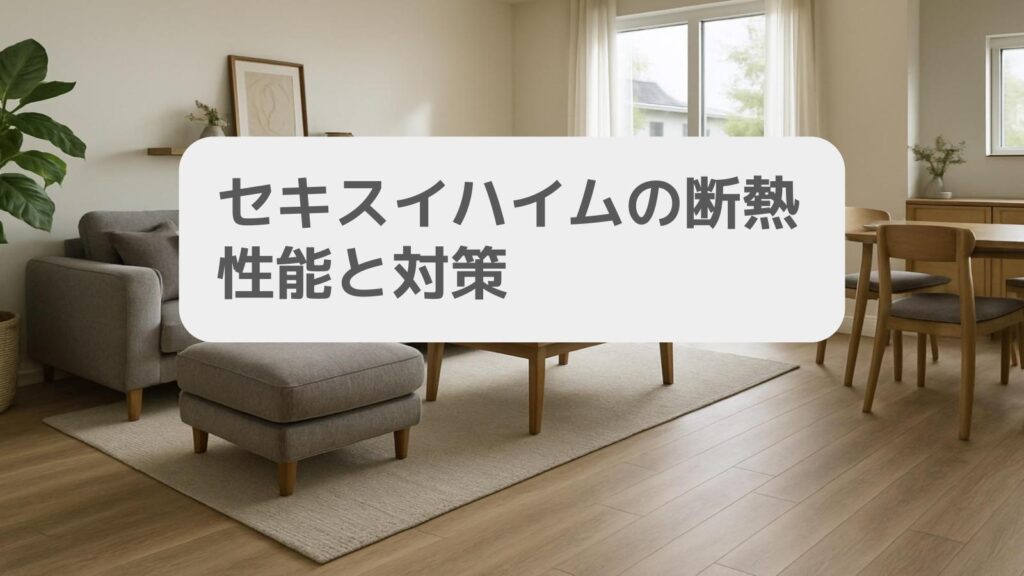
- 北海道セキスイハイム 断熱等級の現状
- セキスイハイムのグランツーユーの断熱等級は?
- カビ対策に必要な追加工事とは
- セキスイハイムの気密と換気性能
- 新築 ゴキブリ対策のポイント
- 断熱性能とアフター対応の評価
北海道セキスイハイム 断熱等級の現状
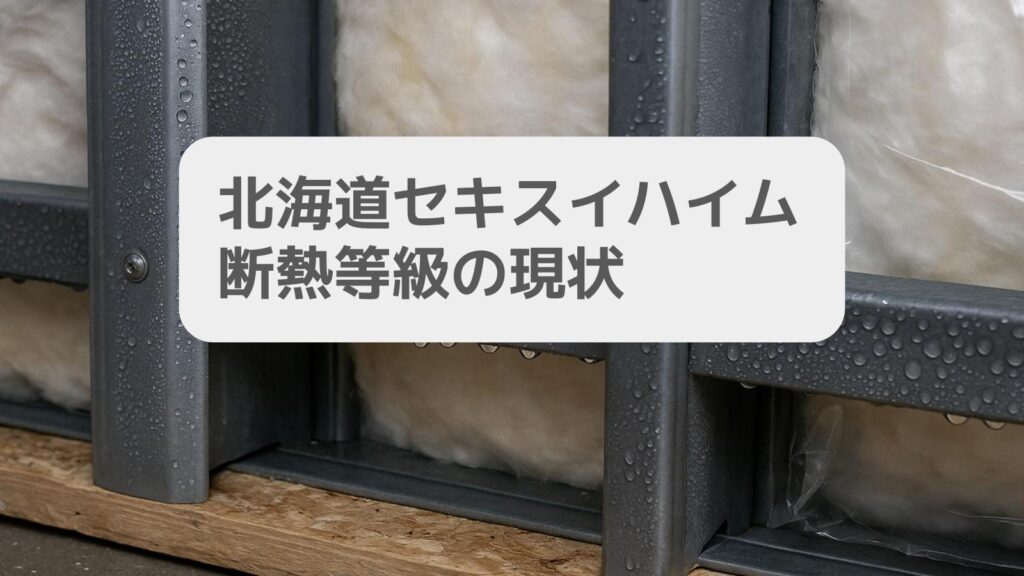
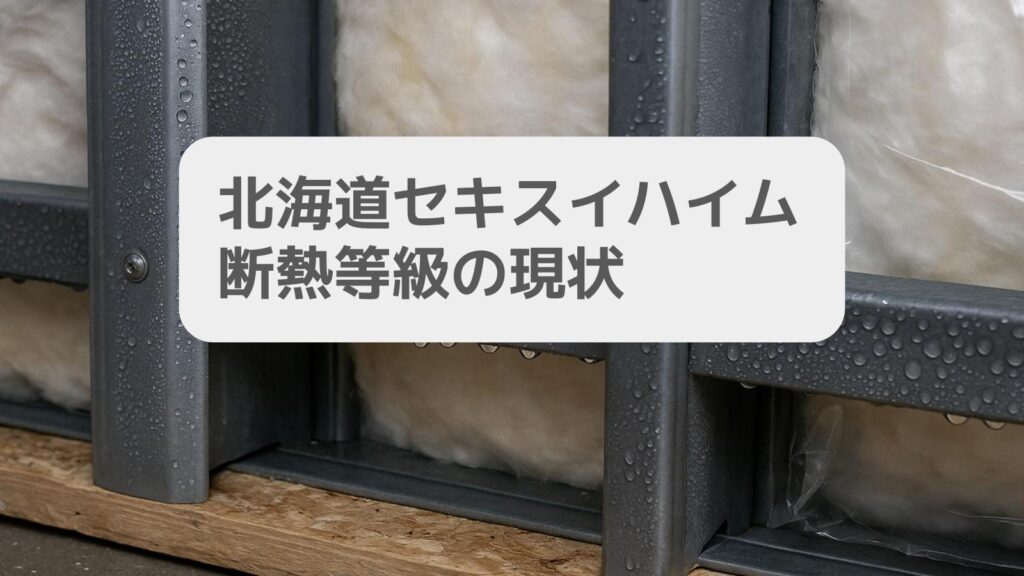
例えば、北海道のような寒冷地では断熱性能が住まいの快適性を大きく左右します。外気温が極端に低くなるこの地域では、暖房効率が住宅の暮らしやすさや光熱費に直結するため、断熱性能の高さが非常に重要です。
セキスイハイムでは、このような地域特性を踏まえて、地域ごとに最適な断熱等級の設計を行っています。特に北海道では、国の省エネ基準である断熱等級5を超える、等級6相当の高性能仕様を提供しており、厳しい気候にも対応可能な断熱構造が整っています。これは、外皮平均熱貫流率(UA値)で0.46以下を達成する設計となっており、業界内でも高い水準といえるでしょう。
その中でも注目されているのが、新仕様の「外壁TR」です。この仕様では、既存の壁構造の外側にさらに断熱材を追加施工する「外張り断熱工法」を採用しており、これによって断熱効果を大幅に向上させることができます。しかもこの工法は、室内に手を加えることなく、住みながら施工が可能という利点があり、リフォーム時の負担が最小限に抑えられます。
さらに、断熱性能の向上は省エネ性だけでなく、家全体の温度差を減らすことでヒートショックの防止やアレルギー対策にもつながります。室内の温度を安定させることができれば、家族全員が一年を通じて快適に暮らすことができるでしょう。
それでは、実際にどのような断熱材が使用されているのか、また施工方法はどうなっているのかを確認しておくと、より安心して選択することができます。建築を検討する際には、モデルハウスの仕様や担当者への質問を通じて、こうした技術的な部分にも目を向けてみてください。
セキスイハイムのグランツーユーの断熱等級は?
このグランツーユーシリーズは、セキスイハイムの中でも木質系住宅に分類されるモデルです。鉄骨構造のシリーズに比べて、木のぬくもりや自然素材の印象を重視した設計がされている一方で、断熱性能においても十分な配慮がなされています。
断熱性能の指標であるUA値(外皮平均熱貫流率)や気密性能については、地域区分や設計条件によって異なるものの、寒冷地での建築にも対応できるように調整されています。たとえば、北海道や東北のような寒さの厳しい地域でも、断熱等級5〜6相当をクリアできるような仕様を選択することが可能です。
断熱材にはグラスウールが採用されており、工場でのプレカットと現場での正確な施工によって、熱の出入りを最小限に抑える構造となっています。また、トリプルガラスの窓や、床・天井の断熱強化により、冷暖房効率の高い快適な住まいが実現されています。
一方で、注意したいのが施工時の湿気管理と気密測定の信頼性です。UA値やC値(気密性能の数値)は設計上の理論値であり、実際の現場での施工精度によって性能が左右されることが少なくありません。特に木造住宅では、構造材や断熱材が湿気の影響を受けやすいため、施工中の資材管理や乾燥状態の確認が欠かせません。
また、気密測定は引き渡し前に一度行われるケースが多いですが、数値だけでなく測定環境や測定方法の正確性にも注目する必要があります。施主が立ち会うことで、安心感が増すだけでなく、施工側もより丁寧に対応してくれる可能性があります。
実際に建てた方の口コミやレビューを確認することも非常に有益です。とくに、居住後数年が経過したユーザーの声は、初期の快適さだけでなく、断熱・気密性能の持続性についてのヒントを得るうえで参考になります。
このように、グランツーユーは木造住宅ながらも高い断熱性能を持ち合わせていますが、より快適な住まいを目指すなら、設計段階から断熱仕様に注目し、施工時にも細やかなチェックを重ねることがポイントとなります。
カビ対策に必要な追加工事とは
こうしたトラブルを防ぐには、必要に応じて「追加工事」を検討することも非常に大切です。とくに新築時やリフォーム時には見落とされがちですが、湿気対策の不足や空気の循環不足が、後々カビの温床になってしまうことは珍しくありません。
そのため、断熱材の性能を高めるだけでなく、防湿層を強化することも有効です。具体的には、壁の内側に湿気を通さない防湿シートを追加したり、天井裏や床下の断熱構造を二重化して湿気の流入を抑えたりする工法があります。また、防湿材と断熱材の接合部分の気密処理をしっかり行うことで、湿気の侵入経路を断つ効果も期待できます。
換気システムを見直すことも重要です。もともと備え付けられている第三種換気を、より高性能な第一種換気(熱交換型)に変更することで、室内の温度差を減らしつつ効率的に湿気を排出できます。これにより、結露やカビのリスクを根本から抑えることができます。
さらに、ダクト内にカビが発生するのを防ぎたい場合は、抗ウイルス対応の高性能フィルターを追加で設置するのが効果的です。これらのフィルターはウイルスやホコリだけでなく、カビの胞子もキャッチし、室内の空気環境を清潔に保ちます。合わせて、快適エアリーのような全館空調システムでは「常時換気モード」や「おすすめタイマー」などの設定を活用して、湿度が溜まりにくい環境を維持する工夫も大切です。
こうした追加工事や設備強化は、新築後でも対応可能なケースが多く、費用対効果の面でも高く評価されています。とくに、住みながらの施工が可能な場合は仮住まいも不要なため、時間や手間の負担を最小限に抑えられます。
気になる箇所がある場合は、まずはセキスイファミエスなどの専門スタッフに相談してみましょう。建物の構造や地域の気候条件に合わせて、最適な対策を提案してもらうことができます。
セキスイハイムの気密と換気性能
実際、セキスイハイムでは高気密・高断熱を強みとしており、C値(隙間相当面積)は0.9㎠/㎡以下を目安に施工が行われています。C値とは、住宅全体にどれだけの隙間があるかを数値で表したもので、この数値が低いほど気密性が高く、外気の影響を受けにくい家といえます。そのため、冷暖房効率が高まり、省エネ性能や室内の快適さにも大きく貢献しています。
さらに、この高い気密性を活かすために、セキスイハイムでは24時間換気システムが標準で設置されています。これは、住まいの空気を常に新鮮な状態に保つための仕組みで、窓を開けなくても室内の空気の入れ替えが自動的に行われます。特に、第三種換気システムを基本とし、オプションで第一種換気(熱交換型)にアップグレードすることも可能です。
ただし、どんなに高性能な換気システムが備わっていても、日常的なメンテナンスを怠ると効果が大きく下がってしまいます。例えば、給気口や排気口のフィルターにホコリが溜まると、風量が低下し、室内に十分な空気が循環しなくなります。これが原因で湿気がこもりやすくなり、壁や天井、家具の裏などにカビが発生するケースもあります。
また、季節によって外気温や湿度が大きく変わるため、その時期に合わせて換気モードを調整することも忘れてはいけません。たとえば、冬は外気の乾燥と寒さを取り込みすぎないように、風量を調整したり、熱交換換気を活用することでエネルギーロスを防ぐことができます。
換気性能を最大限に活かすには、換気システムの動作状況を定期的に確認し、年に1~2回のフィルター清掃や交換を行うことが重要です。取扱説明書に記載された清掃方法を守ることで、快適な空気環境を保ち続けることができます。
このように、セキスイハイムの高気密・高断熱構造は非常に優れていますが、それに見合った換気計画と手入れがあってこそ、その性能を十分に発揮できるのです。
新築 ゴキブリ対策のポイント
新築だからといって、ゴキブリが絶対に出ないとは限りません。新築の家には「虫がいない」というイメージを持つ方が多いですが、実際には建築中や引っ越しの荷物搬入時に、思わぬルートからゴキブリが入り込むことがあります。特にダンボールなどの梱包資材には、卵や成虫が潜んでいることもあるため注意が必要です。
また、引っ越し時には旧居から持ち込まれた家具や家電の裏などにゴキブリが隠れていることも。とくに冷蔵庫や電子レンジのような熱源は、ゴキブリが好む温かく狭い空間なので、搬入前に簡単な清掃や殺虫スプレーの使用を検討するのもよいでしょう。
こうした侵入リスクを抑えるために、バルサンの使用やホウ酸団子の配置といった対策は非常に効果的です。新居に入る前のタイミングで煙タイプの殺虫剤を焚いておけば、入り込んでいたゴキブリを一掃しやすくなります。ホウ酸団子は長期間効力を発揮し、巣ごと駆除できる可能性があるため、キッチンや洗面所、玄関回りなどに設置するのがオススメです。
さらに、侵入経路を塞ぐ物理的な対策も欠かせません。玄関やバルコニー付近、窓のサッシの隙間やエアコンの配管穴など、小さな隙間をシーリング材やパテでしっかりと塞ぎましょう。網戸がきちんと閉まっているか、隙間ができていないかも確認しておくと安心です。
そして、何よりも重要なのは、室内環境を常に清潔に保つことです。ゴキブリは食べ物のカスや湿気のある場所を好むため、食べこぼしはすぐに拭き取る、排水口の掃除を定期的に行う、生ごみは密閉して早めに処分するといった日々の小さな習慣が大きな予防効果につながります。
加えて、ゴキブリが嫌うアロマや忌避剤を使った対策も効果的です。ハーブ系の香り(ミント、ラベンダー、ユーカリなど)には忌避効果があるとされており、ディフューザーやスプレーで香りを広げることで、ゴキブリを寄せ付けにくくすることができます。
このように、新築でもゴキブリの侵入リスクはゼロではありませんが、事前と事後の対策をしっかり行えば、十分に予防できます。安心して新生活をスタートするためにも、ゴキブリ対策は家づくりの一環として意識しておくとよいでしょう。
断熱性能とアフター対応の評価
こう考えると、断熱材や気密性といった性能面だけでなく、実際に暮らし始めてからのアフターサービスの充実度も、住まい選びの大切な判断基準になります。どれだけ優れた性能を誇っていても、入居後に発生するちょっとした不具合やトラブルに迅速かつ丁寧に対応してくれる体制があるかどうかは、暮らしの満足度を大きく左右します。
実際に、セキスイハイムのアフターサポートを担うセキスイファミエスの対応事例を見ると、蟻の侵入や壁紙の浮き、建具の建て付けの微調整など、ごく小さな問題にまで無償で対応している例が多く報告されています。中には、見えない場所にまで潜む湿気トラブルを調査するため、床下へ潜ったり、外壁の隙間に防虫網を二重に設置するようなきめ細かな対応を行っているケースもあります。
このように、目に見える不具合だけでなく、将来的な劣化や健康への影響を見越した処置をしてくれる点も、セキスイハイムの信頼性の高さを裏付けているといえるでしょう。さらに、定期点検のスケジュールも整備されており、建築後数年間にわたって定期的に住まいの状態をチェックしてもらえるのも安心材料です。
万が一、問題が発生したときには、言葉だけで説明するよりも、写真や日付入りのメモなどを添えて相談すると、対応がスムーズになります。特に湿気やカビ、床鳴りなど目に見えにくい現象の場合は、記録があるかどうかで対応のスピードが変わることもあります。
つまり、高い断熱性能や気密性だけでなく、それを維持するための継続的な点検や、丁寧で信頼できるフォロー体制が揃ってこそ、長く快適に安心して暮らせる住まいが実現するのです。
セキスイハイムの断熱材 カビ問題の総まとめ
- 新築でも断熱材に湿気が残ればカビが発生する可能性がある
- 工場生産でも現場作業中の湿気管理が甘ければ意味がない
- 雨天時の施工や乾燥期間不足がカビの要因となる
- 屋外に放置された断熱材の使用はリスクが高い
- グラスウールなど吸湿性の高い断熱材は特に注意が必要
- 結露が起きやすい場所に断熱材があるとカビが発生しやすい
- 快適エアリーのメンテナンス不足もカビの温床になる
- ダクト内の湿気や汚れが放置されると空気中に胞子が拡散する
- 鉄骨構造は結露しやすくサビやカビの原因になり得る
- 防湿層の施工精度が住宅全体の健康を左右する
- ゴキブリや蟻は断熱材周辺の湿気を好んで侵入してくる
- 隙間のある施工は害虫侵入と湿気滞留の両面でリスクがある
- 断熱等級が高くても現場施工の質が悪ければ意味がない
- カビ対策として第一種換気や高性能フィルターの導入が有効
- セキスイファミエスのアフター対応は信頼性の一因となる
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/



セキスイハイムで後悔したくない人は下の記事もチェックしてください。
評判
設備
- セキスイハイムの全館空調ってどう?気になる電気代やデメリットの口コミ紹介
- セキスイハイムの外壁で人気の種類は磁器タイル!塗り替え不要で美しい
- セキスイハイムのハイドア検討中なら見て!施工事例や価格相場を紹介
- セキスイハイムの床材の種類や種類|どんな人におすすめか選び方紹介
- セキスイハイムにサンルームを後付けしたい!リフォーム費用や日数は?
- セキスイハイムの新築でベランダなしってどう?リフォームできる?
- セキスイハイムのお風呂どれを選ぶか|気になるリフォーム費用も
- セキスイハイムの2階は暑い!?快適エアリーや24時間換気ならエアコンいらない?
メンテナンス・トラブル
- セキスイハイムのメンテナンス費用は年間5万〜10万円|外壁・屋根・定期点検について
- セキスイハイムの断熱材にカビが!?新築でも鉄骨内部で結露すればカビが発生
- セキスイハイムで新築なのにゴキブリ!?快適エアリーから虫が入り込むのか
間取り

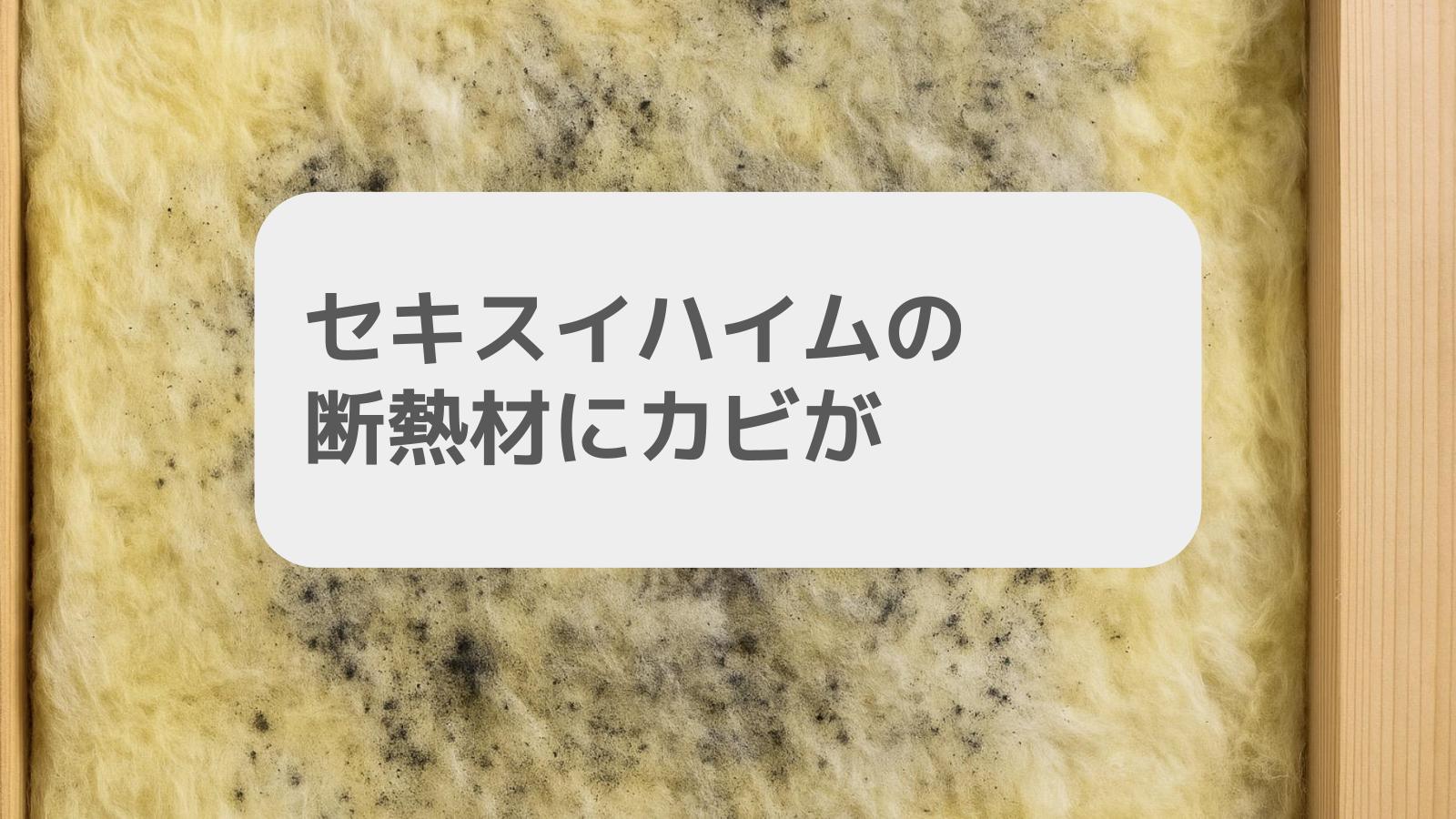


コメント