「一条工務店 ゴキブリ」と検索している方の多くは、高気密・高断熱の住宅でも害虫の侵入をどう防げばよいのか悩んでいるのではないでしょうか。
一条工務店の家は性能が高い反面、給気口やドレンヒーターなどから虫が入ってしまうこともあります。
この記事では、バルサンとロスガードの併用時に注意すべきポイントをはじめ、湿気を好むチャタテムシやコバエ、ムカデ、蚊といった害虫への対策方法を詳しく解説しています。
さらに、トビムシなど一見ゴキブリに似た気持ち悪い虫との見分け方や、換気システムの寿命が室内環境に与える影響についても触れています。
一条工務店の家で快適な暮らしを続けるために、今すぐ始められる防虫対策をまとめました。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 対策ポイント | 具体的な方法 | 補足情報 |
|---|---|---|
| バルサン使用時の注意 | ロスガードを停止してから使用 | 換気は2~3時間後に自然換気で対応 |
| 給気口からの虫侵入 | 防虫フィルター+防虫ネットを設置 | PM2.5対応フィルターならより安心 |
| ドレンヒーター周辺の対策 | 配管の隙間を発泡ウレタン等で封鎖 | 温かさがゴキブリの侵入を誘発 |
| チャタテムシの予防 | 除湿+紙類の整理整頓 | 押し入れ・収納に発生しやすい |
| コバエの対策 | 生ゴミ密閉・排水口の清掃 | 観葉植物の土管理も重要 |
| ムカデの侵入防止 | 外周に防虫粉剤を散布 | 室内は粘着トラップで補完 |
| 蚊の対策 | 水たまり排除・虫除け植物設置 | レモングラスやミントがおすすめ |
| トビムシの見分け | 白く小さく跳ねる虫は無害 | 湿度を下げて予防可能 |
| 換気と家の寿命 | ロスガードの定期メンテナンス | フィルター清掃で性能維持 |
| 清掃習慣の徹底 | キッチン・収納の定期清掃 | ゴキブリゼロの基本対策 |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
一条工務店 ゴキブリ対策の基本
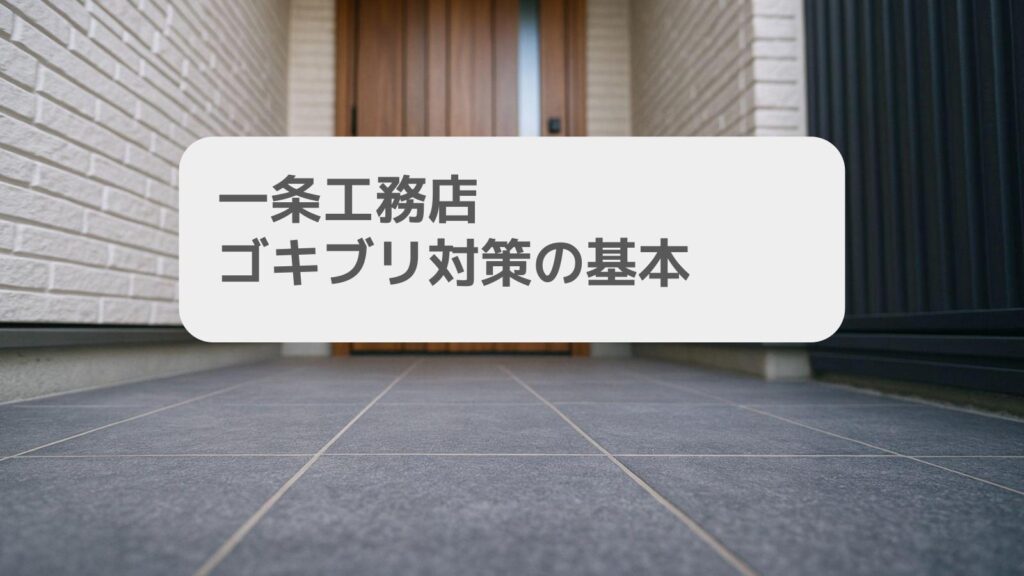
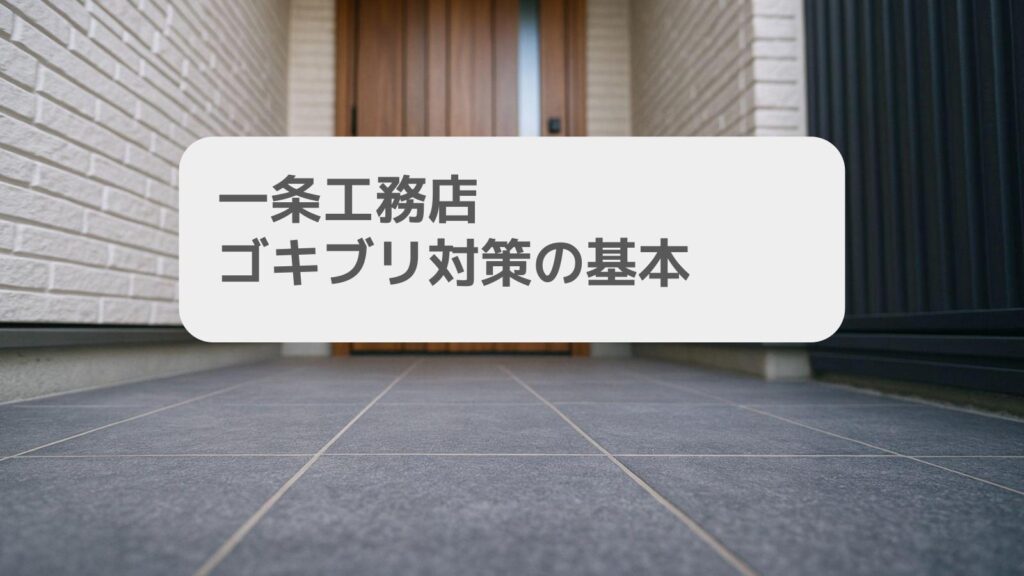
- バルサンとロスガードの併用方法
- 給気口から虫が侵入する理由
- ドレンヒーターとゴキブリの関係
- チャタテムシが発生する原因とは
- コバエの発生源と防止策
- ムカデの侵入経路と撃退法
バルサンとロスガードの併用方法


バルサンを使ってゴキブリ対策を行う場合、一条工務店の家に搭載されている換気システム「ロスガード」との兼ね合いが気になるところです。特に初めて使用する方は、「換気したら薬剤が逃げてしまうのでは?」と不安に思うかもしれません。
実際、ロスガードを稼働させたままバルサンを焚いてしまうと、せっかく部屋全体に広がるはずの殺虫成分が、フィルターを通して外へ排出されてしまいます。これではバルサンの効果が薄れてしまいますよね。
このため、バルサンを使用する際は事前にロスガードを停止することがとても重要です。停止の手順は操作パネルから簡単に行えるため、事前にマニュアルで確認しておくとスムーズです。
例えば、バルサンの煙や霧をしっかり行き渡らせたい場合は、使用後2~3時間ほどはロスガードや換気扇をすべて止めておきましょう。その間は窓やドアも閉めておくことが基本です。
使用後にはしっかりと自然換気を行いましょう。窓を複数箇所開けて、風通しの良い状態を10分~30分ほど確保すれば、薬剤のにおいや残留成分を効率よく追い出せます。その後、ロスガードを再稼働させれば、空気の入れ替えと室内環境の安定が保たれます。
このように言うと面倒に思えるかもしれませんが、事前準備と後片付けを丁寧に行えば、バルサンの効果を最大限に引き出すことができます。ロスガードがあるからこそ、正しい手順を理解して安心して使いましょう。
給気口から虫が侵入する理由
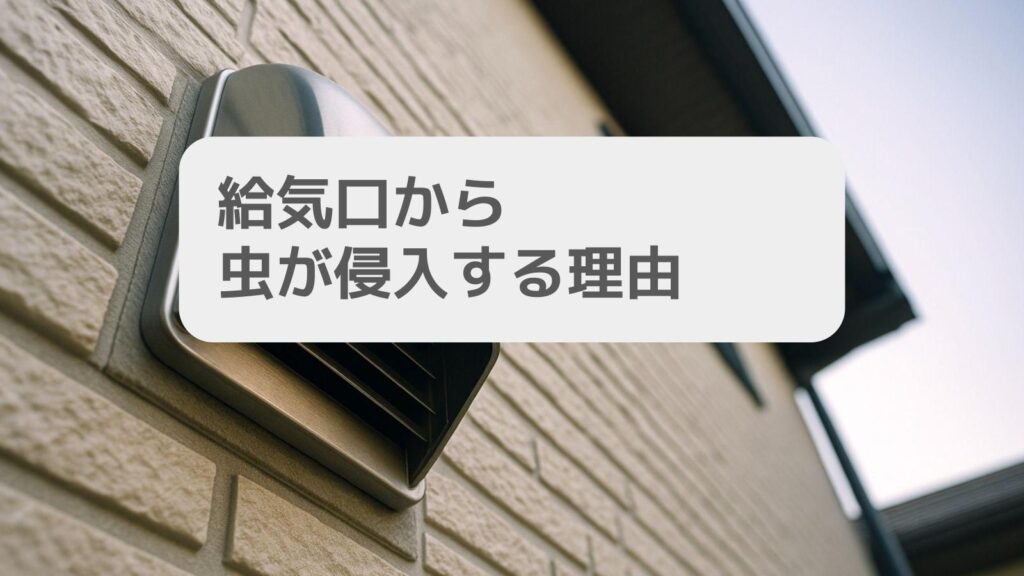
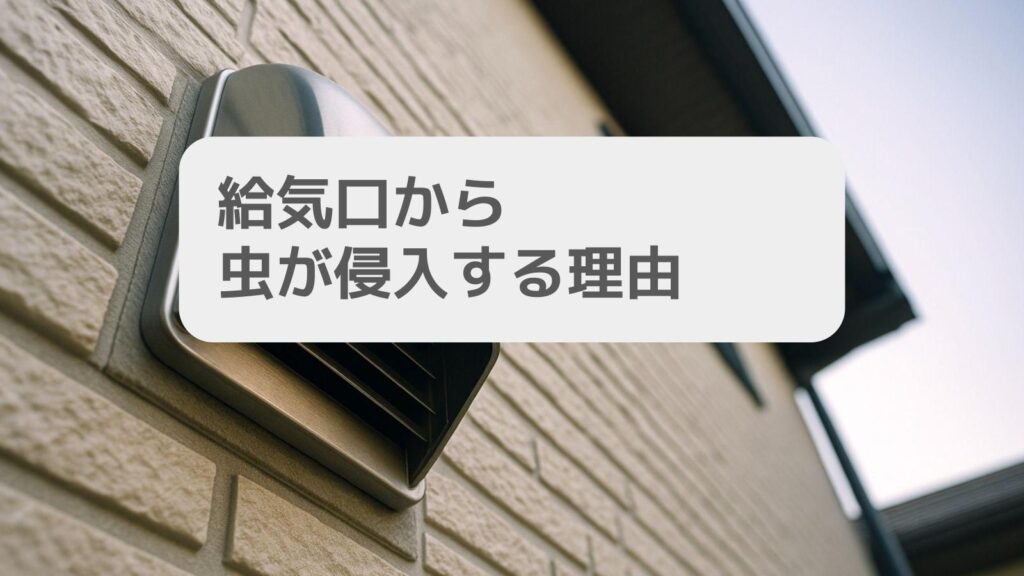
一条工務店の家は高気密構造で、外からの空気や虫の侵入を防ぐ設計になっています。それでも完全に防げるわけではなく、とくに「給気口」は虫の通り道として要注意のポイントです。なぜなら、家の中に新鮮な空気を取り込むために必要な開口部であるため、どうしても外部とつながってしまうからです。
給気口のフィルターには一定の防虫機能が備わっているものもありますが、虫の大きさや種類によってはすり抜けてしまうケースもあります。特に春から夏にかけては、羽虫やコバエのような小さな虫が活発になる時期であり、これらがフィルターの目をすり抜けて室内へ侵入することがあるのです。
また、給気口の設置場所や風向きによっても虫の入りやすさは変わってきます。例えば、植木や雑草が近くにある場合、虫が寄りやすくなるため、より侵入リスクが高まると考えられます。
このような事態を防ぐためには、まず高密度な防虫フィルターを選ぶことが大切です。最近では、PM2.5にも対応した超微細フィルターも販売されており、虫だけでなくホコリや花粉の侵入も防ぐことができます。
さらに、給気口の外側に目の細かい防虫ネットを二重に取り付けると、より安心です。ネットは取り外し可能なものを選べば、掃除や交換も簡単に行えるので、衛生面でもメリットがあります。
このように、給気口の管理を工夫することで、高気密住宅でも虫の侵入を最小限に抑えることができます。ちょっとした工夫で快適な住環境が保てるなら、ぜひ実践してみたいですよね。
ドレンヒーターとゴキブリの関係
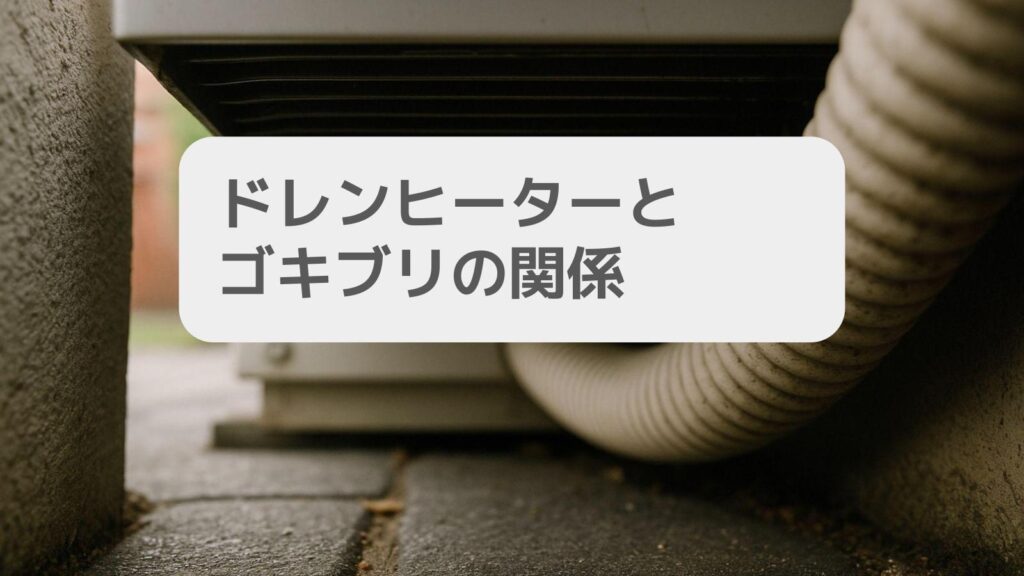
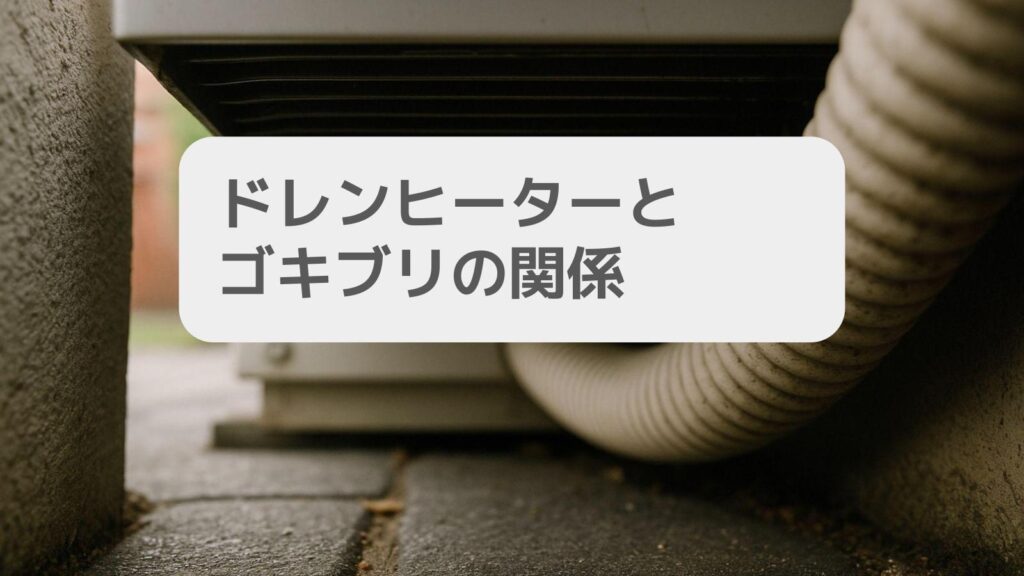
ドレンヒーターは冬季の凍結防止に役立つ設備ですが、意外なことにゴキブリの温床になってしまうことがあります。その理由はとてもシンプルで、ゴキブリは温かくて湿気のある場所を好むからです。冬の寒さから身を守るために、人間が用意した快適な環境が、思わぬ形で虫にも好まれてしまうのです。
特に注意したいのが、室外機や配管の周辺です。ドレンヒーターによって温められた配管部分は、寒い外気と比べて格段に暖かく、ゴキブリにとってはまるで快適な隠れ家のようなものです。そのため、こうした場所を通ってゴキブリが室内へと侵入することも珍しくありません。
さらに、室外機の下や配管の接合部などに隙間があると、そこが格好の侵入口になります。家の断熱や気密性がいくら高くても、こうした細部の隙間から虫が侵入してくる可能性はゼロではありません。そのため、発泡ウレタンや目地材を使って、隙間をしっかり塞いでおくことがとても大切です。
また、ゴキブリは夜行性のため、暗くて人目のつかないところに集まりやすい傾向があります。室外機の裏側や物置の影なども、こまめに点検しておくと安心です。定期的に防虫剤を撒いておくと、より強力な予防策になります。
このように、ドレンヒーターの温もりがゴキブリの快適空間になってしまう可能性があるという点は、あまり知られていないリスクです。ですが、事前に対策を講じることで、しっかりと防げる問題でもあります。
チャタテムシが発生する原因とは
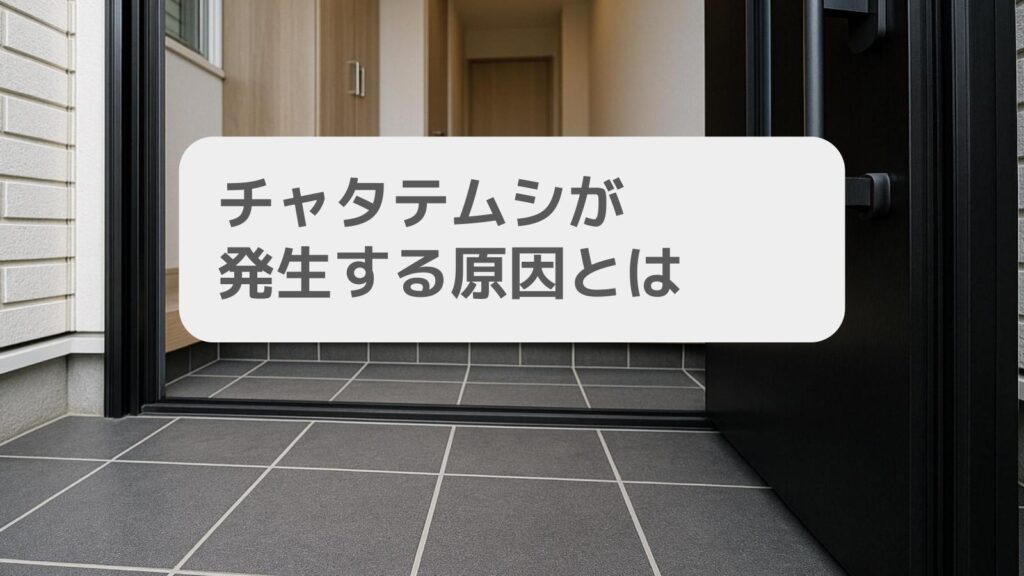
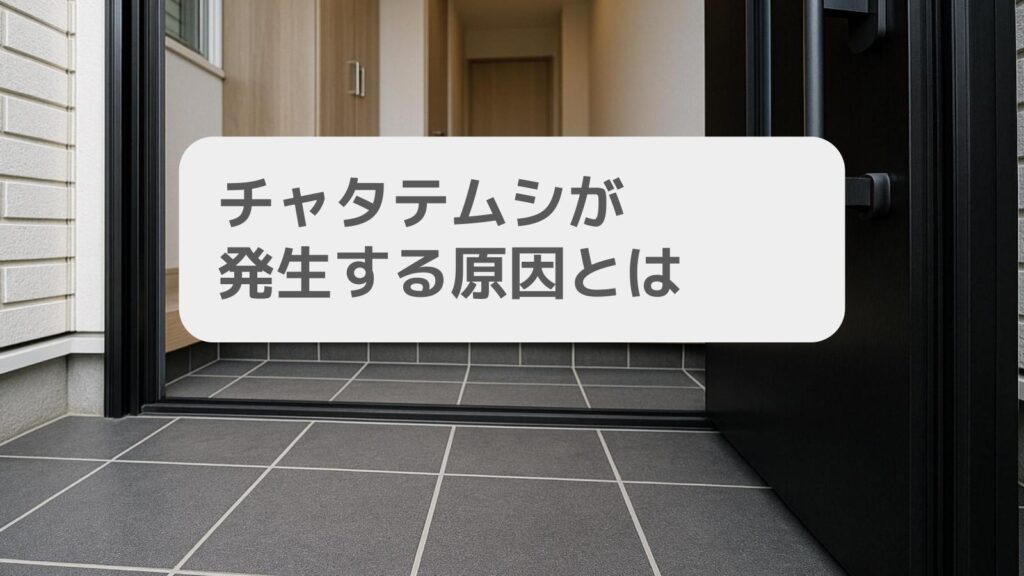
チャタテムシは非常に小さな虫で、見た目は白っぽく透明に近い体を持っているのが特徴です。動きが早く、時には本棚の隙間や収納の奥などでぴょんぴょんと跳ねる姿を見ることもあります。このチャタテムシは、特に湿気の多い環境を好みます。そのため、気密性が高く断熱性能に優れた一条工務店の住宅であっても、室内の湿度管理が十分でないと発生することがあるのです。
実際に発生しやすい場所としては、押し入れや収納の内部が挙げられます。そこには湿気がこもりやすく、加えて本や段ボール、さらには小麦粉や片栗粉といった粉状の食品があると、それらをエサにしてチャタテムシが繁殖します。また、古紙や新聞、封筒類なども栄養源になり得るため、紙類が密集している場所は要注意です。
このような虫が発生すると、見た目が不快なだけでなく、食品の衛生面にも影響を与える可能性があります。小さな子どもがいる家庭や、喘息やアレルギーを持つ方がいる場合は、特に注意が必要です。チャタテムシ自体は人に直接害を与えるわけではありませんが、繁殖力が強く、放置すると短期間で大量に発生してしまうこともあるからです。
対策としては、まず第一に湿気を溜めない工夫が重要です。押し入れや収納に除湿剤を設置したり、湿度が高い日はサーキュレーターやロスガードを活用して空気を循環させたりすると効果があります。また、食品の保管にも注意が必要で、粉物は密閉容器に入れ、紙類はこまめに整理・処分しておくのが安心です。
このように考えると、湿気対策を意識することが、結果的に虫の発生を防ぐための第一歩となります。湿度計を設置して定期的に確認するなど、小さな行動を積み重ねることで、清潔で快適な暮らしを守ることができるのです。
コバエの発生源と防止策
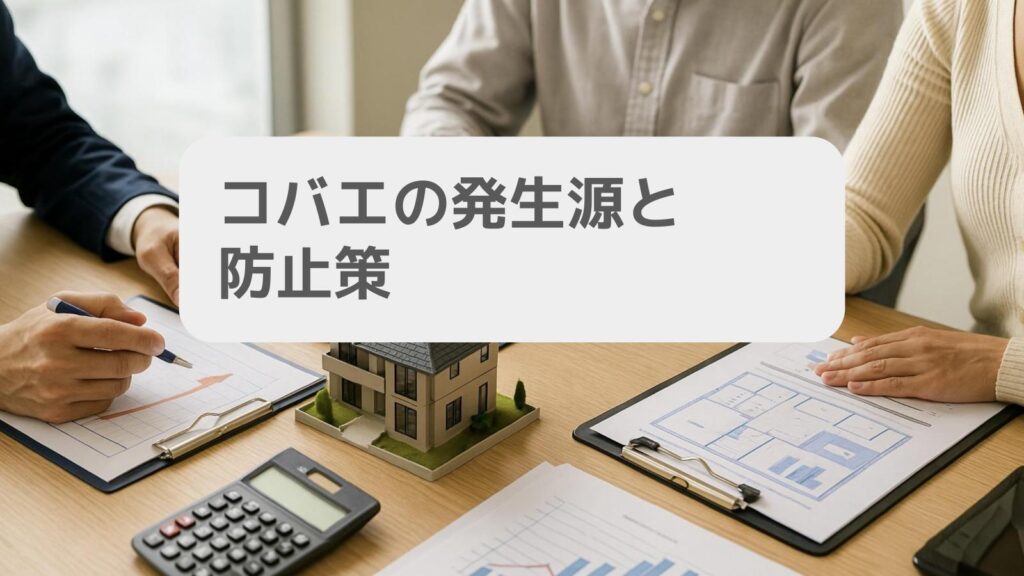
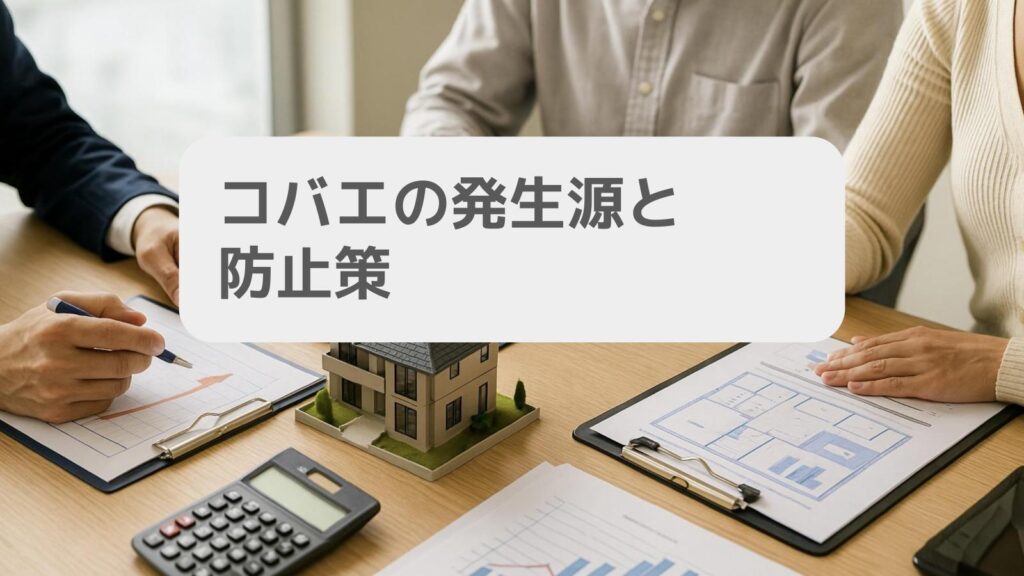
コバエが気になる季節になると、「どこから来たの?」と思うことがありますよね。実際には、室内のいくつかの場所が発生源となっており、代表的なのが生ゴミ、観葉植物の土、そして排水口です。これらはいずれもコバエにとって栄養や産卵場所として最適な環境です。
特に生ゴミは、食品のかけらや液体が残っていると、わずか1日でも臭いを発し始め、それに引き寄せられてコバエが集まってきます。見えない卵がゴミ袋の中で孵化してしまうこともあります。また、観葉植物の土は、湿った状態が続くと有機物が分解され、コバエが発生しやすくなる環境を作り出してしまうのです。
一条工務店の高気密な住宅であっても、臭いや腐敗臭がある場所があれば、わずかな隙間からでもコバエが侵入してきます。密閉されているからこそ、ニオイの拡散が少なく、気づきにくいこともあるため注意が必要です。
では、どう対策すればよいのでしょうか。まず、生ゴミは専用の密閉容器を使い、できる限りその日のうちに処理しましょう。特に夏場は、少量でもすぐに悪臭の原因となります。冷凍庫内に一時的に保存する方法も有効です。
次に、観葉植物の土には市販の防虫剤や、天然素材の忌避剤を混ぜるとよいでしょう。植え替えの際に防虫効果のある鉢底石や土壌も選べます。さらに、水やりの頻度や量にも注意して、土が常に湿った状態にならないように管理することも大切です。
排水口には、重曹とクエン酸を使った掃除がおすすめです。発泡作用で汚れを落とすと同時に、菌の繁殖を防ぎ、コバエが寄りつきにくい状態を保てます。排水口専用のネットや防臭キャップも役立ちます。
このように、コバエの対策は一つではなく、発生源を断つことと予防を組み合わせることが大切です。日々の小さな習慣を少し見直すだけで、コバエの発生を大幅に減らすことができます。
ムカデの侵入経路と撃退法
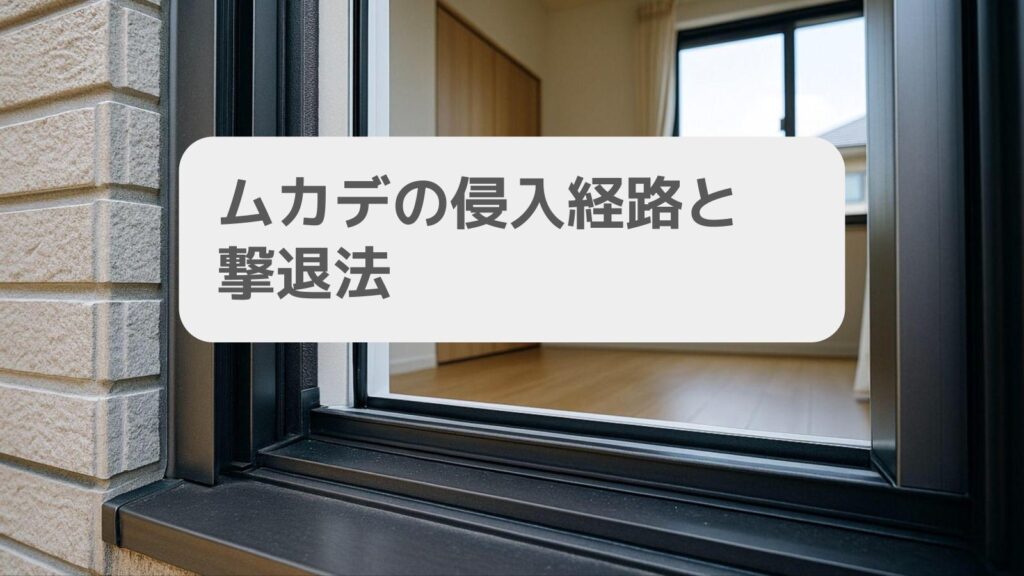
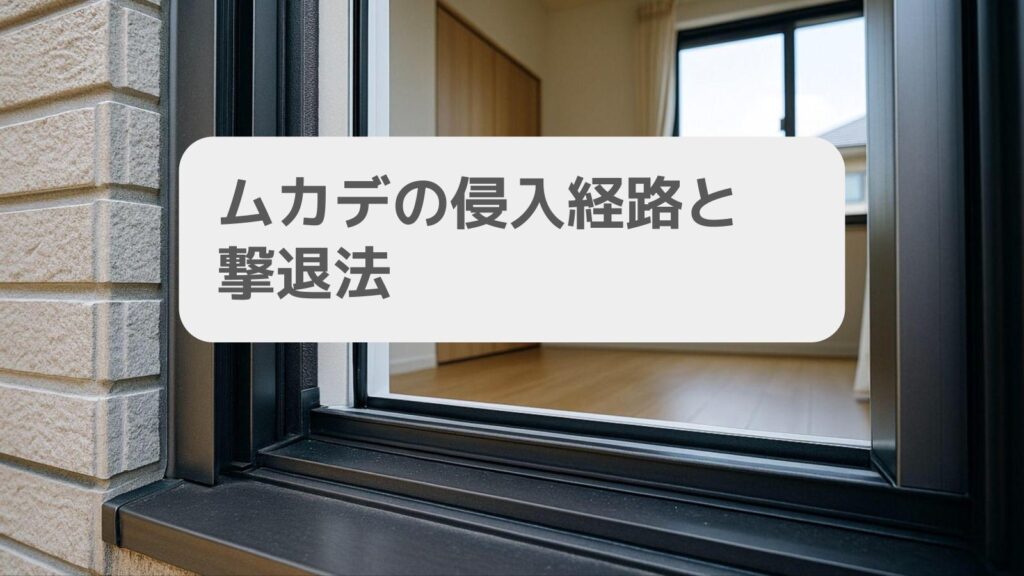
ムカデはジメジメとした環境や隙間がある場所を好むため、たとえ一条工務店のような高気密・高断熱住宅であっても、完全に油断はできません。特に湿度の高い梅雨時期や夏場の夜間には、玄関のちょっとした隙間や、床下換気口、配管の取り付け部分などからムカデが入り込んでくることがあります。
ムカデは夜行性で、静かで暗く、湿った場所を好むため、玄関タイルの隅や靴箱の裏など、普段見落としがちな場所に潜んでいることも。外から侵入したムカデは家の中をうろつき、驚いた拍子に人を噛むこともあります。毒を持っている種類もあり、刺されると強い痛みや腫れが生じることがあるため、小さなお子さんやペットがいる家庭では特に注意が必要です。
これを予防するためには、まず家の外周に防虫用の粉剤をまくことが基本です。特に玄関まわり、ウッドデッキの下、植木鉢の周囲など、ムカデが隠れやすい場所には重点的に散布しましょう。市販されているムカデ専用の忌避剤や殺虫粉剤は、長時間効果が続くものもあるので、定期的に使用すると安心です。
さらに、室内対策としては、出入り口付近や窓辺に粘着トラップを設置することも有効です。万が一侵入された場合でも、目立たないうちに捕獲できる可能性があります。また、精油成分を使った天然由来の忌避スプレーを使うと、化学薬品が気になる方にも優しく対処できます。
こう考えると、ムカデ対策は「侵入させない工夫」と「入ってしまったときの備え」の両方が大切です。とにかく見た目も怖く、遭遇したときの衝撃も大きいムカデは、一度出てしまうと家の中での安心感が損なわれてしまいますよね。そのため、日頃からの予防をしっかり行い、家全体を守る意識を持つことが重要です。
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店 ゴキブリを防ぐ家づくり
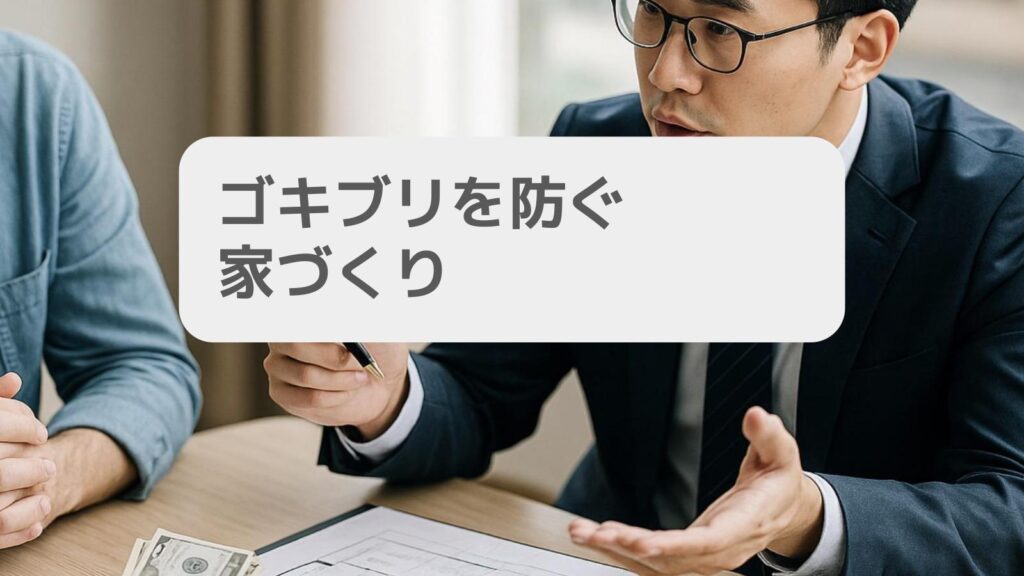
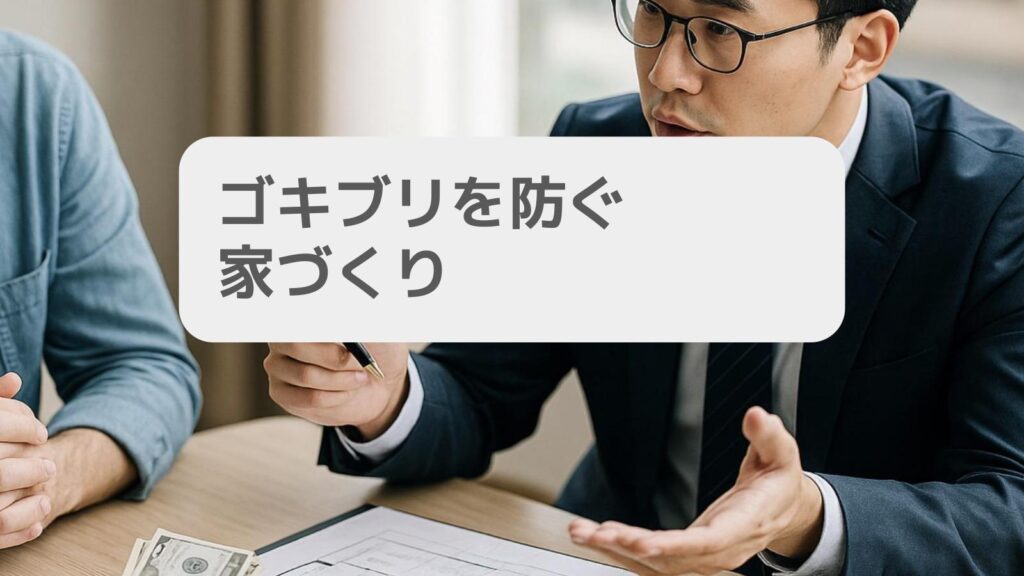
- 換気システムが寿命に与える影響
- ゴキブリが好む湿気と温度とは
- トビムシと間違えやすい虫の見分け方
- 蚊を家に入れない外構の工夫
- 気持ち悪い害虫が増える季節とは
- ゴキブリゼロを目指す清掃習慣
換気システムが寿命に与える影響
ゴキブリは湿度が高くて暖かい場所をとても好むため、換気が行き届いていない住宅ではどうしても繁殖しやすくなります。空気の流れが滞っていると湿気がこもり、カビやホコリも溜まりやすくなり、それらをエサにする害虫たちにとっては、まさに理想的な環境となってしまうのです。
その点、一条工務店の住宅に搭載されているロスガードは、非常に優れた全館換気システムです。このロスガードは、約2時間ごとに家全体の空気をきれいに入れ替える仕組みを持っており、湿気や臭い、空気中の汚れを効果的に排出します。結果として、ゴキブリにとって居心地の悪い環境を作り出してくれるため、防虫効果が期待できるのです。
ただし、いくら高性能な換気システムであっても、メンテナンスを怠ると効果が半減してしまいます。特に注意したいのがフィルターの汚れです。ホコリや花粉、油分がフィルターに付着したままになっていると、空気の通りが悪くなり、換気能力が落ちてしまいます。
そのため、定期的にフィルターを掃除したり、推奨される期間ごとに新しいものに交換したりすることがとても重要です。多くのご家庭では、季節の変わり目や梅雨入り前など、湿度が上がる時期に合わせてメンテナンスを行うのが効果的だとされています。
さらに、ロスガードによって適切に空気が循環している状態を保つことで、建物全体の湿気もコントロールしやすくなり、家そのものの寿命を延ばすことにもつながります。木材の腐敗やカビの発生を防ぐことができれば、構造部分の劣化を抑え、長く快適に住み続けることができるのです。
このように考えると、換気システムは単に空気を入れ替えるための装置というだけでなく、害虫対策や家の健康維持にも大きく関わっていることがわかります。ロスガードを上手に活用し、こまめな点検とケアを心がけることで、より快適で清潔な住まいを保つことができるのです。
ゴキブリが好む湿気と温度とは
ゴキブリは一般的に湿度が60%以上、気温が25~30℃程度の環境を好みます。特にキッチンやお風呂、洗面所などは湿気がこもりやすく、暖かさもあるため、ゴキブリにとっては非常に快適な空間となりやすいのです。
一条工務店の家は断熱性が非常に高く、冷暖房の効率が良いため、夏場でも室内の温度は比較的安定しています。この性能のおかげで、急激な温度上昇は避けられるのですが、その分湿度が高くなりやすい点には注意が必要です。湿気がたまってしまうと、どれだけ温度が適切であっても、ゴキブリが繁殖するリスクが高まります。
このような環境を防ぐためには、湿度のコントロールが非常に大切です。除湿器を活用したり、一条工務店の家に標準装備されているロスガードの湿度調整機能を最大限に利用することで、湿気を適切に管理することができます。ロスガードは、単なる換気装置ではなく、熱交換を行いながら空気の質と湿度を整えてくれる高性能な設備です。
また、浴室やキッチンなどの水回りでは、使用後に換気扇を長めに回して湿気を逃がす工夫や、床や壁の水滴を拭き取る習慣も湿気対策に役立ちます。湿度計を設置して数値を可視化しておくと、調整の目安になり安心です。
このように、温度だけに目を向けるのではなく、湿度の管理にも気を配ることが、ゴキブリの発生を未然に防ぐための鍵となります。季節ごとに空調や換気の方法を工夫して、快適で衛生的な室内環境を保ちましょう。
トビムシと間違えやすい虫の見分け方
ゴキブリだと思って慌てて駆除しようとしたら、実は「トビムシ」だったということは意外とよくある話です。トビムシは白っぽく、サイズも1〜2ミリと非常に小さく、ピョンと跳ねるような独特の動きをするのが特徴です。この跳ね方が、多くの人にとってゴキブリのような印象を与えてしまうのかもしれません。
ただし、トビムシは見た目に反して人に害を及ぼさない虫です。刺すこともなければ、食品を荒らすようなこともありません。しかし、大量に発生すると見た目の不快感が強く、精神的にストレスを感じる方も多いと思います。特に白や淡色の床材の上では目立ちやすく、不潔な印象を与えてしまうことも。
この虫の主な発生源は、湿度の高い場所や、カビや菌が繁殖しやすい環境です。例えば観葉植物の土や、洗面所の排水トラップ周り、押し入れや靴箱の奥などが挙げられます。紙類や落ち葉などの有機物も栄養源となるため、放置された段ボールや新聞の束なども注意が必要です。
対策としては、まず住環境を乾燥気味に保つことが基本です。ロスガードや除湿器を活用し、湿度を40〜50%程度に維持することで、トビムシの発生を抑えることができます。また、紙製品や落ち葉などの有機物を溜めないようにし、観葉植物の土も定期的に入れ替えたり、乾燥しやすい素材を使うと良いでしょう。
このように、トビムシは無害ではあるものの、その存在自体が気になるという方にとっては、日々の湿度管理や掃除が何よりの対策となります。見た目でゴキブリと勘違いしてしまわないよう、特徴を理解して適切に対応することが大切です。
蚊を家に入れない外構の工夫
蚊は夏場に悩まされる代表的な害虫のひとつで、刺されると痒みだけでなく感染症のリスクもあるため、できるだけ家に近づけたくない存在です。特に小さなお子さんや高齢者のいるご家庭では、蚊の対策は健康面でも重要なポイントになります。
蚊を家に寄せ付けないための基本は、まず発生源をしっかりと断つことです。庭やベランダにある水たまり、放置された植木鉢の受け皿、雨どいの詰まり、水のたまったジョウロなど、意外と身近なところに蚊の産卵場所は潜んでいます。蚊はたった1センチほどの水たまりでも卵を産み、数日で成虫になります。そのため、こまめな掃除と水はけの良い環境づくりが非常に効果的です。
さらに、家の外構にひと工夫することで、蚊の侵入リスクを大きく減らすことができます。例えば、砂利やウッドチップなど水が溜まりにくい素材を花壇や通路に使うと、湿気の蓄積を防げます。また、溝や排水溝の水が流れにくい箇所には、防虫ネットや傾斜をつける工夫を取り入れると良いでしょう。
外構だけでなく、家の入り口である玄関前に虫除け効果のある植物を配置するのもおすすめです。レモングラス、ミント、ゼラニウム、ラベンダーなどは、蚊が嫌う香りを放つため、自然なバリアとして機能します。こうした植物は見た目にもおしゃれで、ナチュラル志向の方にぴったりです。
このように、蚊の対策は屋内だけでなく、外構や玄関周辺の整備を含めたトータルな工夫がカギになります。季節が始まる前から意識して準備を進めておくと、蚊が活発になる時期に慌てることもなく、安心して快適な夏を迎えることができます。
気持ち悪い害虫が増える季節とは
春先から夏にかけて気温が上昇すると、さまざまな害虫が活発に動き出します。これは自然界のサイクルに沿ったものですが、私たちの暮らしにとっては不快でストレスの原因にもなります。特にゴキブリやコバエ、ムカデ、蚊といった虫たちは、暖かくなると繁殖活動を本格化させるため、注意が必要な時期となります。
気密性が高く断熱性能にも優れた一条工務店の家であっても、完全に虫の侵入を防ぐことは難しいものです。というのも、ドアや窓の開閉時、さらには人や荷物にくっついて屋内に入ってくるケースがあるからです。特に夜間は、室内の明かりに引き寄せられて玄関周辺に集まることも多く、網戸のない窓などから入り込むリスクが高まります。
この時期には、家の内外において虫が好む環境を作らない工夫が重要になります。湿気、生ゴミ、放置された食べ物、そして埃などは、虫にとって最高の餌場となりかねません。特に雨が続く梅雨の時期には、湿度が急上昇し、虫が一層活発に動き回るようになります。そこで活躍するのが、除湿機やロスガードなどの湿度管理設備です。これらを日常的に活用して、湿度を50%以下に抑えることが、虫を寄せ付けない空間づくりにつながります。
さらに、6月から9月の間は虫のピークシーズンとされているため、この期間は特に対策を強化することが求められます。具体的には、虫除けスプレーの使用、防虫ネットの設置、防虫剤の活用など、多角的なアプローチが効果的です。家の外壁周辺に粉状の忌避剤をまいておくのも、一つの手です。
このように考えると、季節ごとの虫の動きを予測し、それに応じた事前準備と対処をしておくことが、快適な住まいを守るための鍵になります。少しの工夫と日々の意識が、大きな安心につながるのです。
ゴキブリゼロを目指す清掃習慣
最後にご紹介するのは、日々の掃除による基本的な対策です。ゴキブリを家に寄せつけないためには、毎日の清掃習慣が何よりも大切だと言えます。どれだけ設備や防虫グッズを揃えても、家の中が清潔でなければ効果は半減してしまいます。
特にキッチンやダイニングは、食べかすや油汚れが蓄積しやすい場所です。これらはゴキブリにとって格好のエサとなるため、清掃を怠ると一気に虫が集まってきます。コンロ周りや電子レンジの中、調味料の容器まわりも忘れずに拭き取るようにしましょう。
夜のうちにシンクを空にし、生ゴミは必ず蓋付きの容器に入れておくことが大切です。可能であれば、毎日ゴミを屋外に出しておくことで、室内に臭いや湿気がこもらず、虫の発生を抑える効果も高まります。また、生ゴミの一時保管に冷凍庫を活用するご家庭も増えており、匂いや腐敗を防ぐ有効な手段です。
さらに、収納の奥や冷蔵庫の裏など、普段目にしにくい場所の掃除も重要です。こうした「死角」にホコリや食べ物のカスが溜まりやすく、ゴキブリの隠れ場所にもなってしまいます。月に1回程度は家具を動かして丁寧に掃除を行うことで、発生リスクをぐっと減らすことができます。
また、床の拭き掃除やテーブルの消毒、ゴミ箱の内側の拭き取りなども忘れずに行いましょう。清掃時には、アルコールスプレーや中性洗剤などを活用すると、衛生面もさらに向上します。
こうしてこまめな掃除を習慣づけることで、ゴキブリにとって住みにくい環境をつくることができ、結果的に発生を予防することにつながります。清潔を保つ努力は、家族の健康と安心を守る第一歩なのです。
一条工務店 ゴキブリ対策まとめとして知っておきたいこと
- バルサン使用時はロスガードを停止しておく必要がある
- 換気後は窓を開けて自然換気を行うのが効果的
- 給気口の防虫対策には高密度フィルターの導入が有効
- 給気口周辺に防虫ネットを二重設置することで侵入リスクを減らせる
- ドレンヒーター周辺の暖かさがゴキブリの侵入口になる恐れがある
- 室外機まわりは隙間を埋めて物理的に遮断することが重要
- チャタテムシは湿度と紙類が多い環境で繁殖しやすい
- 湿度管理と紙類の整理がチャタテムシ防止につながる
- コバエは生ゴミと観葉植物の土が主な発生源となる
- 排水口掃除や土の管理がコバエの予防に効果を発揮する
- ムカデは湿気と暗所を好むため外周と玄関付近の対策が肝心
- ゴキブリは湿度60%以上・温度25~30℃で活発になる傾向がある
- ロスガードの稼働とメンテナンスが室内環境の安定と防虫に直結する
- 蚊の対策は発生源の水たまりを無くすことが基本となる
- 清掃習慣を徹底することで室内のゴキブリ発生を抑制できる
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店を検討中の方は以下の記事も参考にして後悔をなくしてくださいね!
費用・保険・保証
- 【実例あり】一条工務店の注文住宅の評判と住人だけが知るデメリット
- 一条工務店のメンテナンス費用は高い?30年間の総額を解説
- 一条工務店の火災保険は高い?割引と見積もりで安くする選び方
- 一条工務店が倒産する可能性は?経営状態と業績を見れば安心できる
エクステリア
- 一条工務店のハイドロテクトタイルはいらないと後悔!?メンテナンス楽で人気
- 一条工務店の対水害住宅の注意点|金額や何メートルの浸水まで大丈夫か
- 一条工務店の幹延長費用はいくら?ハグミーやアイキューブ・平屋で大丈夫か
- 一条工務店のバルコニーのメンテナンス費用は高い!?保証はどうなるのか
- 一条工務店のウッドデッキの後悔ポイントは後付け・メンテナンス・色など
- 一条工務店の庇で人気はアーバンルーフ!後付け・費用・後悔ポイント紹介
- 一条工務店の門柱はオプション扱い|位置や後付けで後悔しないために
玄関・ドア・天井
家の構造
- 一条工務店の鉄骨は後悔する?性能と価格を徹底解説
- 一条工務店の木材の品質や種類は!?産地はどこ産のものなのか
- 一条工務店の基礎の種類・ベタ基礎はオプションで費用はいくらか
- 一条工務店の平屋で後悔!?やめたほうがいい噂の理由とは?
- 一条工務店の家は増築できないのか?離れを作るには費用が高い
オプション選び
- 一条工務店のうるケアは後悔する?評判と費用を徹底解説
- 一条工務店の石目調フローリングで後悔しない!価格や特徴を解説
- 一条工務店のV2Hは後付けできる?価格・補助金・欠点を解説
- 一条工務店のクロスはどれがいい?標準とオプションおすすめの使い分け
- 一条工務店で無垢床フローリングにしたい!気になる費用・欠点・ゴキブリについて
- 一条工務店の勾配天井は6畳でもOK?費用やルールで後悔しないために
- 一条工務店のオープンステアで後悔!?下の活用は収納だけじゃない
- 一条工務店なら網戸はいらないと思ったら後悔!勝手口に必要かの判断基準
- 一条工務店の防音ドアはトイレやリビングにも!効果はバツグン
- 一条工務店のカーテンがいらないと思ったらカーテンレールのみで良いか
- 一条工務店の3Dパースを依頼したい!内観パースは作ってくれないの?
- 一条工務店で防音室の設置費用はいくらか|効果は高く「うるさい」を解決
- 一条工務店の防犯カメラは後付け・施主支給できるか?お得に安心したい方へ
- 一条工務店の浄水器おすすめはこれ!後付けできるパナソニック製品など
- 一条工務店の玄関ポーチ人気のタイル色やポーチ延長費用を徹底紹介
- 一条工務店のランドリールーム必要か?乾かない噂や間取りなど後悔ポイントまとめ
- 一条工務店のキッチンにリクシルを施主支給したい!標準メーカーはダサい?
- 一条工務店でダウンライトにすべきか?いらないの声やシーリングにすればよかったなど
- 一条工務店の本棚(ブックシェルフ)で後悔!?背中合わせで賢く収納
- 一条工務店 御影石のキッチンカウンターはダサい?おしゃれを実現するヒント
- 一条工務店の階段を完全紹介!パターンの選び方・必要なマス数を知り失敗を防ぐ
- 一条工務店の屋根裏収納で後悔しないポイント|後付け・費用・見積もり
- 一条工務店の1.5階建ての費用・人気の理由・デメリットや間取りの注意点
- 一条工務店の押し入れ選び!観音開き・引き戸・開き戸のメリットデメリット
- 一条工務店で和室はいらない!?小上がりや畳選びで後悔しがち
- 一条工務店でゴキブリ出現!?換気システムから侵入か給気口か
- 一条工務店のロフトの費用は意外と安い!平屋との相性も良し
設備
- 一条工務店ヘッダーボックスの場所は玄関と階段下が最適!音と床暖的効果
- 一条工務店のインターホンの選び方|標準モデルMT101から後付けまで網羅
- 一条工務店の物干し金物ホスクリーンは後付けできるのか|耐荷重や設置値
- 一条工務店の自在棚にシンデレラフィットするゴミ箱
- 一条工務店のスマートキーつけるべきか?後付けやピーピー音・紛失トラブルも
- 一条工務店のエコキュートおすすめモデルは快適重視ならPシリーズ
- 一条工務店のレンジフード選び|操作選びやフィルター有無
- 一条工務店の蓄電池を2台に!価格や容量、後付け費用を解説
- 一条工務店の浴室乾燥機はオプションでつけるべきか?後悔しない判断基準
- 一条工務店シューズボックスの全て!種類・収納・価格を解説

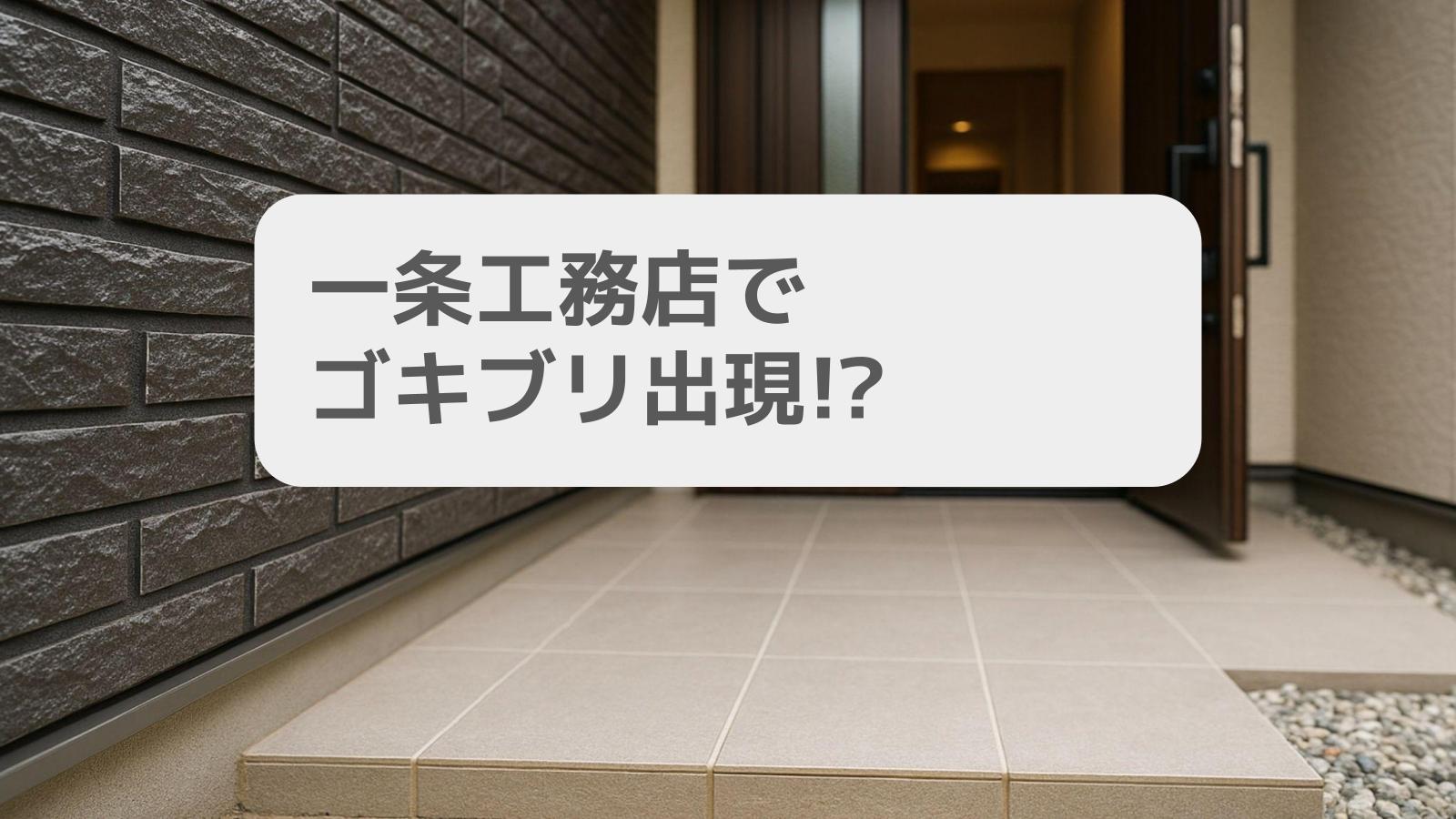


コメント