「一条工務店 倒産」と検索してこのページにたどり着いた方の多くは、「もし家を建てた後に会社が倒産したらどうなるのか」「そもそも一条工務店の経営状態は大丈夫なのか」といった不安を抱えているのではないでしょうか。住宅は人生でもっとも大きな買い物の一つだからこそ、選ぶ会社の信頼性や安定性は極めて重要です。
この記事では、近年ネットで話題になる「一条工務店 やばい」といった噂の真相を冷静に分析しつつ、実際に過去に倒産した大手住宅メーカーや、ハウスメーカー 倒産 埼玉の事例、潰れそうな工務店の特徴なども取り上げます。また、タマホーム 倒産秒読みといった憶測の背景にも触れながら、ハウスメーカー 倒産 予想に役立つ財務指標の見方も解説します。
さらに、大手住宅メーカーでもハウスメーカー 倒産 過去に学ぶべき点は多く、安心して家を建てるためには何をチェックすべきかという視点で読み進められる内容となっています。一条工務店の今後を正しく理解し、リスクを回避するための情報収集にお役立てください。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一条工務店の経営状態 | 自己資本比率が高く、売上・利益は安定。倒産リスクは低い |
| 倒産の噂の真相 | SNSや口コミによる一部誇張で、実態とは乖離がある |
| 「やばい」と言われる理由 | 施工精度や対応にばらつきがあり、不満の声が目立つことも |
| 安心材料 | 自社工場での内製化による品質・コスト管理の強み |
| 埼玉での倒産事例 | アーバンエステートのように前金重視の経営は要注意 |
| 過去の大手ハウスメーカーの倒産 | 富士ハウス、三井物産系など。規模だけでは安心できない |
| 潰れそうな工務店との違い | 財務体質・施工体制・集客力で明確な差がある |
| 倒産リスクを測る指標 | 自己資本比率、営業利益率、流動比率など |
| 保証制度の重要性 | 完成引き渡し保証制度の有無が安心材料になる |
| 契約時の注意点 | 前払い比率が高すぎる会社は避けるべき |
| 相見積もりの活用 | 複数社を比較して営業姿勢や価格の妥当性を確認 |
| アフターサポート体制 | 施工後も安心できるサポート内容か要確認 |
| 倒産予想に役立つ判断材料 | 決算情報、施工実績、企業の戦略などを多角的に評価 |
| 他社との比較ポイント | 経営安定性、保証制度、顧客対応の3点が重要 |
| 結論 | 一条工務店は現時点で倒産リスクは低いが、慎重な確認は必要 |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
一条工務店 倒産の可能性を検証
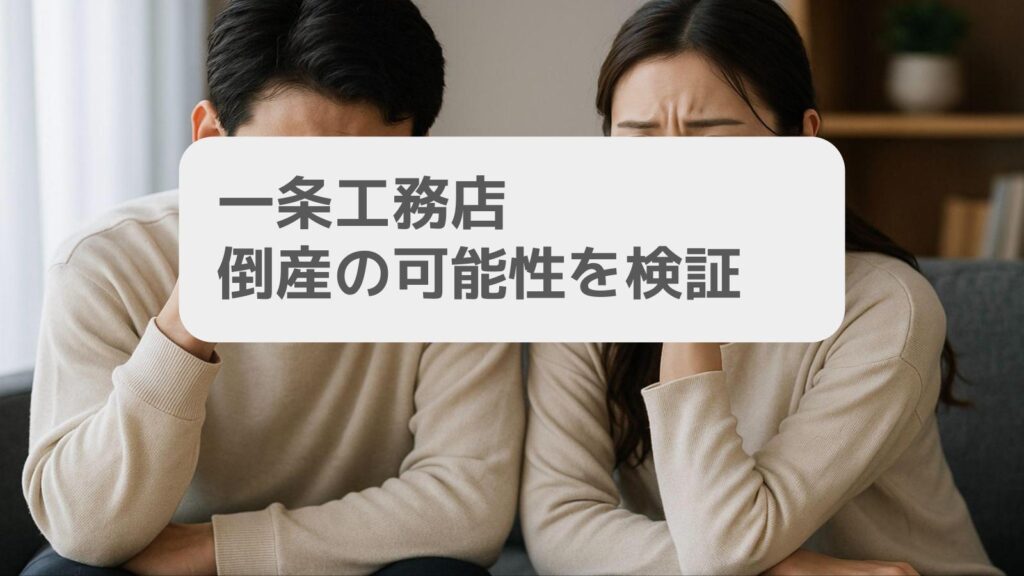
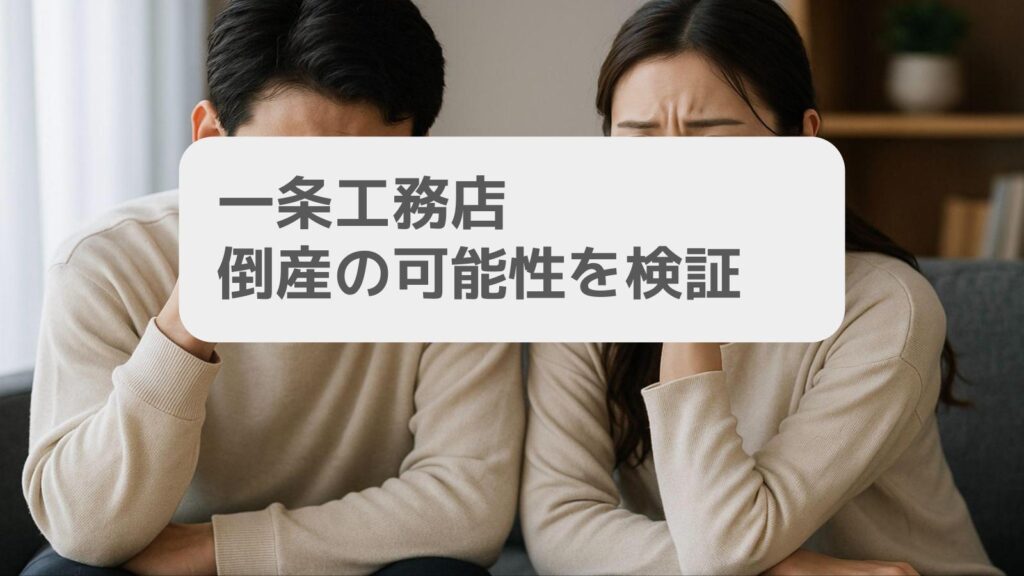
- 一条工務店の経営状態と業績推移
- 一条工務店は本当にやばいのか?
- 倒産が懸念される埼玉の事例
- 大手住宅メーカーの倒産事例と教訓
- 潰れそうな工務店との違い
- ハウスメーカー倒産予想の見方
一条工務店の経営状態と業績推移
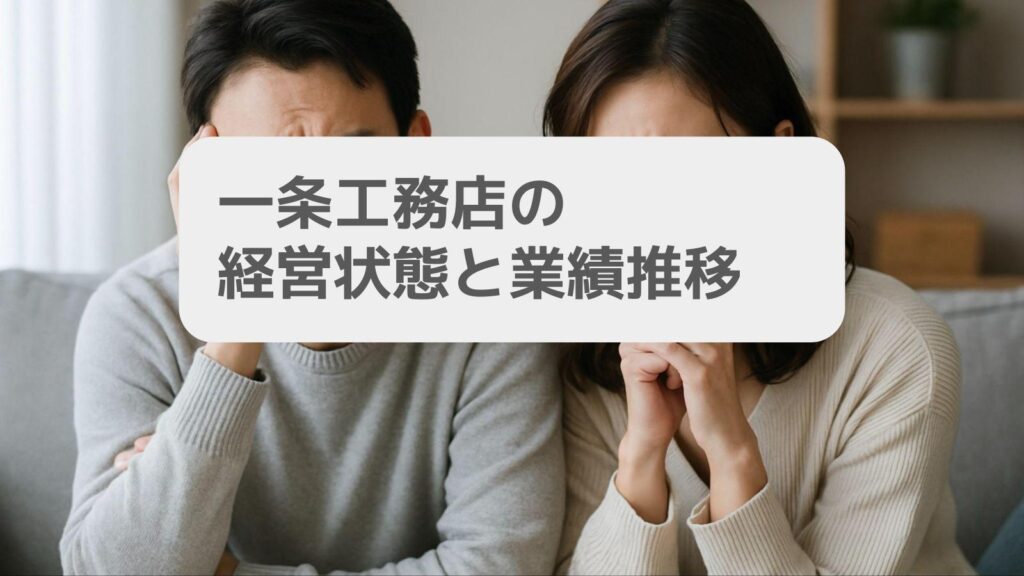
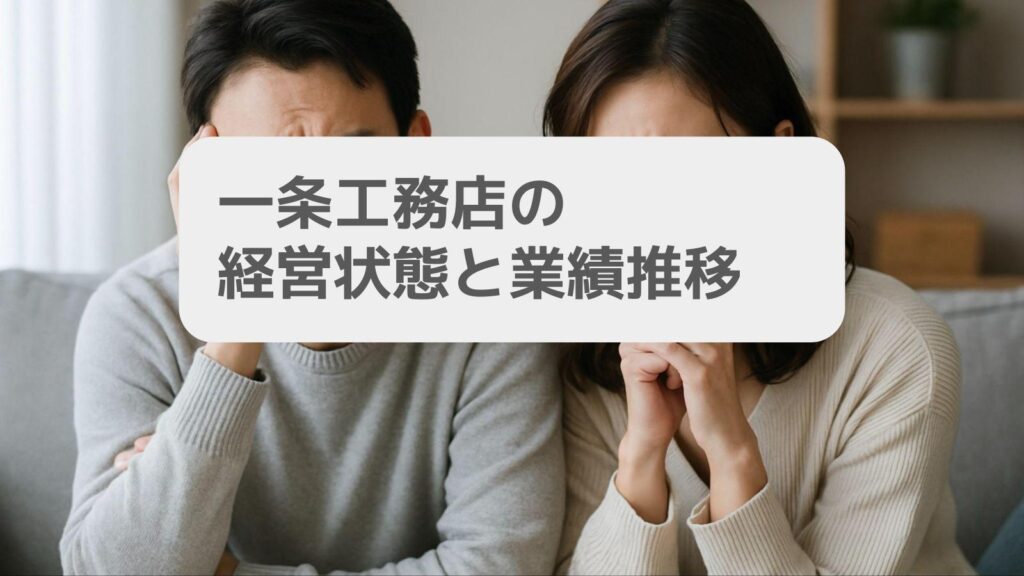
一条工務店の経営状態は、近年の住宅業界の中でも比較的安定している部類に入ると考えられます。特に注目すべきは、売上高や利益の推移に大きな乱れが見られないことです。たとえ厳しい経済状況や建築資材の高騰といった外部要因があったとしても、一条工務店の財務体質はそれらの影響をある程度吸収できる力を持っているようです。
この理由のひとつが、高性能住宅に特化した商品戦略にあります。省エネルギー性や断熱性に優れた住宅を、ある程度パッケージ化して提供しているため、原価の管理がしやすく、利益構造が安定しているのです。また、自己資本比率が高いという点も見逃せません。自己資本比率が高い企業は、借入に頼らない経営が可能なため、景気変動や資材価格の高騰に対しても柔軟に対応できます。
例えば、2023年度の決算では売上が横ばいに推移していたにもかかわらず、利益率はほぼ維持されており、コスト管理がうまく機能していることがうかがえます。さらに、一条工務店は自社で工場生産を行っており、住宅設備の内製化を進めることでコスト削減と品質の安定化を両立しています。このような取り組みも、業績の安定に大きく貢献しているといえるでしょう。
このため、少なくとも現時点で一条工務店が急速に倒産に向かうリスクは低いと見られています。ただし、今後の住宅着工数の動向や金利の変動、そして人件費や資材価格のさらなる上昇があれば、その影響をどれだけ吸収できるかが注目されるでしょう。
一条工務店は本当にやばいのか?
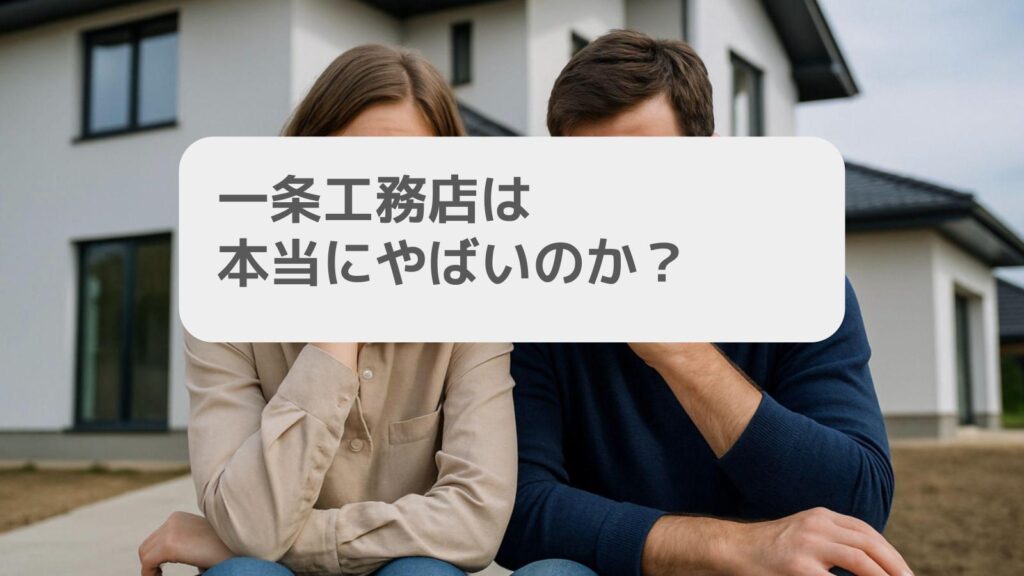
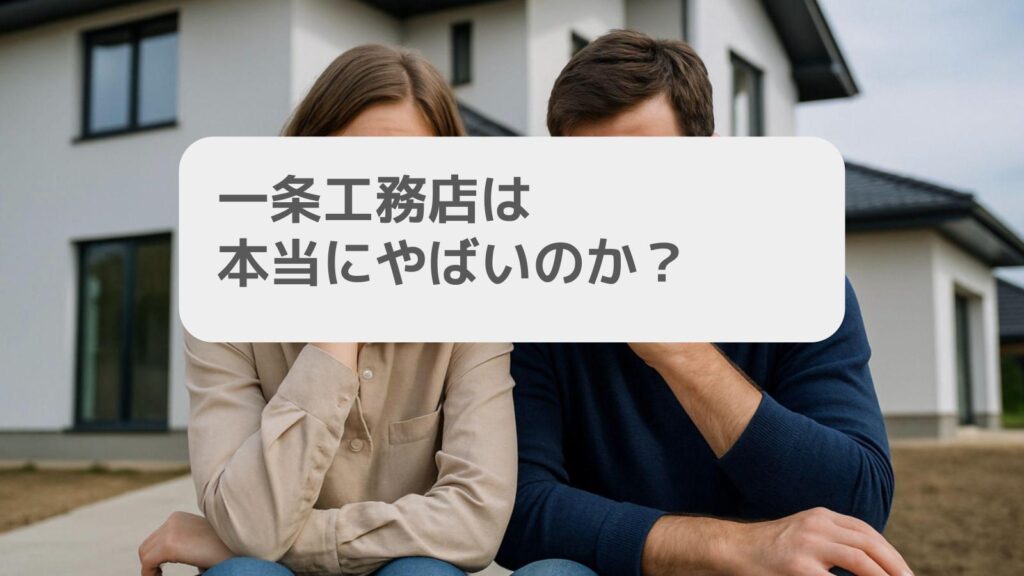
「やばい」といった言葉が一部のメディアやSNSで広まると、不安を抱く方も多いかもしれません。しかし、結論から言えば、一条工務店が直ちに倒産するような切迫した状況にはないと考えられます。確かに、インターネット上では「隙間風が入る」「施工が雑」「対応が遅い」といったネガティブな意見も見られます。けれども、これらは個別の体験に過ぎず、統計的に見ればごく一部のケースです。
また、一条工務店は年間1万棟以上の建築実績がある大手企業です。そのため、施工件数が多い分だけ、自然とトラブル事例も目立ってしまう傾向にあります。例えば、全国展開している飲食チェーン店と個人経営の店とでは、口コミ数が大きく違うのと同じような現象です。そのうえ、口コミには個人の感情や価値観が反映されるため、同じ内容でも捉え方が大きく異なることがあります。
さらに、企業の健全性を図るには、財務面のチェックが欠かせません。一条工務店は非上場企業ではあるものの、業界誌や企業調査機関による情報では、売上・利益ともに安定して推移していると報告されています。これまで大きな経営トラブルも表面化しておらず、業界内でも比較的堅実な経営を続けている会社のひとつです。
もちろん、どんな企業にもリスクは存在しますが、それを過剰に誇張して「やばい」と決めつけるのは早計です。だからこそ、ネットの噂に振り回されず、客観的なデータや第三者の評価にも目を向けて、冷静に判断することが大切です。
倒産が懸念される埼玉の事例
実際に倒産してしまった工務店の中には、埼玉県に本社を構えていた企業も複数存在します。特に有名なケースとしては、「アーバンエステート」の倒産が挙げられます。同社はテレビCMや派手な広告展開を通じて急速に契約数を増やしました。その一方で、実際の工事体制や資金管理体制は追いついておらず、短期間で経営が悪化してしまったのです。
アーバンエステートでは、契約時に「前金を多めに支払ってもらえれば工事費を割引する」といったセールストークがよく使われていたといわれています。顧客側としては少しでも安く建てられると期待しがちですが、これに応じてしまった結果、着工前に多額の資金を支払ってしまい、倒産後に工事がストップしてしまったケースが多数報告されました。
倒産時には、未完成のまま放置された住宅が約500棟、支払い済みの金額は70億円以上にも上り、そのうち約4割が1000万円を超える前払い金だったとされています。このような状況では、被害を受けた施主が裁判を起こすことも珍しくなく、実際に弁護団が結成され、損害賠償請求や刑事告訴も検討されました。
こうした埼玉県での事例を通じて学べるのは、「前金方式の危うさ」や「完成引き渡し保証制度に未加入のリスク」です。住宅契約を結ぶ前に、保証制度への加入状況や支払いスケジュールの妥当性をしっかり確認することが、施主としてのリスク管理につながります。価格や条件の良さだけで判断せず、会社の経営体制や過去の実績もあわせて慎重にチェックすることが大切です。
大手住宅メーカーの倒産事例と教訓
大手企業だからといって、必ずしも安泰とは限りません。これまでにも、業界内で広く認知されていた住宅メーカーが突如として倒産に追い込まれた事例がいくつか存在します。たとえば、富士ハウスや三井物産が出資していたハウステクノなどの住宅関連企業が挙げられます。これらの会社はいずれも、一時は信頼性の高いブランドとして多くの顧客に支持されていたものの、無理な事業拡大や急速な拡張戦略により、財務のバランスを崩し、結果的に経営が立ち行かなくなったのです。
富士ハウスの倒産では、工事途中の住宅が多数残され、施主や関連業者に多大な損害をもたらしました。また、三井物産系の会社でも、親会社の支援を受けきれないまま事業撤退に至った事例もあります。これらの倒産は、リーマンショックといった外的要因も絡み合い、資金調達の難しさや急激な需要の変化に企業が耐えきれなかったことが背景にあります。
このような事例から学べることは、「規模が大きい=安心」ではないということです。大手企業であっても、過剰な投資や景気変動に対する脆弱さがあれば、一気に経営が傾くことも十分に起こりえます。したがって、住宅会社を選ぶ際には、単に知名度や規模だけで判断するのではなく、その企業がどのような経営戦略を持ち、どれだけの柔軟性と持続可能性を持っているかを見極めることが重要です。
特に、近年の住宅市場では、新築需要の減少や建材費の上昇といったリスクが常に存在しており、企業の財務健全性やアフターサービスの体制なども含めて、多面的な評価が必要とされます。長く安心して暮らすための家を託すパートナーとして、本質的な信頼に値する企業を選びたいところです。
潰れそうな工務店との違い
一条工務店と、経営が不安視されている中小規模の工務店とでは、企業としての体力や安定性に大きな開きがあります。まず、多くの潰れそうな工務店に共通しているのは、自己資本比率が著しく低いことです。これは、会社が自己資金をあまり持っておらず、資金繰りの多くを借入れに依存している状態を意味します。そのため、急な受注減や原価の上昇といった外的要因が発生した際に、事業継続が困難になるのです。
また、そうした工務店では利益率も非常に薄く、営業キャッシュフローがマイナスになっている場合も珍しくありません。さらに、現場を支える職人の確保が難しく、品質のばらつきや工期の遅延といった問題を抱えてしまうこともしばしばです。経営のスリム化を進めすぎた結果、広告や営業活動に十分な投資ができず、受注が先細るという悪循環に陥ってしまうケースも見られます。
一方で、一条工務店は大手ハウスメーカーとして、全国に広がる販売網と生産拠点を有しており、ある程度のスケールメリットを活かした経営が可能です。ブランド力も確立されており、集客の面でも優位性があります。特に、省エネ性能や気密性に優れた住宅商品が一定の評価を得ており、価格と性能のバランスを重視する顧客層から高い支持を受けています。
また、同社は自社で製造から施工までの一貫体制を採用しているため、コストの最適化がしやすく、突発的な原価高騰にも柔軟に対応できる仕組みがあります。こうした運営体制が財務面にも反映されており、自己資本比率が高く、安定した収益構造を実現しています。結果として、急激な経済変動があった場合でも、一定期間は耐えうる余力を持っていると評価されています。
このように考えると、たとえ同じ住宅業界に属していても、工務店によって経営の健全性や将来性には大きな差があることが分かります。家を建てるという大きな買い物だからこそ、施主としては単に価格やデザインだけでなく、選んだ企業の経営基盤やリスク管理体制までしっかり見極めることが重要です。
ハウスメーカー倒産予想の見方
倒産リスクを見極めるには、さまざまな財務指標に目を向けることが重要です。中でも代表的な指標として、自己資本比率、営業利益率、流動比率の3つが挙げられます。自己資本比率は、その企業がどれだけ自社資本で運営されているかを示す指標であり、これが低い企業は、借入金への依存度が高く、財務体質が不安定である可能性があります。
営業利益率は、本業でどれだけ利益を出しているかを見るための指標です。たとえ売上が多くても、利益率が低い場合は経費や原価がかさみ、儲けが残らないビジネス構造になっているかもしれません。特に住宅業界のように原材料費の影響を受けやすい業種では、営業利益率の変動が経営の安定性を大きく左右します。流動比率は、短期的な資金繰りにどれだけ余裕があるかを測る指標で、一般的には100%を下回ると注意が必要とされています。
これに加え、有利子負債比率やキャッシュフローも参考になります。有利子負債比率が高すぎると、金利上昇時に返済負担が重くなり、経営に影響を及ぼします。さらに、営業活動によって安定的にキャッシュを生み出せているかどうかも確認ポイントです。たとえば、黒字経営でもキャッシュフローがマイナスの場合は、将来的に資金繰りが悪化するリスクがあります。
また、数字だけでなく企業の姿勢や戦略も評価対象です。たとえば、環境配慮型住宅やリフォーム事業に注力しているか、将来性のある分野への投資が行われているかといった点も、経営の健全性を判断する材料になります。公開されている決算書や業界レポート、企業評価サイトなどを複合的に活用しながら、冷静にリスクを見極めることが、後悔しない住宅会社選びに直結するのです。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店 倒産は現実的なのか?
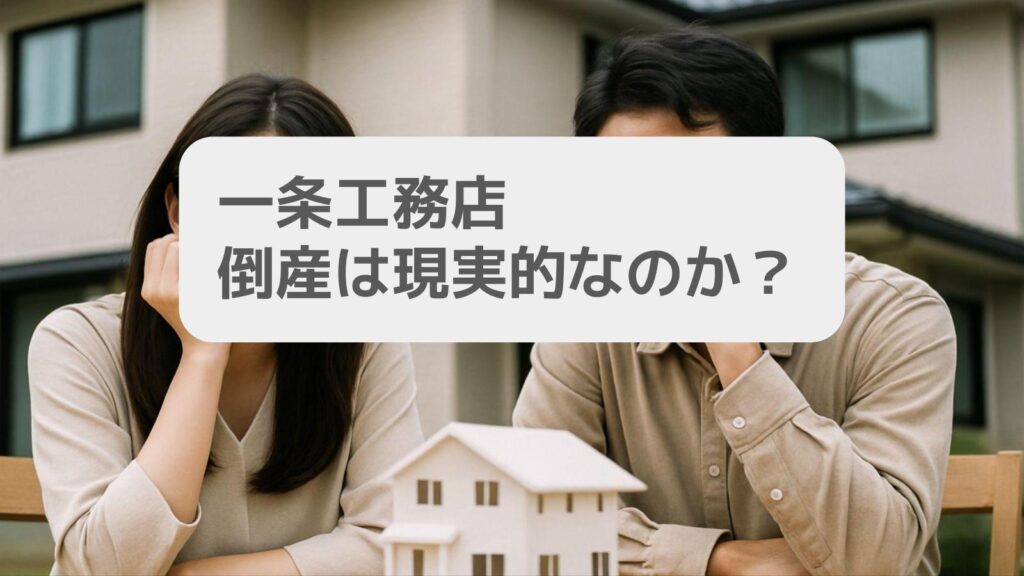
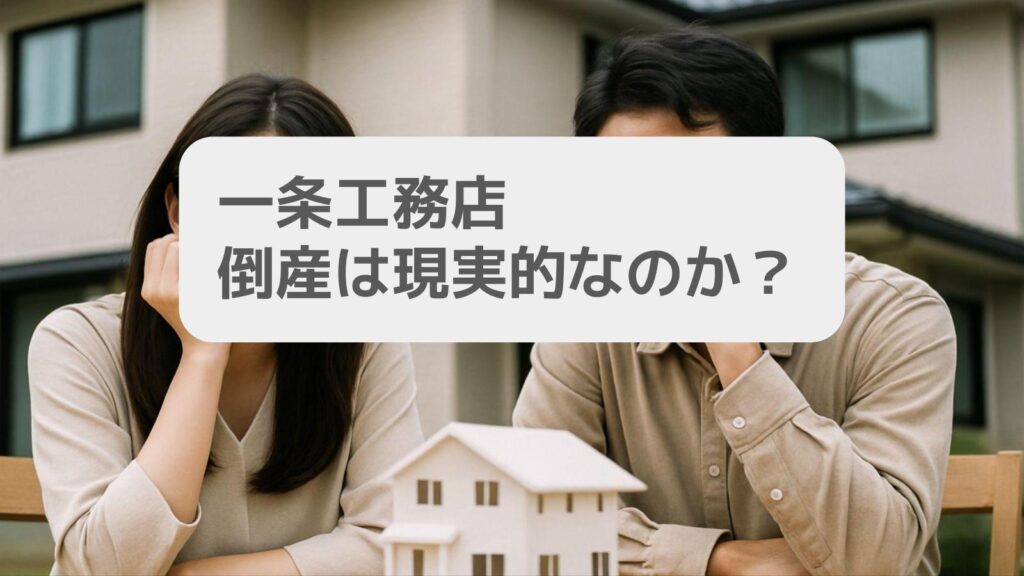
- タマホーム倒産秒読みの真偽とは
- ハウスメーカーの倒産原因ランキング
- 注文住宅業界全体のリスク要因
- 倒産回避のポイントと対策
- 安心して建てられる会社の選び方
タマホーム倒産秒読みの真偽とは
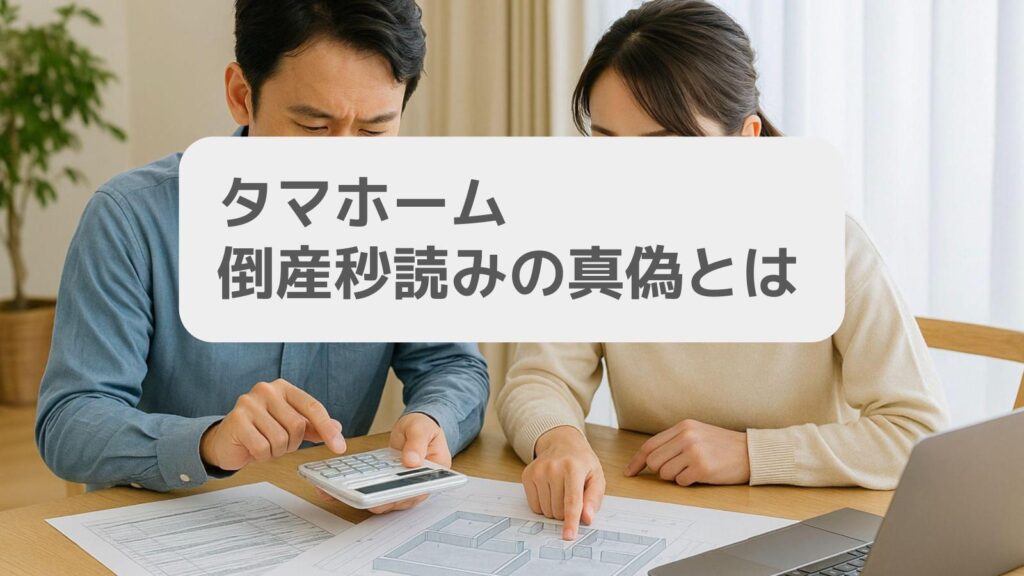
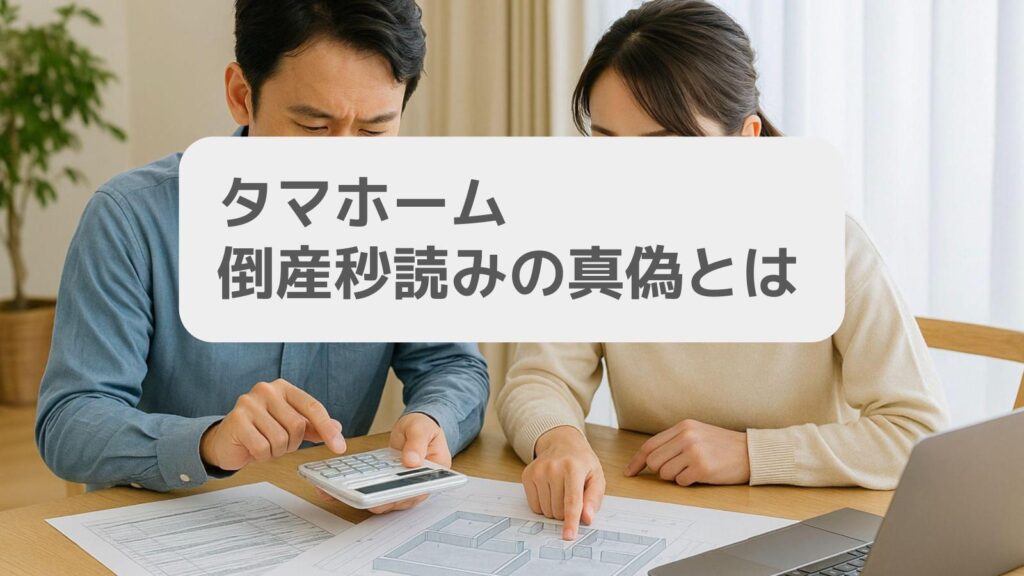
インターネットで「タマホーム 倒産秒読み」といった刺激的なフレーズを目にすることがありますが、実際の状況はそこまで深刻ではありません。最新の決算資料を確認すると、売上や営業利益が減少傾向にあることは事実ですが、財務体質そのものが大きく揺らいでいるわけではないのです。
具体的には、自己資本比率は30%前後を維持しており、これは建設業界の中では比較的健全な水準といえます。また、流動比率も一定の基準を上回っており、短期的な支払い能力についても懸念は小さいと考えられます。つまり、資金繰りが破綻しているような兆候は見られません。
ではなぜ「倒産秒読み」といった噂が出るのでしょうか? その背景には、営業利益率の急激な低下や、受注棟数の減少といった事実が影響しています。実際、最新四半期では営業利益率が1%を切る水準まで落ち込み、利益構造に不安を感じる声があるのも無理はありません。
また、タマホームはローコスト住宅で市場シェアを拡大してきた企業であり、建材費の高騰や住宅ローン金利の上昇といった業界全体の課題に直撃されやすいビジネスモデルを採っています。そのため、原価上昇を価格転嫁しきれないまま利益を圧迫されているという構図があります。
とはいえ、企業としては分譲住宅やリフォーム事業などにも力を入れており、事業の多角化によって収益基盤を広げようとする姿勢も見られます。今後の注目点は、営業利益率の回復と、受注数の下げ止まりが見られるかどうかです。
結論として、「倒産秒読み」と決めつけるのは早計であり、慎重に財務データを確認すれば、タマホームの現状はあくまで一時的な業績悪化であり、即座に経営破綻に直結する状況ではないことが分かります。
ハウスメーカーの倒産原因ランキング
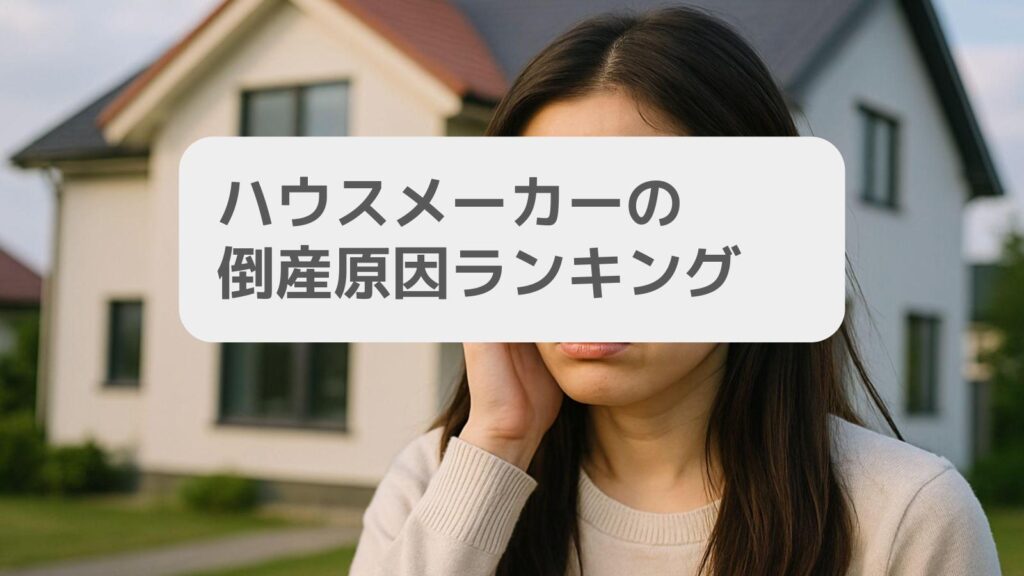
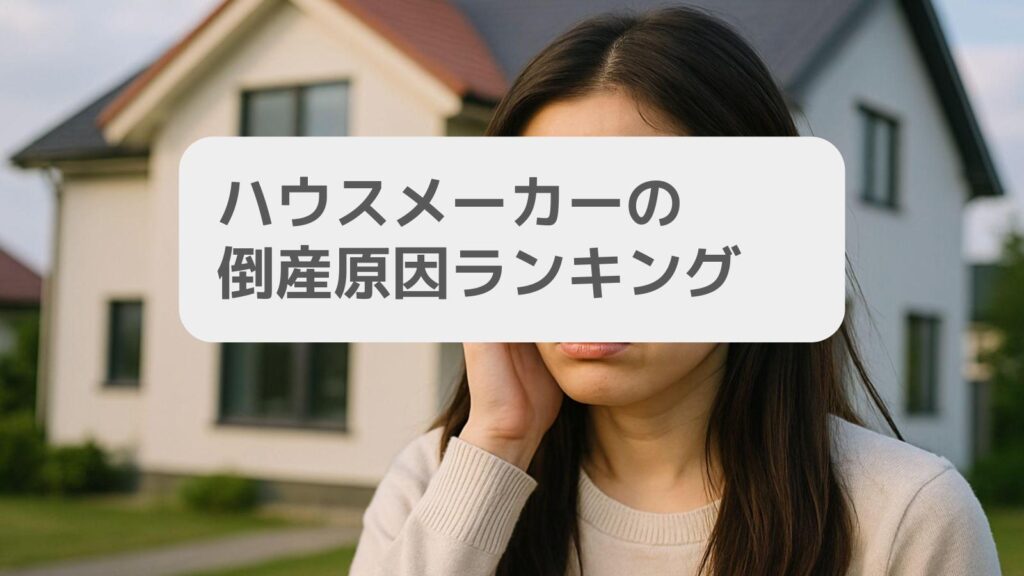
ハウスメーカーが倒産する理由にはいくつかの共通するパターンがありますが、特に多く見られるのは「資金繰りの悪化」「過剰な投資」「販売不振」の3つです。資金繰りの悪化とは、毎月の支払いに対して現金が不足し、取引先への支払いが滞ったり、従業員への給料が払えなくなったりする状態です。これが長引くと、金融機関からの信用も落ち、追加の融資も受けにくくなるため、経営は一気に苦しくなってしまいます。
次に過剰な投資です。企業が急成長を狙って展示場を一気に拡大したり、工場を新設したりすることがありますが、それらに見合った売上が伴わなければ、固定費の負担が重くなり、赤字に転落してしまうケースが多いです。特に、景気が悪化して住宅購入の需要が落ち込んだときには、このような大規模投資が裏目に出ることが少なくありません。
販売不振も見逃せない要因です。商品力や営業力が落ちてくると、次第に新築住宅の受注が減少していきます。そうなると収益が確保できず、企業の持続性が揺らぐようになります。特に地方のハウスメーカーや工務店では、地域の人口減少や高齢化により、顧客層そのものが縮小しているため、販売不振の影響はより深刻になります。
さらに、保証制度への未加入や、前金を多く集める営業手法も倒産リスクを高める要因です。保証制度に加入していない会社が倒産してしまうと、家が完成しないまま終わる可能性が高くなり、施主にとっても大きな損害となります。また、着工前に高額な前払い金を要求する企業の場合、経営状態が悪化するとその資金が戻ってこないリスクもあります。
特にローコスト系のハウスメーカーでは、価格を抑える代わりに利益率が極端に低くなりがちです。こうした経営モデルでは、一時的な受注減や原価上昇に対して脆弱であり、継続的な運営が難しくなることもあります。リスクを最小限にするためには、経営の健全性をチェックし、どのような販売戦略や資金管理体制を持っているかも確認することが大切です。
このようなリスク要因を事前に知っておくだけでも、信頼できる会社を見極める手助けになります。特に、家という大きな買い物においては、金額だけでなく企業の信頼性を総合的に評価する視点が必要です。
注文住宅業界全体のリスク要因
注文住宅業界は現在、大きな構造変化の波に直面しています。特に注目されるのが、消費税増税の影響による需要の減退や、新築着工件数の長期的な減少傾向です。国土交通省の統計によれば、2020年以降は少子高齢化の影響もあり、新築住宅の需要が縮小し続けています。これにより、住宅業界全体の成長鈍化が避けられない状況となっています。
加えて、人手不足の問題も深刻です。職人の高齢化が進む一方で、若手の新規就業者は減少傾向にあり、現場での人材確保が難しくなっています。このため、施工の質や工期にも悪影響が出やすく、特に小規模な工務店ではリソースのやり繰りに限界が出てくるケースが多く見られます。
さらに、資材価格の高騰が経営を圧迫しています。ウッドショックや鉄鋼資材の値上げ、物流費の増加といったコスト上昇要因が重なり、ハウスメーカーや工務店の原価管理に大きな負担を強いているのが現状です。こうした外的要因によるコスト上昇をすべて価格に転嫁できない企業は、利益率の低下に直面しやすく、資金繰りにも影響を及ぼします。
このような複数のリスクが同時に進行している今、注文住宅業界においては、柔軟かつ戦略的な経営判断が不可欠です。特に中小の工務店では、これらすべての変化に対応するための体力が不足していることが多く、倒産や事業縮小のリスクが高まっています。
だからこそ、施主としては経営基盤が安定しており、変化に強い体制を持つハウスメーカーを選ぶことが、結果的に安心して家づくりを進める大きなポイントになります。財務の健全性や過去の実績、施工体制や保証制度の内容まで含めて、総合的に判断する目を持つことが重要です。
倒産回避のポイントと対策
倒産リスクを避けるためには、住宅会社側の経営健全性はもちろんですが、施主自身の注意深い行動も欠かせません。最も基本的な対策の一つとして挙げられるのが、契約前に会社の決算書を確認することです。自己資本比率や営業利益率、流動比率といった数字をチェックすることで、その企業が安定した財務体質を持っているかをある程度判断することができます。上場企業であればIR情報が開示されていますし、非上場でも企業調査機関のレポートなどを活用すればある程度の情報を得ることが可能です。
また、完成引き渡し保証制度に加入しているかどうかの確認も非常に重要です。この保証制度は、万が一施工途中で住宅会社が倒産した場合に、別の会社が引き継いで工事を完成させてくれるものです。すべての会社が加入しているわけではないため、契約前に明確に確認しておくべきポイントです。この保証があるだけで、施主の心理的な安心感は大きく異なります。
次に、支払いスケジュールの設定も慎重に行う必要があります。できるだけ完成に近づいてからの支払い比率を高め、工事の進行状況に応じた段階的な支払いスキームを組むことが望ましいです。前払い比率が高すぎると、途中で倒産が起きた際に回収が困難になるリスクが高まります。
さらに、他社と相見積もりを取ることも有効なリスク回避策です。相見積もりを通じて価格や仕様の違いだけでなく、各社の対応姿勢や説明の丁寧さ、見積もり内容の透明性なども比較できます。この段階で対応が不明瞭だったり、説明を急がせるような会社には注意が必要です。
他にも、契約書の内容を専門家に確認してもらったり、口コミや施主ブログ、住宅展示場での営業担当者との会話から得られる印象なども判断材料となります。特に長期的なアフターサポートの内容や、トラブル時の対応実績については、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
このように、倒産リスクへの対策は多方面から行うことができます。小さな努力の積み重ねが、結果として自分の家づくりを守るための大きな盾となるのです。
安心して建てられる会社の選び方
家づくりを成功させるうえで、信頼できるパートナーを選ぶことは非常に大切です。どれほど魅力的な間取りや設備を備えていても、会社自体に問題があれば、後悔の残る家づくりになってしまう可能性があります。そのため、慎重な会社選びが求められます。
まず、安心して任せられる会社には共通点があります。それは、財務状況が健全であること、過去の施工実績が豊富にあること、そしてアフターサポートの体制が整っていることです。特に、自己資本比率が高く、営業利益率が安定している企業は、万が一の経済変動にも耐えられる体力を持っています。また、過去の施工実績を具体的に提示できる会社は、信頼性の裏付けとも言えるでしょう。
次に注目したいのが、営業担当者の対応です。こちらの希望や不安に対して親身になって耳を傾けてくれる担当者であれば、契約後の対応にも期待が持てます。逆に、契約を急がせたり、不明点に明確な回答がない担当者には注意が必要です。営業担当者の姿勢は、その会社全体の社風を表していることも多く、重要な判断材料の一つになります。
また、長期保証やメンテナンス体制も確認しておきたいポイントです。住宅は建てて終わりではなく、暮らしが始まってからも維持管理が必要です。だからこそ、トラブル時にすぐに対応してくれるアフターサービスがしっかり整っているかを事前にチェックしましょう。施工エリアごとの対応力や、実際の利用者の口コミなども参考になります。
最終的には、「この会社に頼んでよかった」と心から思えるような、誠実で実力のある企業を見つけることが理想です。そのためには、会社の理念や経営ビジョン、施工方針などにも目を向け、自分の価値観と合っているかを見極めましょう。価格だけでなく、安心感と信頼性を重視してパートナー選びをすることが、後悔のない家づくりへの近道になります。
一条工務店 倒産の可能性に関する総括ポイント
- 一条工務店は財務体質が健全で経営の安定性が高い
- 売上や利益の推移に大きな変動は見られない
- 高性能住宅のパッケージ戦略が利益構造の安定に寄与している
- 自己資本比率が高く、借入依存度が低い
- 自社工場による内製化でコストと品質を管理している
- 倒産リスクは現時点で低いと見られる
- ネット上の「やばい」という噂は一部の体験談に過ぎない
- SNSの評判には事実と異なる誇張も含まれる可能性がある
- 非上場企業ながら業界内での評価は高い
- 埼玉の倒産事例に学ぶべきは前金リスクと保証未加入の危険性
- 大手ハウスメーカーでも過去に倒産事例があるため油断は禁物
- 中小工務店との最大の違いは財務余力と施工体制の安定性
- 倒産リスクの見極めには財務指標の確認が有効
- タマホームのような業績悪化例はあるが倒産とは直結しない
- 最終的には経営体制・保証制度・営業姿勢を総合的に見て判断すべき
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店を検討中の方は以下の記事も参考にして後悔をなくしてくださいね!
費用・保険・保証
- 【実例あり】一条工務店の注文住宅の評判と住人だけが知るデメリット
- 一条工務店のメンテナンス費用は高い?30年間の総額を解説
- 一条工務店の火災保険は高い?割引と見積もりで安くする選び方
- 一条工務店が倒産する可能性は?経営状態と業績を見れば安心できる
エクステリア
- 一条工務店のハイドロテクトタイルはいらないと後悔!?メンテナンス楽で人気
- 一条工務店の対水害住宅の注意点|金額や何メートルの浸水まで大丈夫か
- 一条工務店の幹延長費用はいくら?ハグミーやアイキューブ・平屋で大丈夫か
- 一条工務店のバルコニーのメンテナンス費用は高い!?保証はどうなるのか
- 一条工務店のウッドデッキの後悔ポイントは後付け・メンテナンス・色など
- 一条工務店の庇で人気はアーバンルーフ!後付け・費用・後悔ポイント紹介
- 一条工務店の門柱はオプション扱い|位置や後付けで後悔しないために
玄関・ドア・天井
家の構造
- 一条工務店の鉄骨は後悔する?性能と価格を徹底解説
- 一条工務店の木材の品質や種類は!?産地はどこ産のものなのか
- 一条工務店の基礎の種類・ベタ基礎はオプションで費用はいくらか
- 一条工務店の平屋で後悔!?やめたほうがいい噂の理由とは?
- 一条工務店の家は増築できないのか?離れを作るには費用が高い
オプション選び
- 一条工務店のうるケアは後悔する?評判と費用を徹底解説
- 一条工務店の石目調フローリングで後悔しない!価格や特徴を解説
- 一条工務店のV2Hは後付けできる?価格・補助金・欠点を解説
- 一条工務店のクロスはどれがいい?標準とオプションおすすめの使い分け
- 一条工務店で無垢床フローリングにしたい!気になる費用・欠点・ゴキブリについて
- 一条工務店の勾配天井は6畳でもOK?費用やルールで後悔しないために
- 一条工務店のオープンステアで後悔!?下の活用は収納だけじゃない
- 一条工務店なら網戸はいらないと思ったら後悔!勝手口に必要かの判断基準
- 一条工務店の防音ドアはトイレやリビングにも!効果はバツグン
- 一条工務店のカーテンがいらないと思ったらカーテンレールのみで良いか
- 一条工務店の3Dパースを依頼したい!内観パースは作ってくれないの?
- 一条工務店で防音室の設置費用はいくらか|効果は高く「うるさい」を解決
- 一条工務店の防犯カメラは後付け・施主支給できるか?お得に安心したい方へ
- 一条工務店の浄水器おすすめはこれ!後付けできるパナソニック製品など
- 一条工務店の玄関ポーチ人気のタイル色やポーチ延長費用を徹底紹介
- 一条工務店のランドリールーム必要か?乾かない噂や間取りなど後悔ポイントまとめ
- 一条工務店のキッチンにリクシルを施主支給したい!標準メーカーはダサい?
- 一条工務店でダウンライトにすべきか?いらないの声やシーリングにすればよかったなど
- 一条工務店の本棚(ブックシェルフ)で後悔!?背中合わせで賢く収納
- 一条工務店 御影石のキッチンカウンターはダサい?おしゃれを実現するヒント
- 一条工務店の階段を完全紹介!パターンの選び方・必要なマス数を知り失敗を防ぐ
- 一条工務店の屋根裏収納で後悔しないポイント|後付け・費用・見積もり
- 一条工務店の1.5階建ての費用・人気の理由・デメリットや間取りの注意点
- 一条工務店の押し入れ選び!観音開き・引き戸・開き戸のメリットデメリット
- 一条工務店で和室はいらない!?小上がりや畳選びで後悔しがち
- 一条工務店でゴキブリ出現!?換気システムから侵入か給気口か
- 一条工務店のロフトの費用は意外と安い!平屋との相性も良し
設備
- 一条工務店ヘッダーボックスの場所は玄関と階段下が最適!音と床暖的効果
- 一条工務店のインターホンの選び方|標準モデルMT101から後付けまで網羅
- 一条工務店の物干し金物ホスクリーンは後付けできるのか|耐荷重や設置値
- 一条工務店の自在棚にシンデレラフィットするゴミ箱
- 一条工務店のスマートキーつけるべきか?後付けやピーピー音・紛失トラブルも
- 一条工務店のエコキュートおすすめモデルは快適重視ならPシリーズ
- 一条工務店のレンジフード選び|操作選びやフィルター有無
- 一条工務店の蓄電池を2台に!価格や容量、後付け費用を解説
- 一条工務店の浴室乾燥機はオプションでつけるべきか?後悔しない判断基準
- 一条工務店シューズボックスの全て!種類・収納・価格を解説

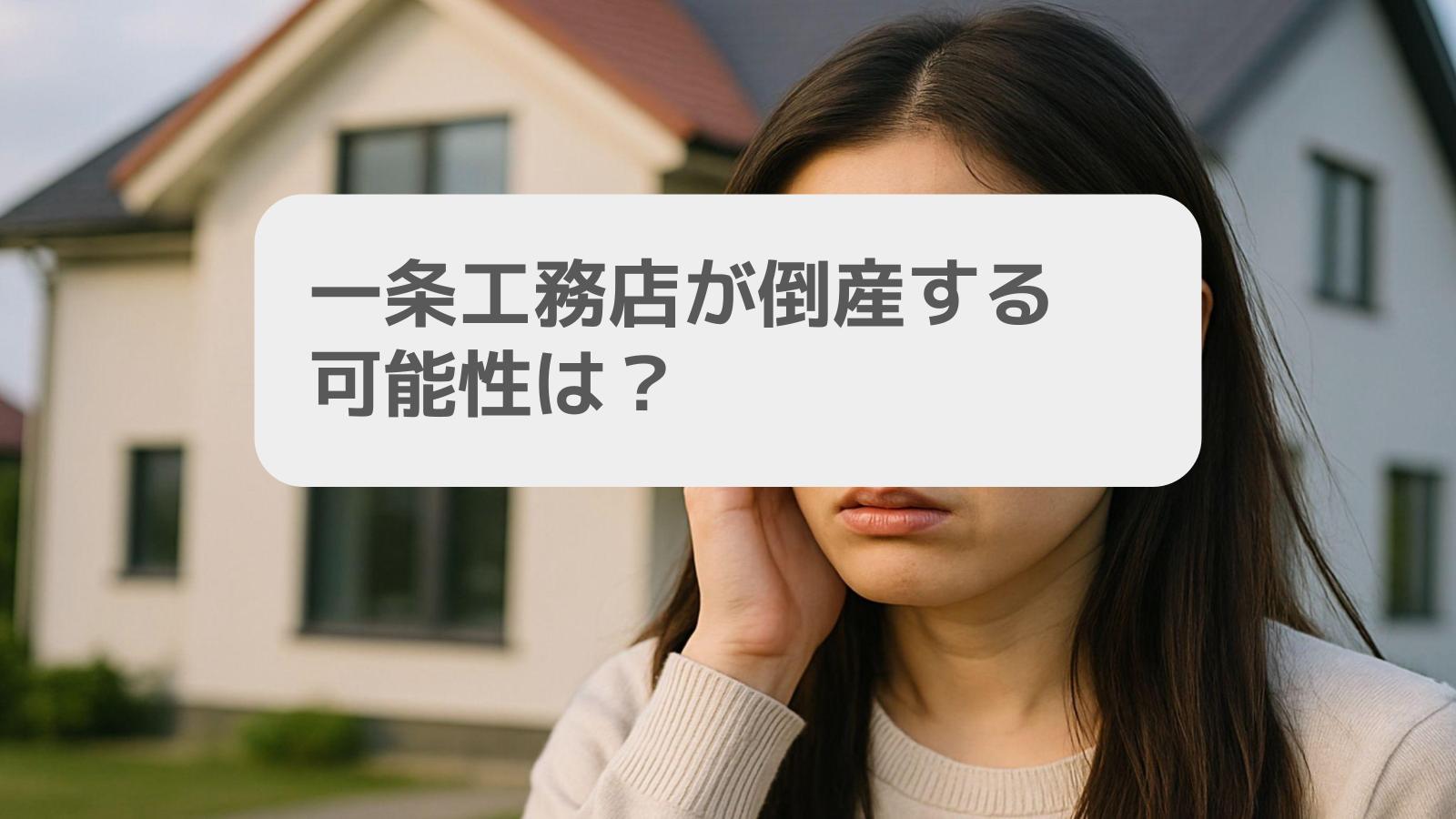



コメント