「一条工務店 屋根裏収納」と検索してたどり着いた方は、おそらく収納力をアップさせたい、あるいは限られた空間を有効活用したいと考えていることでしょう。
本記事では、平屋での屋根裏活用や、グランスマートとの相性、小屋裏収納に固定階段を設けるべきかといった設計面のポイントから、小屋裏収納のフローリング仕上げや温度・湿度管理、窓の設置といった快適性に関する要素まで幅広く解説しています。
また、後付けでの施工やDIYによる工夫、ロフトと小屋裏の違い、費用の目安や後悔しないための判断基準についても触れており、これから屋根裏収納を検討する方にとって役立つ情報が詰まっています。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収納方式 | 小屋裏収納(天井高1.4m未満で延床面積に含まれない) |
| 設置住宅タイプ | 平屋やグランスマートなど(構造に応じて設計が必要) |
| アクセス方法 | はしご式・固定階段(固定階段は利便性と安全性に優れる) |
| 収納の快適性 | 断熱材と換気が重要。温度・湿気対策必須 |
| 窓の有無 | 採光・換気向けに設置可能(防犯・断熱性に注意) |
| 仕上げ仕様 | 標準は板張り。フローリングはオプション(見た目・快適性UP) |
| 用途例 | 季節物・思い出品・防災用品など年数回利用の物に最適 |
| DIY活用 | 棚や照明、ラベル整理などで快適性向上が可能 |
| 後付け対応 | 可能だが構造制限や追加費用、断熱性に注意が必要 |
| 費用目安 | 基本は1坪10万円、オプション込みで30万〜100万円 |
| 後悔しないポイント | 収納頻度・物の種類を考慮した計画が重要 |
| ロフトとの違い | ロフトは居住空間、小屋裏収納はあくまで収納用 |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
一条工務店 屋根裏収納の魅力と活用術
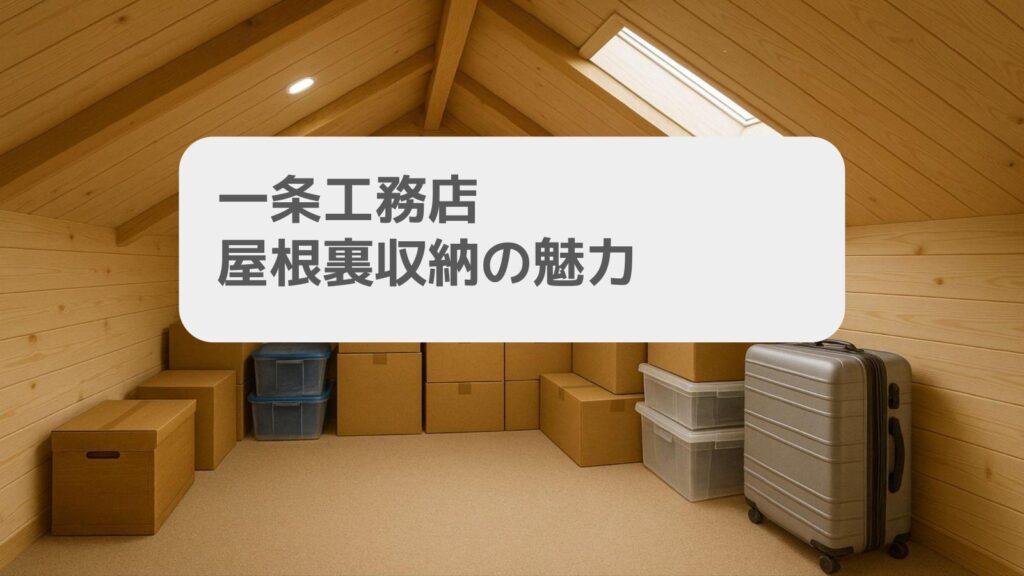
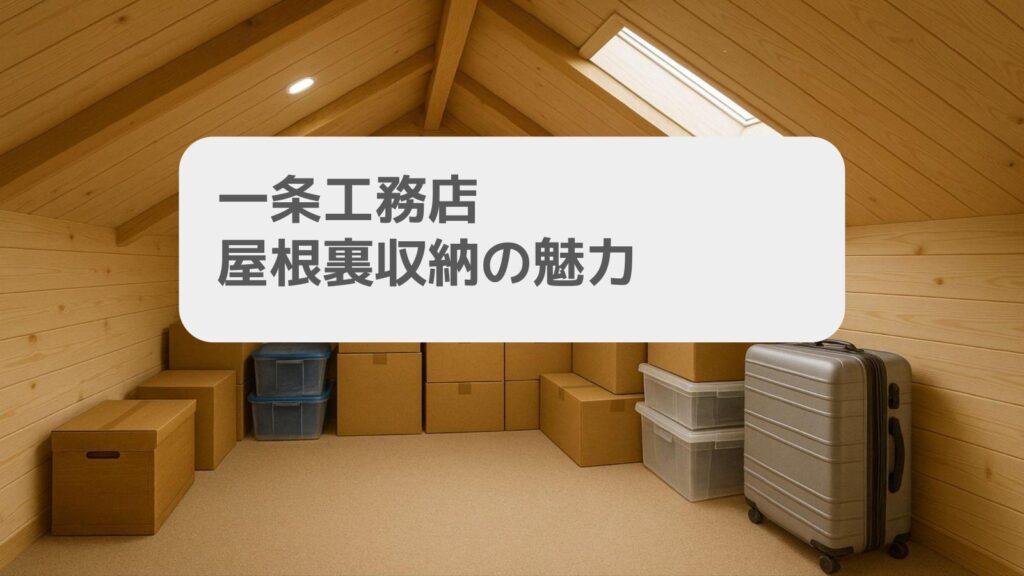
- 小屋裏収納に固定階段は必要?
- 平屋で屋根裏収納を作るメリット
- グランスマートとの相性をチェック
- 小屋裏収納の温度と湿気対策
- 小屋裏収納に窓を付けるべき?
- ロフトと屋根裏収納の違いとは
小屋裏収納に固定階段は必要?
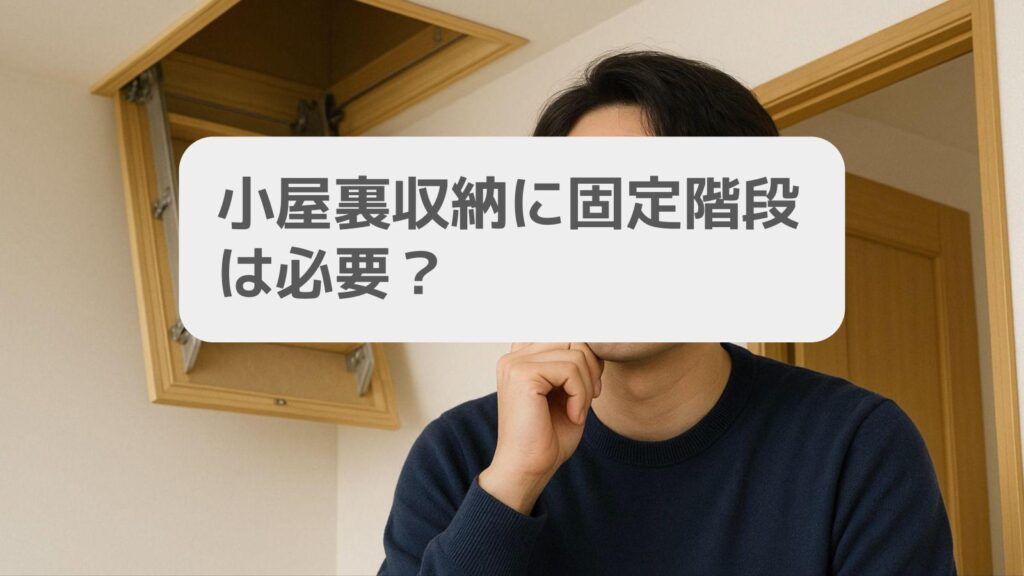
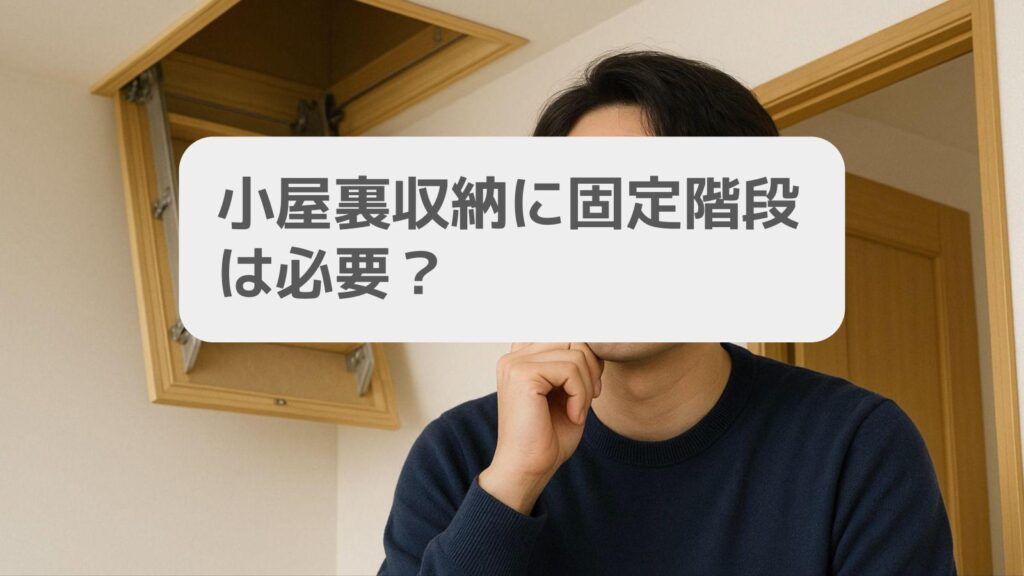
結論から言うと、屋根裏収納を頻繁に使うご家庭では、固定階段の設置が非常におすすめです。なぜなら、折りたたみ式のはしごよりも安全性が高く、荷物の持ち運びや昇り降りがスムーズになるからです。はしごだとバランスを崩しやすく、小さなお子さんやご年配の方が使用する場合は特に不安が残ります。
例えば、季節物の大きなアイテム、クリスマスツリーや雛人形、布団やキャリーケースなどを収納する際、安定した階段があることで、負担なく出し入れができるようになります。さらに、手すりがあることで安心感が増し、落下リスクも減らせます。
ただし、固定階段を設けるには一定のスペースが必要になります。階段が場所をとる分、収納に使える面積が少なくなる場合もありますし、設置場所によっては間取りの工夫も必要です。また、固定階段を設置することで、屋根裏収納が「居室」と見なされる可能性がある点にも注意が必要です。
このような理由から、固定階段をつけるかどうかは、使用頻度や収納する物の大きさ・重さ、家族構成などを総合的に考えて判断するのが良いでしょう。将来のライフスタイルも見越して設計できれば、より使い勝手の良い収納空間をつくることができます。
平屋で屋根裏収納を作るメリット
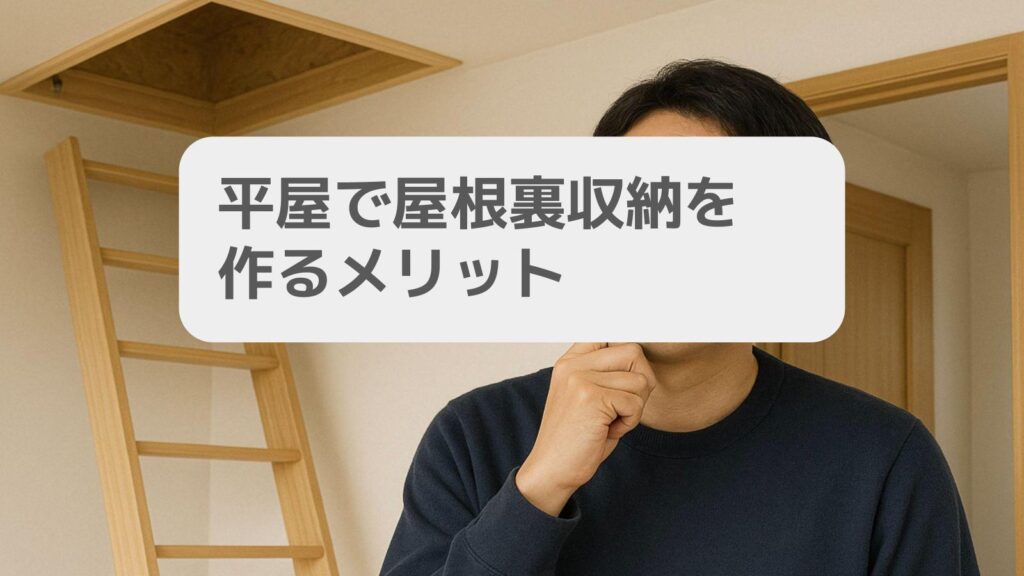
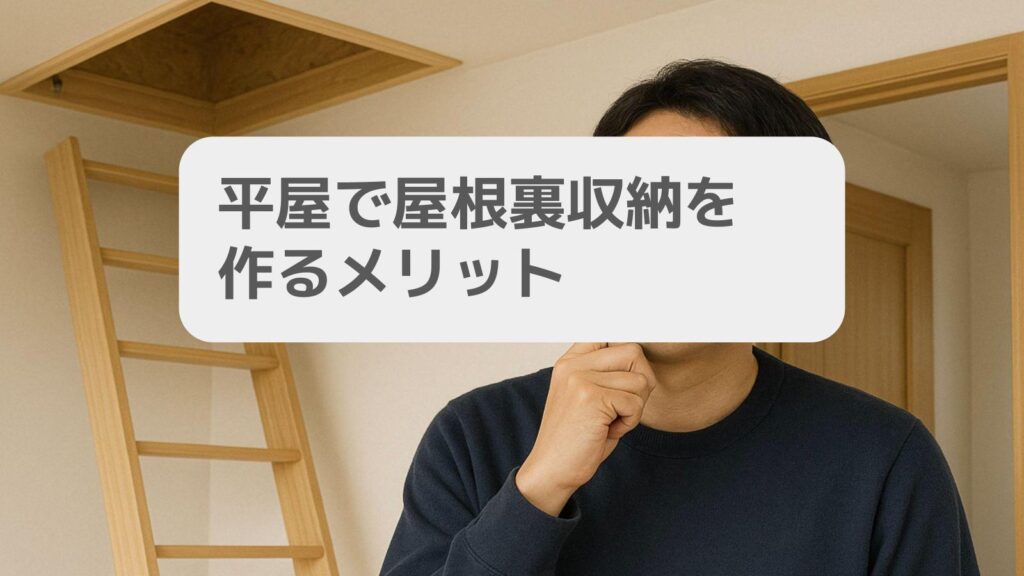
平屋に住んでいる方にとって、屋根裏収納はとても魅力的な選択肢です。なぜなら、平屋は2階がない分、収納スペースがどうしても不足しがちで、物が増えていく中で「置き場が足りない」と感じることが多いからです。
このため、屋根裏という本来使われにくいスペースを活用することで、空間を無駄なく使うことができます。例えば、季節ごとの飾りやアウトドア用品、年に数回しか使わない防災グッズなどをしまっておくには、屋根裏収納が非常に便利です。
特に、勾配天井がある平屋では、屋根の形状を活かして比較的簡単に屋根裏スペースを確保しやすくなります。天井裏のデッドスペースを有効に活用できるため、間取りを変えることなく収納力だけを増やせる点が大きな魅力です。
また、固定階段や折りたたみ式の階段を設けることでアクセス性を高めれば、日常的な使い勝手も良くなります。子育て中の家庭では、子どもの成長とともに増えていく思い出の品を保管する場所としても重宝するでしょう。
ただし、天井高の制限(1.4メートル以下)や、屋根の形・勾配によって収納の広さが変わる点には注意が必要です。また、断熱・換気が不十分な場合は湿気やカビの原因にもなりやすいため、設計段階で施工会社としっかり話し合っておくことが重要です。
このように、平屋での屋根裏収納は空間を最大限に活用できる方法のひとつです。限られたスペースでも工夫次第で生活の快適さを大きく向上させることができます。
グランスマートとの相性をチェック
グランスマートシリーズとの相性も気になるところですよね。実は、グランスマートのような総2階構造の住宅では、屋根裏収納の設置に工夫が必要です。屋根の構造がフラットだったり、勾配が緩やかであることが多いため、十分な天井高(1.4メートル未満)を確保しにくい場合があるのです。
また、屋根裏収納を設ける際には、断熱や換気などの快適性を保つための施工も重要になりますが、総2階建ての場合はそのためのスペース的余裕が限られてしまうことがあります。たとえば、構造上の制約で収納スペースを設けられる位置が限定されたり、アクセスするための階段の設置場所に悩むことも少なくありません。
一方で、グランセゾンのように2階の床面積が1階よりも小さい設計の住宅では、屋根裏収納のスペースを確保しやすいという利点があります。このような設計では、階段や出入口の配置にも自由度があり、収納の使い勝手が格段に良くなります。
そのため、グランスマートで屋根裏収納を考える場合は、勾配屋根の採用や、収納をどこに設けるかといった詳細な計画が欠かせません。断熱性を高めつつも収納力を確保するには、間取りと構造の両方を丁寧に調整する必要があります。
このような条件をふまえて、事前に設計士とじっくり相談し、どのような形式で収納スペースをつくるかを明確にしておくと安心です。建てた後に「やっぱり屋根裏収納をつけておけばよかった」と後悔しないためにも、早い段階での検討がおすすめです。
小屋裏収納の温度と湿気対策
小屋裏収納は、屋根のすぐ下という位置にあるため、外気の影響を非常に受けやすい場所です。そのため、夏場はサウナのように高温になりやすく、冬場は氷点下近くまで冷え込むことも珍しくありません。こうした極端な温度差が原因で、収納した物が劣化したり、カビが生えたりするリスクが高まります。つまり、温度と湿気の管理を怠ると、せっかくの収納スペースが「使えない場所」になってしまう恐れがあるのです。
このため、まずは断熱対策がとても重要になります。一条工務店の屋根裏収納では高性能グラスウールが使われることが多く、断熱性に優れていますが、それでも完璧とは言い切れません。空気の流れがない空間では、湿気がこもってしまいがちなので、換気設備の有無も確認することが大切です。
例えば、湿気対策として最も手軽にできるのが「除湿剤の設置」です。市販の除湿剤を複数置くだけでもかなりの効果が期待できます。さらに、天気の良い日には収納口を開けて空気を入れ替えることも習慣にするとよいでしょう。空気を循環させるだけで、湿度が下がりカビの発生も抑えられます。
収納するアイテムの選び方もポイントです。紙製品や革製品、家電など湿気や温度変化に弱いものは避けるのが無難です。代わりに、プラスチック製の収納ケースを使うことで、湿気から守りつつ中の荷物の仕分けも簡単になります。できれば蓋つきの密閉タイプを選ぶと安心です。
また、荷物を床に直置きするのではなく、棚やスノコなどを使って通気性を確保する工夫もおすすめです。これにより、空気の通り道ができて湿気がたまりにくくなります。
このように、屋根裏収納の環境をきちんと整えておけば、長期間にわたって快適に使い続けることができます。多少の手間はかかりますが、その分大切な物をしっかり守れる、頼もしい収納スペースになるでしょう。
小屋裏収納に窓を付けるべき?
結論から言えば、小屋裏収納に窓を設けるかどうかは、その収納スペースをどのように使いたいかによって大きく変わってきます。換気や採光をしっかり取りたい場合には窓は便利で、自然光が差し込むと中の物が見やすくなるというメリットもありますし、湿気対策としても一定の効果が期待できます。
例えば、日中に出入りする機会が多く、収納物の出し入れを頻繁に行う場合には、窓があると明るく快適な空間となり、作業がしやすくなるでしょう。通気性を高めることで、カビの予防にもつながります。
しかし一方で、防犯の観点から考えると、窓があることで外部からの侵入経路となる可能性も否定できません。防犯ガラスを採用したり、面格子を設置したりすることでリスクを下げることはできますが、費用が増える要因にもなります。また、断熱性に関しても、壁に比べて窓の部分は熱を通しやすいため、夏は熱気が入りやすく、冬は冷気が入りやすくなる傾向があります。
さらに、窓を設けることで発生する追加の建築コストも無視できません。窓のサイズや種類、施工場所によって差はありますが、設置費用は一般的に数万円〜十数万円の追加となるケースが多いです。つまり、快適さと安全性、コストのバランスを考えて判断する必要があります。
おそらく、普段はめったに出入りしない、あくまで物を収納するためだけの空間であれば、無理に窓を付けなくても問題ありません。窓なしでも、除湿剤の使用や定期的な空気の入れ替えを行えば、十分に湿気対策は可能です。空調設備を追加することで、さらに快適性を高めることもできるでしょう。
このように、小屋裏収納に窓を付けるかどうかは、使い方や家族のライフスタイル、そして予算によって変わってきます。設計段階での丁寧な検討が、後悔しない家づくりにつながります。
ロフトと屋根裏収納の違いとは
ロフトと屋根裏収納は名前が似ているため、混同されることも多いですが、実際には目的や設計の意図、使用方法に大きな違いがあります。ロフトは、主に居住空間の延長として設けられることが多く、書斎や寝室、子どもの遊び場など、多目的に活用できるスペースです。
ロフトにはフローリングや壁紙、照明やエアコンなどが標準的に設置されることが多く、居住性に配慮された設計になっています。天井高も比較的高く、快適に過ごせる環境が整っているのが特徴です。また、窓を設けることも可能で、自然光が入る開放的な空間をつくりやすいのも魅力のひとつです。
一方、屋根裏収納(小屋裏収納)は、あくまでも「収納」を目的としたスペースであり、人が長時間滞在するような設計にはなっていません。建築基準法では天井高を1.4メートル未満に抑えることで、延床面積に含まれず、固定資産税の対象外になるというメリットがあります。
そのため、小屋裏収納は最低限の板張りの床にとどめられていることが多く、フローリングや壁紙の施工はオプションになります。また、エアコンや照明の設置も基本的には含まれないため、ロフトに比べて快適性は劣りますが、コストは圧倒的に抑えられます。
このように、ロフトは「空間を楽しむ」ための設備であるのに対して、屋根裏収納は「空間を活かす」ための設備といえるでしょう。設置にかかる費用や、利用頻度、家族構成、生活動線などをふまえて、どちらが自分の暮らしに合っているかをじっくり検討することが大切です。
ライフスタイルに合わせて使い分けることで、住まい全体の快適性と機能性がさらに高まります。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店 屋根裏収納の費用と失敗回避


- 小屋裏収納のフローリング費用は?
- 屋根裏収納を後付けする際の注意点
- DIYで屋根裏収納を快適に使う
- 固定階段のあるロフトは便利?
- 小屋裏収納で後悔しないために
- 一条工務店の屋根裏収納の総費用
小屋裏収納のフローリング費用は?
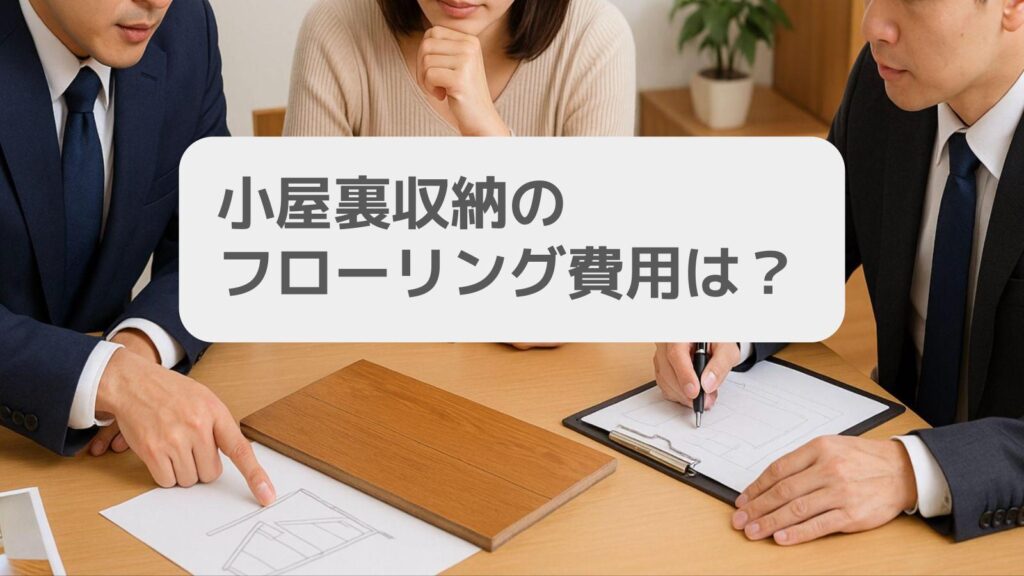
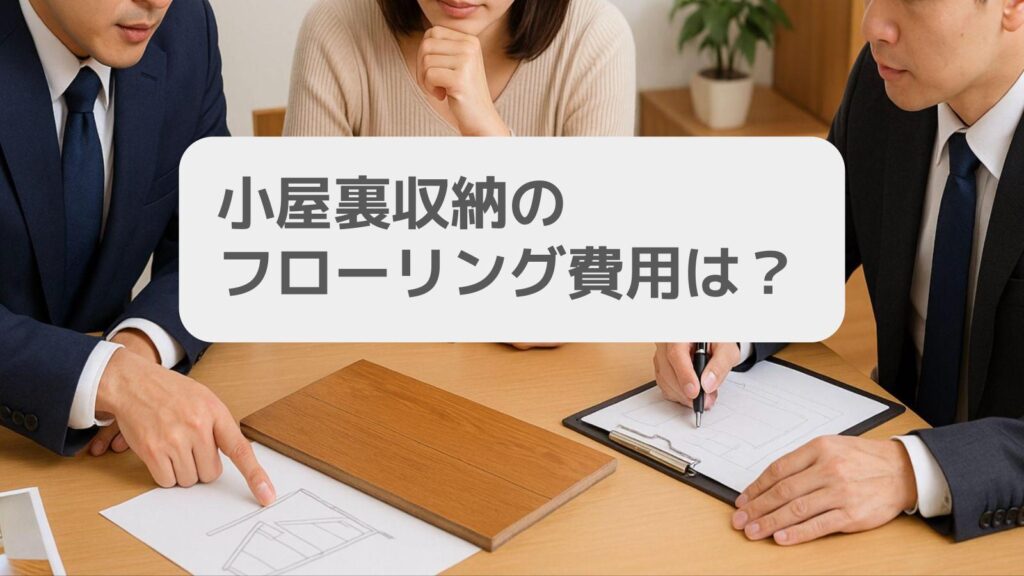
小屋裏収納のフローリング施工には、基本的にオプション費用が発生します。標準では板張りが施されており、素朴で実用的な仕上がりにはなっていますが、見た目の高級感や快適性を求める方には少し物足りなく感じるかもしれません。そのため、見た目や肌触り、使いやすさを重視する人の中には、フローリング仕上げを選ぶケースが少なくありません。
実際にフローリングを導入する場合、費用は1帖あたり数万円が相場です。ただし、選ぶフローリングの素材や仕様によって価格は上下します。たとえば、防水性や防汚性に優れたフローリングを選べば、湿気がこもりやすい屋根裏空間でも安心して使えますし、掃除もしやすくなります。また、滑りにくい加工が施されたフローリングであれば、安全性も向上します。
さらに、フローリングのカラーや質感を室内の雰囲気と揃えることで、見た目の統一感も得られます。屋根裏収納を半分趣味スペースや作業スペースとして使いたい方にとっては、インテリア性のあるフローリングは魅力的な選択肢となるでしょう。
とはいえ、収納スペースとしてのみ利用するのであれば、標準仕様の板張りでも機能的には十分です。コストを抑えたい場合や、収納物が主に段ボールやプラスチックケースであるなら、あえてフローリングにこだわらない選択も賢明です。見た目よりも実用性を重視し、必要性をよく見極めて判断することが大切です。
このように、フローリングにするかどうかは、屋根裏収納の用途と使用頻度、そして予算によって最適な判断が異なります。無理のない範囲で、自分にとって使いやすい空間づくりを目指しましょう。
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
屋根裏収納を後付けする際の注意点


屋根裏収納は新築時に設けるのが理想ですが、後付けも不可能ではありません。ただし、後から設置するとなると、設計や構造上の制約が多くなるため、事前の確認が必須です。特に天井高や屋根の勾配が重要で、1.4メートル以下の高さを確保できなければ、建築基準法上「階」として扱われてしまい、固定資産税が加算されるリスクがあります。
また、屋根の構造によっては、梁や配線、ダクトなどが干渉してしまい、思ったようにスペースを確保できない場合もあります。既存の住宅では間取りの変更が難しく、屋根裏へのアクセス経路をどう確保するかも大きな課題です。はしごタイプでは不便な場合、固定階段の設置が必要となりますが、それには大がかりなリフォームが伴うこともあるため、工事費用が膨らみがちです。
断熱や換気に関しても、後付けの場合は十分な施工が難しくなることが多いです。特に断熱材を入れるスペースが確保しにくく、結果として夏は高温、冬は極寒という過酷な環境になりやすい傾向があります。湿気がこもりやすくなることで、カビや結露のリスクも増します。そのため、除湿機や換気ファンなどの追加工事を前提とした予算設計が必要です。
さらに、後付け工事の費用は内容によって差がありますが、簡易な施工でも30万円以上、本格的な設備を整える場合は50万〜100万円程度を見込んでおいた方が安心です。屋根裏部分の補強が必要な場合もあり、その際には構造計算や補強材の追加施工が発生します。
こうした点を総合的に考慮すると、屋根裏収納は新築時に他の工事と一緒に計画しておく方が、費用も工期も抑えられ、全体的に効率的です。後付けを検討する際は、信頼できる業者に相談し、現地調査と構造確認をしっかり行った上で進めることが大切です。
DIYで屋根裏収納を快適に使う
収納スペースをもっと使いやすくしたいなら、DIYはとても有効な手段になります。限られた空間を有効活用するには、自分の使い方に合ったカスタマイズが必要であり、それを実現しやすいのがDIYです。ちょっとした工夫を加えるだけで、屋根裏収納の快適性や使い勝手が大きく変わってきます。
例えば、収納力を上げたい場合は、壁面に棚やフックを取り付けて立体的に使えるようにすると便利です。工具不要の突っ張り棚や収納ラックなら手軽に取り付けられ、模様替えや調整も簡単です。また、収納ボックスにラベルを貼って中身がわかるようにすることで、探し物の時間がぐっと短縮されます。
さらに、屋根裏収納は暗くなりがちな空間でもあるため、照明の追加もおすすめです。乾電池式のLEDライトやセンサー付きのライトを使えば、配線工事をせずとも明るく快適に使えるようになります。特に、夜間に出し入れする機会があるご家庭では、視認性が大きく向上します。
加えて、床面にクッション性のあるジョイントマットやフロアタイルを敷くことで、見た目の印象が一変しますし、足元の冷え対策にもなります。おしゃれさを重視するなら、木目調やタイル調のデザインを取り入れてみるのも良いアイデアです。
ただし、DIYで作業する際には安全性への配慮も忘れてはいけません。はしごを使用して上り下りする場合は特に、足場が安定しているかを確認しながら作業を行いましょう。また、重いものは高所に置かず、軽いものを上段に、重いものは下段に配置することで落下のリスクを減らせます。
このように、DIYを活用すれば屋根裏収納は「ただの物置」から「使いやすくて楽しい空間」へと生まれ変わります。ご自身のライフスタイルに合わせた工夫を取り入れて、より快適で実用的な収納スペースを目指してみてください。
固定階段のあるロフトは便利?
固定階段付きのロフトは、見た目のデザイン性だけでなく、実用性の面でも非常に優れています。階段がしっかりと設置されていることで、日常的な上り下りがしやすくなり、重い荷物や頻繁に使う物を運ぶ際のストレスも軽減されます。また、急な来客時にも安心して案内できる空間として利用できるのもメリットのひとつです。
一方で、ロフトは屋根裏収納と違って居住スペースとして扱われるため、延床面積に含まれるという点は押さえておく必要があります。これはつまり、建物全体の評価額が上がることにつながり、固定資産税の課税対象にもなってしまう可能性があるということです。
また、施工にかかる費用についても、固定階段を設置する分だけ高くなる傾向があります。特に、階段の素材やデザインにこだわる場合や、間取りの調整が必要になる場合には追加費用が発生しやすく、コスト面の負担は避けられません。安全性を高めるために手すりを設けたり、階段の角度や踏板の幅を調整するなどの工夫も必要です。
とはいえ、ロフトを日常的に使う予定があるならば、固定階段を選ぶことで利便性と安全性が大きく向上します。例えば、読書スペースや趣味の部屋、子どものプレイスペースなど、用途に応じて快適に使える空間として設計しやすくなります。
このように、ロフトに固定階段を設置するかどうかは、使用目的や家族構成、そして予算とのバランスを見て判断することが大切です。デザイン性と実用性を両立させた、暮らしに合ったロフト空間を目指しましょう。
小屋裏収納で後悔しないために
屋根裏収納を設けたものの、「思ったほど使いやすくなかった」「こんなはずじゃなかった」と感じる方は、意外にも少なくありません。後悔しないためには、計画段階で自分たちのライフスタイルや収納スタイルをしっかりと見つめ直し、どのような物をどれくらいの頻度で出し入れするのかを明確にイメージしておくことが重要です。
たとえば、収納する予定の物が季節限定の衣類やクリスマスツリーなどであれば、年に数回の出し入れで済むため屋根裏収納は非常に便利です。しかし、日用品や掃除機、工具など頻繁に使う物をしまい込んでしまうと、毎回の昇降が負担となり、結果的に使われなくなるというパターンも少なくありません。
また、屋根裏は温度と湿度の変化が激しいため、収納物の種類にも注意が必要です。特に、アルバムや電子機器、革製品などデリケートな素材を収納すると、カビが生えたり劣化したりするリスクがあります。空調設備が入っていない場合は、断熱材の性能や換気の有無が非常に重要になります。
設計段階で「何をどのように収納したいのか」「どれだけアクセスしやすくしたいのか」といった使い方を具体的に想定し、その内容を図面に落とし込んでおくことが、失敗を避ける第一歩です。場合によっては、はしごタイプよりも固定階段の方が安全で便利ですし、収納口を広く取るだけでも格段に出し入れしやすくなります。
さらに、定期的な換気や湿気対策も重要なポイントです。天井に通気口を設けたり、除湿剤やサーキュレーターを使って空気を循環させる工夫を取り入れると、長期間にわたって快適に使用できる収納空間になります。
このように、屋根裏収納は便利でコストパフォーマンスも良い設備ですが、後悔しないためには「使う人の目線」で丁寧に計画することが欠かせません。
一条工務店の屋根裏収納の総費用
一条工務店で屋根裏収納を作る際、基本の坪単価は約10万円とされています。これはほかの収納スペースと比較しても非常にコストパフォーマンスが高く、手軽に広い収納空間を得られるため、多くの方に支持されています。
ただし、基本プランに含まれるのはあくまで板張り仕様のシンプルな仕上げであり、実際に使いやすく快適な収納空間にするためには、追加オプションの検討が不可欠です。たとえば、フローリング仕上げにすると見た目が良くなり、床の耐久性や掃除のしやすさも向上します。固定階段を選べば、日常的な出し入れがスムーズになり、安全性も高まります。また、窓や換気設備を追加することで湿気やカビのリスクを軽減できるため、長期的なメンテナンスの手間を減らすことにもつながります。
これらのオプションをすべて含めた場合、最終的な費用は30万円〜60万円前後が一般的な目安となります。しかし、収納スペースの広さや選ぶ仕様によっては、それ以上の金額になることもあります。たとえば、6帖以上の大きな屋根裏収納をつくる場合や、デザイン性の高い内装材を使用する場合は、100万円近くかかることも想定しておいたほうがよいでしょう。
コストを無駄にしないためには、自分たちにとって本当に必要な仕様が何かを明確にして、優先順位をつけたプランニングが大切です。「とりあえず全部盛り」で選んでしまうと、予算オーバーになるだけでなく、使わない設備にお金をかけてしまうリスクもあります。逆に、必要最低限に絞ってしまうと、結局あとで「やっぱり追加すればよかった」と後悔する可能性も。
このように、費用面と実用性をバランスよく両立させるには、生活スタイルや使い方に合ったカスタマイズを意識しながら、予算内で効率的な屋根裏収納プランを組み立てることがとても大切です。
一条工務店 屋根裏収納の特徴と活用ポイントまとめ
- 頻繁に使うなら固定階段の設置が望ましい
- 平屋住宅では屋根裏を活かすと収納力が大幅に増す
- グランスマートは設計に工夫が必要な構造である
- 高温・低温に晒されやすいため断熱と湿気対策が必須
- 換気目的で窓を設ける際は防犯と断熱性にも配慮すべき
- ロフトは居住空間、小屋裏収納は収納専用と役割が異なる
- フローリング仕上げにより見た目と機能性が向上する
- 後付けには構造や税制上の制限があるため慎重な判断が必要
- DIYで棚や照明を追加すれば使い勝手が大きく向上する
- 固定階段付きロフトは実用性が高い反面コストがかかる
- 屋根裏収納は用途や頻度を明確にしたうえで設計すべき
- 除湿剤やスノコなどで湿気と通気性をしっかり管理する
- 窓なしでも除湿対策と換気ができれば快適性は確保できる
- 費用はオプション次第で数十万〜100万円近くまで変動する
- 実用性と予算のバランスを見極めてプランニングすることが大切
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店を検討中の方は以下の記事も参考にして後悔をなくしてくださいね!
費用・保険・保証
- 【実例あり】一条工務店の注文住宅の評判と住人だけが知るデメリット
- 一条工務店のメンテナンス費用は高い?30年間の総額を解説
- 一条工務店の火災保険は高い?割引と見積もりで安くする選び方
- 一条工務店が倒産する可能性は?経営状態と業績を見れば安心できる
エクステリア
- 一条工務店のハイドロテクトタイルはいらないと後悔!?メンテナンス楽で人気
- 一条工務店の対水害住宅の注意点|金額や何メートルの浸水まで大丈夫か
- 一条工務店の幹延長費用はいくら?ハグミーやアイキューブ・平屋で大丈夫か
- 一条工務店のバルコニーのメンテナンス費用は高い!?保証はどうなるのか
- 一条工務店のウッドデッキの後悔ポイントは後付け・メンテナンス・色など
- 一条工務店の庇で人気はアーバンルーフ!後付け・費用・後悔ポイント紹介
- 一条工務店の門柱はオプション扱い|位置や後付けで後悔しないために
玄関・ドア・天井
家の構造
- 一条工務店の鉄骨は後悔する?性能と価格を徹底解説
- 一条工務店の木材の品質や種類は!?産地はどこ産のものなのか
- 一条工務店の基礎の種類・ベタ基礎はオプションで費用はいくらか
- 一条工務店の平屋で後悔!?やめたほうがいい噂の理由とは?
- 一条工務店の家は増築できないのか?離れを作るには費用が高い
オプション選び
- 一条工務店のうるケアは後悔する?評判と費用を徹底解説
- 一条工務店の石目調フローリングで後悔しない!価格や特徴を解説
- 一条工務店のV2Hは後付けできる?価格・補助金・欠点を解説
- 一条工務店のクロスはどれがいい?標準とオプションおすすめの使い分け
- 一条工務店で無垢床フローリングにしたい!気になる費用・欠点・ゴキブリについて
- 一条工務店の勾配天井は6畳でもOK?費用やルールで後悔しないために
- 一条工務店のオープンステアで後悔!?下の活用は収納だけじゃない
- 一条工務店なら網戸はいらないと思ったら後悔!勝手口に必要かの判断基準
- 一条工務店の防音ドアはトイレやリビングにも!効果はバツグン
- 一条工務店のカーテンがいらないと思ったらカーテンレールのみで良いか
- 一条工務店の3Dパースを依頼したい!内観パースは作ってくれないの?
- 一条工務店で防音室の設置費用はいくらか|効果は高く「うるさい」を解決
- 一条工務店の防犯カメラは後付け・施主支給できるか?お得に安心したい方へ
- 一条工務店の浄水器おすすめはこれ!後付けできるパナソニック製品など
- 一条工務店の玄関ポーチ人気のタイル色やポーチ延長費用を徹底紹介
- 一条工務店のランドリールーム必要か?乾かない噂や間取りなど後悔ポイントまとめ
- 一条工務店のキッチンにリクシルを施主支給したい!標準メーカーはダサい?
- 一条工務店でダウンライトにすべきか?いらないの声やシーリングにすればよかったなど
- 一条工務店の本棚(ブックシェルフ)で後悔!?背中合わせで賢く収納
- 一条工務店 御影石のキッチンカウンターはダサい?おしゃれを実現するヒント
- 一条工務店の階段を完全紹介!パターンの選び方・必要なマス数を知り失敗を防ぐ
- 一条工務店の屋根裏収納で後悔しないポイント|後付け・費用・見積もり
- 一条工務店の1.5階建ての費用・人気の理由・デメリットや間取りの注意点
- 一条工務店の押し入れ選び!観音開き・引き戸・開き戸のメリットデメリット
- 一条工務店で和室はいらない!?小上がりや畳選びで後悔しがち
- 一条工務店でゴキブリ出現!?換気システムから侵入か給気口か
- 一条工務店のロフトの費用は意外と安い!平屋との相性も良し
設備
- 一条工務店ヘッダーボックスの場所は玄関と階段下が最適!音と床暖的効果
- 一条工務店のインターホンの選び方|標準モデルMT101から後付けまで網羅
- 一条工務店の物干し金物ホスクリーンは後付けできるのか|耐荷重や設置値
- 一条工務店の自在棚にシンデレラフィットするゴミ箱
- 一条工務店のスマートキーつけるべきか?後付けやピーピー音・紛失トラブルも
- 一条工務店のエコキュートおすすめモデルは快適重視ならPシリーズ
- 一条工務店のレンジフード選び|操作選びやフィルター有無
- 一条工務店の蓄電池を2台に!価格や容量、後付け費用を解説
- 一条工務店の浴室乾燥機はオプションでつけるべきか?後悔しない判断基準
- 一条工務店シューズボックスの全て!種類・収納・価格を解説

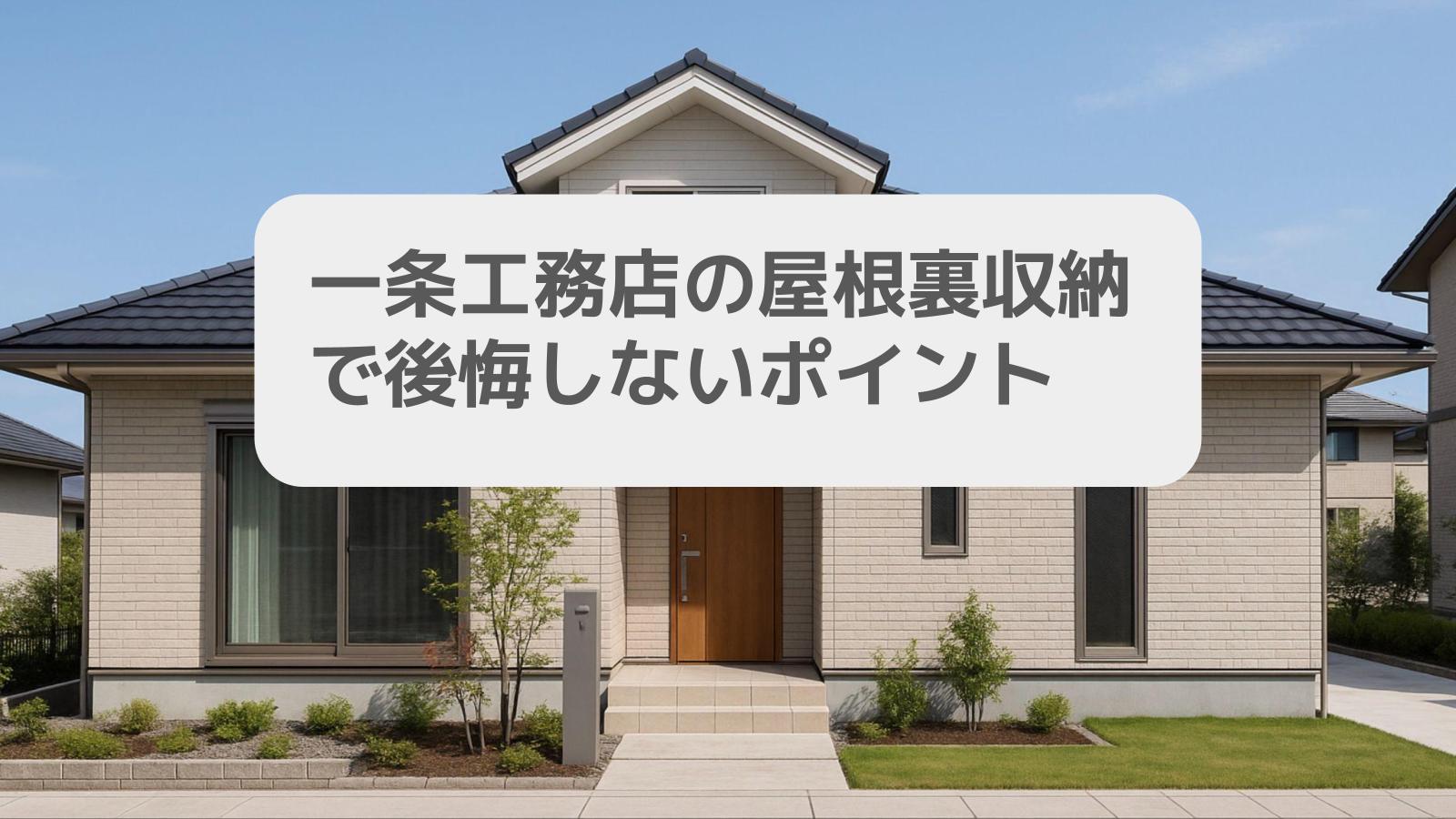



コメント