「トクサ 植えてはいけない」と検索してこの記事にたどり着いた方は、トクサに関して不安や疑問を感じているのではないでしょうか。
確かに、トクサは和の雰囲気によく合う美しい植物ですが、縁起が悪いとされる理由や風水上の注意点など、知っておくべき点がいくつもあります。
また、地下茎で増える性質のため、適切な植え方をしないと根絶が難しくなることもあり、慎重な管理が必要です。
さらに、剪定方法や鉢植えでの育て方、毒性に関する情報も含め、トクサを育てる際にはさまざまな視点からの配慮が求められます。
特に冬に枯れやすい地域では越冬の工夫も欠かせません。
 著者
著者この記事では、トクサをこれから育てようと考えている方、または既に植えて後悔している方に向けて、トクサとの付き合い方を総合的に解説していきます。


こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 縁起 | 硬くまっすぐな茎が「縁を切る」と連想され、風水的に敬遠されることがある |
| 風水 | 気の流れを乱すとされ、玄関やリビング付近には不向きとされる |
| 毒性 | 微量ながら動物への毒性があり、特に家畜やペットへの影響に注意 |
| 植え方 | 地下茎で増殖するため、地植えの場合は防根シートで囲うなどの対策が必要 |
| 繁殖力 | 非常に強く、放置すると他の植物を圧迫し庭全体に広がる |
| 剪定方法 | 春や冬の終わりに不要な茎を根元から切り、風通しを確保する |
| 根絶の難しさ | 地下茎が残ると再生するため、完全な除去には時間と労力がかかる |
| 鉢植えの育て方 | 排水性の良い鉢と用土を使い、1〜2年ごとに植え替えが必要 |
| 冬に枯れる | 寒冷地では地上部が枯れるが、地下茎が残っていれば春に再生する |
| 越冬対策 | 鉢植えは室内に移動し、地植えは腐葉土やワラで根元を覆って保温する |
| 実例① | 石垣の隙間から茎が出て見栄えが悪くなり、撤去に手間がかかった |
| 実例② | 隣家まで地下茎が侵入し、ご近所トラブルに発展した |
| 代替植物 | フッキソウ、ヤブラン、トベラなどは縁起も良く管理しやすい |
- 庭木を完全に根絶するのは素人では難しい
- 業者に頼むと費用が高い
- 何件も相見積もりをすれば安くできるけど面倒
そこで、カンタンに安く庭木を除去する方法をご紹介します。
タウンライフ外構工事で相見積もりする。
値下げに必須な相見積もりをたった一手間で取得できる。



費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
トクサを植えてはいけない理由とは


- トクサを根絶したい時の対処法
- 縁起が悪い植物とされる理由
- トクサに毒性はあるのか?
- トクサの剪定方法と注意点
- トクサの植え方で失敗しやすい例
トクサを根絶したい時の対処法


いったん庭に根づいてしまったトクサを完全に取り除くのは、想像以上に手間と根気が求められる作業です。地上部をどれだけ刈り取っても、地下に張り巡らされた茎が少しでも残っていると、そこから再び芽を出して復活してしまいます。トクサの地下茎は非常にしぶとく、条件のよい場所では数メートル先まで広がることもあるため、一度繁殖が進んでしまうと厄介です。
特に柔らかい土壌や傾斜のある土地では、地下茎がより深く、広く伸びている可能性が高くなります。このような場所では、地表の様子だけではトクサの広がり具合を把握するのが難しいため、地中の根を確認しながら慎重に掘り進める必要があります。
根絶を目指すなら、まずはスコップや移植ゴテなどを使って、地面を広範囲に掘り起こし、可能な限り地下茎を取り除きましょう。このとき、ちぎれた根の一片でも残っていればそこから再生する恐れがあるため、丁寧に作業することが大切です。作業は雨の翌日など、土がやわらかくなっているタイミングが適しています。乾燥時よりも地下茎が抜けやすく、無理に引き抜いて周囲の植物にダメージを与えるリスクも減ります。
それでも完全に取りきれない場合は、植物専用の除草剤を活用する方法があります。トクサには一般的な除草剤が効きにくいこともあり、専用の成分が入った製品を選ぶのがポイントです。効果的に散布するには、茎を刈り取った直後に除草剤を茎の切り口や葉に直接塗布したり、成分が地中に届くように土に注入する方法が有効です。
ただし、除草剤の使用には慎重さが求められます。特に周囲に芝生や家庭菜園がある場合は、飛散によって他の植物に悪影響を与えてしまう可能性があります。風のない日を選び、ピンポイントで使用するよう心がけましょう。また、使用後は数日間、ペットや子どもが近づかないよう配慮することも重要です。
さらに、根絶までには時間がかかることを覚悟しましょう。一度の作業ですべてを除去するのは難しいため、数ヶ月おきに再びチェックし、新たな芽が出ていないかを確認します。必要であればその都度処理を繰り返すことが、確実な根絶につながります。
このように、トクサの除去には「一気に解決」ではなく、「計画的にじっくり取り組む」という姿勢が求められます。根気のいる作業ではありますが、丁寧な対応を重ねることで、確実に根絶へと近づくことができるでしょう。
- 庭木を完全に根絶するのは素人では難しい
- 業者に頼むと費用が高い
- 何件も相見積もりをすれば安くできるけど面倒
そこで、カンタンに安く庭木を除去する方法をご紹介します。
タウンライフ外構工事で相見積もりする。
値下げに必須な相見積もりをたった一手間で取得できる。



費用も時間もかからなないのに、良い庭のアイデアや値引きに使える見積もりがもらえるからやらなきゃ損です
\簡単3分!20万円以上安くなった例も!/
縁起が悪い植物とされる理由
トクサは昔から日本の庭や建物の周囲に用いられてきた植物のひとつで、その凛とした姿や管理のしやすさから人気を集めています。しかし一方で、地域や人によっては「縁起が悪い」と言われることもあるのです。
この理由のひとつとして挙げられるのが、トクサのまっすぐで硬い茎の形状です。その性質が「縁を切る」「人を遠ざける」といった象徴的な意味に結びつけられているため、特に風水やスピリチュアルな観点を重視する人々の間で敬遠される傾向があるようです。
また、風水においては植物の形状や流れる気のイメージが非常に重要とされますが、トクサのように一直線に突き上がる姿は「気を突き抜けさせる」「調和を乱す」と受け取られることもあります。引っ越しや新築などの節目では、運気を気にする方が増えるため、そういった場面でトクサを避ける選択をされるケースが多くなるのです。
具体的には、ある家庭では新居にトクサを植えた直後に家族間で喧嘩が絶えなくなったという経験談があり、これがトクサの「悪縁を呼ぶ」という噂のきっかけになったとも言われています。また、ビジネスの場でも「商売繁盛を妨げる」と信じる人がいるため、店舗の外構に選ばれることは少ないようです。
もちろん、こうした話には科学的根拠はありませんし、トクサが直接的に悪い影響を与えるとは限りません。ただし、心配な気持ちを抱えながら育てるよりも、最初から縁起の良いとされる植物を選ぶことで、精神的にも穏やかにガーデニングを楽しむことができるでしょう。
代替案としては、和風庭園にぴったりなフッキソウや、縁起が良く育てやすいヤブラン、さらにはササ類やトベラなども選択肢に入ります。これらは落ち着いた印象を与えるだけでなく、「家庭円満」や「魔除け」の象徴としても親しまれており、安心感のある庭づくりには最適です。
トクサに毒性はあるのか?
実際のところ、トクサには微量ながら毒性があるとされています。これは特に、馬などの草食動物が大量に食べた場合に中毒症状を引き起こす可能性があるためで、家畜を飼っている農家では注意喚起が行われていることもあります。トクサに含まれる成分の中には、腎臓や消化器官に負担をかけるとされる物質があるとされ、慢性的に摂取すると健康被害を引き起こす恐れもあります。
こうした毒性の情報は一般家庭で育てる際にはそこまで神経質になる必要はないものの、特にペットを飼っているご家庭では注意したいポイントです。例えば、好奇心旺盛な猫や小型犬が茎にじゃれついたり、噛んでしまうことがあるため、鉢植えで管理し、できるだけペットの手の届かない場所に置くのが理想的です。
また、小さなお子様がいるご家庭では「観葉植物の葉っぱは触っていいもの」と思い込んでしまうケースもあるため、トクサに限らず植物全般に注意が必要です。万が一の誤飲や接触を避けるためには、子どもが遊ぶ場所とは距離を置くようなレイアウトを考えましょう。
トクサは葉ではなく茎のみで構成されているため、葉をかじるといったリスクはありませんが、その茎も独特な硬さと質感があるため、場合によっては皮膚が敏感な方が触れると刺激を感じることがあります。そのため、庭作業の際には軍手をはめるなど、簡単な対策をしておくとより安全です。
さらに、剪定や植え替えの際には切り口から樹液がにじむことがあるため、これが手に触れないようにする配慮も大切です。もし皮膚にかゆみや赤みが出た場合には、流水でしっかり洗い流し、必要であれば皮膚科を受診するようにしましょう。
こうした点に気を付けながら育てれば、トクサは丈夫で美しい植物として長く楽しむことができます。育てる環境と周囲の安全性を考慮して、適切に管理していきたいですね。
トクサの剪定方法と注意点
トクサは見た目が整っていて手入れが楽そうに見える一方で、実は剪定のタイミングややり方が意外と重要です。放任していると茎が乱れてしまい、せっかくの直線的な美しさが損なわれてしまいます。
剪定に適した時期は春先や冬の終わりごろです。この時期は寒さで弱った部分がはっきりとわかりやすく、不要な茎を取り除くことで新しい成長を促しやすくなります。冬越しのダメージが目に見える形で現れるので、茶色く変色した茎や倒れてしまった茎を丁寧に選別して整理しましょう。
特に冬を越えた直後は、カビや細菌が繁殖しやすい条件が揃いやすいため、放置しておくと病気の原因になります。茶色くなった茎や柔らかくなっている部分は、根元近くまでしっかりと剪定します。その際には、必ず清潔な剪定バサミを使い、前後でアルコール消毒をしておくと安心です。
剪定のあとには、軽く水を与えるのもポイントです。乾燥しすぎると新芽の出が遅れる場合があるので、適度な湿り気を保つようにしましょう。また、風通しを良くするために、茎同士が密集している部分を間引くようにすると、全体の通気性が向上してカビの予防にもなります。
ただし、あまり強く切りすぎると株全体のバランスが崩れてしまい、かえって形が悪くなることもあります。剪定は一度で完璧に整えようとせず、数回に分けて行うくらいの余裕を持つことが大切です。一本一本の茎の状態をよく観察しながら、無理のない範囲で優しく手を加えるのが理想です。
何よりも、トクサの剪定は「定期的な健康診断」のようなイメージで行うとよいでしょう。季節ごとに様子を見て、必要に応じて手を加えることで、常にすっきりとした美しさと健康な状態を保つことができます。日々の小さなケアが、長くトクサを楽しむ秘訣になります。
トクサの植え方で失敗しやすい例
トクサはとても丈夫で生命力が強い植物ですが、その強さゆえに思わぬトラブルにつながることもあります。特に、何も計画せずに地植えしてしまうと、数年後には庭全体にトクサが広がり、他の植物が育たなくなってしまうというケースが多く報告されています。
トクサは地下茎で増える性質があり、その地下茎は地中でどんどん広がっていきます。一見、目に見える部分だけを見ていると増えていることに気付きにくいのですが、気づいたときには他の植物のエリアにも入り込み、根の競合が起きてしまっていることもあります。こうなると、本来植えていた花や低木が栄養不足で枯れてしまうこともあるため、非常に厄介です。
このような事態を防ぐには、最初の段階から「どこに、どれだけ、どう植えるか」を明確にしておくことが重要です。たとえば、庭の一部にトクサ専用のスペースを確保し、その周囲にしっかりと深さ30~40cmほどの防根シートやコンクリートブロックで囲いを設けると、地下茎の広がりを抑えることができます。
実際、プロの植栽業者でもトクサを扱う際には、このような地下茎対策を必ず行うことが基本とされています。植える範囲を明確に区切ることで、後々の手入れや除去作業の手間も大きく軽減されます。
また、鉢植えでトクサを育てるというのも非常に有効な方法です。鉢であれば根の広がりを物理的に制限できるうえ、移動も簡単ですし、鉢の素材や大きさを工夫することで、和風からモダンまで様々なスタイルの庭にマッチさせることができます。
鉢選びでは通気性と排水性を確保できるものを選び、定期的に根詰まりのチェックを行うことがポイントです。特に1〜2年ごとには植え替えを行うことで、根が鉢の中で過密にならず、元気な状態を保つことができます。
これらの対策を行わず、何気なく地植えしてしまうと、数年後にはトクサの除去に膨大な労力と時間を要することになりかねません。最初に少し手間をかけておくだけで、長く快適にトクサを楽しめるようになりますので、ぜひ計画的な植え方を心がけてみてください。
トクサを植える前に知るべき知識【植えてはいけない】


- トクサと風水の意外な関係
- 鉢植えでの育て方と注意点
- 冬に枯れる?越冬のコツ
- トクサの繁殖力と管理の難しさ
- 知らずに植えて後悔した実例
トクサと風水の意外な関係
風水の観点から見ると、トクサは「土」のエネルギーを持つとされ、家の安定や家庭運を整える効果があるといわれています。「土」の気は堅実さや信頼、落ち着きを象徴し、家庭の基盤を安定させるという意味合いも含まれています。そのため、特に南西方向にトクサを配置することで、落ち着いた空気や安心感をもたらすとされ、心の平穏を求める方や家族との調和を重視する人には人気の植物となっています。
さらに、トクサはそのシンプルで直線的なフォルムから「整理整頓」「けじめ」といった意味も持ち合わせており、思考をクリアにしたい場所や作業スペースに配置するというアイデアもあります。実際、書斎のデスク近くに小さなトクサの鉢を置くことで、気の流れが整い集中力が高まると感じる方もいるようです。
ただし、一方でトクサの持つ直線的で硬い印象が「冷たい」「とげとげしい」と捉えられることもあり、人間関係を遮るという否定的な解釈をされることもあります。特に玄関やリビングなど、家の中心的な「気の入口」となる場所では、こうした印象がマイナスに働くこともあるため、植える位置には慎重になる必要があります。風水に詳しい方の中には、トクサをあえて玄関前や南向きの窓の近くなど「気の流れ」をスムーズに保ちたい場所には避けるという意見もあります。
また、風水では植物同士の相性も重要です。例えば、火のエネルギーを持つ赤系の花や尖った葉の植物とトクサを隣同士に配置すると、気がぶつかりあってしまう可能性があります。逆に、丸みを帯びた葉を持つ植物や、柔らかい印象の花と組み合わせることで、トクサの硬質な印象を和らげ、全体のバランスが整うとも言われています。
このように、同じ植物であっても見る人の価値観や信じる風水の流派によって、解釈や植え方が大きく異なります。ご自身の直感や生活スタイル、家族の価値観とすり合わせながら、無理なく楽しめる配置を選ぶのがよいでしょう。風水の効果を積極的に取り入れたい場合は、植える方角や高さ、他の植物との相性にも注目しながら、トクサの個性を活かしたガーデニングに挑戦してみてください。
鉢植えでの育て方と注意点
トクサを鉢で育てることには、いくつもメリットがあります。まず第一に、地下茎が無秩序に広がるのを防ぐことができるため、他の植物とのトラブルを回避しやすくなります。庭全体を管理する上でも、制限のある空間内で育てられる鉢植えは非常に扱いやすい存在です。特に小規模なスペースやベランダガーデンでは、鉢植えの柔軟性が大きな武器になります。
また、鉢植えは管理がしやすく、日当たりや湿度の調整も比較的容易です。例えば、夏の直射日光が強すぎるときは日陰に移動させたり、雨が続く日には軒下に避難させることも可能です。このように、環境に合わせて柔軟に対応できる点は、鉢植えならではの魅力といえます。
鉢を選ぶ際には、必ず底に排水用の穴があるものを選びましょう。トクサは湿地性の植物で水を好みますが、常に根が水に浸かった状態だと根腐れを起こすリスクがあります。過湿は根の健康を損ないやすいため、水はけの良い鉢と適切な用土の組み合わせが必要不可欠です。
用土に関しては、市販の花と野菜用培養土でも問題ありませんが、赤玉土や腐葉土をブレンドすることで、より適した環境を整えることができます。赤玉土は水はけと通気性を良くし、腐葉土は水もちと栄養分を補います。このように、土の質を工夫するだけで、トクサの生育スピードや見た目にも違いが出てきます。
さらに注意したいのが根詰まりです。トクサは根の成長が早いため、鉢の中で根が密集してしまいやすい傾向があります。そのため、1〜2年ごとに一回り大きな鉢へ植え替えるのが理想的です。植え替えの際には、古い根や土を軽くほぐし、根の状態を観察することも大切です。
植え替え後は数日間半日陰で管理し、根が新しい土になじむのを待ちましょう。また、鉢の位置も定期的に変えることで、光の当たり具合が偏らず、全体が均等に育ちやすくなります。こうしたちょっとしたひと手間が、健康なトクサを育てる上で非常に役立ちます。
このように、鉢植えでも適切に管理をすれば、トクサはその魅力を十分に発揮してくれます。初心者にもおすすめの育て方なので、まずは小さな鉢からスタートしてみるのも良いかもしれません。
冬に枯れる?越冬のコツ
トクサは比較的寒さに強い植物ですが、冬になると見た目に変化が現れることがあります。例えば、地上部が茶色く変色したり、倒れたような状態になったりすることがあります。これを見ると「枯れてしまったのでは?」と心配になるかもしれませんが、多くの場合は一時的な休眠状態に入っているだけで、春になると地下茎から新芽を再び出して復活します。
しかしながら、氷点下の日が続くような寒冷地では事情が少し異なります。気温が長時間マイナスの状態になると、地面の深部まで冷え込み、地下茎そのものがダメージを受けてしまう可能性があるのです。そうなると、春を迎えても芽が出てこない、つまり完全に枯れてしまう恐れがあります。そのため、特に寒さの厳しい地域でトクサを育てている場合は、越冬対策がとても重要になります。
寒冷地で鉢植えのトクサを育てている場合は、気温が下がる前に屋内に取り込んであげるのが最も安全です。室内に取り込むことで急激な温度変化を避けられ、地下茎を守ることができます。地植えの場合でも、根元に腐葉土やワラ、落ち葉などを厚く敷いて、保温効果を高めることが効果的です。植え付けの際にあらかじめ土の中に断熱材の役割を持つマルチング材を仕込んでおくのも良い方法です。
また、冬場はトクサの成長が著しく鈍化するため、水やりも控えめにしましょう。表土が乾いてもすぐに水を与える必要はなく、数日〜1週間程度様子を見てからで十分です。水の与えすぎは根腐れの原因となりやすく、寒い時期は特に土の中の水分が蒸発しにくいため注意が必要です。
日当たりの良い場所に鉢を移動することも忘れないようにしましょう。冬の間もできるだけ陽光に当てることで、最低限の光合成を助け、春の芽吹きをスムーズにします。加えて、冷たい北風や霜が直接当たらない場所を選んで管理すると、トクサにとってより快適な環境を整えることができます。
こうしたひと手間をかけてあげれば、春になったときに再び青々とした美しい姿を見せてくれるはずです。特に寒さの厳しい地域では、事前の対策がトクサの寿命を大きく左右するので、気候条件をよく観察しながら適切に対応していきましょう。
トクサの繁殖力と管理の難しさ
トクサはとにかく繁殖力が強く、放っておくと手に負えなくなるほど広がってしまう植物です。その主な原因は、地下茎による旺盛な成長力にあります。地下茎は地表から見えない場所でどんどんと伸びていき、わずかな隙間さえあればそこから新しい芽を出して勢力を広げていきます。
一度根を張ってしまうと完全にコントロールするのは非常に難しく、庭の他の植物を侵食してしまったり、予期せぬ場所から芽が出て景観を損なってしまうこともあります。特に柔らかい土壌や湿度の高い場所では成長スピードも速く、気づかないうちに広範囲に広がっていたという例も少なくありません。
このため、トクサを庭に植える際は、事前に対策を講じることが重要です。植える前には必ず植栽範囲を明確にし、定期的に様子を見て、意図しない場所から新たな芽が出ていないか確認する習慣をつけましょう。予防策としては、防根シートを土中に設置する方法が有効です。深さ30〜40cm程度のシートを地面に垂直に埋めることで、地下茎の横への拡大をある程度食い止めることができます。
また、レンガやコンクリートブロックで物理的に囲いをつくるのも、トクサの拡散を防ぐ一つの方法です。特に庭の隣地境界や芝生のエリアとの間には、こうした仕切りを設けておくと、後々の管理が格段に楽になります。
さらに注意したいのが、茎を切った後の切れ端です。トクサは非常に強健な性質を持っており、茎の切れ端からでも条件がそろえば簡単に発根してしまうことがあります。そのため、剪定した後の切りくずはそのまま地面に放置せず、しっかりと処分する必要があります。具体的には、ごみ袋に入れて密封したうえで、一般ごみとして出すか、完全に乾燥させてから焼却するのが安全です。
このように、トクサは美しい見た目とは裏腹に、管理には細やかな注意と定期的な点検が欠かせません。広がりすぎを防ぎ、他の植物との調和を保ちながら育てるには、あらかじめしっかりとした準備と意識が必要です。それでも正しい知識と方法をもって向き合えば、トクサはとても魅力的な存在となってくれることでしょう。
知らずに植えて後悔した実例
見た目の美しさや手入れの少なさに惹かれてトクサを植えたものの、数年後に「こんなはずじゃなかった」と感じる方は少なくありません。初めてのガーデニングで「丈夫そう」「水が好きな植物だから安心」と軽い気持ちで選んだ結果、後々大きなトラブルに発展してしまったという声も耳にします。
あるご家庭では、和風の庭に合うと思ってトクサを石垣の近くに植えました。その直線的な姿が趣のある景観を演出してくれると期待していたそうですが、数年が経過すると石垣の隙間から硬い茎が突き出してくるようになり、見た目が乱れるばかりか、石垣そのものにダメージを与える可能性まで出てきました。最終的には専門業者に依頼して撤去作業を行ったものの、石の隙間に入り込んだ根の除去には時間と費用がかかり、決して簡単な作業ではなかったといいます。
また、別のケースでは、トクサの地下茎が思いのほか広がってしまい、敷地境界を越えて隣家の庭へと侵入してしまったというトラブルが発生しました。最初はお隣さんから「変わった植物ですね」と穏やかに声をかけられたものの、ある日を境に「うちの芝生が枯れているのはこれのせいかもしれない」とクレームに発展。結果的に抜根作業と地中の仕切り設置、さらに関係修復のためのやり取りが続き、大きなストレスになったというお話もあります。
いずれの事例にも共通するのは、トクサの性質を十分に理解しないまま、「見た目がよいから」「育てやすそうだから」という理由だけで植えてしまったことです。繁殖力の強さ、地下茎の伸び方、管理の難しさなど、見た目からは分かりにくい特徴を知らずに植えてしまうと、あとから後悔することにもなりかねません。
このように、トクサは確かに魅力的な植物ですが、扱い方を誤ると想像以上に大きな影響をもたらす可能性があります。植える前には「この場所で長く付き合っていけるか?」「周囲に迷惑がかからないか?」といった視点でしっかりと考え、必要であれば対策を講じた上で取り入れることが、トクサと上手に付き合うための第一歩となるでしょう。
トクサ 植えてはいけないと言われる理由のまとめ
- 硬く直線的な茎が「縁を切る」と連想されやすい
- 風水では気の流れを乱すと考えられることがある
- 地下茎で際限なく広がるため管理が困難
- 一度植えると根絶に時間と労力がかかる
- 剪定の手間を怠ると病害のリスクが高まる
- 隣家に侵入する可能性がありトラブルに発展しやすい
- トクサの切れ端からでも再生する繁殖力の強さがある
- 植える場所によっては他の植物を駆逐することがある
- 土地や構造物を傷めるリスクがある
- 微量ながら動物に有害な成分を含むことがある
- 子どもやペットがいる家庭では管理場所に注意が必要
- 冬の寒さに弱く地域によっては越冬が難しい
- 鉢植えでも根詰まりしやすく植え替えが頻繁に必要
- 和風の景観には映えるが、誤って選ぶと景観を損なう
- 庭全体を計画的に設計しないと後悔につながる

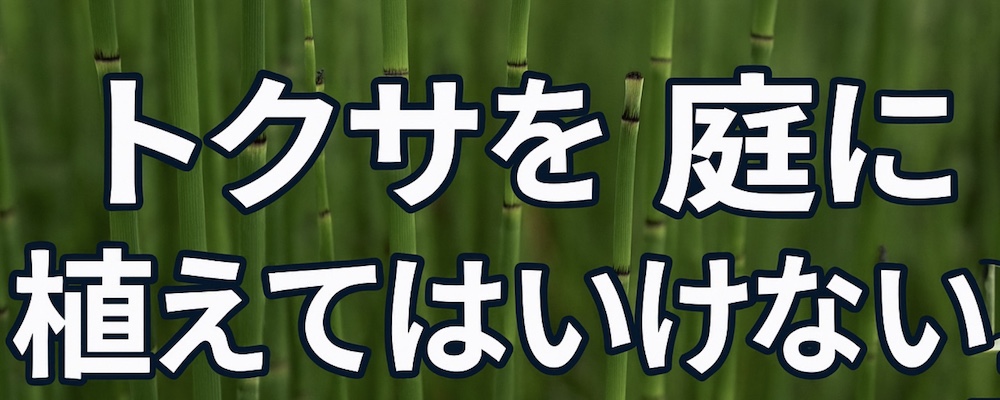

コメント