一条工務店で家を建てるとき、「押入れ」の選び方に悩む方は少なくありません。特に検索で「一条工務店 押入れ」と調べている方は、収納の機能性や使い勝手を重視していることでしょう。
本記事では、そんな方のために、実際に採用されることの多い押入れbタイプの特徴から、収納効率を最大化する自由棚の使い方、シンデレラフィットを目指す内寸の測り方、そして床との距離がもたらす影響まで、実用的な視点で詳しく解説していきます。
また、扉を外すというリメイクの選択肢や、観音開き・開き戸・引き戸といった扉の種類によるメリット・デメリットにも触れ、あなたの暮らしに合った収納のヒントを提供します。
押入れのサイズに合ったレイアウトを知りたい方、収納の自由度を上げたい方にとって、この記事が実用的なガイドになるはずです。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 概要 | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| 押入れbタイプ | 標準的な収納仕様。中段ありで布団や掃除機向き | 高さのある物は収納しづらい場合あり |
| 幅サイズ | 90cm・135cm・180cmから選択 | 部屋の広さと収納量に応じて選ぶ |
| 奥行きサイズ | 60cmと90cmの2種類 | 布団収納なら90cmが推奨 |
| 内寸の重要性 | 外寸より数cm狭くなるため計測が必要 | 収納ボックス選びに必須の情報 |
| シンデレラフィット | 内寸にぴったり合う収納を選ぶ考え方 | 無駄なスペースを防ぎ整理しやすくなる |
| 自由棚 | 棚板の高さを調整できる可動棚 | 使い方に合わせて収納を最適化できる |
| 床の高さ | 和室では床置き型が基本 | 腰をかがめる動作に配慮が必要 |
| 引き戸 | スライド式で省スペースに最適 | 片側ずつしか開かない点に注意 |
| 観音開き(開き戸) | 全開できて中身が一目で見える | 前方に開くスペースが必要 |
| 扉を外す | リメイクしてオープン収納に | ホコリ対策や見せ方に注意 |
| 収納ボックスの選び方 | 内寸を元にシリーズ統一がおすすめ | キャスター付きで移動も楽に |
| DIY活用 | 突っ張り棒や棚板で空間を有効利用 | 原状回復可能な設計が安心 |
| 家族構成との相性 | 子育て世帯〜単身者まで用途に応じて設計 | 使用頻度や年齢層に合わせた配置が鍵 |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
一条工務店 押入れの種類と選び方
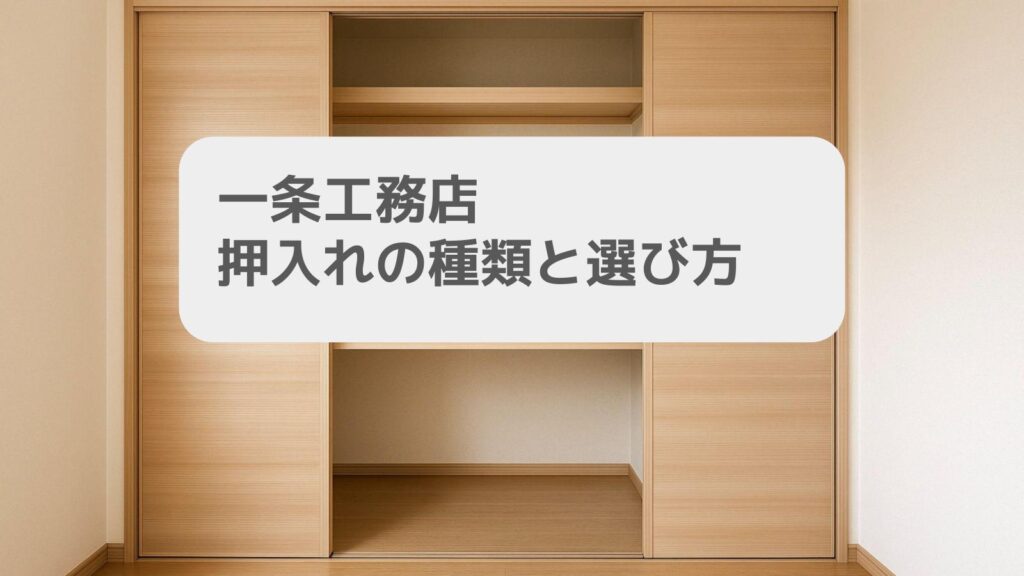
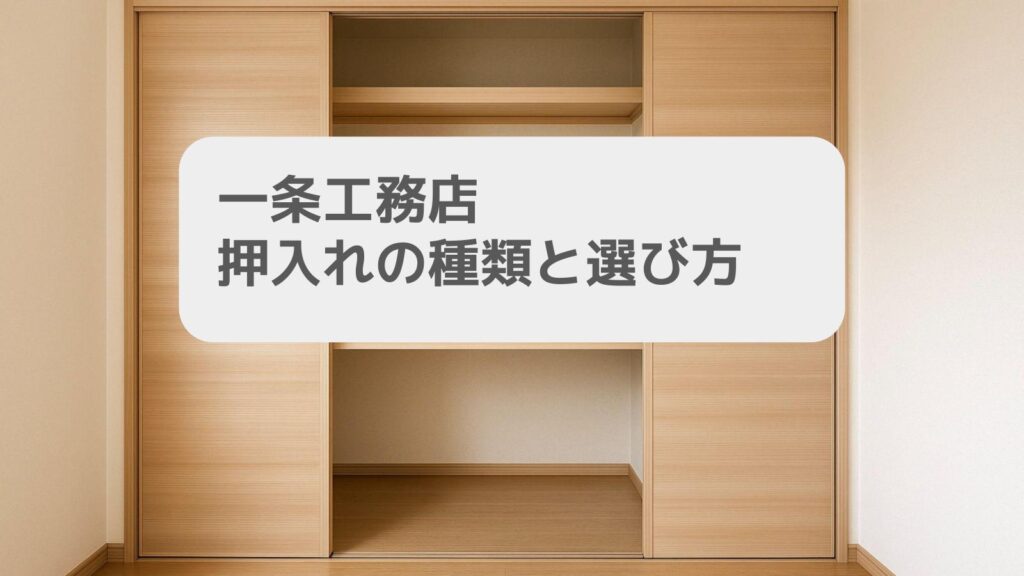
- 押入れbタイプの特徴とは
- 一条工務店の押入れサイズ解説
- 内寸で見る収納力の違い
- シンデレラフィットする収納術
- 自由棚の活用で収納を最適化
- 床からの高さも考慮しよう
押入れbタイプの特徴とは
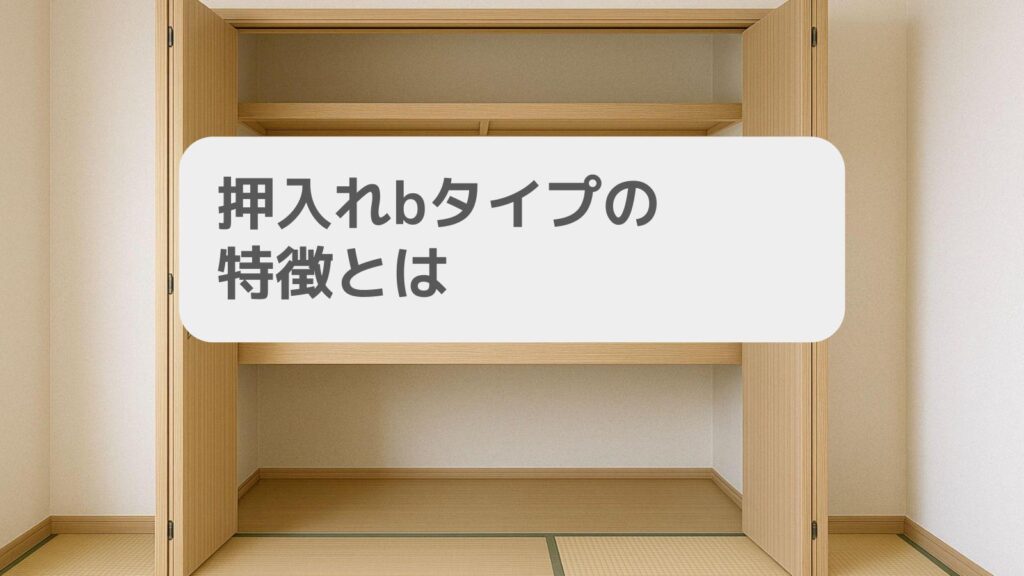
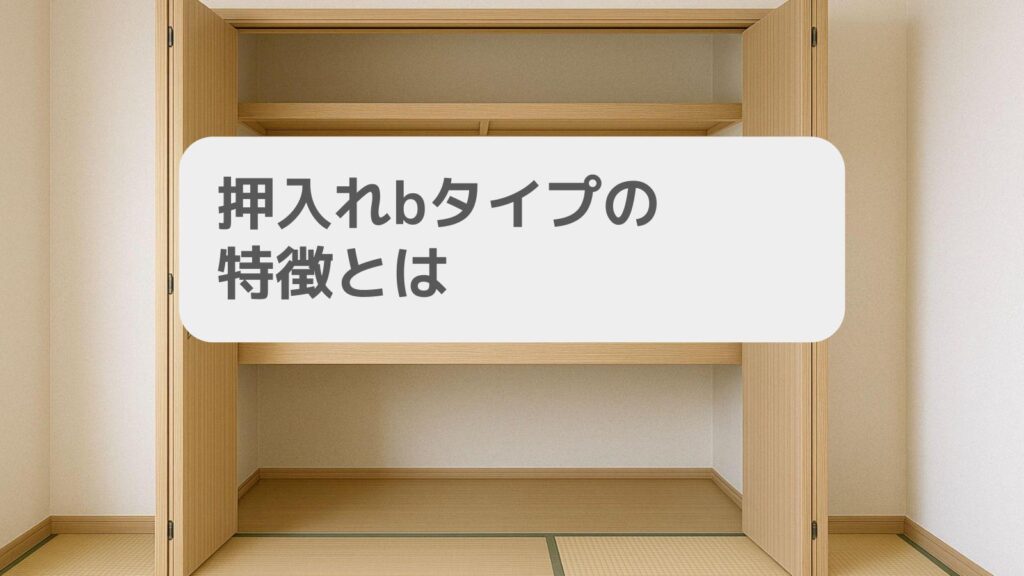
言ってしまえば、押入れbタイプは一条工務店の中でもよく選ばれる標準的な収納タイプです。見た目のシンプルさと使い勝手のバランスが良く、特に初めて家づくりをする方や迷っている方にもおすすめされることが多い仕様です。
理由としては、布団や衣類を効率よく収納できる中段構造と、手頃な奥行きが人気だからです。中段があることで収納スペースを上下に分けることができ、上段には軽い布団や季節の衣類、下段には掃除機や収納ボックスなどを入れるなど、使い分けがしやすくなっています。
例えば、布団の3つ折り収納や掃除機など縦に長いものも収納可能です。特に布団は、押入れbタイプの奥行きがしっかり確保されているため、無理なく収まるのが嬉しいポイントです。また、掃除機やモップといった縦型家電も斜めにせずにスッと入るので、日常的に出し入れするアイテムの収納にも適しています。
ただし、上下の仕切りがしっかりしているため、大型のものを一括で収納するのには少し不便に感じるかもしれません。例えば、高さのある箱や長さのあるスポーツ用品などは、中段が邪魔になって入らないことがあります。そのため、収納する物のサイズや形状によっては、押入れbタイプ以外の選択肢も視野に入れるとよいでしょう。
このように考えると、用途が明確な方にはとても便利な仕様だと言えます。特に「布団をしまいたい」「掃除機を隠したい」「衣類を整理したい」といった具体的なニーズがある場合には、押入れbタイプが非常に実用的な選択肢になります。生活スタイルに合った使い方をすることで、その魅力をより実感できるはずです。
一条工務店の押入れサイズ解説
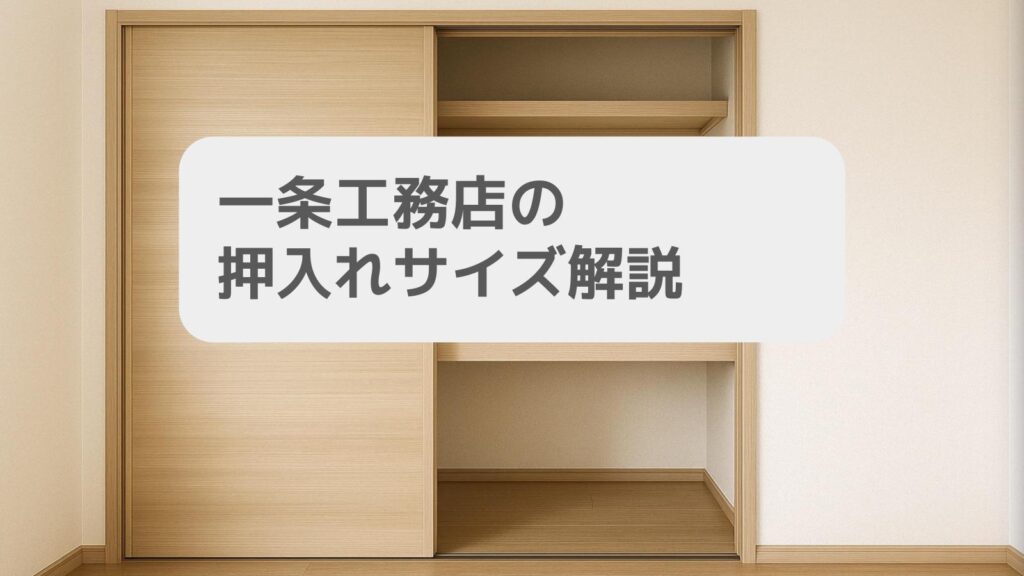
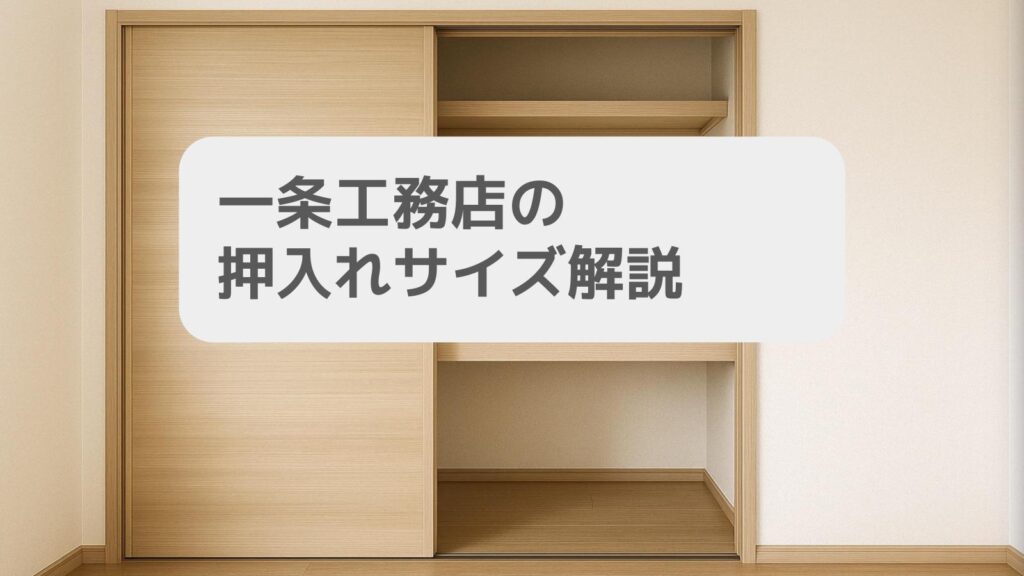
ここでは、一条工務店で採用されている押入れのサイズ感についてお伝えします。押入れは、収納計画を立てるうえで重要な要素のひとつ。どのサイズを選ぶかによって、使い勝手や収納量に大きな差が出てきます。
まず押さえておきたいのは、押入れの幅には90cm・135cm・180cmの3種類が基本で用意されているということです。どの幅を選ぶかは、設置する部屋の広さや収納する物の量によって判断すると良いでしょう。幅90cmはコンパクトで場所を取りませんが、収納力は控えめ。一方、180cmはたっぷり収納できますが、設置場所にゆとりが必要です。135cmはその中間にあたるため、最もバランスが良いとされる選択肢です。
奥行きについては、60cmと90cmの2パターンがあります。例えば、布団収納を想定しているなら90cmの奥行きがベストです。なぜなら、シングル布団を三つ折りにして収納するには約70cmほどの奥行きが必要になるため、60cmでは収まりきらない可能性が高くなるからです。特に来客用布団や季節布団など、しっかりとしたボリュームのある物を収納するなら、奥行き90cmを選ぶ方が安心です。
ただ、奥行きが深いと物が取り出しづらくなるというデメリットもあります。奥の方に入れた物が見えづらく、結局取り出さなくなってしまう…という経験がある方も多いのではないでしょうか。そのため、頻繁に使うものを入れるのであれば、浅めの60cmタイプの方が使い勝手が良いこともあります。深さに合わせてスライド式の収納ボックスやキャスター付きの棚を活用するなど、使い方次第で工夫も可能です。
このように、一条工務店の押入れはサイズの選択肢が多く、住まい方に応じて調整できるのが魅力です。収納するアイテムの種類や使い方、頻度をしっかりとイメージしながら選ぶことで、無駄のない快適な収納スペースを手に入れることができます。
内寸で見る収納力の違い
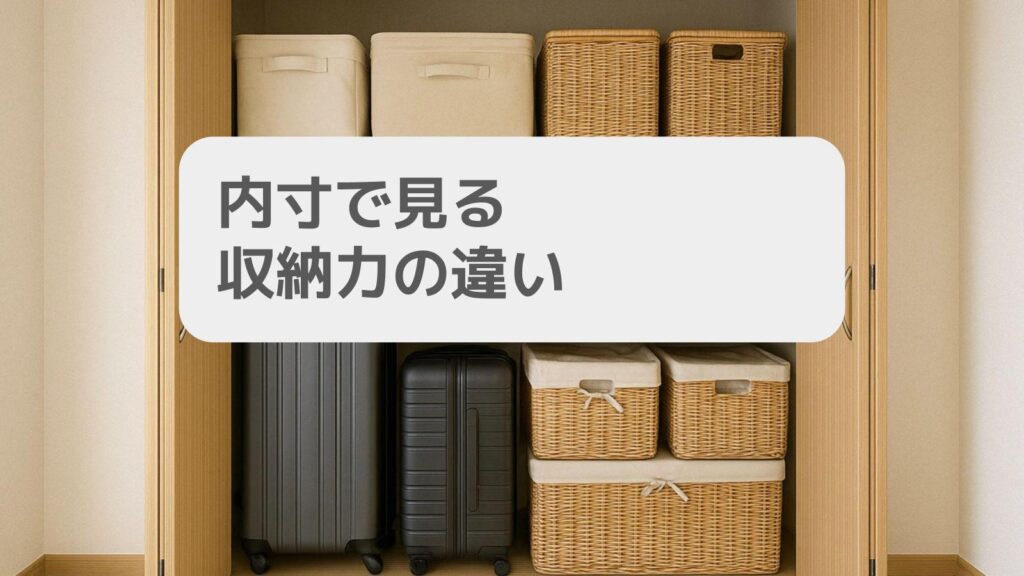
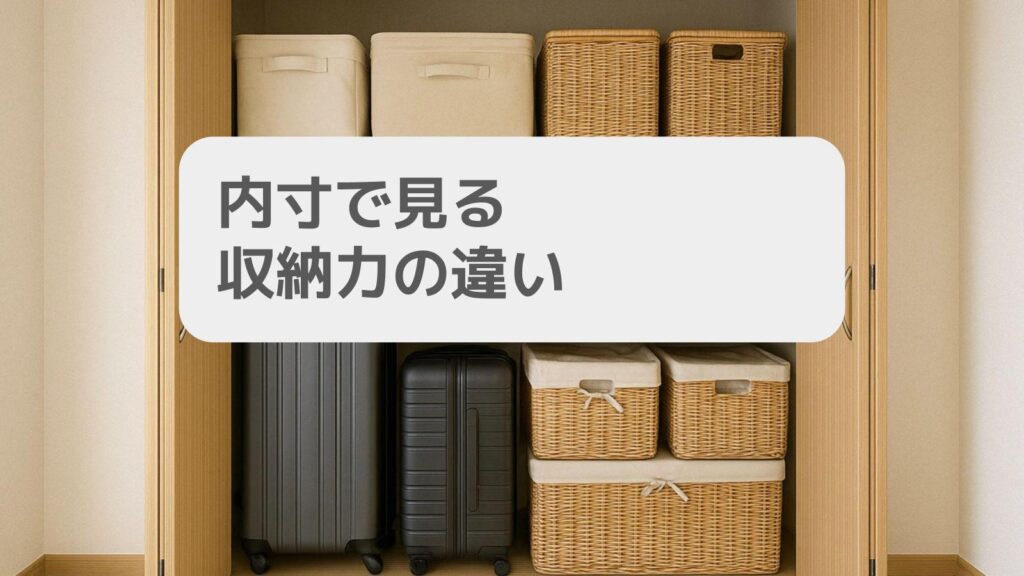
このため、押入れの収納力を測るには「内寸」を確認するのがポイントになります。多くの方が外寸だけを見て収納をイメージしてしまいがちですが、実際にどれだけの物が収まるのかを判断するには、内寸の把握が欠かせません。
内寸とは、実際に物が入る空間の大きさのこと。押入れの壁や仕切り板の厚み、建具の構造などによって、外寸よりも数センチ小さくなるのが一般的です。収納ボックスや布団がぴったり収まるかどうかを見極めるには、この内寸の数値を正確に知ることが非常に重要です。
例えば、幅135cm・奥行90cmの押入れでも、実際の内寸はおよそ130cm×85cmほどしかありません。このわずかな差でも、収納ケースが入らなかったり、思い通りに並べられなかったりと、想定外の不便を感じることがあります。特にボックスを並列に置こうとしたときや、布団を折って収めようとしたときに、数センチの誤差が大きな差を生むことも。
また、押入れに入れる予定のアイテムが規格サイズであっても、設置場所や周辺の構造物(例えば引き戸のレールや取っ手部分)によっては、実際には使える空間がさらに狭くなっていることもあります。こうした事実に気づかずに購入してしまうと、せっかく選んだ収納グッズが無駄になってしまう恐れも。
このように言うと意外に思われるかもしれませんが、購入前に内寸をメジャーでしっかり確認するだけで、後悔のない収納計画が立てられます。収納の「見た目」だけでなく「使いやすさ」にも直結する要素なので、ぜひ内寸確認を習慣にしてください。
シンデレラフィットする収納術


私であれば、押入れの無駄なスペースをなくすために「シンデレラフィット」を目指します。この考え方は、見た目を整えるだけでなく、毎日の使いやすさにも直結する収納の基本とも言えます。
理由は明快で、デッドスペースがない方が収納効率が格段に上がるからです。余計な隙間があると、無駄に物が動いてしまったり、せっかく整理したのに中が乱雑になりやすくなります。特に家族全員で使う共有の収納では、この“ぴったり感”がとても重要になってきます。
例えば、無印良品やニトリの収納ボックスは、さまざまなサイズが展開されており、事前に内寸をしっかり測っておけば、ピッタリはまるものを見つけやすいです。シンデレラフィットするボックスが収まると、見た目が揃っていてスッキリ見えるだけでなく、出し入れの動作もスムーズになり、使い勝手が格段にアップします。
これには、あらかじめ内寸を確認したうえで、ボックスのサイズも比較しておく必要があります。できれば、内寸だけでなく扉の開き方や手前のスペースも意識して選ぶと、より実用的です。収納ボックスの高さや奥行きも押入れに合わせて選ぶことで、重ねられるものやキャスター付きのものなど、より便利な選択肢も出てきます。
こう考えると、ただ収納するよりも見た目も使い勝手もアップしますよ。さらに、同じボックスを複数そろえることで、スペースの無駄をなくしながら統一感のある印象に仕上がります。結果として、押入れを開けるたびに気持ちよく使える空間になるのです。



一条工務店の棚にシンデレラフィットするゴミ箱については下の記事をチェック


自由棚の活用で収納を最適化
ここから、押入れ内の「自由棚」について解説します。自由棚とは、棚板の高さを自分で調整できる可動式の収納棚のことで、家庭ごとのライフスタイルや持ち物の変化に柔軟に対応できるのが大きな魅力です。
例えば、季節ごとに収納物が変わる家庭では、冬は布団や加湿器などの大きくてかさばるもの、夏は扇風機や除湿機などの季節家電を収納することが一般的です。こういった場合に、自由棚があれば、その都度高さを変えて、収納スペースを有効に使うことができます。
また、衣類や雑貨などサイズの異なるものを整理したいときにも便利です。棚板を高めに設定してバッグやスーツケースを収納したり、逆に細かい小物をまとめたいときは棚板を細かく区切ることで、無駄な空間を減らすことができます。子どもの成長に合わせて、おもちゃや学用品、制服類などの収納も変化していくため、自由棚なら長く柔軟に対応できます。
ただし、棚を付けすぎてしまうと、今度は大型の物や高さのある荷物が入らなくなってしまうこともあります。自由度が高い分、収納の全体バランスを考える必要があります。上下の空間が均等すぎると、結果的に使いづらくなることもあるので、実際に何を収納するのかを想定したうえで配置を決めるのがコツです。
さらに、棚板を設置する際は、棚受けの強度や耐荷重も忘れずに確認しましょう。特に重い家電や収納ボックスを載せる場合は、しっかりとした支えが必要です。棚受け金具が簡易なものだと、使っているうちに傾いたり外れたりするリスクもあるため、安全性を重視した選び方が重要です。
このように、自由棚は工夫次第で押入れの可能性をぐっと広げてくれます。収納の見直しや模様替えのタイミングでぜひ取り入れてみてください。
床からの高さも考慮しよう
このような理由から、押入れの床の高さにも注目すべきです。押入れは収納力が魅力ですが、その使い勝手は床との距離に大きく影響を受けます。特に日常的によく使う物を収納する場合、少しの高さの差が使いやすさを左右します。
特に掃除機や重い荷物を収納する場合、あまりに床が高いと出し入れが大変になります。中腰の姿勢を強いられると、腰への負担が増し、長く使い続けるうちに体へのストレスにもなりかねません。毎日の掃除や取り出し作業をスムーズに行いたい場合は、低めの位置に収納スペースがある方が圧倒的に便利です。
一条工務店の押入れは和室に配置されることが多く、床に直置きされているタイプがほとんどです。そのため、床との段差は少なく、出し入れの際にかがむ動作が必要になります。これは布団や季節用品など大きめで重いものを収納するには適している反面、小物や頻繁に使うものの収納にはやや不便な面もあります。
つまり、腰をかがめる作業が多くなるので、高さに無理があると使いにくく感じてしまうかもしれません。特に高齢者や妊娠中の方にとっては、しゃがむ・持ち上げるといった動作が負担になることも多いため、収納場所の高さは健康や安全面からも慎重に考える必要があります。
そこで、あらかじめ収納するアイテムの重さや出し入れ頻度を考えておくことをおすすめします。例えば、重い家電や来客用の布団などは下段に、軽くてよく使う小物は上段に置くなど、目的に応じた高さの使い分けをすると、快適な収納空間が実現します。ちょっとした配慮が、毎日の生活をずっとラクにしてくれるのです。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店 押入れの使い方と工夫


- 引き戸と観音開きの違い
- 扉を外すリメイク術とは
- 開き戸タイプのメリット比較
- 押入れの内寸で見るDIY活用
- 収納ボックスのシンデレラ配置
- 家族構成に応じた押入れ選び
引き戸と観音開きの違い
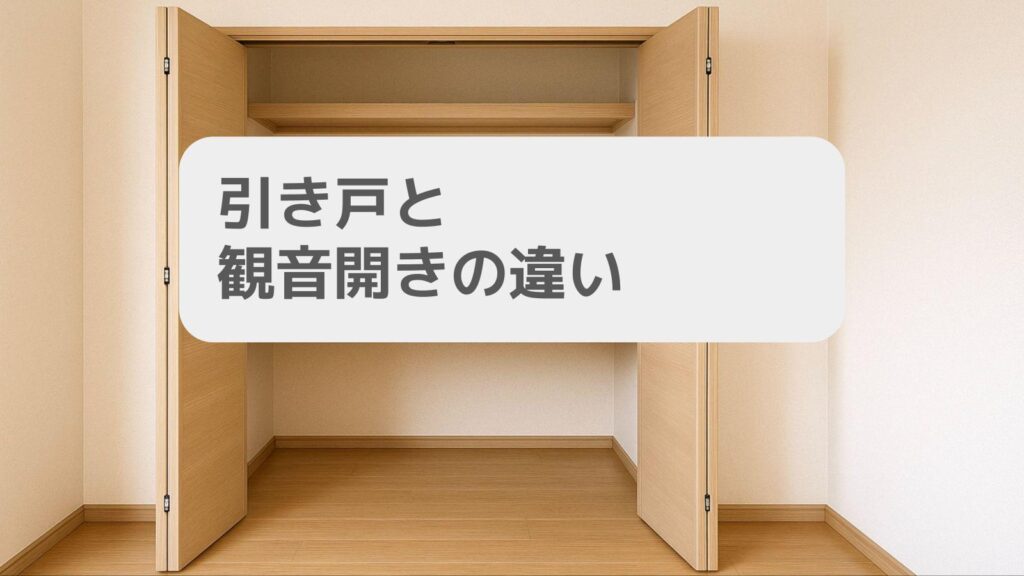
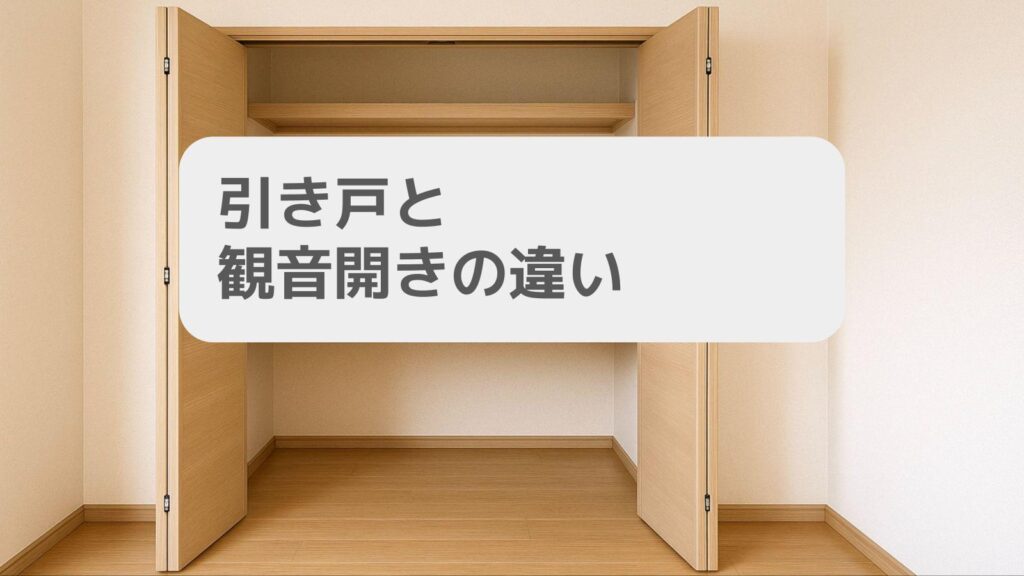
扉の開き方にも注目してみましょう。 一条工務店の押入れには「引き戸」「観音開き(開き戸)」の2種類があります。どちらも特徴があり、部屋のレイアウトや使用頻度によって向き不向きがあるため、それぞれの違いをよく理解して選ぶことが大切です。
引き戸は、開ける際に前方のスペースを必要としないため、狭い部屋やベッド・机など家具が近接している場所でもスムーズに使用できます。特に通路に面した押入れや小さな子供部屋などでは重宝されます。また、半開きにして一部だけ開閉できるのも意外と便利なポイントです。ただし、左右どちらか片方ずつしか開かない構造のため、全面を一度に見渡すことは難しく、奥の物を取り出す際には工夫が必要です。
一方で観音開き(開き戸)は、両側の扉を大きく開くことができるため、中に収納した物を一目で把握できるのが大きなメリットです。物の出し入れがとても簡単で、整理整頓しやすくなります。特に家族で共有する収納スペースや、衣類や日用品を頻繁に取り出す場所に向いています。
ただし、観音開きには扉を開くスペースが必要なため、扉の前に物を置いておけなかったり、狭い通路では開閉がしづらいといったデメリットもあります。収納の前に十分な空間を確保できるかどうかが、採用するか否かの判断材料になります。
あなたの生活スタイルや部屋の広さ、家具の配置、使用する頻度などを総合的に考えて、引き戸と観音開きのどちらが暮らしに合っているかを選ぶことが大切です。
扉を外すリメイク術とは
これは少し大胆な方法かもしれませんが、押入れの「扉を外す」という選択肢もあります。見た目の変化はもちろん、機能面でも大きなメリットを感じられる方法です。
理由は、開け閉めの手間がなくなり、収納物をスムーズに取り出せるようになるからです。また、扉がないことで中の様子が一目で見えるため、整理整頓をしやすくなり、使い勝手が格段に向上します。さらに、見せる収納として空間をおしゃれに演出することも可能になります。
例えば、扉の代わりにカーテンやロールスクリーンを取り付ければ、視覚的な柔らかさを演出しながら、目隠し効果を持たせることができます。布の質感や色合いを部屋のテイストに合わせれば、インテリアとしての魅力も高まります。ロールスクリーンであれば開閉も簡単で、圧迫感も少なく済みます。
また、扉がないことで空間の抜け感が生まれ、部屋全体が広く感じられるという視覚的効果も期待できます。ただし、オープン収納にはホコリが入りやすいというデメリットもあるため、収納アイテムにカバーをかけたり、定期的な掃除を行うなどの工夫が必要です。
このように考えると、押入れの扉を外すというリメイクは、単なる見た目の変更にとどまらず、日々の暮らしをより快適にする実用的な工夫のひとつでもあります。収納スタイルを自分好みにアレンジしたい方にとっては、試してみる価値のある選択肢といえるでしょう。
開き戸タイプのメリット比較
私の場合、観音開き(開き戸)タイプを選ぶことが多いです。観音開きは両側の扉がしっかり開くため、収納スペースの全体を一目で確認できるという点が大きな魅力です。
その理由は、開放感があり、物の出し入れがとてもスムーズに行えるからです。収納の中を広く見渡せることで、奥にしまった物も見落とすことが少なくなり、整理整頓がしやすくなります。衣類や日用品をカテゴリー別に収納しておくと、一目で場所がわかるのがとても便利ですし、家族みんなで使う収納スペースとしても効率的です。
例えば、タオル類や文房具など、用途ごとにまとめて収納したい物を仕切りボックスに入れて並べておくと、見た目も整い、誰でも使いやすくなります。また、急いでいるときにも探す時間が省けてストレスが減るのは嬉しいポイントです。
ただし、観音開きは扉を全開にするスペースが必要なため、通路が狭い場所や家具が近い場合には不向きとなることもあります。特に廊下に面した押入れや、部屋の角に設置された収納では、扉が十分に開かず、使い勝手が悪く感じられることがあります。そのため、設置場所の広さや周囲の動線も含めて、開き戸タイプが適しているかどうかを見極めることが大切です。
このように、観音開きタイプは使い勝手の良さと視認性の高さが大きなメリットですが、空間的な余裕がある場所にこそ本領を発揮します。日常の使い勝手と設置環境の両面を考慮して選ぶことで、より快適な収納が実現できます。
押入れの内寸で見るDIY活用
こうして見てくると、内寸を活かしたDIY活用も押入れの楽しみ方の一つです。押入れは単なる収納スペースとしてだけでなく、自分好みにアレンジできる自由度の高さが魅力です。
例えば、突っ張り棒で簡易ハンガーラックを作ることで、洋服をかけるスペースに早変わりします。さらに、ホームセンターなどで木材を購入し、押入れの幅に合わせてカットすれば、棚板を追加して上下に空間を分けることもできます。収納ケースやカゴのサイズに合わせたカスタム設計をすれば、より効率的に活用できます。
このとき最も大切なのが、内寸を正確に測ることです。1cmのズレでも棚が傾いたり、突っ張り棒が外れやすくなったりすることがあります。特に木材を使う場合、加工後のサイズや取り付け方法まで考慮した寸法取りが求められます。
また、原状回復が難しいDIYには注意が必要です。ネジや釘を使ってしまうと、壁や柱に穴が残る場合があります。そのため、取り外し可能な構造を考えたり、両面テープやマグネットなどを活用して、賃貸住宅でも安心して使える仕様にすることがポイントです。さらに、将来的に再販売や賃貸化を考えている持ち家の方も、可逆性の高いDIYを意識することで、資産価値を損なうリスクを減らせます。
このように、押入れの内寸を把握したうえで適切な材料と設計を行えば、自分だけの使いやすい収納空間を作ることができます。工夫次第で快適な暮らしが実現できる、DIYの醍醐味を存分に楽しんでみてください。
収納ボックスのシンデレラ配置
それでは最後に、収納ボックスの配置について触れておきます。押入れを最大限に活用するには、ボックスの配置とサイズの最適化が非常に重要です。
シンデレラフィットを目指すには、まず内寸とボックスの外寸をミリ単位で正確に測ることが必要です。これを怠ると、せっかく購入した収納用品がうまく収まらず、使いにくくなってしまいます。
たとえば、横幅44cmのボックスを3つ並べると、内寸135cmの押入れにちょうど良く収まるケースが多く見られます。さらに、奥行きにも注意を払えば、前後に物を詰めすぎて取り出せないといった問題も防げます。
このように、収納ボックスの外寸に合わせた配置を考えると、使い勝手のよさだけでなく、見た目にもすっきり整った印象になります。加えて、同じシリーズのボックスで統一すれば、積み重ねがしやすくなり、全体の強度やバランスも良くなります。
また、キャスター付きの収納ボックスを使えば、掃除や模様替えの際にもスムーズに移動ができて便利です。ただし、床に傷がつかないようにマットを敷くなどの工夫も忘れないでください。
このように言うと難しく感じるかもしれませんが、一度ピッタリはまると見た目も美しく、毎日の出し入れもしやすくなります。結果として、片付けが習慣化し、家の中が自然と整っていくでしょう。
家族構成に応じた押入れ選び
ここでは、家族の人数やライフスタイルに合った押入れの選び方をご紹介します。押入れと一口に言っても、使い方や求める機能は家庭ごとに大きく異なります。
例えば、小さいお子さんがいる家庭では、おもちゃや絵本を出し入れしやすいように、低めの位置に棚を設けたり、自由棚で細かく区切るのがおすすめです。また、安全面も重要なポイントなので、扉の開閉がスムーズで指を挟みにくいタイプを選ぶと安心です。加えて、遊び終わったものを自分で片付けやすくなる配置にすれば、自然と整理整頓の習慣も身につきます。
一方で、二人暮らしや単身者の場合は、収納の「量」よりも「使い勝手」や「美観」を重視したいところです。例えば、シンプルな収納ケースを並べてインテリア性を高めたり、自由棚を活用してワンアクションで出し入れできる構造にするのも良いでしょう。さらに、生活パターンに合わせて季節物をまとめて収納するなど、効率的なレイアウトにすると毎日の家事もスムーズになります。
このように、家族構成や暮らし方に応じて押入れの種類や配置を工夫することで、機能的でストレスの少ない収納が可能になります。結果として、日常生活の中で「片付けやすさ」が自然と実現できるようになるのです。
一条工務店 押入れの特徴と選び方の総まとめ
- 押入れbタイプは中段構造で布団や家電の収納に適している
- 標準的な奥行きで使い勝手と設置性のバランスが取れている
- 押入れの幅は90・135・180cmから選択可能
- 奥行きは60cmと90cmがあり、用途に応じた使い分けが必要
- 布団収納には90cmの奥行きが最適
- 内寸は外寸よりも小さいため事前の計測が重要
- 内寸に合わせて収納用品を選ぶことで無駄なスペースが減る
- シンデレラフィットを目指すと整理整頓がしやすくなる
- ボックスや棚は高さ・奥行きも含めて検討が必要
- 自由棚の導入で季節や用途に応じた収納が可能になる
- 棚を増やしすぎると大物収納に支障が出ることがある
- 床からの高さによって出し入れのしやすさが変わる
- 引き戸は省スペース向き、観音開きは視認性に優れる
- 扉を外すとオープン収納としての活用もできる
- 家族構成に合わせた収納設計が快適な暮らしにつながる
一条工務店を検討中の方は以下の記事も参考にして後悔をなくしてくださいね!
費用・保険・保証
- 【実例あり】一条工務店の注文住宅の評判と住人だけが知るデメリット
- 一条工務店のメンテナンス費用は高い?30年間の総額を解説
- 一条工務店の火災保険は高い?割引と見積もりで安くする選び方
- 一条工務店が倒産する可能性は?経営状態と業績を見れば安心できる
エクステリア
- 一条工務店のハイドロテクトタイルはいらないと後悔!?メンテナンス楽で人気
- 一条工務店の対水害住宅の注意点|金額や何メートルの浸水まで大丈夫か
- 一条工務店の幹延長費用はいくら?ハグミーやアイキューブ・平屋で大丈夫か
- 一条工務店のバルコニーのメンテナンス費用は高い!?保証はどうなるのか
- 一条工務店のウッドデッキの後悔ポイントは後付け・メンテナンス・色など
- 一条工務店の庇で人気はアーバンルーフ!後付け・費用・後悔ポイント紹介
- 一条工務店の門柱はオプション扱い|位置や後付けで後悔しないために
玄関・ドア・天井
家の構造
- 一条工務店の鉄骨は後悔する?性能と価格を徹底解説
- 一条工務店の木材の品質や種類は!?産地はどこ産のものなのか
- 一条工務店の基礎の種類・ベタ基礎はオプションで費用はいくらか
- 一条工務店の平屋で後悔!?やめたほうがいい噂の理由とは?
- 一条工務店の家は増築できないのか?離れを作るには費用が高い
オプション選び
- 一条工務店のうるケアは後悔する?評判と費用を徹底解説
- 一条工務店の石目調フローリングで後悔しない!価格や特徴を解説
- 一条工務店のV2Hは後付けできる?価格・補助金・欠点を解説
- 一条工務店のクロスはどれがいい?標準とオプションおすすめの使い分け
- 一条工務店で無垢床フローリングにしたい!気になる費用・欠点・ゴキブリについて
- 一条工務店の勾配天井は6畳でもOK?費用やルールで後悔しないために
- 一条工務店のオープンステアで後悔!?下の活用は収納だけじゃない
- 一条工務店なら網戸はいらないと思ったら後悔!勝手口に必要かの判断基準
- 一条工務店の防音ドアはトイレやリビングにも!効果はバツグン
- 一条工務店のカーテンがいらないと思ったらカーテンレールのみで良いか
- 一条工務店の3Dパースを依頼したい!内観パースは作ってくれないの?
- 一条工務店で防音室の設置費用はいくらか|効果は高く「うるさい」を解決
- 一条工務店の防犯カメラは後付け・施主支給できるか?お得に安心したい方へ
- 一条工務店の浄水器おすすめはこれ!後付けできるパナソニック製品など
- 一条工務店の玄関ポーチ人気のタイル色やポーチ延長費用を徹底紹介
- 一条工務店のランドリールーム必要か?乾かない噂や間取りなど後悔ポイントまとめ
- 一条工務店のキッチンにリクシルを施主支給したい!標準メーカーはダサい?
- 一条工務店でダウンライトにすべきか?いらないの声やシーリングにすればよかったなど
- 一条工務店の本棚(ブックシェルフ)で後悔!?背中合わせで賢く収納
- 一条工務店 御影石のキッチンカウンターはダサい?おしゃれを実現するヒント
- 一条工務店の階段を完全紹介!パターンの選び方・必要なマス数を知り失敗を防ぐ
- 一条工務店の屋根裏収納で後悔しないポイント|後付け・費用・見積もり
- 一条工務店の1.5階建ての費用・人気の理由・デメリットや間取りの注意点
- 一条工務店の押し入れ選び!観音開き・引き戸・開き戸のメリットデメリット
- 一条工務店で和室はいらない!?小上がりや畳選びで後悔しがち
- 一条工務店でゴキブリ出現!?換気システムから侵入か給気口か
- 一条工務店のロフトの費用は意外と安い!平屋との相性も良し
設備
- 一条工務店ヘッダーボックスの場所は玄関と階段下が最適!音と床暖的効果
- 一条工務店のインターホンの選び方|標準モデルMT101から後付けまで網羅
- 一条工務店の物干し金物ホスクリーンは後付けできるのか|耐荷重や設置値
- 一条工務店の自在棚にシンデレラフィットするゴミ箱
- 一条工務店のスマートキーつけるべきか?後付けやピーピー音・紛失トラブルも
- 一条工務店のエコキュートおすすめモデルは快適重視ならPシリーズ
- 一条工務店のレンジフード選び|操作選びやフィルター有無
- 一条工務店の蓄電池を2台に!価格や容量、後付け費用を解説
- 一条工務店の浴室乾燥機はオプションでつけるべきか?後悔しない判断基準
- 一条工務店シューズボックスの全て!種類・収納・価格を解説

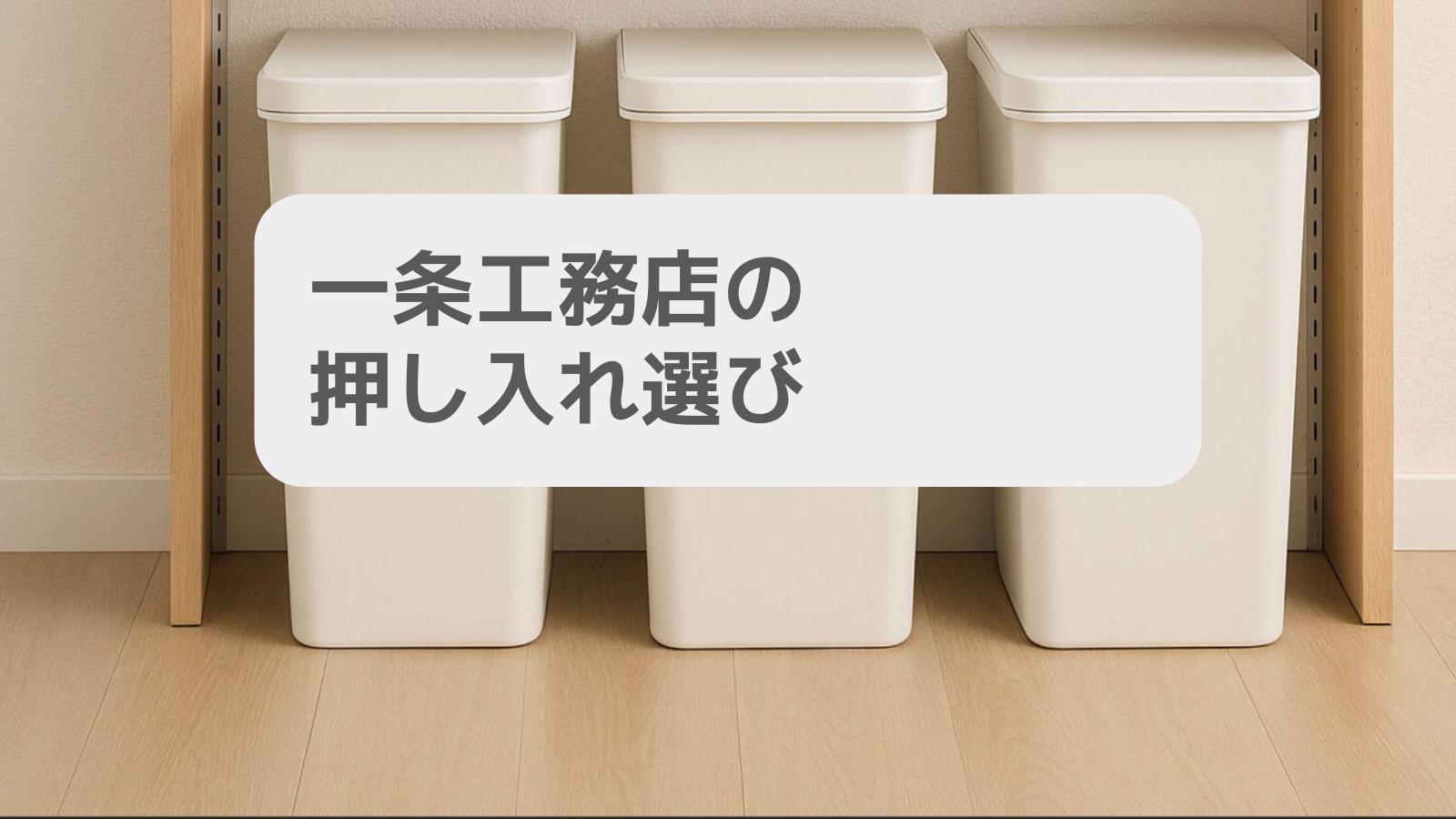


コメント