注文住宅で一条工務店を検討している方の中には、「階段ってどんな種類があるの?」「間取りに必要なマス数は?」と疑問を持つ方も多いはずです。
特に階段パターンは住まいの動線や空間の印象を左右する重要な要素であり、慎重な選択が求められます。
本記事では、一条工務店の階段に関する基本的なルールから、人気のオープンステアやボックスステアの違い、階段に必要なマス数や幅の選び方まで、実例を交えて分かりやすく解説します。
さらに、グランスマートで採用される階段パターンや、階段下トイレの活用法、照明による安全性の工夫、色の選び方、そして踊り場を設けた設計のメリットまで、知っておくと間取りづくりがスムーズになる情報を網羅しています。
階段設計で後悔しないためにも、一条工務店での階段に関する知識をしっかりと身につけておきましょう。
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 階段の種類 | ボックスステア(囲いあり・収納活用可) / オープンステア(開放感・デザイン重視) |
| 階段パターン(形状) | ストレート型、L字型、コの字型(踊り場あり) |
| 採用シリーズ例 | グランスマートでは天井が高く階段段数が多くなる傾向 |
| 必要なマス数 | 3〜4.5マス(形状・段数・勾配により異なる) |
| 階段の幅 | 標準76cm / 広め96cm(家具搬入の有無で検討) |
| 段差(蹴上げ)と踏面 | シリーズにより異なるため設計時に確認 |
| 階段下スペース | 収納・階段下トイレ・家事スペースなどに活用可能 |
| 踊り場のメリット | 転倒リスクの軽減、デザイン性・空間のゆとり向上 |
| 照明の工夫 | 人感センサー、間接照明で安全性と雰囲気アップ |
| 色のバリエーション | ライト、レッド、ビターの3色展開(内装との調和を考慮) |
| 設計ルール | 階段横にドア不可、引き戸との距離など制約あり |
| 配置の注意点 | 玄関・リビング階段の動線や冷暖房効率を考慮 |
| 収納の工夫 | 階段下にウォークイン収納や引き出し収納を設置可能 |
| 快適性向上の工夫 | 手すりの追加・滑り止め・照明設置で使いやすく |
| デザイン性 | アートやクロス装飾で空間のアクセントになる |
 著者
著者10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
一条工務店 階段の選び方と特徴


- 階段パターンと選び方の基本
- グランスマートの階段パターン解説
- 一条工務店の階段寸法と幅の違い
- 階段は何マス必要か?
- 階段と間取りマスの関係とは
- 階段の色とインテリアの統一感
階段パターンと選び方の基本


一条工務店の階段には、主に「ボックスステア」と「オープンステア」の2種類があり、それぞれに異なる魅力や特性があります。どちらを選ぶかは、家族構成や住まいのデザイン、さらに普段の生活スタイルに深く関わるため、慎重に検討することが大切です。
例えば、小さなお子さんがいるご家庭や、ご年配の方と暮らしている場合は、安全性を最優先に考える方が多いです。そのようなときには、壁でしっかりと囲まれていて、手すりも最初から備えられている「ボックスステア」が安心です。落下のリスクが少なく、支えとなる壁や手すりによって昇り降りが安定します。また、階段下のスペースを収納やトイレとして活用しやすいのも、このタイプの大きな魅力です。
一方で、空間の広がりや洗練された雰囲気を重視したい方には、「オープンステア」がおすすめです。段ごとに隙間があるスケルトン構造になっており、圧迫感がなく、リビングや吹き抜けと組み合わせることで、視覚的に部屋を広く見せることができます。そのため、開放感を演出したいときに最適です。
ただし、オープンステアには注意点もあります。段と段の間に隙間があるため、小さなお子さんが足を滑らせたりするリスクがゼロではありません。安全対策として、ステアカバーやベビーゲートの導入を検討するのが現実的です。
このように考えると、階段は家の中で単に上下の移動をする場所というだけでなく、インテリアの一部であり、家族の安全や快適性に直結する存在です。だからこそ、間取りの初期段階から階段のパターンを十分に検討し、最適なタイプを選ぶことが大切です。
グランスマートの階段パターン解説
グランスマートでは、階段のパターン選びにもいくつかの独自の特徴があり、家づくりの計画において大きなポイントとなります。標準仕様でも十分満足できるクオリティがありますが、実際の生活スタイルや家族構成に合わせて、さらに細かくカスタマイズしていくことで、より理想的な住まいに近づけることができます。
まず、グランスマートは天井高が比較的高めに設計されているため、それに対応するように階段の段数がやや多くなる傾向があります。段数が多いと聞くと不便に思うかもしれませんが、実際にはその分だけ勾配が緩やかになるため、日常的な上り下りの負担が軽減され、身体への負担も少なくなるというメリットがあります。ただし、段数が増えることで階段の全体長が伸びるため、設置スペースが広く必要になる点は間取り全体に影響を及ぼします。
例えば、リビング階段を採用したいと考えている場合は、ストレートタイプのオープンステアを選ぶケースが多いです。リビングと階段が自然につながることで、家族の行き来がしやすくなり、コミュニケーションも活発になります。また、オープンステアの特徴である開放感により、リビング全体が明るく広々と感じられる効果も得られます。
一方で、階段の位置によっては周囲の収納や動線設計に影響を与えることもあるため、設計段階でしっかりとシミュレーションしておくことが重要です。例えば、玄関近くに階段を配置すると、外出・帰宅時の移動がスムーズになるという利点がありますが、プライバシーの確保や来客動線とのバランスにも配慮が必要です。
このように、グランスマートでは天井高や開放感を活かした階段設計が魅力である一方、全体の間取りとの調整も求められます。自分たちの暮らしにぴったりの階段パターンを見つけるためには、実際の暮らしをイメージしながら、細かな部分まで丁寧に検討することが成功の鍵になります。
一条工務店の階段寸法と幅の違い
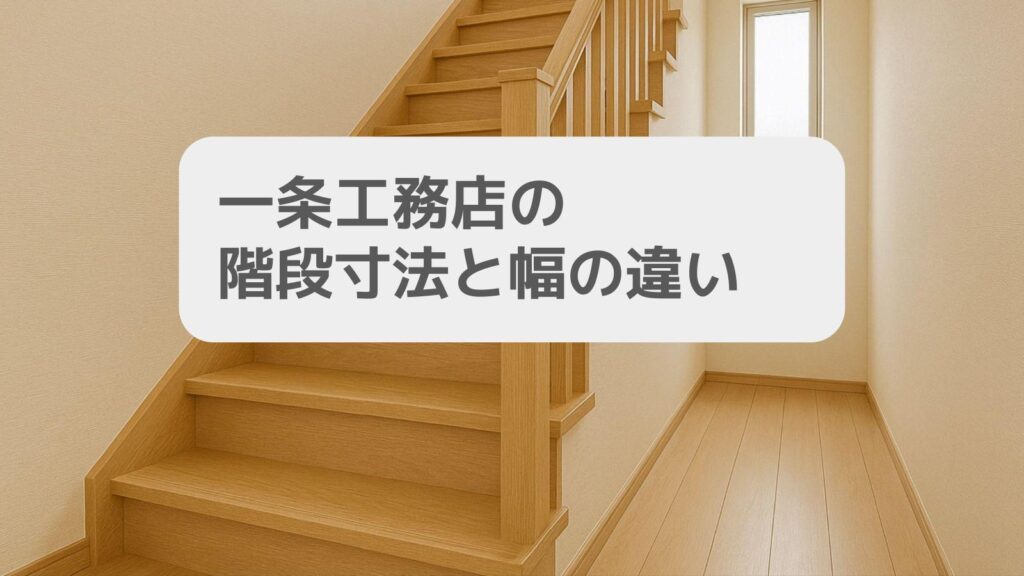
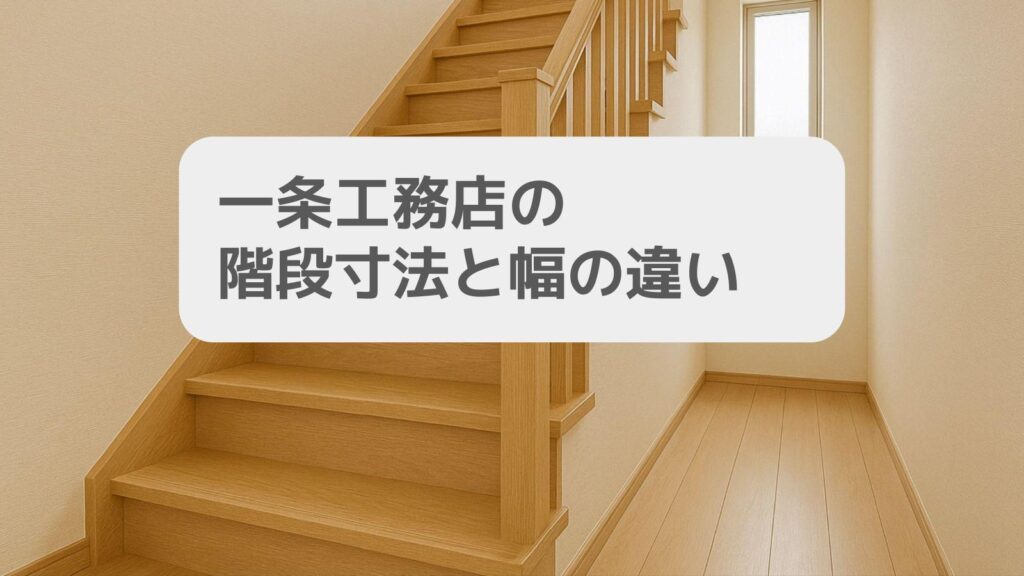
一条工務店の階段には、主に2つの幅のバリエーションがあります。ひとつは標準的な76cm幅、もうひとつはより広めの96cm幅です。一般的な日常生活では76cmでも十分に使いやすく、特に問題を感じることは少ないかもしれません。しかし、引っ越しの際や大型家具の搬入時には96cm幅の方が圧倒的に利便性が高く、後悔しにくい選択となります。
例えば、2階にセミダブル以上のベッドや、大型のテレビボード、ソファなどを搬入する予定がある場合、階段幅が狭いと搬入作業が困難になることがあります。最悪の場合、クレーンで窓から搬入するなど、追加の費用や手間が発生するリスクもあるのです。このようなケースでは、最初から96cmの幅広タイプを選んでおけば、将来的なトラブルを回避できる可能性が高まります。
一方、敷地面積に制約があったり、居住空間をなるべく広く取りたい場合には、76cm幅でも十分に実用的です。特に各部屋をコンパクトにまとめて動線を短くしたいと考える家庭では、標準幅の階段でも快適に暮らすことができます。
また、階段には「幅」だけでなく「段数」「蹴上げ(段差の高さ)」「踏面(足を置く奥行き)」といった細かい寸法もあります。例えば、蹴上げが高すぎると階段の昇り降りが急になり、足腰に負担がかかることもあります。踏面が狭いと足をしっかり置けず、滑りやすくなってしまう場合もあるため、安全性を考える上でこれらの要素も見逃せません。
これらの寸法はシリーズや設計条件によって異なることがあるため、モデルハウスで実際に体験したり、設計士と相談しながら決めることが重要です。暮らしの中で毎日使う階段だからこそ、使いやすさや安全性を考慮した上で、納得できる寸法を選ぶことが後悔しない家づくりにつながります。
階段は何マス必要か?
一条工務店の階段は、その形状や段数によって必要なマス数が大きく変わります。基本的に、ストレートタイプの階段では3マスから3.5マスのスペースが必要とされていますが、これはあくまで標準的な設計に基づいた目安です。家族の人数や生活動線によっても最適な配置は異なってくるため、単純に数値だけを見るのではなく、実際の暮らしを想定したうえでスペースを確保する必要があります。
例えば、オープンステアを15段で設計した場合、勾配がゆるやかになるため、安全性が高まる一方で、どうしても階段が長くなり、3.5マス以上のスペースが必要になることがあります。より緩やかな昇り降りを希望する場合は、マス数に余裕を持って計画しておくと後悔が少なくなるでしょう。
一方、ボックスステアでL字型や折り返し型を選択する場合には、構造的な違いからより多くのスペースが必要になります。ケースによっては4マスから4.5マスほど使うこともあり、その分、他の部屋の配置や収納スペースにも影響を及ぼします。特に間取りにこだわりがある方は、階段に必要なマス数を早い段階で把握しておくとスムーズに進められます。
また、マスの計算においては“階段下”の利用も見逃せません。例えば、階段下にトイレや収納を配置することで、限られたスペースを有効に使うことができますが、その際にもどの程度の高さや奥行きが確保できるかを含めて検討することが重要です。
このように、一条工務店の階段はパターンによって必要なマス数が異なるため、見た目や安全性だけでなく、機能性や他スペースとのバランスも考慮しながら設計士さんと一緒に進めることをおすすめします。計画初期に十分な打ち合わせを重ねておくことで、後からの変更や修正を避け、理想的な住まいづくりに近づけるはずです。
階段と間取りマスの関係とは
階段に必要なマス数を正しく把握することは、家全体の間取り設計において極めて重要なポイントです。階段は上下階をつなぐ動線として不可欠な存在ですが、同時にそのスペースが他の部屋の配置やサイズに直接影響を与えるため、十分に配慮した配置が求められます。
例えば、3.5マスの階段を設置すると仮定した場合、それだけでリビングやダイニング、キッチンの面積をある程度削らなければならないことになります。たとえ1マスの差であっても、部屋の使い勝手や家具のレイアウトに大きく関わってくるため、見落としがちな要素ですが後悔しやすいポイントでもあります。
また、階段はその上部だけでなく、下部のスペースも有効に活用できるチャンスがあります。多くの家庭では、階段下を収納スペースやトイレに転用することで、限られた空間を無駄なく使う工夫がされています。収納であれば、掃除道具や季節用品の置き場として。トイレであれば、省スペースながらもしっかりとした設備を設けることも可能です。ただし、階段下にトイレを配置する場合は、天井の高さや換気の位置に注意が必要です。
さらに、階段をどの位置に配置するかによって家の動線にも影響を及ぼします。例えば、玄関から近い場所に階段を設けると、来客時の動きやすさがアップしますが、同時にプライバシーの問題も出てくるため、扉の位置や間仕切りの工夫が必要になります。逆にリビング階段を採用すると、家族のコミュニケーションは増えますが、冷暖房効率や音の伝わりやすさといったデメリットも考慮しなければなりません。
このため、階段と間取りは切っても切れない関係にあり、一つの設計ミスが住み心地に大きく影響することも少なくありません。設計段階から家族の暮らし方や生活動線を丁寧にシミュレーションし、全体のバランスを見ながら配置を計画することが、後悔しない家づくりを実現するための鍵となります。
階段の色とインテリアの統一感
階段の色選びは、空間全体の雰囲気や統一感に大きく影響する大切な要素です。特にリビング階段やオープンステアのように目に付きやすい位置にある場合は、色が与える印象の違いを十分に意識して選ぶことが重要です。一条工務店では、「ライト」「レッド」「ビター」の3色が標準で用意されており、それぞれに異なる雰囲気や魅力があります。
例えば、明るく開放感のある空間を演出したい場合には「ライト」が適しています。ナチュラルな木目調が映え、北欧風のやわらかいインテリアや白を基調とした空間にもよく合います。家全体をすっきりと広く見せたい場合にも効果的です。
逆に、落ち着きのある重厚な雰囲気を好むなら「ビター」が人気です。濃いブラウン系の色味は高級感を演出しやすく、家具や建具とも調和しやすいのが特長です。インテリアにメリハリをつけたいときや、大人っぽく仕上げたい方に向いています。
また、ややアクセントを持たせたい場合には「レッド」も魅力的です。赤みがかった木調カラーで、あたたかみのある空間にしたいときに効果を発揮します。特にダイニングやキッチンなど、活気を感じさせる場所との相性が良いとされています。
このように、色選びはフローリングやドア、家具などとのバランスを取りながら進めることが肝心です。異なるトーンや材質が混在してしまうと、統一感に欠けてしまい、せっかくのこだわりが活かされなくなってしまいます。そこで、色のトーンを揃える、またはコントラストを活かすかを意識するだけでも、見違えるような仕上がりになります。
インテリアのイメージがなかなか掴めないという方は、モデルハウスを訪問したり、カラーサンプルを実際の床材やクロスと並べて確認することをおすすめします。照明の色や自然光の入り方によっても見え方は変わるため、できるだけ実物に近い環境で選ぶのが失敗を防ぐコツです。
このように考えると、階段の色は単なる装飾ではなく、家の雰囲気を左右する“インテリアの軸”ともいえる存在です。全体のバランスを考慮しながら、自分たちの暮らしに合った色をじっくり選ぶことが、満足度の高い住まいづくりにつながります。
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
一条工務店 階段の活用と注意点


- オープンステアとボックスステア比較
- 階段下トイレの設置ポイント
- 踊り場付き階段のメリット
- 照明計画で階段を安全に演出
- 階段設置の一条ルールとは
- 階段を快適に使うための工夫
オープンステアとボックスステア比較
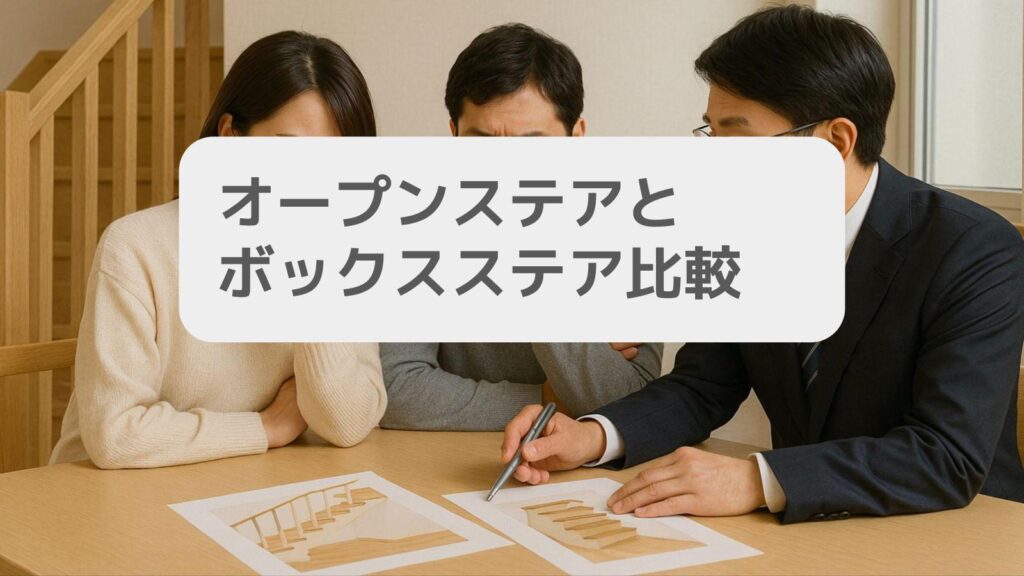
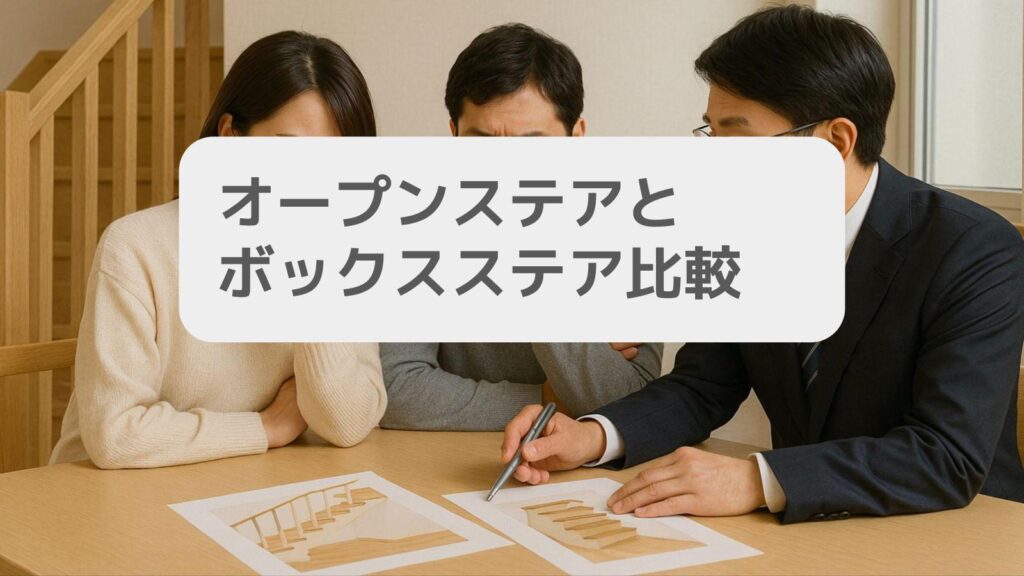
オープンステアとボックスステアは、一条工務店で選べる代表的な階段の2タイプであり、それぞれ異なるメリットと注意点があります。両者の特徴を理解することで、自分たちの家族構成やライフスタイルに適した階段を選ぶことができます。
まず、オープンステアは段ごとに隙間があるスケルトンタイプの階段で、視界が抜けるデザインが特徴です。開放感を演出しやすく、室内に圧迫感を与えないため、リビング階段として採用する方に人気があります。吹き抜けと合わせて設計すれば、空間全体が広く感じられ、モダンでスタイリッシュな印象を与えることができます。デザイン性の高さから、階段そのものをインテリアの一部として見せたいと考えている方に特におすすめです。
一方、ボックスステアは壁に囲まれた階段で、非常に安定感があり安全性に優れています。階段下が完全に閉じられている構造になっているため、その空間を収納やトイレなどに有効活用できるのも大きな魅力です。小さな子どもや高齢者がいる家庭では、視覚的な不安感が少ないこのタイプが選ばれる傾向にあります。また、冷暖房の効率が比較的良く、音や匂いの伝わり方を抑えられるという点もメリットの一つです。
ただし、オープンステアには段の隙間があるため、安全性に配慮した追加の対策が必要になることがあります。特に小さなお子さんがいるご家庭では、足を滑らせたり、物を落とすリスクを考慮しなければなりません。そのため、手すりの位置やステアカバー、ベビーゲートなどを設置して補強するのが一般的です。また、掃除の手間もややかかる点は事前に理解しておくとよいでしょう。
逆にボックスステアは構造上、階段下のスペースを確保できる代わりに、空間全体の開放感はやや失われがちです。階段自体に存在感が出てしまうことから、間取りによってはやや重たい印象になることもあるため、照明計画や壁紙の色合いで工夫をするとバランスが取れます。
このように、オープンステアとボックスステアはそれぞれの特徴を活かしながら設計に取り入れることが可能です。デザイン性を優先したいのか、安全性と機能性を重視するのか、ご家庭の優先順位を明確にして選ぶことで、満足度の高い階段選びにつながります。
階段下トイレの設置ポイント


階段下にトイレを設けることは、限られた空間を有効活用できる素晴らしいアイデアです。特にコンパクトな住宅や、収納スペースを極力削りたくない間取りでは、階段下のスペースを活かすことで居住性を高めることができます。
ただし、設置にあたってはいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。まず最も気をつけたいのが天井の高さです。階段の形状によっては、トイレの天井が斜めになってしまい、使用時に頭をぶつける危険があります。そのため、設計段階でしっかりと立ち上がる位置や便器の向き、ドアの開閉方向をシミュレーションしておくことが大切です。
また、トイレの配置場所によっては、建築基準法に基づく採光や換気の条件も満たす必要があります。窓を設置する余裕がない場合でも、換気扇を取り付けたり、明かり取りの工夫をすることで、閉塞感を感じにくい快適な空間にすることができます。可能であれば、間接照明やダウンライトなどを採用し、暗くなりがちな空間を明るく見せる工夫をするとさらに良いでしょう。
加えて、トイレとしての使い勝手も無視できません。収納スペースが取りにくい場所ではありますが、壁面に小さな棚を設けたり、トイレットペーパーや掃除道具をすっきりとまとめられるような工夫をすることで、実用性もアップします。音漏れが気になる場合は、防音性のある建材やドアの選定も検討材料となります。
このような点をトータルで考慮しながら設計することで、階段下のトイレは“妥協した設備”ではなく、生活動線の中にしっかり馴染む便利で快適なスペースとなります。設計士としっかり相談しながら、理想の使い勝手を叶える設計を目指しましょう。
踊り場付き階段のメリット
踊り場付き階段には、安全性と使いやすさという2つの大きなメリットがあります。特に高齢者や小さな子どもがいるご家庭では、階段の途中に一時的に休めるスペースがあることで、物理的にも精神的にも安心感を得られます。急な階段で一気に昇り降りするのが難しい場合でも、踊り場で一呼吸おくことができるのは、非常にありがたいポイントです。
例えば、直線型の急な階段では、足を踏み外した際にそのまま一気に下まで落下してしまう危険性があります。しかし、踊り場があることで万が一の転倒時にも落下距離が短くなり、事故のリスクが軽減されます。この構造上の安心感は、家づくりの安全面で非常に重要な評価ポイントとなります。
また、踊り場があることで階段のデザインに柔らかさが加わり、視覚的な圧迫感が軽減されるのも見逃せません。特にL字型やコの字型の階段では、動線に変化が出て空間のアクセントになりやすく、結果として階段の存在感がやわらぎます。これにより、階段がインテリアに溶け込みやすくなるため、全体の調和が取りやすくなるのです。
さらに、踊り場部分にはちょっとした装飾や機能を加えることも可能です。例えば、小さな観葉植物を置いたり、写真フレームを飾ったりすることで、単なる通路だった階段が「魅せる空間」へと変わります。窓が近くにあれば採光も取りやすくなり、自然光の入り方によって空間全体が明るくなるという副次的な効果も期待できます。
このように、踊り場付き階段は、安全性と美観の両方を満たす機能的な要素であり、日々の暮らしの中で安心感や利便性、そしてインテリア性を高めてくれる存在です。特に家族全員が安心して使える住まいを目指すなら、踊り場のある階段は非常におすすめできる選択肢と言えるでしょう。
照明計画で階段を安全に演出
階段の照明は、単なる明るさの確保だけでなく、安全性と空間の演出という両方の役割を担う非常に重要なポイントです。階段は日常的に何度も使う場所であるだけに、少しの暗さや影の存在が転倒などのリスクを高めてしまうことがあります。だからこそ、照明計画は計画段階からしっかりと考えておきたい要素です。
例えば、階段の上部と下部だけでなく、踊り場や中間地点にも照明を設けることで、階段全体が均一に明るくなり、視認性が高まります。LEDの間接照明をステップの下に取り付けるという方法もあり、足元の陰影をやわらげて安全性が向上すると同時に、デザイン性のある空間にもなります。
さらに、最近では人感センサー付きの照明が多く採用されています。これは、人が階段に近づいたり動いたりすることで自動的に照明が点灯する仕組みで、夜間のトイレや寝室からの移動時にもスムーズでとても便利です。スイッチを探す手間がないため、小さなお子さんや高齢者にも安心です。
また、階段がリビングなどの開放的な空間とつながっている場合は、見た目にも配慮した照明の選び方が求められます。シーリングライトだけでなく、壁付けのブラケットライトや手すりに沿った間接照明を組み合わせることで、柔らかく上品な雰囲気を演出できます。
このように、照明計画は安全性だけでなく、住まい全体の快適さやデザインにも関わってくる要素です。日中と夜間で照明の見え方が異なる点も考慮し、実際に使用するシーンをイメージしながら計画を立てることが大切です。照明の配置や種類を工夫することで、安心して使えるだけでなく、家の印象をより洗練されたものに変えることができるのです。
階段設置の一条ルールとは
一条工務店では、高品質な住宅づくりを実現するために、多くの設計項目において独自のルールが設けられています。階段に関してもその例外ではなく、他社とは異なる制約がいくつか存在します。これらのルールを理解し、設計段階でしっかりと把握しておくことが、理想の家づくりを成功させる鍵となります。
まず、一条工務店では「階段のすぐ横にドアは設置できない」というルールがあります。これは、階段の周囲に必要な壁の構造強度や開閉スペースを確保するためです。特に開き戸だけでなく、引き戸についても注意が必要で、「引き戸と階段が干渉しないよう、壁を一定の距離設けなければならない」といった制約もあります。このような設計制限があることで、階段周辺の安全性と施工精度を保つことができます。
こうしたルールがある背景には、一条工務店の住宅が工場であらかじめ部材を精密に製造し、現場で効率よく組み立てるというプレハブ工法を採用していることが関係しています。プレカットされた部材はあらかじめ寸法が決まっており、現場での柔軟な加工がしにくいため、あらゆるパーツが設計通りに配置されなければならないのです。そのため自由度はやや制限されますが、その分、品質の均一性や工期の短縮が実現できるというメリットもあります。
このような独自ルールは、住まい手から見ると「細かすぎるのでは?」と感じるかもしれません。しかし、実際に住み始めてから気付くトラブルや不具合を未然に防ぐために、あらかじめ用意されたルールと捉えると納得しやすいでしょう。
前述の通り、これらのルールによって間取りや家具の配置に制約が生じることもあります。だからこそ、打ち合わせの初期段階から設計担当者と具体的な希望をしっかり共有し、どのような配置が可能で、どこに制限があるのかを丁寧に確認しておくことが大切です。納得のいく階段設計を実現するためには、このような細やかな配慮と情報のすり合わせが不可欠となります。
階段を快適に使うための工夫
階段をより快適で使いやすいものにするには、日々の生活動線や家族構成を考慮した小さな工夫が大きな違いを生むことがあります。設計段階だけでなく、住み始めてからも簡単に取り入れられる工夫が多く存在するため、少しの工夫で階段の使い心地は格段に向上します。
例えば、安全面での配慮として、手すりは外側だけでなく内側にも設置することで、左右どちらからも支えられる安心感が生まれます。特に小さなお子さんや高齢のご家族がいる場合は、両側に手すりがあることで安全性がグッと高まります。また、手すりの高さを家族に合わせて調整することも一つの工夫です。
さらに、滑り止め付きの踏板や階段専用のカーペットを導入することで、転倒防止にもつながります。最近ではデザイン性の高い滑り止め素材も多く、見た目を損なわずに安全性を確保できるようになっています。階段が暗く感じる場合は、段ごとにLED照明を設けると安全かつ美しい印象になります。
収納面でも工夫の余地があります。階段下のスペースを有効に使い、収納棚や引き出し式の収納ボックスを設置することで、掃除用具や日用品、季節物の収納場所として活躍します。場合によっては、ウォークインクローゼットのように人が入れる収納空間をつくるのもおすすめです。このようなアプローチを取れば、階段がただの移動手段ではなく、家の機能的な一部として活用されるようになります。
また、階段にアクセントクロスやアートを飾ることで、空間に個性を加えることもできます。デザイン面での配慮を加えることで、毎日使う階段に対して自然と愛着が湧き、住まい全体の印象も向上します。
このように、階段は単なる上下の移動手段にとどまらず、工夫次第で生活の質を大きく高める存在です。快適性と利便性を重視した工夫を積極的に取り入れることで、毎日使う階段がより安心で心地よい空間に生まれ変わるでしょう。
一条工務店 階段に関する知識の総まとめ
- 階段は「ボックスステア」と「オープンステア」の2種類がある
- ボックスステアは安全性と収納性に優れている
- オープンステアは開放感とデザイン性を重視した階段
- グランスマートでは天井高により階段段数が増える傾向がある
- 階段は間取りに応じて3〜4.5マス程度のスペースが必要
- 76cmと96cmの2種類の階段幅が選べる
- 蹴上げや踏面の寸法も使用感に大きく影響する
- 家具の搬入を考慮して階段幅を選ぶと失敗が少ない
- 階段の位置は動線やプライバシーに影響する
- 階段下は収納やトイレなどに活用できる貴重なスペース
- 踊り場付き階段は安全性と視覚的なゆとりがある
- 照明計画によって階段の安全性と美観が向上する
- 色の選び方で階段の印象や空間の統一感が変わる
- 階段設計には独自の一条ルールが存在する
- 階段の使い勝手は手すりや滑り止め、装飾で改善できる
一条工務店を検討中の方は以下の記事も参考にして後悔をなくしてくださいね!
費用・保険・保証
- 【実例あり】一条工務店の注文住宅の評判と住人だけが知るデメリット
- 一条工務店のメンテナンス費用は高い?30年間の総額を解説
- 一条工務店の火災保険は高い?割引と見積もりで安くする選び方
- 一条工務店が倒産する可能性は?経営状態と業績を見れば安心できる
エクステリア
- 一条工務店のハイドロテクトタイルはいらないと後悔!?メンテナンス楽で人気
- 一条工務店の対水害住宅の注意点|金額や何メートルの浸水まで大丈夫か
- 一条工務店の幹延長費用はいくら?ハグミーやアイキューブ・平屋で大丈夫か
- 一条工務店のバルコニーのメンテナンス費用は高い!?保証はどうなるのか
- 一条工務店のウッドデッキの後悔ポイントは後付け・メンテナンス・色など
- 一条工務店の庇で人気はアーバンルーフ!後付け・費用・後悔ポイント紹介
- 一条工務店の門柱はオプション扱い|位置や後付けで後悔しないために
玄関・ドア・天井
家の構造
- 一条工務店の鉄骨は後悔する?性能と価格を徹底解説
- 一条工務店の木材の品質や種類は!?産地はどこ産のものなのか
- 一条工務店の基礎の種類・ベタ基礎はオプションで費用はいくらか
- 一条工務店の平屋で後悔!?やめたほうがいい噂の理由とは?
- 一条工務店の家は増築できないのか?離れを作るには費用が高い
オプション選び
- 一条工務店のうるケアは後悔する?評判と費用を徹底解説
- 一条工務店の石目調フローリングで後悔しない!価格や特徴を解説
- 一条工務店のV2Hは後付けできる?価格・補助金・欠点を解説
- 一条工務店のクロスはどれがいい?標準とオプションおすすめの使い分け
- 一条工務店で無垢床フローリングにしたい!気になる費用・欠点・ゴキブリについて
- 一条工務店の勾配天井は6畳でもOK?費用やルールで後悔しないために
- 一条工務店のオープンステアで後悔!?下の活用は収納だけじゃない
- 一条工務店なら網戸はいらないと思ったら後悔!勝手口に必要かの判断基準
- 一条工務店の防音ドアはトイレやリビングにも!効果はバツグン
- 一条工務店のカーテンがいらないと思ったらカーテンレールのみで良いか
- 一条工務店の3Dパースを依頼したい!内観パースは作ってくれないの?
- 一条工務店で防音室の設置費用はいくらか|効果は高く「うるさい」を解決
- 一条工務店の防犯カメラは後付け・施主支給できるか?お得に安心したい方へ
- 一条工務店の浄水器おすすめはこれ!後付けできるパナソニック製品など
- 一条工務店の玄関ポーチ人気のタイル色やポーチ延長費用を徹底紹介
- 一条工務店のランドリールーム必要か?乾かない噂や間取りなど後悔ポイントまとめ
- 一条工務店のキッチンにリクシルを施主支給したい!標準メーカーはダサい?
- 一条工務店でダウンライトにすべきか?いらないの声やシーリングにすればよかったなど
- 一条工務店の本棚(ブックシェルフ)で後悔!?背中合わせで賢く収納
- 一条工務店 御影石のキッチンカウンターはダサい?おしゃれを実現するヒント
- 一条工務店の階段を完全紹介!パターンの選び方・必要なマス数を知り失敗を防ぐ
- 一条工務店の屋根裏収納で後悔しないポイント|後付け・費用・見積もり
- 一条工務店の1.5階建ての費用・人気の理由・デメリットや間取りの注意点
- 一条工務店の押し入れ選び!観音開き・引き戸・開き戸のメリットデメリット
- 一条工務店で和室はいらない!?小上がりや畳選びで後悔しがち
- 一条工務店でゴキブリ出現!?換気システムから侵入か給気口か
- 一条工務店のロフトの費用は意外と安い!平屋との相性も良し
設備
- 一条工務店ヘッダーボックスの場所は玄関と階段下が最適!音と床暖的効果
- 一条工務店のインターホンの選び方|標準モデルMT101から後付けまで網羅
- 一条工務店の物干し金物ホスクリーンは後付けできるのか|耐荷重や設置値
- 一条工務店の自在棚にシンデレラフィットするゴミ箱
- 一条工務店のスマートキーつけるべきか?後付けやピーピー音・紛失トラブルも
- 一条工務店のエコキュートおすすめモデルは快適重視ならPシリーズ
- 一条工務店のレンジフード選び|操作選びやフィルター有無
- 一条工務店の蓄電池を2台に!価格や容量、後付け費用を解説
- 一条工務店の浴室乾燥機はオプションでつけるべきか?後悔しない判断基準
- 一条工務店シューズボックスの全て!種類・収納・価格を解説
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/




コメント