セキスイハイムで家づくりを検討している方の中には、「セキスイハイム ユニット ずらす」と検索して情報を集めている方も多いのではないでしょうか。
セキスイハイムはユニット工法によって精密な住宅を短期間で建築できる点が魅力ですが、その構造ゆえにセキスイハイムの間取りには制限がありますか?という疑問が生まれたり、階段ユニットに関する「階段なぜ小さいのか」といった不満も見受けられます。
 著者
著者結論、新工法により間取り自由度は上がっています。
さらに、天井裏の配線制限や軒天と外壁の取り合い、水切り処理の違いなど、構造的な特徴を正しく理解しておくことが快適な住まいづくりの第一歩です。
一方で、施工ミスや欠陥によるトラブル、基礎やり直しのリスクも報告されており、実際に住んでからの後悔を防ぐには事前の情報収集が欠かせません。
本記事では、セキスイハイムの施工にまつわる特徴や注意点を詳しく解説し、「セキスイハイムのダメなところは?」といった不安に対しても具体的に触れていきます。
加えて、セキスイハイムの外壁は何年持ちますか?セキスイハイムは60年持つのですか?という疑問にも実例とともにお答えしながら、グランツーユー後悔などの実際の声も交えて紹介します。
ユニットをずらすことで得られる設計の柔軟性と、その裏にあるリスクをきちんと把握した上で、満足のいくマイホームを目指しましょう。



10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ユニット工法とは | 工場で製造された箱型のユニットを現場で組み立てる方式 |
| 間取りの自由度 | ユニット規格の制約あり、一部制限が発生する |
| シフトジョイント工法 | ユニットを前後左右にずらすことで設計自由度を拡張 |
| 施工ミスのリスク | 接合部のずれによる傾きや段差が生じる可能性 |
| 階段ユニットの特徴 | 階段が小さいのは構造上の制限による。広さの調整は要相談 |
| 天井裏スペース | ほとんどないため、配線・設備追加に制限がある |
| 音が響く対策 | 雨音対策に雨戸・厚手カーテン・断熱材強化が有効 |
| 水切り構造 | ユニット密閉構造で土台水切りが無い場合もある |
| 軒天の施工 | 接合部のシーリング処理が甘いと雨漏りリスクあり |
| 基礎の重要性 | 傾きや段差を防ぐために地盤調査と水平確認が必須 |
| 外壁の耐久年数 | 一般的に15~20年。立地や塗料で差が出る |
| 60年サポートの意味 | 定期点検と有償メンテナンスで性能を維持する制度 |
| グランツーユー後悔例 | 家鳴り・きしみ・内装の歪みなど経年による不満の声あり |
| 欠陥・トラブル例 | 床の不陸、段差、配管ミスなど施工精度に注意が必要 |
セキスイハイムのユニットをずらす施工とは
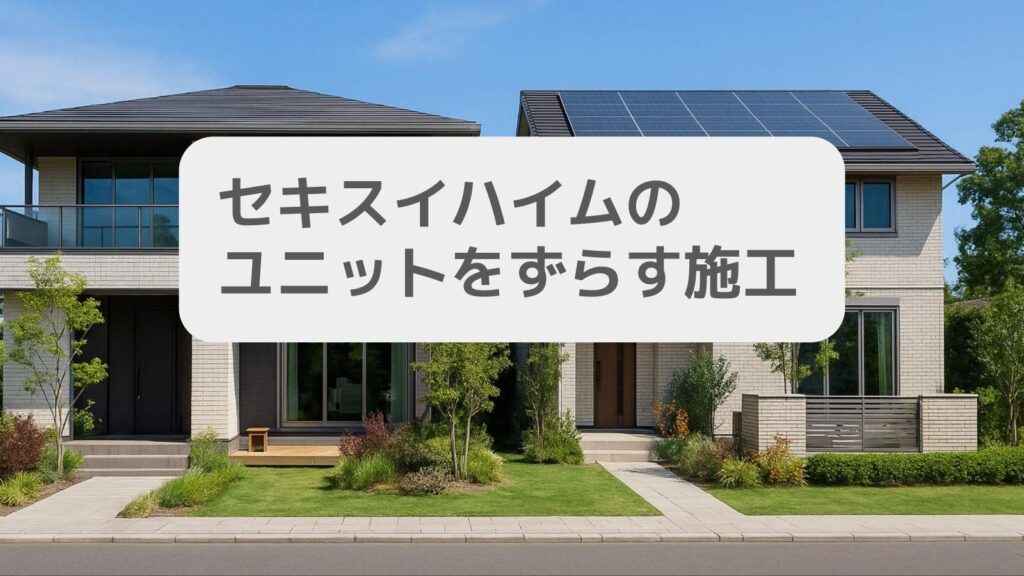
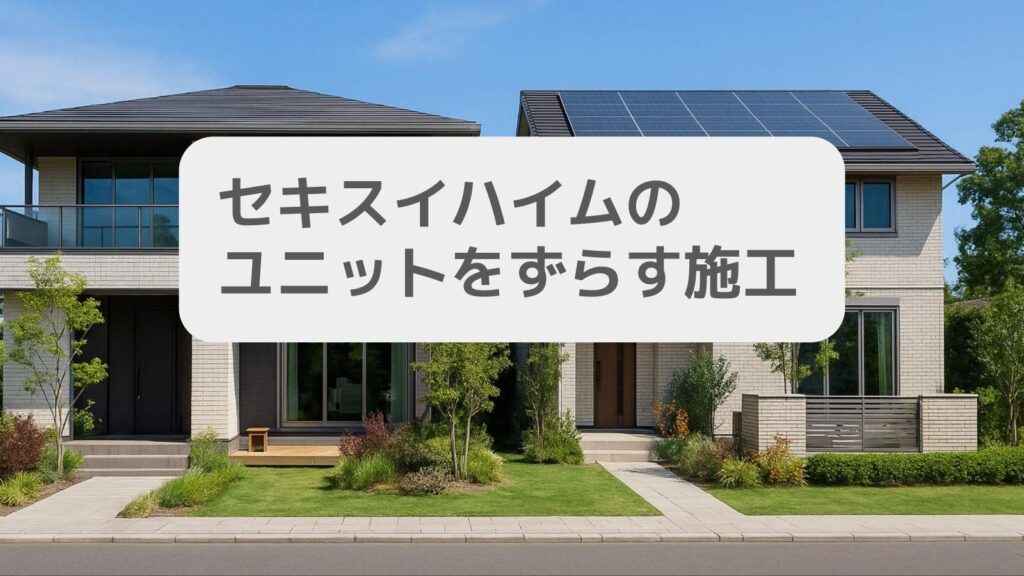
- ユニット工法と間取り制限の関係
- ユニットずらしと施工ミスの注意点
- ユニット間の階段はなぜ小さい?
- 天井裏の空間と設備の制約
- セキスイハイムの水切り処理とは
- 音が響く家の特徴と対策
ユニット工法と間取り制限の関係
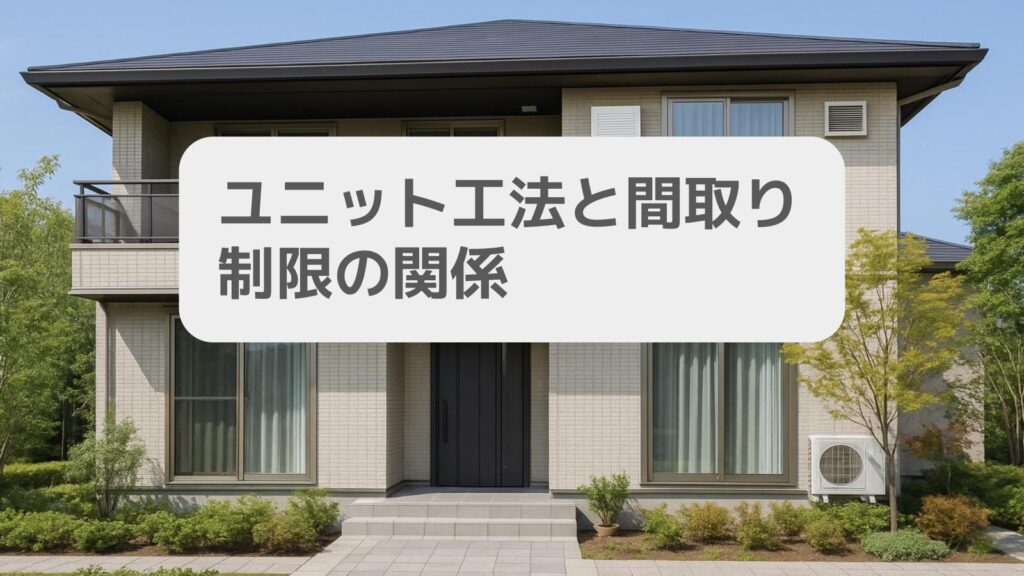
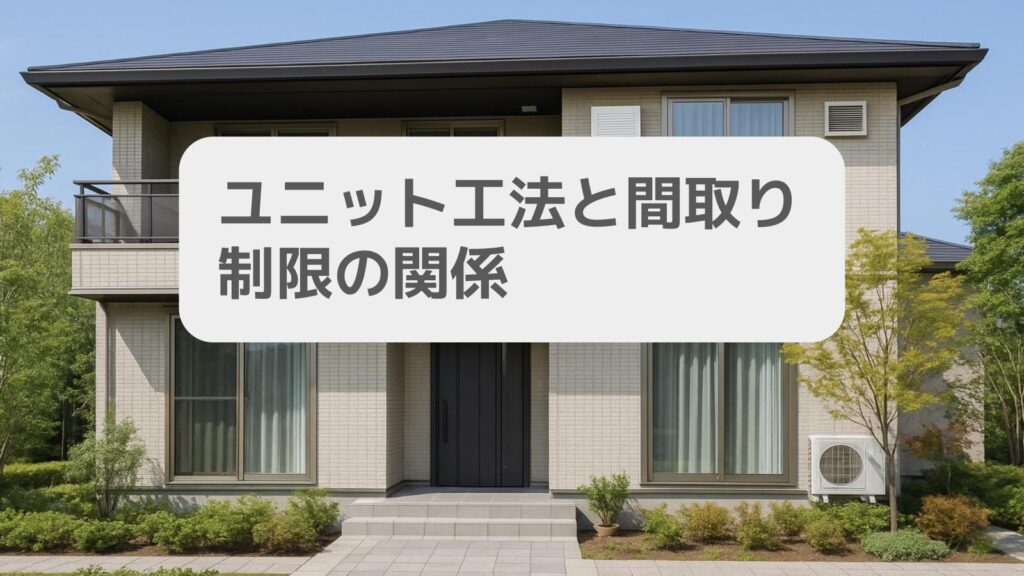
セキスイハイムではユニット工法という独自の構造を採用しています。これは工場であらかじめ製造された箱型のユニットを現地で組み合わせて家を建てる方式です。
このため、間取りには一定の制限が生じます。特に壁や柱の位置は、ユニットの規格に合わせて設計されるため、自由な間取り変更が難しい場合もあります。たとえば、キッチンを広げたいと思っても、ユニットの接合部分が干渉してしまうことがあります。
ただし、最近ではユニットを前後左右に少しずらして配置する「シフトジョイント工法」によって、従来よりも自由度の高い設計が可能になっています。
これにより、変化のある外観や、採光を確保しやすいレイアウトなどが実現できるようになりました。
タウンライフ家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
ユニットずらしと施工ミスの注意点
ユニットをずらすことで間取りや外観に変化をつけることができ、設計の幅が広がります。しかし一方で、この自由度が高まる分、施工時に生じるリスクも増えるため、慎重な判断と丁寧な施工が欠かせません。
特に注意したいのは、ユニットの接合部で水平がしっかり取れていない場合です。接続がずれてしまうと、後々になって床に傾きが出たり、壁にひび割れが発生するなど、建物全体の歪みにつながる可能性があります。これは住み心地に直結する深刻な問題であり、放置すれば補修にも時間と費用がかかる恐れがあります。
また、ユニットとユニットの間に段差があると、そこに施工されるフローリングや建具がきちんと収まらず、隙間ができたり、開閉がスムーズにいかなくなったりといった不具合が生じることもあります。とくに建具まわりは日常的に使う箇所なので、わずかなズレでもストレスに感じてしまうことがあります。
このような施工ミスを未然に防ぐためには、事前の現場調査が非常に重要です。図面の段階でユニットの配置がどのようになるかを確認し、現場では水平器やレーザー機器を使って精度の高い設置が行われているかをチェックすることが求められます。
さらに、施工後には必ず立ち会い確認を行い、目視や触感で接合部や床の状態に違和感がないかを確認してください。できればその場でスマートフォンなどを使って写真を撮っておくと、後から状況を正確に伝えやすくなります。こうした小さな積み重ねが、後々のトラブルを防ぐ大きな手助けになります。
ユニット間の階段はなぜ小さい?
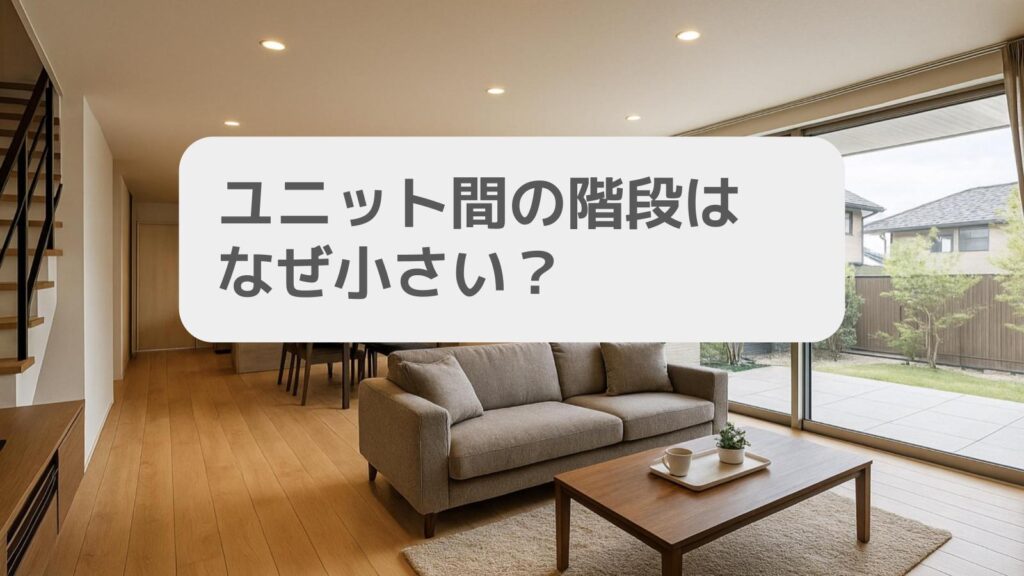
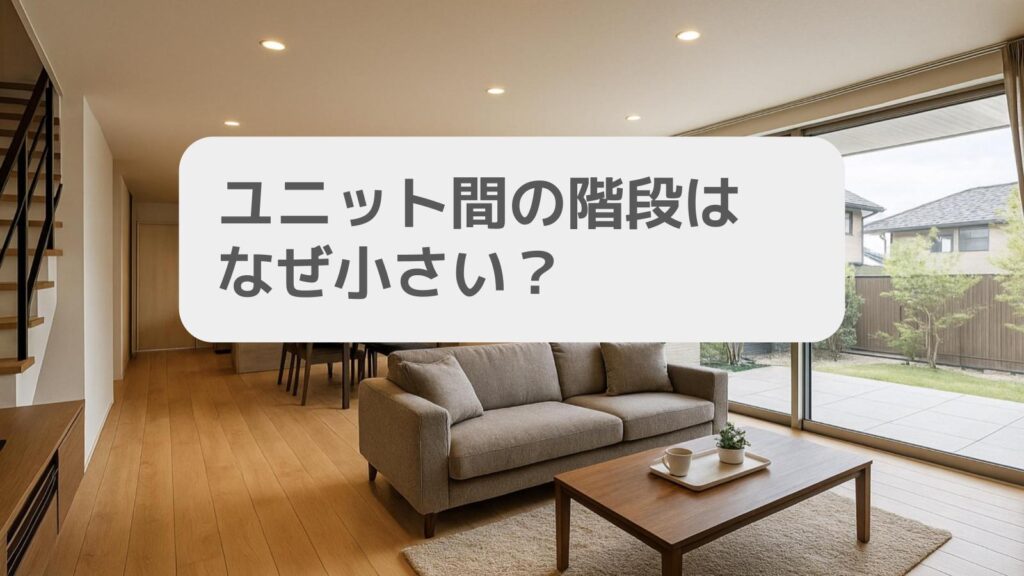
セキスイハイムの階段が他社と比べてややコンパクトに感じられるのは、主にユニット工法による設計制約があるためです。ユニット工法では、あらかじめ工場で製造された直方体の構造体(ユニット)を現場で組み合わせるため、内部の空間もこの規格に沿って設計されます。
通常、階段は1階と2階を繋ぐようにユニットにまたがって設置されます。しかし、階段を設置できるスペースはユニットの接合部分や構造の制限によって制約を受けやすくなっています。結果として、階段の踏板幅が狭くなったり、傾斜がやや急になったりするケースが見られるのです。
また、階段部分は工場である程度まで組み立てられてくることが多く、現場での微調整には限界があります。そのため、柔軟な階段設計がしづらく、標準仕様の範囲内で調整されることになります。
ただし、これは決して安全性を犠牲にしているわけではありません。建築基準法の規定に従って、安全性や強度は十分に確保されています。それでも「階段の幅をもっと広くしたい」「ゆるやかな勾配にしたい」といった希望がある場合は、早めに設計段階で相談しておくことが重要です。
オプションで踊り場を設ける、ステップ数を増やすことで傾斜をゆるくするといった工夫も可能な場合があります。さらに、見た目の開放感を演出するために手すりのデザインや素材を変更するのも一つの方法です。
こうした階段のサイズやデザインに関する調整は、ユニット構造という制限の中でも工夫の余地があります。希望する階段の形状がある場合は、早い段階で担当者に伝え、実現可能な範囲を一緒に検討することが、後悔しない家づくりのために大切です。
天井裏の空間と設備の制約
セキスイハイムの住宅においては、フラットな屋根構造、いわゆる陸屋根(りくやね)を採用しているため、屋根と天井の間に天井裏のスペースがほとんどないという点が大きな特徴です。この構造は断熱性や耐震性に優れているというメリットがある反面、居住後に設備を追加・変更する際にはいくつかの制約を伴います。
通常の戸建住宅では、屋根裏にある程度の空間が確保されており、そこを配線・配管の通り道として活用したり、小規模な収納スペースとして使ったりすることが可能です。しかしセキスイハイムの場合、このような空間がほぼ存在しないため、後から天井に何かを設置したいときに大きなハードルとなります。
例えば、ダウンライトや天井埋め込み型スピーカーを後から取り付けたいと考えても、天井裏の高さが十分でないと、配線のルートを確保するのが非常に困難です。場合によっては、天井を一部解体する必要が出てきてしまうこともあり、追加工事費がかさむ要因になります。
また、換気設備や空調のダクトを通す場合にも、狭いスペースに無理やり収める形になりやすいため、空気の流れがスムーズでないなど、機能面での不具合が発生する可能性があります。さらに、将来的に点検やメンテナンスを行いたいときにも、人が入れるほどのスペースがないため、対応に制限が出てくる点にも注意が必要です。
このような状況を避けるには、契約時や設計段階で「どこに何を設置するか」「将来どのような設備を追加したいか」といったビジョンをしっかり共有し、必要があればオプション対応を選んでおくことが大切です。天井裏スペースを確保する仕様に変更できるか、あらかじめ相談してみるのも良い方法です。
こうした配慮ができれば、完成後の住まいに対してより満足感が得られるだけでなく、将来的な設備拡張の自由度も高まります。セキスイハイムの特徴を理解し、その上で計画的に設計することで、天井裏という“見えない空間”も快適な住まいづくりの一部として有効活用できるようになります。
セキスイハイムの水切り処理とは
水切りとは、外壁や基礎、屋根などの継ぎ目部分から雨水が建物内部に浸入しないようにするための、非常に重要な部材や処理のことを指します。一般的な住宅では、外壁の下端やサッシ周り、屋根の接合部などに設けられ、水はけを良くする役割を担っています。
セキスイハイムの住宅においては、伝統的な「土台水切り」が設置されていないことも珍しくありません。これは、一見すると不安に思えるかもしれませんが、実はセキスイハイムならではの構造的な理由によるものです。同社が採用するユニット工法では、建物を箱型のユニットで構成し、それらを現場で組み上げる方式を取っているため、各ユニット間の密閉性が高く、そもそも雨水が入りにくい構造となっています。
このような構造を前提にしているため、従来の住宅に必要だった水切りの一部は省略可能であり、その代わりとして「中間水切り」や「専用のジョイントカバー」といった、ユニット特有の雨仕舞部材が使われています。これにより、ユニット間で発生する段差や継ぎ目部分からの雨水の侵入を効率的に防いでいるのです。
しかし、このシステムが機能するのは、設計通りに施工が行われていることが前提です。実際には、わずかな施工ミスやコーキングの不備などが原因で、水切り部に水が溜まり、時間とともに外壁内部に浸透してしまうケースもあります。さらに、長期間メンテナンスされていない場合には、ゴミの堆積や部材の劣化により排水性能が低下するリスクも考えられます。
こうしたトラブルを防ぐためにも、定期的な目視点検はもちろん、外壁や水切りの接合部に浮きやひび割れが見られた場合は、すぐに専門業者に相談することをおすすめします。特に築10年を超える住宅では、雨仕舞部のチェックを重点的に行うことで、将来的な雨漏りや構造体の腐食リスクを大幅に減らすことができます。
セキスイハイムの水切り処理は、その独自工法に根ざした合理的な構造ですが、だからといって完全にメンテナンス不要というわけではありません。むしろ「高気密・高断熱」という性能を長く維持するためには、こうした細かな部分の維持管理が非常に重要となってくるのです。
音が響く家の特徴と対策
セキスイハイムの家で「音が響く」と感じる方がいる場合、その要因の多くは屋根や壁の構造、さらには断熱材や遮音材の種類と施工方法に起因していると考えられます。特にユニット工法で建てられた建物は、パネルの継ぎ目や構造体の特性によって、音の伝わり方に影響が出ることがあります。
例えば、陸屋根(フラットルーフ)構造を採用している場合、屋根裏の空間が少ないために、屋根に当たる雨音が天井を通じて室内へ届きやすいという特徴があります。特に2階に寝室を設けている場合には、深夜の雨音が気になって眠りづらく感じることもあるかもしれません。
しかし、実際のところ雨音の多くは、屋根からというよりも窓に直接打ちつけられる音による影響が大きいのです。大粒の雨が強風とともに窓に叩きつけられると、室内にその振動が響き渡ることがあります。屋根自体の遮音性能はセキスイハイムの設計上、それほど低いわけではありません。
それでも音の問題が気になる場合には、いくつかの対策を講じることで快適性を高めることが可能です。たとえば、窓には雨戸やシャッターを設置することで、物理的に雨音の侵入を抑える効果が期待できます。さらに、断熱性と遮音性を兼ね備えた厚手のカーテンを使うことも、音の軽減に役立ちます。
また、施工段階で断熱材や遮音材をグレードアップすることも一つの手です。壁や天井に使用されるグラスウールやロックウールの厚みを増したり、高性能な遮音ボードを使用したりすることで、外部からの音の伝達を抑えることができます。これは家づくりの初期段階で相談しておくことで、より柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
さらに、空間の配置や間取りにも工夫ができます。例えば、寝室の位置を窓から遠ざけたり、外壁側に収納スペースやクローゼットを配置することで、音の伝わり方を間接的に緩和させることができます。これは、外部の騒音だけでなく、室内の音漏れ対策にも有効です。
このように、セキスイハイムの家における「音が響く」といった問題は、一概に建物の欠陥とは言えませんが、居住者のライフスタイルや立地環境によっては敏感に感じられる場合もあります。事前にどのような生活を想定しているのか、どんな音環境を望むのかを明確にし、それに応じた対策を講じることで、快適な住空間を実現することができるでしょう。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
セキスイハイム ユニットずらしの実例と注意点


- 軒天と外壁に見られる施工トラブル
- グランツーユー購入後の後悔例
- 基礎やり直しが必要になるケース
- セキスイハイムの外壁は何年持つ?
- “60年持つ”は本当かを検証
- セキスイハイムの欠陥とトラブル事例
軒天と外壁に見られる施工トラブル
軒天とは、屋根の裏側にあたる部分で、外部から見える建物の仕上げの一部です。この部分は単に見た目を整えるだけでなく、屋根裏の換気を助けたり、雨風の吹き込みを防いだりするなど、建物の機能面でも重要な役割を果たしています。
セキスイハイムの軒天は、工場で生産されたユニットを現場で接合するという建築方式の特性上、ユニットの継ぎ目や出隅・入隅との取り合い部分が複雑になる傾向があります。このため、軒天と外壁の接合部分で仕上げがうまくいかない、シーリング処理が甘いなどの施工ミスが見られるケースが少なくありません。
具体的には、軒天と外壁との間にわずかな隙間が生じたり、その隙間を埋めるシーリング材が不十分だったりすると、そこから雨水がじわじわと侵入して内部構造を劣化させてしまうリスクがあります。特に雨の多い地域や風向きが変わりやすい場所では、こうした細かな部分の仕上がりが家の耐久性に大きく影響します。
また、軒天材自体が経年によって変色・はがれ・膨らみなどの症状を見せることもあります。見た目が損なわれるだけでなく、内部に水が回って木部が腐食する恐れもあるため、放置は禁物です。加えて、鳥や虫が軒天の隙間に巣を作ることで、さらに劣化が進行することもあります。
こうしたリスクを回避するためには、引き渡し時の目視確認はもちろん、定期的な点検の中で軒天の状態をチェックすることが重要です。特に外壁の塗装時期に合わせて軒天の劣化も確認し、必要に応じて塗装やシーリングの打ち直し、場合によっては部分的な張り替えといった対応を行うことで、長期的に家の健全性を保つことができます。
軽微な症状に見えても、軒天のトラブルは建物全体に波及する可能性があるため、早めの発見と対処が肝心です。万が一、異変を感じた場合は、専門業者に相談して詳しい診断を受けると安心です。
グランツーユー購入後の後悔例
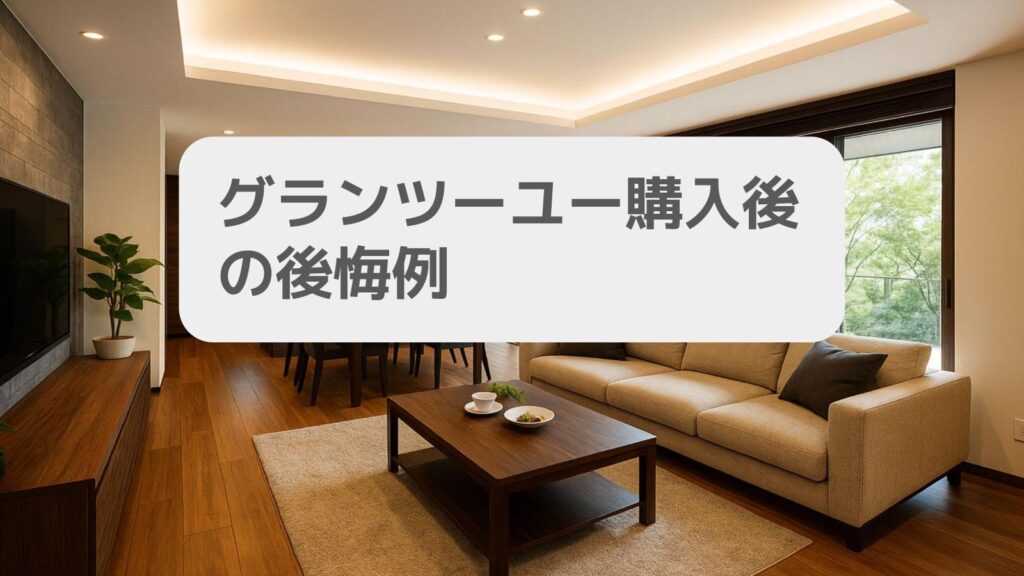
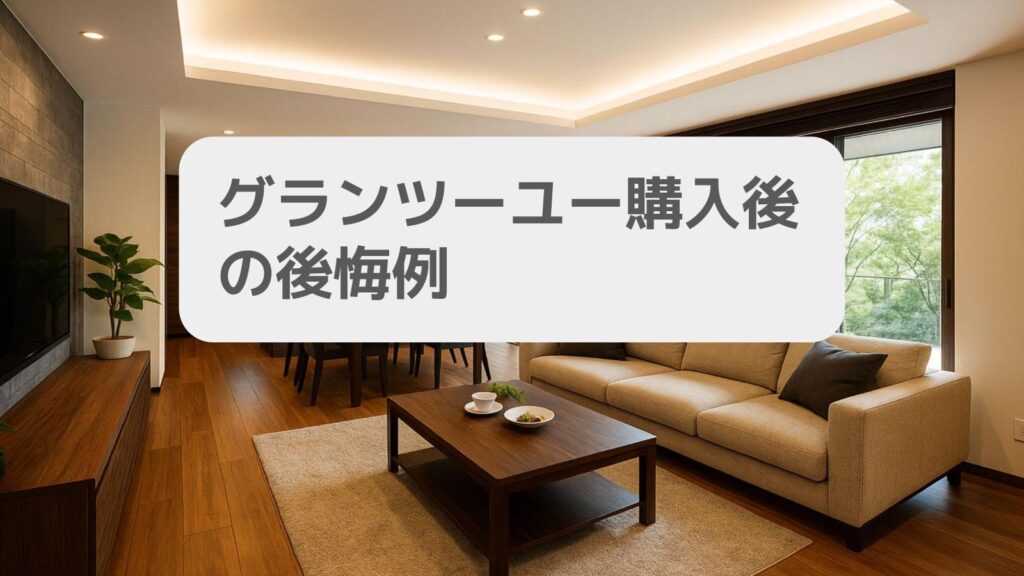
グランツーユーシリーズは、セキスイハイムが提供する木質系ユニット住宅として、多くの家庭に選ばれている人気のラインナップです。外観のデザイン性や断熱性能、ユニットによる高精度な施工などが魅力とされています。
しかしながら、実際に暮らしてみて「思っていたのと違った」と感じる方も一定数存在します。購入後の後悔の声として特によく聞かれるのが、「家鳴り」や「床のきしみ」といった音に関する問題です。家鳴りは、木造住宅特有の現象ともいえますが、夜間や静かな時間帯には特に気になりやすく、住まいの快適性を損ねる要因になり得ます。
また、内装材に使用されているフローリングやクロス、造作棚などが数年で変色したり、歪みや反りが見られたりするケースもあります。これは経年変化の一環とも言えますが、家族構成や使用環境によっては予想以上に劣化が早く感じられることも。さらに、構造面で剛性が不足していると感じられるような、壁のたわみやドアの閉まりの悪さなど、生活に支障が出るような症状を訴える方もいます。
特に木質構造は湿気や乾燥の影響を受けやすいため、地域の気候条件や建築時期によっても差が生まれやすいです。そのため、あらかじめ「どんな素材が使われているか」「メンテナンスの頻度はどれくらいかかるのか」といった点について理解を深めておくことが、満足度の高い購入につながります。
これらのトラブルを未然に防ぐには、契約前に実際にグランツーユーに住んでいるオーナーの話を聞いたり、完成後の実邸を訪問して細部まで観察することが非常に有効です。また、SNSやブログなど、リアルな使用感が記録されている情報も参考になります。パンフレットや展示場だけでは分かりづらい点も多いため、できるだけ多角的に情報を収集する姿勢が大切です。
そのうえで、気になることがあれば営業担当者や設計担当者に遠慮なく質問し、納得できるまで確認することが、後悔しない家づくりへの第一歩となるでしょう。
基礎やり直しが必要になるケース
ユニット工法とはいえ、建物を支える基礎の施工精度が極めて重要であることは言うまでもありません。どれほど高性能な構造体を用いていても、基礎が正確に施工されていなければ、その上に建てられる建物全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。
とくに注意したいのは、地盤の状態に関する見落としや、基礎工事時のちょっとした施工ミスです。地盤が不均一であるにも関わらず、それに応じた補強や改良がなされていなかった場合、建物全体にゆがみが生じる恐れがあります。ユニットを設置した際に、基礎にわずかな傾斜があるだけで、ユニット間の高さにズレが生まれてしまい、段差ができる原因になります。
この段差は、床の仕上がりに大きく影響し、歩くと違和感を覚えたり、家具の水平が取れなかったりといった実生活に不便をもたらすことがあります。また、床だけでなく、壁のクロスにシワや浮きが見られるようになったり、ドアや引き戸の開閉に不具合が出るなど、さまざまなトラブルを引き起こすことも少なくありません。
これらの問題が発覚した際、状況によっては部分的な補修で済むこともありますが、根本的に解決するには基礎そのものをやり直さなければならない場合もあります。基礎をやり直す工事には、既に設置したユニットの一時撤去が必要になることもあり、非常に大きな手間と費用が発生します。
そのため、着工前には必ず詳細な地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良工事を施すことが強く推奨されます。また、基礎工事完了後には、現場監督や第三者機関による水平確認や耐圧検査を行い、問題がないかを十分にチェックすることが重要です。少しでも不安を感じた場合は、遠慮せずに確認を求める姿勢も、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
初期段階の「基礎」に対する対策と意識が、家全体の品質と安心感を支える大きな土台となるのです。
セキスイハイムの外壁は何年持つ?
外壁の耐久年数は、使用されている塗料の種類や外壁材の性能、さらに日々の気候条件や住まい方、メンテナンスの頻度によって大きく異なってきます。つまり、どれだけ外壁が持つかは、一概に「何年」と断定できるものではなく、複数の要素が複雑に絡み合って決まるのです。
セキスイハイムが採用している標準的な外壁材は、一般的に15年から20年程度が再塗装や点検の目安とされています。これはあくまで平均的な数値であり、周囲の環境やメンテナンス状況によって短くなることも、逆にもう少し長持ちすることもあります。
たとえば、海沿いや山間部など、塩害や強風、頻繁な雨にさらされるようなエリアでは、外壁へのダメージが蓄積しやすく、劣化のスピードが速くなる傾向にあります。このような地域では、10年を過ぎたあたりからこまめな点検を始め、必要に応じて補修や塗装の検討をするのが安心です。
具体的な劣化のサインとしては、塗装面の色あせや、指で触れると白い粉が付着する「チョーキング現象」、外壁のひび割れやシーリングの剥がれなどが挙げられます。これらの症状が見られたら、放置せずにできるだけ早めに専門業者に診断を依頼することが重要です。小さな劣化を見逃すと、後々の補修費用が膨らむ可能性もあります。
また、セキスイハイムでは、外壁の張替えではなく再塗装によるメンテナンスが前提とされている場合が多く、塗料の選択によって次のメンテナンス時期が大きく変わることもあります。例えば、シリコン系やフッ素系など耐久性の高い塗料を使用すれば、メンテナンス周期を延ばすことが可能になります。
定期点検はこうした外壁の状態を見極めるうえで非常に有効です。セキスイハイムでは点検制度が整備されており、プロによるチェックを受けることで、素人では見落としがちな小さな異常も早期に発見できます。
結果として、外壁の美観や防水性能を長く保つためには、耐久年数の目安だけに頼るのではなく、日々の観察と定期的な専門点検を組み合わせて、適切なタイミングでメンテナンスを実施することが何より大切です。
“60年持つ”は本当かを検証
セキスイハイムでは「60年サポートシステム」という長期保証制度を打ち出しており、一定期間ごとに住宅の状態を確認し、必要に応じた点検や有償メンテナンスを行うことで、住まいの品質と安心を長く保つことを目指しています。
一見すると、家自体が60年間問題なく持続するような印象を与えがちですが、実際にはこの制度は“60年間なにもしなくても大丈夫”という意味ではありません。むしろ、定期的な点検やメンテナンスを前提とすることで初めて、長寿命住宅としての価値を維持できる仕組みとなっています。
たとえば、5年・10年・20年といった節目で実施される点検では、外壁や屋根の劣化状況、シーリングの剥がれ、水回り設備の不具合、構造部分の損傷などを細かくチェックします。必要に応じて外壁の再塗装やシーリングの打ち替え、屋根材の補修、給湯器や換気扇の交換といった有償工事を行うことが推奨されます。
こうした対応を計画的に続けていくことで、家は「安全で快適に暮らせる状態」を長期間維持することが可能になるのです。つまり、60年サポートというのは“建物の寿命が60年”という意味ではなく、“住まいの性能を60年間維持できるよう支援する仕組み”と理解するのが正しい捉え方と言えます。
また、60年サポート制度を利用するには、あらかじめ点検契約を締結しておく必要がありますし、有償でのメンテナンス工事を適切なタイミングで実施しなければ、その後の保証対象から外れることもあります。したがって、制度のメリットを十分に享受するためには、費用面や将来的な修繕計画も視野に入れておくことが重要です。
近年では、建物の資産価値を保つ観点からも定期メンテナンスが注目されています。とくに将来的に売却や相続を検討する場合、適切に管理された住宅の方が評価されやすく、トラブルのリスクも低くなります。60年サポートを活用することで、そうした長期的な住まいの価値も守ることができるのです。
このように、セキスイハイムの「60年持つ」という表現は単なるキャッチコピーではなく、実際には住まい手が積極的に管理・維持していくことを前提とした、長期品質保証の仕組みであると理解しておきましょう。
セキスイハイムの欠陥とトラブル事例
「欠陥住宅」とまでは言わないものの、セキスイハイムの家でもさまざまなトラブルが起こる可能性があることは否定できません。特に工場生産と現場組立という二段階に分かれた施工方式を採用しているため、それぞれの工程で細かな不備が発生するリスクが存在します。
代表的な事例としてよく挙げられるのは、床の不陸(表面の波打ちや傾き)、ユニット接合部の段差、配管設計ミスによる水漏れなどです。床の不陸に関しては、日常生活の中で椅子や家具がガタついたり、視覚的に違和感を覚えることがあり、居住者のストレスの原因になることもあります。これらの不具合は施工初期の段階で生じるケースが多く、完成後しばらく経ってから気づくことも珍しくありません。
さらに、配管や電気設備の設置ミスが見つかった場合、見えない部分での修繕が必要となり、壁や床を一部開口して作業を行うこともあります。これによって、入居後に再工事が必要となると、生活に支障が出るだけでなく、精神的な不満にもつながります。
また、目に見える不具合だけでなく、構造的なズレや断熱材の施工不良など、気づきにくい問題も潜んでいることがあります。たとえば、ユニット接合部の隙間に気密処理が不十分であれば、室内の温度が安定せず、冷暖房効率が下がる原因になります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、引き渡し前の立ち会いチェックが極めて重要です。この段階で床や壁の水平状態、設備の設置状況、仕上げの精度などをしっかり確認することで、施工ミスを早期に発見できる可能性が高まります。また、引き渡し後に気づいた点についても、遠慮せずに担当者に伝えることが大切です。
小さな違和感でも「気のせいかも」と見過ごさず、必要に応じて記録や写真を残しておくと後々のやり取りがスムーズになります。定期点検の際にも、気になる箇所を具体的に指摘することで、早期修繕につながる可能性があります。
セキスイハイムのような大手ハウスメーカーであっても、完全にミスをゼロにすることは難しいのが現実です。だからこそ、施主自身が適切に情報を集め、確認と対応の姿勢を持つことが、安心・快適な住まいを維持するための大きな鍵となるのです。
セキスイハイム ユニット ずらす施工の要点まとめ
- ユニット工法は工場生産された箱型ユニットを現場で接合する方式
- 間取り設計にはユニット規格による制限がある
- ユニットをずらすことでデザインや採光の自由度が増す
- 「シフトジョイント工法」により空間設計の幅が広がる
- 接合部の水平精度が悪いと建物全体に歪みが出る
- 段差のある施工ではフローリングや建具に不具合が生じる
- 施工ミス防止には現場確認と立ち会いチェックが重要
- 階段はユニット構造上コンパクトになりやすい
- 標準仕様内では階段設計の自由度に限りがある
- 天井裏のスペースが狭く配線や設備追加に制限がある
- 水切り処理はユニット間の密閉性を前提とした構造になっている
- 雨仕舞部のトラブルを防ぐには定期的な点検が有効
- 陸屋根構造では雨音が2階に響きやすい可能性がある
- 遮音対策としては窓シャッターや厚手カーテンが有効
- 事前に施工や構造の制約を理解することが後悔回避の鍵となる
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/



セキスイハイムで後悔したくない人は下の記事もチェックしてください。
評判
設備
- セキスイハイムの全館空調ってどう?気になる電気代やデメリットの口コミ紹介
- セキスイハイムの外壁で人気の種類は磁器タイル!塗り替え不要で美しい
- セキスイハイムのハイドア検討中なら見て!施工事例や価格相場を紹介
- セキスイハイムの床材の種類や種類|どんな人におすすめか選び方紹介
- セキスイハイムにサンルームを後付けしたい!リフォーム費用や日数は?
- セキスイハイムの新築でベランダなしってどう?リフォームできる?
- セキスイハイムのお風呂どれを選ぶか|気になるリフォーム費用も
- セキスイハイムの2階は暑い!?快適エアリーや24時間換気ならエアコンいらない?
メンテナンス・トラブル
- セキスイハイムのメンテナンス費用は年間5万〜10万円|外壁・屋根・定期点検について
- セキスイハイムの断熱材にカビが!?新築でも鉄骨内部で結露すればカビが発生
- セキスイハイムで新築なのにゴキブリ!?快適エアリーから虫が入り込むのか
間取り

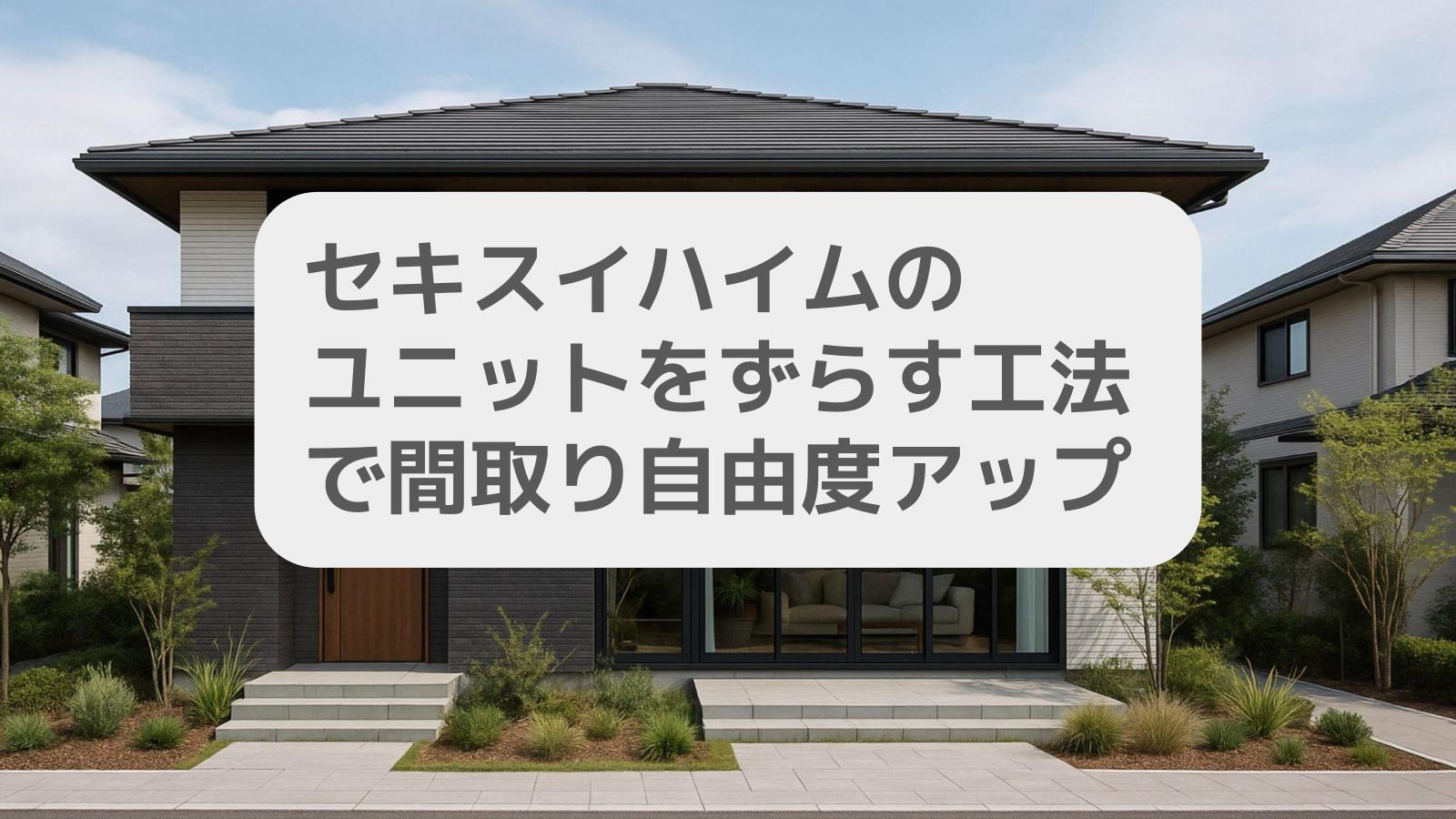



コメント