 著者
著者タウンライフの一括見積もり
「工務店に見積もり
この記事では、工務店が見積もりを嫌がる背景や、見積の内訳を出せないと言われたときの対応、さらには相見積もりがばれることはあるのかといったリアルな実情を分かりやすく解説していきます。
また、「ハウスメーカーの見積もりがおかしい」と感じるケースや、「注文住宅の見積もりでトラブルが起きた」といった体験談にも触れながら、見積もりをスムーズに進めるためのヒントをお届けします。
他にも、「相見積もりは意味ないのでは?」「工務店の見積もりは何社が頼んだらいいですか?」「工務店の見積もりはどれくらいの期間かかりますか?」「工務店の見積もりはいくら値引きしてくれますか?」「工務店の見積もりを取る流れは?」など、見積もりに関するよくある質問にも具体的にお答えします。
見積もりが出ないのは違法なのか?といった法律的な観点から、見積もり書類の確認ポイントまで、これから家づくりやリフォームを検討する方にとって知っておくべき内容をまとめました。
初めての方にもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。



10,000戸以上の戸建を見てきた戸建専門家のはなまる(X)です。不動産業界における長年の経験をもとに「はなまる」なマイホームづくりのための情報発信をしています。
ハウスメーカー・工務店から見積もりや間取りプランを集めるのは大変。
タウンライフ家づくりなら1150社以上のハウスメーカー・工務店から見積りと間取りプランを無料でGET!
\理想の暮らしの第一歩/
▶︎タウンライフ家づくり公式のプラン作成へ【完全無料】
\この記事を読むとわかることの要点/
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| なぜ見積もりを出さない? | 作成に手間がかかる・契約確約がなくタダ働きになるリスクがあるため |
| 小規模工務店の事情 | 人手不足・営業と現場兼任で時間が取れないケースが多い |
| 相見積もりの影響 | 過去に“当て馬”扱いされた経験から慎重になっていることがある |
| 「一式」表記のリスク | 内容が不明確で後から追加費用が発生する恐れがある |
| 見積内訳を出せない理由 | 仕様が未確定、過去に情報を流用されたなどの背景がある |
| 違法かどうか | 見積もりを出さないこと自体は違法ではない |
| 注意すべき契約前行動 | 詳細な内訳なしで契約を急かされる場合は要注意 |
| 注文住宅での見積トラブル | 契約後に高額な追加費用が発生するケースがある |
| ハウスメーカーとの違い | 営業と設計が分離しており、見積もりに齟齬が出ることがある |
| 相見積もりはばれる? | 業者同士のつながりでばれる可能性が高い |
| 相見積もりは意味ない? | 条件を統一すれば比較に有効。ただし依頼方法に注意 |
| 見積もりは何社に依頼? | 2〜3社が比較しやすく、やり取りの負担も少ない |
| 見積もりの期間目安 | 簡単なものは数日、大規模工事は1〜3週間程度 |
| 値引き交渉のポイント | 他社との比較や予算を示し、誠実に相談することが大切 |
| 信頼できる業者の見極め方 | 見積内訳の明確さ・対応の丁寧さ・説明力をチェック |
工務店が見積もりを出さない理由とは
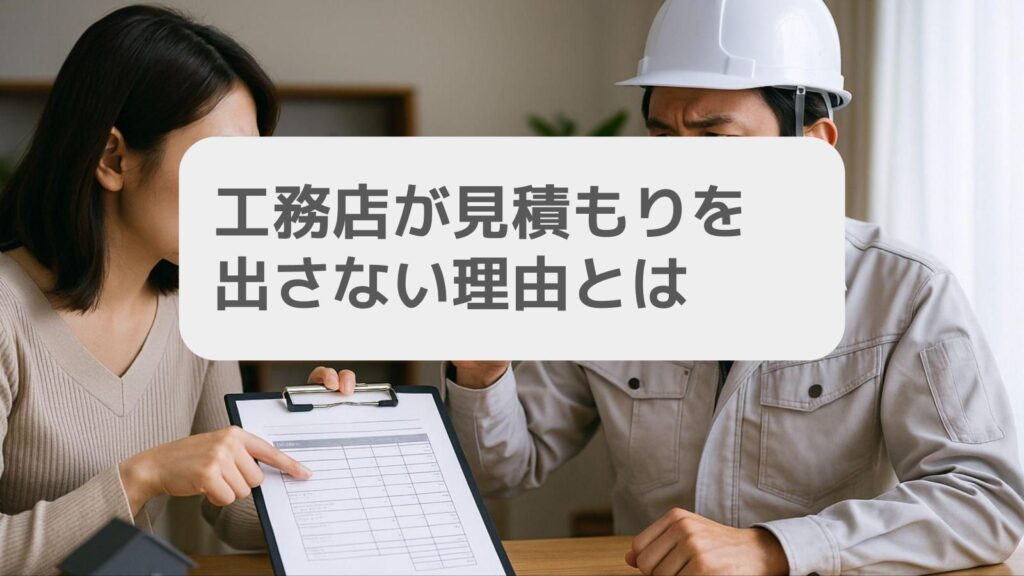
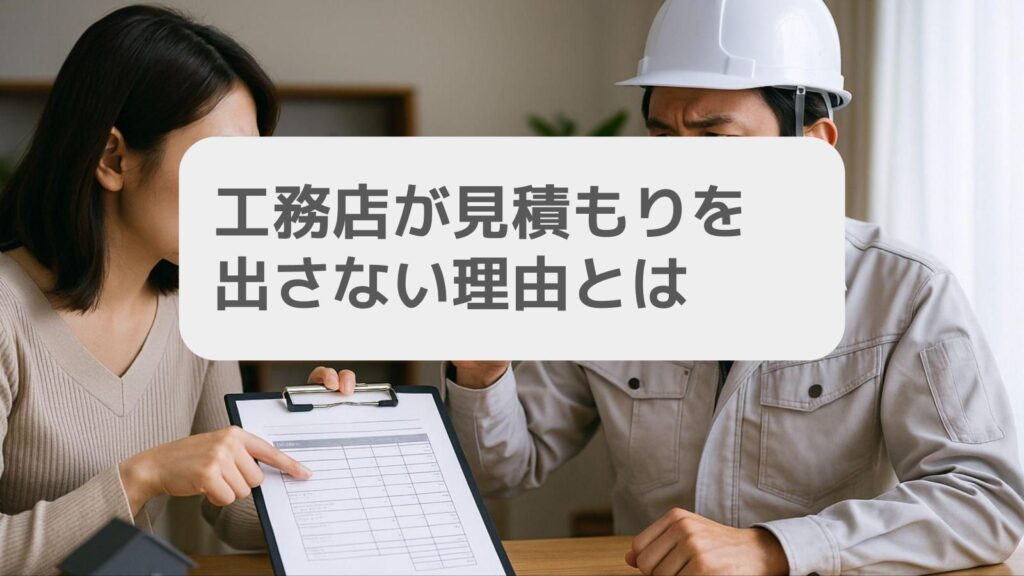
- 工務店が見積もりを嫌がる本音とは?
- 見積書「一式」表記のリスクと注意点
- 見積の内訳が出せないと言われたら?
- 見積もりを出さないのは違法なのか?
- 注文住宅での見積もりトラブル事例
- ハウスメーカーの見積もりが不自然な理由
工務店が見積もりを嫌がる本音とは?


工務店が見積もりを出し渋る背景には、いくつかの複雑な事情があります。まず、見積書を丁寧に作成するには、現場の確認、工法の検討、必要な資材の選定、人件費や輸送費などの積算といった作業が含まれます。
これらは非常に手間がかかるうえに、発注につながる保証がないため、業者にとっては「タダ働きになるかもしれない」という大きなリスクを抱えているのです。特に人員に余裕がない地域密着型の小規模な工務店では、その負担がより重くのしかかります。
また、過去に相見積もりに応じたものの、単なる“当て馬”として扱われて不快な思いをしたという経験を持つ工務店も少なくありません。このような出来事が重なると、せっかく見積もりを作成しても最初から他社に決まっているのでは?という不信感が生まれ、結果的に新たな見積もり依頼に対しても慎重にならざるを得なくなるのです。
さらに言えば、工務店の多くは営業と現場を兼務しており、見積作成にかける時間が確保しづらいという現実もあります。
お客様への説明資料を揃えたり、他社と価格競争するために細かい調整をしたりと、意外と裏方の業務が多いため、利益に直結しない案件については後回しになるケースも多いのです。このような事情から、工務店が見積もりを嫌がるのは、単なるわがままではなく、業務負担と過去の経験に基づく慎重な判断といえるでしょう。



タウンライフの一括見積もりなら、全国1160以上の工務店を含む優良企業の見積もりを無料ですぐ取得できます。嫌な思いをしたくない人に選ばれてます。
見積書「一式」表記のリスクと注意点


「一式」という言葉が見積書に並んでいると、一見シンプルでわかりやすく感じるかもしれません。特に工事内容について詳しくない方にとっては、「全部まとめてやってくれるのかな?」という安心感すらあるかもしれませんね。でも実際には、この「一式」表記がトラブルの火種になることが少なくありません。
なぜなら、「一式」とだけ記載されていると、工事の具体的な内容や施工範囲、使われる資材の種類や数量などが不明確になります。そのため、完成後に「この作業は含まれていませんでした」「追加費用が発生します」と言われる可能性が高くなります。特に電気工事や給排水工事など、目に見えにくい部分の工事では注意が必要です。
例えばエアコンの取り付けで、電気配線が既存の回路から無理やり分岐されていた場合、使用時にブレーカーが落ちるなどのトラブルが起こるかもしれません。それが「電気工事一式」としか記載されていないと、どのような施工がなされたのかを後から確認することが難しくなってしまいます。
このように考えると、見積もりを依頼する際には「一式」表記だけではなく、必ず内訳が記載された明細付きの見積書をお願いすることがとても大切になります。さらに2社以上から見積もりを取って比較することで、それぞれの工事内容の違いや費用感も見えてきます。
また、「内訳を出せない」と言われた場合は、工事の透明性やその業者の信頼性について再検討してみても良いかもしれません。信頼できる業者であれば、手間がかかってもできる限り丁寧に説明しようとしてくれるはずです。
最終的に安心して工事を任せるためにも、見積書の記載内容をしっかりとチェックする意識がとても大事です。
見積の内訳が出せないと言われたら?


「内訳は出せません」と業者に言われたとき、多くの人は戸惑ってしまいますよね。でも、まずは感情的にならずに、落ち着いて状況を受け止めましょう。大切なのは、なぜ内訳を出せないのか、その理由を丁寧に尋ねることです。
実際には、業者側にもそれなりの事情があることがあります。例えば、「まだ仕様が確定しておらず、細かな見積もりが出せない」といったケースや、「過去に提出した見積もり内容を別業者に流用された経験があり、慎重になっている」といった事情が背景にあるかもしれません。つまり、すぐに悪意があるとは限らないのです。



とはいえ、早く見積もりが欲しいですよね。タウンライフの一括見積もり
このようなときには、説明の内容に納得できるかどうかが大きな判断ポイントになります。誠実な業者であれば、こちらの不安を汲み取り、できる限りわかりやすく理由を説明してくれるはずです。一方で、曖昧な言い回しや答えをはぐらかすような返答、もしくは高圧的な態度が見られる場合は注意が必要です。
さらに、見積もりの透明性に対して消極的な姿勢がある場合、その後のやり取りでもトラブルが生じやすくなります。そういった兆候が見えた時点で、依頼先として本当に信頼できるのかを再検討してみるのも一つの手です。
どうしても不安が残るようであれば、「できる範囲で構わないので、分かる部分だけでも内訳を提示してもらえますか?」と提案してみても良いでしょう。それでも対応が難しいと言われた場合は、他の業者への見積もり依頼も並行して行い、比較検討することをおすすめします。
結局のところ、工事という大きな買い物を安心して進めるためには、納得と信頼が欠かせません。見積もりの段階から不信感があるようであれば、その後の工程でも同じようにストレスがかかってしまう可能性が高いのです。
見積もりを出さないのは違法なのか?
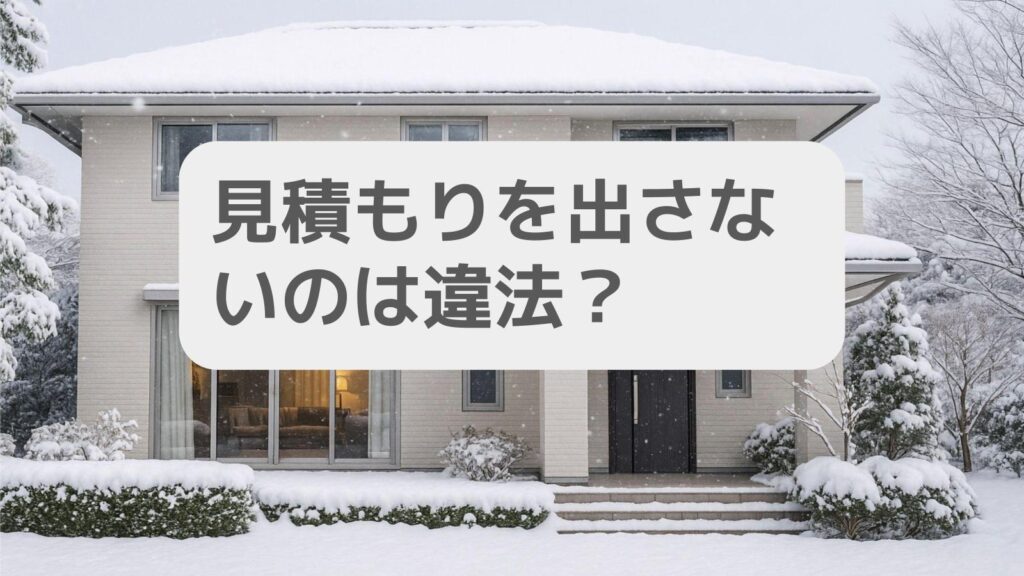
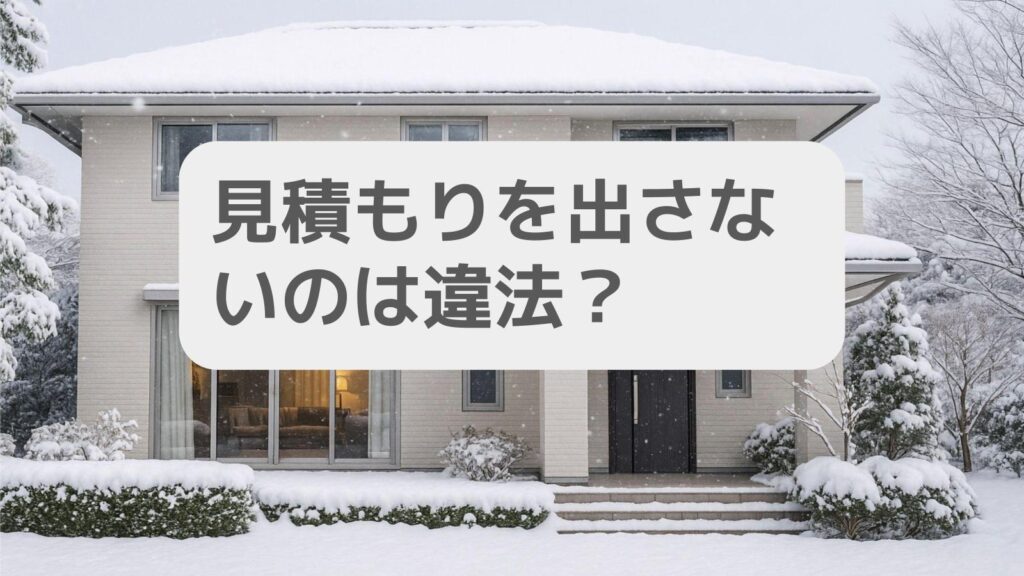
実際のところ、工務店が見積もりを出さないこと自体は違法ではありません。見積書の提示は日本の法律で義務づけられているわけではなく、どちらかといえば商慣習として行われているものです。つまり、業者が見積書を出さなかったからといって、すぐに法的な処罰の対象になるわけではないのです。
ただし、これはあくまでも“見積もりを出さない”という行為そのものに関しての話です。問題なのは、見積もりを出さないことで顧客が不利益を被った場合や、業者側が不誠実な契約手続きを行った場合です。たとえば、契約の直前になって「実はこの工事も必要でした」と金額を大きく上乗せされたり、「詳細はあとで出します」と言いながら契約を急がせるような対応をされたりするケースです。
このような場合、消費者契約法や景品表示法、さらには民法の契約に関する条文に触れる可能性もあります。特に、見積内容が不明確なまま契約を交わしてしまい、後から追加料金を請求されたり、工事内容が当初の説明と異なっていた場合は、「情報提供義務違反」や「不実告知」にあたるとして問題視されることがあります。
このため、たとえ法律上は義務でなくても、業者に対しては見積書の提出やその内容の明確な説明を求めるのが大切です。また、見積書がない状態で契約を進めることには大きなリスクがあるという認識を持っておくことも重要です。特に初めて住宅関連の契約をする方は、書面での確認を怠らず、わからない点はしっかり質問することを心がけましょう。
納得できないまま進めてしまうと、後から「そんな話は聞いていない」「契約内容が違っていた」といったトラブルに発展する可能性が高まります。結果として、精神的にも金銭的にも大きな負担を背負うことになりかねません。見積もりは契約前の重要な判断材料であるということを意識して、しっかりと確認する姿勢が大切です。
注文住宅での見積もりトラブル事例
注文住宅において、見積もりに関するトラブルは決して珍しいものではありません。その中でも特に多いのが、「契約後に追加費用が発生した」というケースです。これは住宅建築という複雑なプロジェクトの性質上、起こりやすい問題とも言えます。
たとえば、ある家庭では契約後に「構造計算の見直しが必要になった」と言われ、当初の見積もりに対して250万円もの増額を請求されたという事例がありました。これは最初の段階での見積もりが十分に精査されておらず、結果的に計算ミスや仕様の変更が後から発覚したために発生したものです。こうした誤差は、業者側の経験不足や確認不足に起因することもあり、契約前にどこまで詰められていたかが問われます。
さらに、トラブルの原因として多いのが「設備のグレードアップ」や「土地の地盤補強」といった、施主側が希望した追加工事が適切に反映されていなかった場合です。最初の見積もりでは入っていなかった工事が、後から必要になって金額が跳ね上がるというケースも非常に多いです。
これらの問題を避けるためには、見積もりの段階で内容や金額の根拠をしっかり確認し、分からない点は遠慮なく質問することが大切です。また、「このまま契約しないと金額が上がりますよ」などと急かされるような場面では、一度立ち止まって冷静に考え直すことが重要です。
契約前にしっかりとした仕様書や図面、詳細な見積明細を提示してもらうことで、後からのトラブルを回避しやすくなります。業者の中には、契約を急ぐあまりに説明を省略したり、あいまいな言葉で濁したりするところもありますので、そういった兆候があれば一度検討を見直す勇気も必要です。
注文住宅は、人生で何度も経験することではありません。だからこそ、納得できるまで確認し、信頼できる業者と進めていくことが、成功への第一歩になるのです。
ハウスメーカーの見積もりが不自然な理由
大手のハウスメーカーであっても、見積もりに対して「なんだかおかしい」と違和感を抱くケースは決して少なくありません。特に、詳細な打ち合わせを何度も重ねた後に、急に金額が大きく跳ね上がったりするような状況は、多くの施主にとって納得しがたいものです。
このようなケースの多くは、初回に提示される見積もりがあまりにもざっくりしすぎていることが原因です。つまり、最初に提示された金額はあくまで参考価格に過ぎず、詳細が決まっていく過程でさまざまな要素が追加されていき、結果的に総額が膨らんでしまうのです。特に注意したいのが、最初の見積もりでは設備や素材のグレード、施工の複雑さなどがきちんと反映されていないことです。
たとえば、キッチンやバスルームの仕様変更、外壁の素材選び、窓の断熱性能など、少しの変更で金額が数十万円単位で変動することも珍しくありません。こういった細かな調整が積み重なることで、気が付けば当初の予算を大きくオーバーしていた、という事態になるのです。
また、大手ハウスメーカーでは営業担当と設計・見積担当が別になっていることが多く、情報の共有不足から内容にズレが生じる場合もあります。営業担当から「この内容でこの金額」と言われて安心していたのに、後から設計担当から「実はこの仕様だと追加費用がかかります」と言われるような事態も考えられます。
見積もりを受け取る際は、「これは正式な見積書ですか?」としっかり確認し、単なる仮の金額ではないことを確かめるようにしましょう。そして、各項目に対して根拠があるか、内訳が明記されているか、予備費や諸経費がどのように扱われているかなど、細部までチェックすることが重要です。
このように、見積もりに違和感がある場合は、そのまま受け入れずに一度立ち止まり、納得できるまで質問してみましょう。それが、予算内で理想の住まいを建てるための第一歩になります。
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/
工務店から見積もりを取る側が出さない時に注意すべきこと
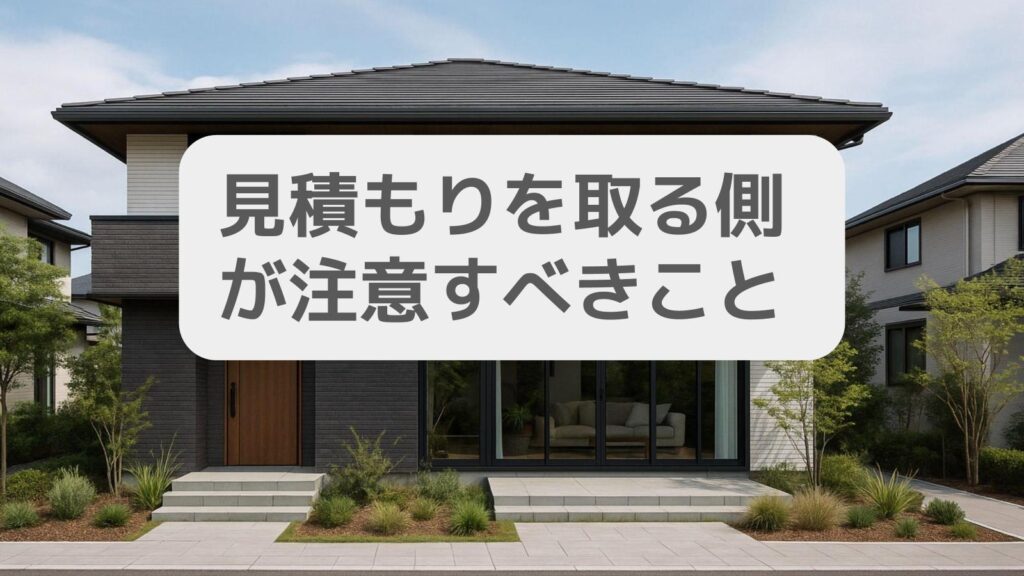
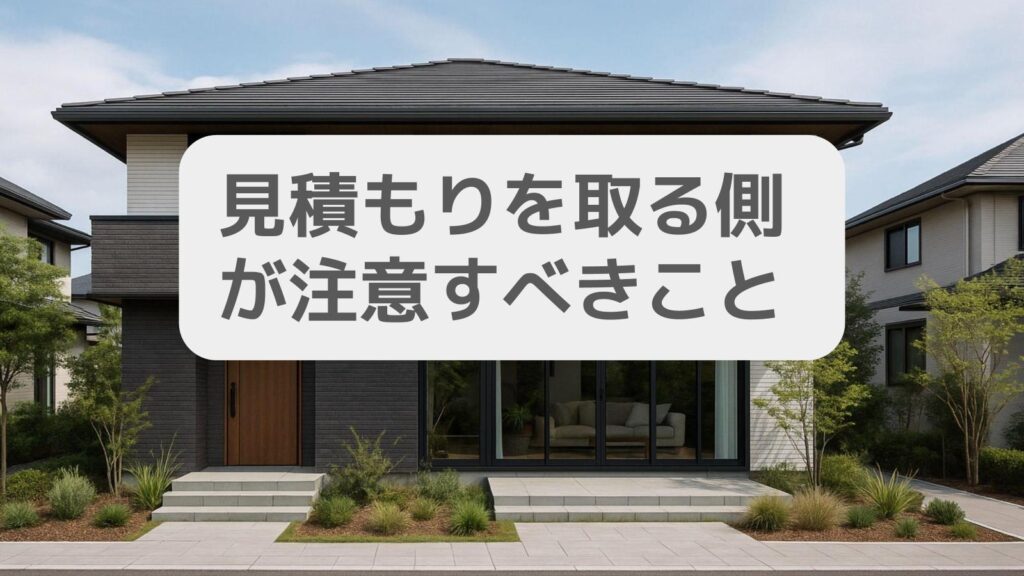
- 相見積もりはばれる?業者の反応とは
- 相見積もりは意味ないって本当?
- 工務店の見積もりを取る正しい流れ
- 見積もりを頼むのは何社がベスト?
- 工務店の見積もり期間と目安とは?
- 工務店の見積もりでの値引き交渉術
相見積もりはばれる?業者の反応とは
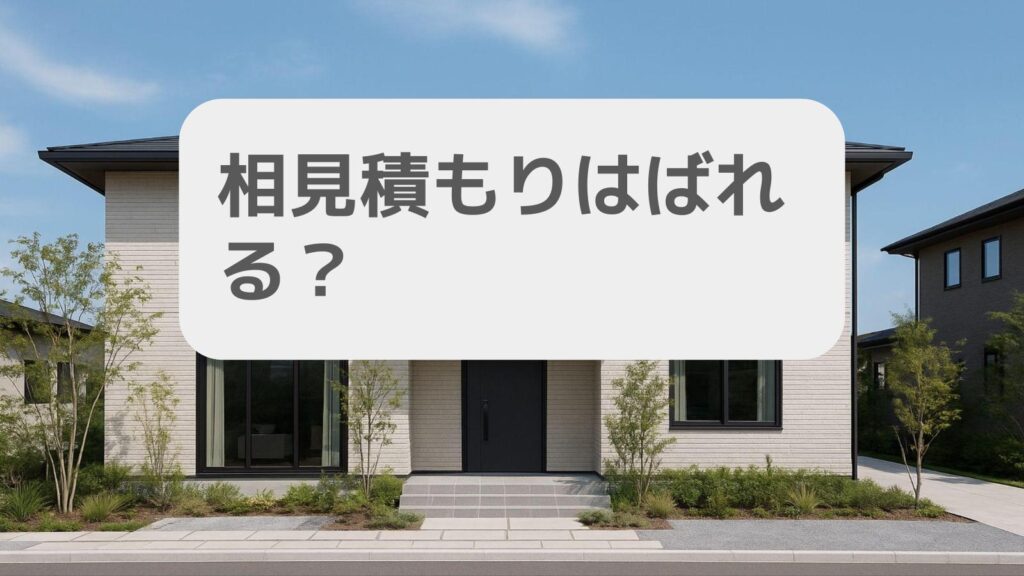
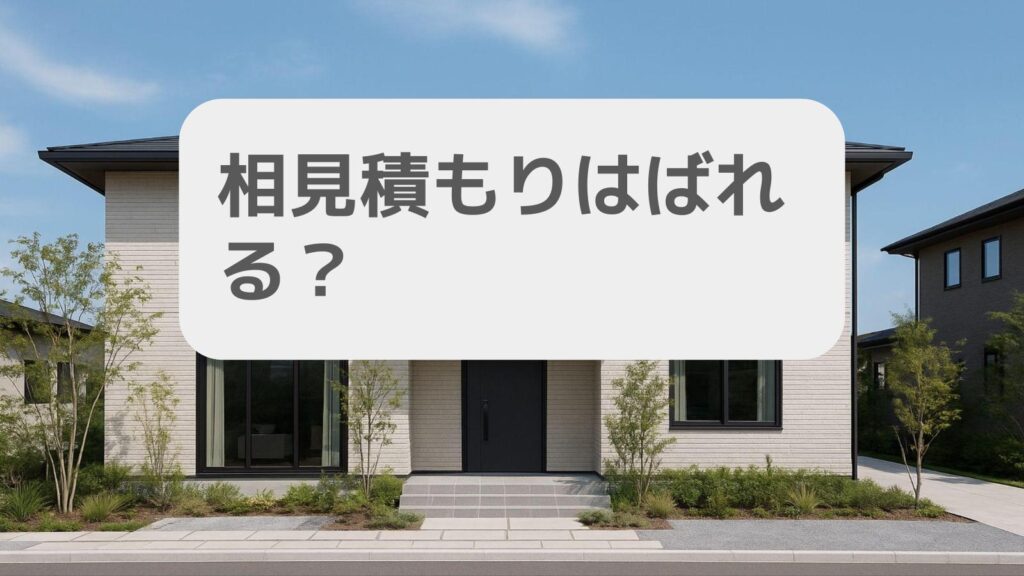
相見積もりはばれるものなのでしょうか?結論から言うと、「ばれる可能性はかなり高い」です。建築・リフォーム業界は思っている以上に狭い世界であり、業者同士の横のつながりも意外と深いものです。地元の業者であればなおさら、過去に取引のある業者同士が情報交換をしていたり、現場の出入りや工程が重なることで自然とバレてしまうケースもあります。
また、見積もりの依頼時の言い回しや時期、相談内容の類似性から「この案件は他でも声をかけているな」と業者側が勘づくことも少なくありません。たとえば、同じ条件で同時期に複数の業者に見積もりをお願いした場合、担当者が共通の材料仕入れ先に聞いたり、業界内でのやり取りの中で話題に出て、知られてしまうこともあります。
しかし、ばれること自体が悪いわけではありません。むしろ最初に「相見積もりを取っています」と正直に伝えておくことで、業者側も納得した上で対応してくれるケースが多くなります。このようにオープンな姿勢を取ることで、余計な誤解を防ぎ、誠実なやり取りが生まれやすくなります。
ただし注意したいのは、相見積もりを理由に業者に過剰な価格競争をさせたり、他社の見積もり内容を材料に値切るような行為は避けるべきです。これでは本来の目的である「納得できる適正価格と信頼できる施工内容の比較」から逸れてしまい、結果として業者からの信頼を損ねてしまいます。
信頼関係を築く第一歩として、相見積もりであることを正直に伝えた上で、「内容をしっかり比較して、納得できる提案を選びたい」と誠意ある姿勢を示すことが大切です。そうすれば、相手も丁寧に対応してくれる可能性が高まり、より良い工事へとつながっていくはずです。
相見積もりは意味ないって本当?
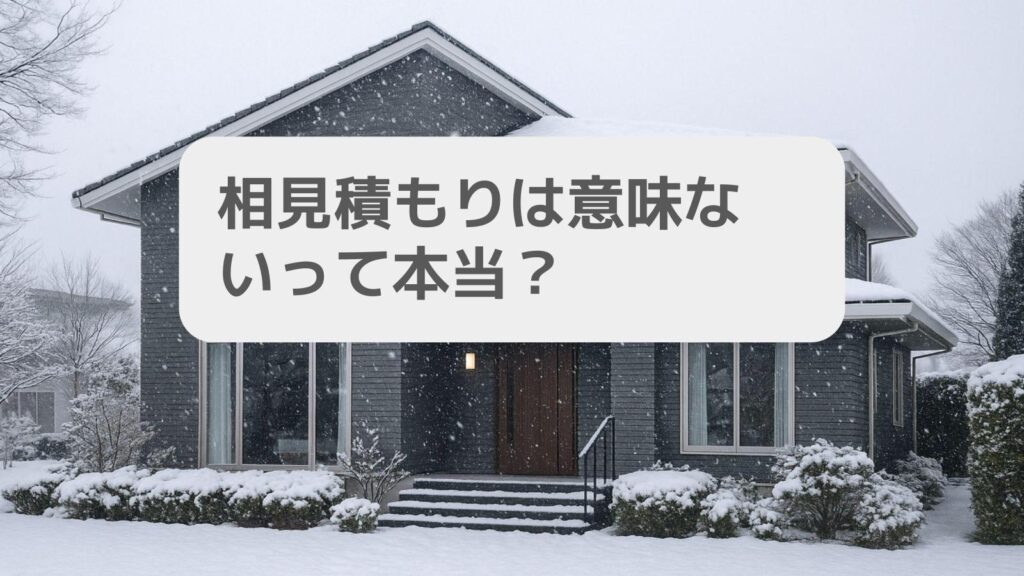
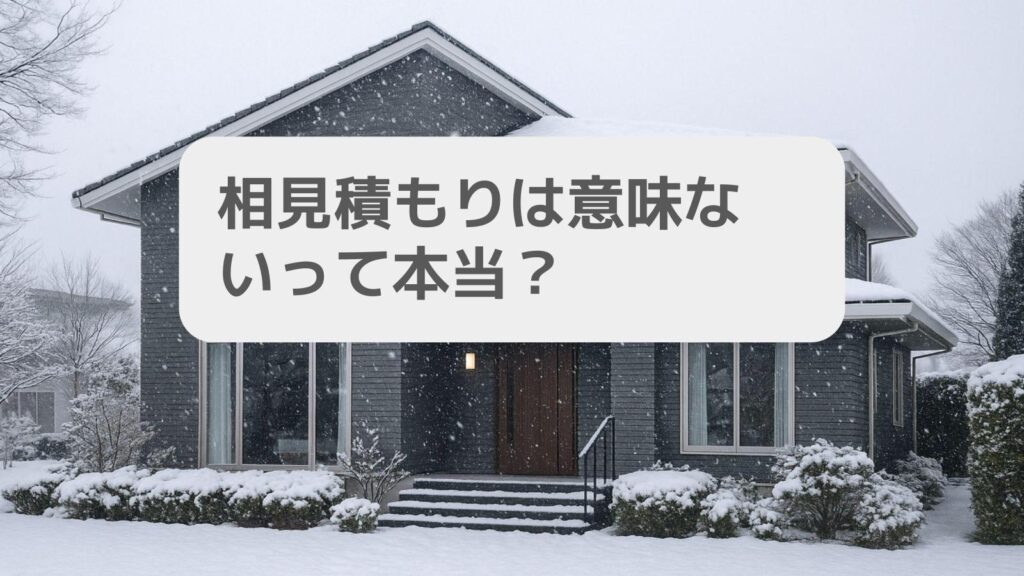
「相見積もりは意味がない」という意見を耳にしたことがあるかもしれません。たしかに、条件がバラバラな状態で複数の業者に見積もりを依頼してしまうと、各社の出してくる金額や工事内容にばらつきが出てしまい、何を基準に比較すればよいのかわからなくなります。その結果、「比較すること自体に意味がなかった」と感じてしまうこともあるのです。
ただし、これは見積もりの取り方に問題があった場合に限った話です。相見積もりが本来持っている意義を正しく活かすためには、依頼時に「同じ条件」「同じ希望内容」「同じ施工範囲」をしっかり伝えることが重要です。たとえば、使用したい建材の種類やグレード、間取りの仕様、設備の詳細などを明確に決めた上で、それを各業者に共通して伝えるようにします。
このように条件を揃えることで、各社の価格や提案の違いが明確になり、比較がしやすくなります。ある業者は価格が安いけれど保証内容が薄い、一方で別の業者は金額は高めだけどアフターサービスが充実している――そんな違いが浮かび上がると、単なる金額だけでなく、どこに価値を置くかという視点で選べるようになります。
また、相見積もりを取ることで、業者の対応力や誠実さも垣間見ることができます。質問への答え方や書類の丁寧さ、説明の分かりやすさなどをチェックすることで、信頼できるパートナーかどうかの判断材料にもなります。価格だけでなく、人としての対応にも注目することが、後悔しない選択につながるのです。
相見積もりのコツは「条件を揃えて依頼する」こと、そして「数字の裏にある価値」を見極めること。こうすれば、相見積もりはとても意味のある有効な手段になります。
工務店の見積もりを取る正しい流れ
見積もりを取る際に最も大切なのは、まず自分たちの希望を明確にすることです。具体的には、どんな工事をしたいのか、どこまでの範囲をお願いしたいのか、予算はどれくらいかといった情報を自分たちで整理しておくことが、スムーズな進行への第一歩となります。特に注文住宅やリフォームなどでは、要望が細かくなるほど伝達ミスが起こりやすいため、できれば書面やリストにしておくと安心です。
次に行うのが、候補となる工務店への問い合わせです。このときに、どのような内容の工事で、どのくらいの予算を見込んでいるかを簡潔に伝えましょう。その後、工務店が現地調査を実施し、必要に応じて詳細なヒアリングや測量が行われます。ここでの対応や質問に対する受け答えなどから、その工務店の姿勢や専門性も見えてくるため、慎重に観察することが大切です。
現地調査を経て、工務店から見積書が提出されます。このとき、見積書の内容はしっかり確認しましょう。価格だけに注目するのではなく、項目ごとに何が含まれているのか、材料や工法の指定があるのか、工期や保証内容はどうなっているかといった点まで目を通す必要があります。不明点があれば遠慮せず質問するようにしましょう。
さらに、比較・検討の段階では、複数社の見積もり内容を見比べて、単なる価格差だけでなく、その根拠や対応の違いにも注目してください。口頭でのやりとりだけで判断せず、必ず書面での記録を残すことが、後々の誤解やトラブルを防ぐために非常に重要です。やり取りの履歴を残しておくことで、後から「言った・言わない」の水掛け論を避けられます。
このように、見積もりを取る流れは意外とやるべきことが多いですが、一つひとつ丁寧に進めることで、納得のいく選択につながります。焦らず、冷静に段取りを組み立てていきましょう。
見積もりを頼むのは何社がベスト?
工務店に見積もりを依頼する際、いったい何社にお願いするのが最適なのか迷う方も多いと思います。一般的には、2〜3社に依頼するのがちょうど良いバランスだと言われています。これは、多すぎても少なすぎても比較・判断がしづらくなってしまうからです。
たとえば、5社以上に依頼した場合、集まった見積もりの内容をひとつひとつ精査し、条件や価格を比較するだけでかなりの労力がかかります。さらに、それぞれの工務店とのやり取りも増え、時間的にも精神的にも負担になりかねません。結果として「比較するのが面倒」と感じてしまい、判断が曖昧になるリスクもあります。
逆に1社だけだと、他との比較ができないため、その金額や内容が適正なのか判断する材料がありません。また、営業トークに流されてしまいやすく、気づかないうちに相場より高い契約をしてしまう可能性もあります。
2〜3社に依頼することで、それぞれの見積もりや対応の違いが見えてきます。例えば、ある工務店は対応がとても丁寧で、見積書も明細までしっかり書かれている。一方で、別の工務店は金額は安いけれど説明が曖昧だった……など、実際のやり取りを通じて、価格以外の重要なポイントも判断材料になります。
また、工務店によっては見積もり作成に時間がかかる場合もあるため、スケジュールに余裕を持って進めることも大切です。余裕を持った中で、2〜3社の見積もりを比較検討し、自分たちに合った工務店を選ぶという流れが、納得感のある家づくりにつながります。
そのため、見積もりの依頼先は多すぎず少なすぎず、2〜3社という数を目安に検討するのが現実的でおすすめです。



タウンライフの一括見積もりなら、全国1160以上の工務店を含む優良企業の見積もりを無料ですぐ取得できます。
工務店の見積もり期間と目安とは?
見積もりの作成には実際どれくらいの時間がかかるのでしょうか?これは工事の規模や内容、依頼する工務店の体制によって大きく異なります。簡単なリフォームや修繕のような小規模な工事であれば、現地調査を含めても数日以内に見積もりが出ることもあります。一方で、注文住宅のように複数の工種が関わる大規模な工事の場合は、図面の確認や構造計算、仕様の検討などが必要になるため、1〜2週間、場合によっては3週間近くかかることも珍しくありません。
また、工務店の規模や対応状況にも影響されます。地域密着型で少人数体制の工務店であれば、現場作業と並行して見積もり作業を行う必要があり、忙しい時期には見積もりが後回しにされることもあります。そのため、問い合わせ時に「今どのくらいの時間がかかりますか?」と事前に確認しておくと安心です。
さらに注意したいのは、見積もりが早く出たからといって、それが「丁寧な仕事」とは限らない点です。スピード重視で内容が不十分だったり、必要な項目が抜け落ちていたりすると、後から追加費用が発生する原因になります。逆に、時間をかけて細かい項目まで丁寧に算出してくれる業者は、全体像をしっかり把握した上で対応してくれていると考えられます。
したがって、急ぎたい気持ちがあっても「早さ」だけに注目するのではなく、「内容の充実度」や「説明の丁寧さ」も含めて評価することが重要です。無理のないスケジュールを組み、安心して依頼できる業者を見極めるようにしましょう。
工務店の見積もりでの値引き交渉術
工務店との見積もり交渉では、単純に「もっと安くしてください」とお願いするよりも、具体的な根拠や状況を示すことが効果的です。たとえば、「他社の見積では○○円でした」といった比較情報を出したり、「予算が○○円なので、できればその範囲に収めたいのですが」と伝えることで、業者側も現実的な対応を考えやすくなります。
このように、値引き交渉にはちょっとした工夫と配慮が必要です。いきなり無理な価格を提示すると、相手に不信感を与えてしまったり、丁寧な対応をしてもらえなくなる可能性もあります。むしろ、「今後もお願いしたいと思っている」「この金額ならお願いできそうです」といった前向きな姿勢を見せることで、工務店側も誠意を持って相談に乗ってくれることが多いのです。
また、値引きの幅は内容によっても異なります。たとえば、グレードの高い素材を別の代替品に変えることで、数万円単位の調整が可能な場合もありますし、オプションの設備を見直すことで費用を抑えるケースもあります。単なる値引きではなく、費用を下げるための提案をこちらから出すのも、良い交渉のスタイルです。
さらに、交渉のタイミングも重要です。契約直前に値引き交渉をすると、業者側も対応が難しいと感じる場合があります。できれば見積もりを受け取った段階で早めに相談し、お互いの妥協点を探るようにしましょう。タイミングと伝え方を工夫すれば、柔軟な対応を引き出しやすくなります。
ただし、しつこく無理な交渉を続けると、相手との信頼関係が損なわれるおそれもあるため注意が必要です。値引きはあくまで「より良い取引のための提案」であり、無理強いするものではありません。節度を守りつつ、お互いが納得できるラインを見つけることが、満足のいく契約につながる鍵となります。
工務店が見積もりを出さない理由と対応策まとめ
- 見積もり作成には多大な手間と時間がかかる
- 発注確約がないと「タダ働き」になりやすい
- 小規模工務店ほど人的リソースに余裕がない
- 相見積もりで“当て馬”にされた経験がある
- 営業と現場を兼務しており対応が追いつかない
- 「一式」表記は内容が不透明になりやすい
- 詳細な見積もりが出せないと言われることがある
- 見積もり提示は法律上の義務ではない
- 契約前に金額が大きく変わることがある
- 見積書がないまま契約すると後々トラブルになりやすい
- 注文住宅では見積もり誤差が大きくなりがち
- ハウスメーカーでも見積もりのズレは発生する
- 相見積もりは業者にばれることが多い
- 条件を揃えれば相見積もりは効果的である
- 値引き交渉はタイミングと伝え方が重要
ハウスメーカーを決めていないあなたへ。タウンライフの家づくり
\300万円以上の値下げ事例あり!/

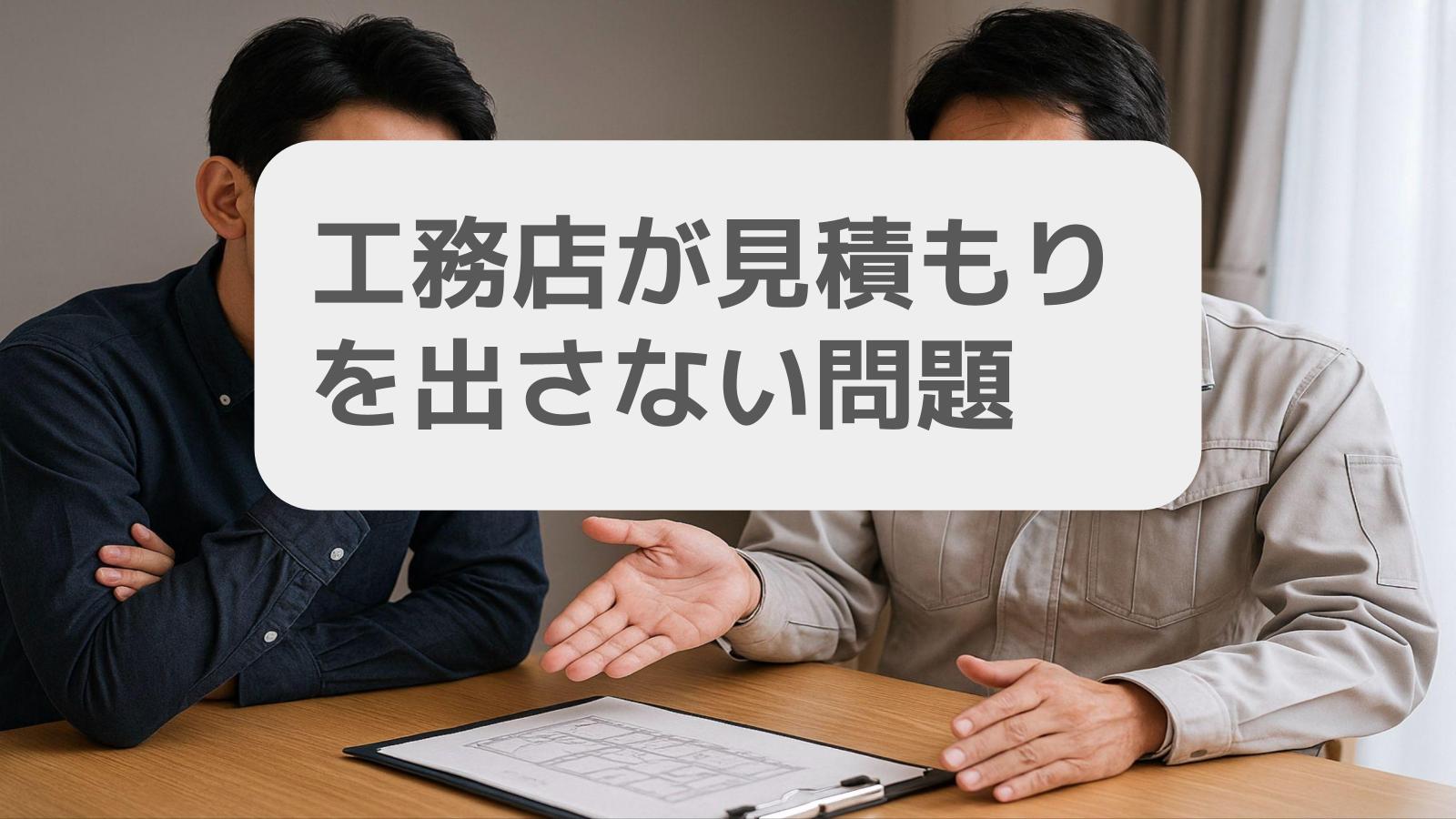


コメント